「退職時誓約書のサインを拒否されたら、どう対応すべきか?」
この悩みに直面した企業担当者や人事労務関係者も多いのではないでしょうか。退職時の誓約書は競業避止義務や秘密保持義務を担保する重要なツールですが、従業員が拒否した場合の法的リスクや実務対応に不安を感じるケースが多発しています。
今回のコラム記事では、退職時の誓約書を作成する背景から、拒否された場合の対応方法まで解説いたします。今後の労務管理の参考にいただければ幸いです。
退職時の誓約書とは何か?
退職時の誓約書とは、企業が従業員の退職に際して求める文書であり、退職後の行動に関する約束事を明文化したものです。
主に「競業避止義務(同業他社への転職の制限)」「機密保持義務(社内情報の漏洩防止)」「会社資産の返却」などが記載されていることが一般的です。
この誓約書は、企業にとっては事業の競争力を守るための重要な手段ですが、従業員にとっては自由なキャリア形成を妨げる可能性もあります。そのため、単に会社から求められるがままに署名するのではなく、内容をよく理解した上で慎重に判断することが大切です。
誓約書の目的と一般的な内容
退職時の誓約書は、企業が従業員にサインを求める主な目的として
- 機密情報の保護
- 競業避止の確保
- 会社資産や資料の返却
これら3つが一般的です。
機密情報の保護
企業は、取引先情報や技術データ、経営戦略などの機密情報を外部に漏らされることを防ぐため、退職者に対して「機密保持義務」を求めます。これにより、退職後に競合他社へ情報が流れるリスクを軽減できます。
競業避止の確保
特定の業界や企業では、退職後すぐに競合他社に転職することで、これまでの業務経験やノウハウが競争相手に流れる可能性があります。そのため、「競業避止義務」を設け、一定期間は同業他社での勤務を制限する条項を設けるケースが多いです。ただし、日本の労働法では過度な制限は無効となる場合もあります。
会社資産や資料の返却
企業は、従業員が会社のパソコンや顧客リスト、業務用のツールなどを適切に返却することを求めます。退職後に会社の資料を持ち出してしまうと、情報漏洩や不正利用につながる可能性があるため、誓約書で確約させるのです。
企業が誓約書を求める理由
企業が退職者に誓約書の提出を求める理由は、単なる形式的なものではなく、自社の利益を守るために必要な措置だからです。主な理由を詳しく見ていきましょう。
競争力の維持
企業は、競争市場の中で優位性を保つために独自のノウハウや戦略を築いています。退職者がこれらの知識を持ったまま競合他社に転職すると、企業の競争力が損なわれる可能性があります。そのため、誓約書によって一定期間の競業を制限し、事業の安全性を確保しようとするのです。
取引先や顧客情報の保護
企業にとって、顧客リストや取引先との関係性は貴重な資産です。もし退職者が顧客情報を持ち出し、新たな職場や独立後の事業で活用すれば、元の会社のビジネスに大きな影響を与えることになります。誓約書には「顧客情報の不正利用を禁止する条項」が含まれることが多いのはこのためです。
法的トラブルの予防
従業員が退職後に会社の重要情報を持ち出して問題を起こした場合、企業が法的措置を取ることになります。しかし、事前に誓約書を交わしておけば、違反があった際に証拠として提示でき、企業側が有利な立場を築くことができます。そのため、誓約書は「法的な抑止力」としての役割も果たしているのです。
このように、企業が誓約書を求める背景には、事業の安全性や競争力の維持といった明確な目的があります。とはいえ、従業員にとって不利益になる内容も含まれていることがあるため、署名する前には慎重な確認が必要です。
退職時誓約書を拒否されるケース
企業が従業員に対して退職時の誓約書の提出を求めても、必ずしも全員がサインするとは限りません。実際には、従業員が誓約書への署名を拒否するケースも少なくありません。特に、内容に不明瞭な点がある場合や、従業員にとって不利益が大きい場合には、サインをためらうことが多くなります。
企業側としては、「なぜ従業員が誓約書を拒否するのか?」を理解し、対応を検討することが重要です。また、拒否された場合にどのようなリスクがあるのかを把握し、必要に応じて事前に対策を講じることで、スムーズな退職手続きを進めることができます。
従業員が拒否する主な理由
従業員が退職時の誓約書にサインすることを拒否する理由はさまざまですが、特に以下のようなケースが多く見られます。
内容が一方的で不公平
誓約書の内容が、企業側の都合のみを優先し、従業員にとって不利益になるものだと判断される場合、拒否される可能性が高くなります。たとえば、競業避止義務の期間が長すぎる、対象範囲が広すぎる、違反時のペナルティが重すぎるなどが挙げられます。
退職後のキャリアに悪影響を及ぼす可能性がある
競業避止義務が厳しすぎる場合、同業他社への転職が制限されたり、フリーランスや起業の道が閉ざされたりすることになります。このような制限があると、従業員は誓約書にサインすることをためらいます。
法的拘束力が疑わしい
誓約書の条項の中には、法的に無効となる可能性があるものもあります。特に、労働者の職業選択の自由を過度に制限する条項は、裁判で無効と判断されることが多いため、従業員が「そもそもこの誓約書は法的に無意味では?」と疑念を持ち、署名を拒否するケースもあります。
会社への不信感やトラブルの背景
退職時に企業との関係が悪化している場合、誓約書へのサインを拒否するケースもあります。例えば、退職の原因がハラスメントや労働条件の悪化であった場合、従業員が会社に対して不信感を抱き、契約書の締結を拒否する可能性が高くなります。
署名する義務がないと認識している
法的に退職時の誓約書へのサインが義務ではないことを理解している従業員は、当然ながら「強制されるものではない」と考え、拒否する場合があります。特に、インターネット上の情報や労働組合などのアドバイスを受けている場合、より慎重に判断する傾向が強くなります。
拒否された場合の会社側のリスク
退職時の誓約書が従業員に拒否された場合、企業側にはいくつかのリスクが発生します。これらのリスクを理解し、事前に対策を講じることで、円満な退職手続きが可能になります。
企業機密の流出リスク
誓約書を拒否された場合、企業の機密情報が流出するリスクが高まります。従業員が在職中に得た顧客リスト、取引情報、技術情報、社内のノウハウなどを持ち出し、退職後に競合企業や新しい職場で活用する可能性があります。
特に、競業避止義務がない場合は、元従業員がすぐに競合他社に転職し、会社の重要な情報が直接ライバル企業へ流れるという事態も考えられます。
取引先・顧客との関係悪化
元従業員が退職後に会社の顧客と直接取引を始めたり、ライバル企業に移って顧客を引き抜いたりするケースも考えられます。企業としては、こうしたリスクを防ぐために、誓約書で一定の制約を課したいところですが、拒否されてしまうと抑止力が働かなくなります。
企業ブランドや評判の低下
退職者が誓約書を拒否したことが社内外で話題になると、「この会社の誓約書は不公平だ」「退職時の扱いが悪い」などの悪評が広がる可能性があります。特に、SNSや口コミサイトで企業の労働環境に関するネガティブな情報が拡散されると、新しい人材の採用にも影響が出ることがあります。
法的措置が取れなくなる可能性
退職者が誓約書にサインしていない場合、何らかのトラブルが発生しても、企業側は法的措置を取りにくくなります。たとえば、機密保持義務違反や競業避止義務違反で訴える場合、誓約書が証拠として機能するため、サインがないと企業にとって不利な状況になる可能性があります。
従業員との交渉が必要になる
誓約書を拒否された場合、企業側は代わりに何らかの合意形成を図る必要があります。たとえば、退職金の支給を条件にして誓約を求めたり、個別に口頭で説明して誓約の重要性を理解してもらうといった対応が考えられます。しかし、このような交渉には時間と労力がかかるため、スムーズな退職手続きを進める上では課題となります。
誓約書拒否への対応方法
退職時の誓約書にサインを求めたものの、従業員が拒否するケースは少なくありません。このような場合、企業側は強引にサインを迫るのではなく、冷静かつ適切に対応することが重要です。誓約書を拒否される理由を理解し、円滑な解決策を模索することで、無用なトラブルを避けることができます。
以下では、誓約書を拒否された際の具体的な対応方法について解説します。
従業員との対話と交渉
まず、誓約書の署名を拒否された場合、企業側は従業員との対話を重視し、合理的な交渉を行うことが不可欠です。頭ごなしに「サインしなければならない」と押し付けるのではなく、従業員の懸念を理解し、誓約書の目的や重要性を丁寧に説明することが重要です。
1. 拒否の理由を確認する
誓約書へのサインを拒否する理由は、従業員によって異なります。主な理由としては以下のようなものがあります。
- 競業避止義務の期間や範囲が広すぎる
- 退職後のキャリアに悪影響を及ぼす
- 内容が一方的で不公平
- 法的な拘束力が疑わしい
まずは、従業員がどの点を問題視しているのかを確認し、その懸念に対して企業側がどのように対応できるのかを考えましょう。
2. 誓約書の目的を明確に伝える
従業員が誓約書に対して不信感を抱いている場合、その背景には「なぜサインを求められるのかが分からない」という疑念があります。そのため、誓約書の目的が企業の利益を守るためだけではなく、従業員自身の信頼性向上にもつながることを説明すると、納得してもらいやすくなります。
例えば、「機密情報の保護は、従業員が今後のキャリアで信用を得るためにも重要」といった視点を伝えることで、より協力的な姿勢を引き出せる可能性があります。
3. 強制ではなく合意形成を目指す
労働基準法上、誓約書の署名を強制することはできません。従業員が納得しないままサインをさせると、後々トラブルの原因になりかねません。したがって、話し合いを通じて合意を形成し、双方にとって納得のいく形で解決することが望ましいでしょう。
誓約書の内容修正と柔軟な対応
誓約書が拒否される大きな理由のひとつに、内容が一方的で不公平な点があることが挙げられます。そのため、従業員の意見を踏まえ、必要に応じて誓約書の内容を修正する柔軟な対応が求められます。
競業避止義務の見直し
特に、競業避止義務に関する条項が厳しすぎると、従業員がサインを拒否する確率が高くなります。以下の点を再検討すると、合意が得やすくなる可能性があります。
- 制限期間の短縮:1~2年の競業避止義務は長すぎると感じる従業員も多い。業界標準や実務に即した期間に見直す。
- 対象範囲の明確化:競業避止の対象企業が広すぎると問題になりやすい。具体的な企業名や業種を限定することで納得感を高める。
- 補償の提供:競業避止義務を課す場合、一定期間の補償金を支払うことで従業員の負担を軽減する方法もある。
機密保持義務の明確化
機密保持義務の内容が漠然としていると、従業員は不安を感じます。そのため、どの情報が機密情報に該当し、どの範囲までが保護対象なのかを明確に記載することが重要です。
また、機密情報の保持期間についても、「永久に守るべき」などの極端な表現を避け、合理的な期間を設定することが求められます。
従業員にメリットを伝える
誓約書の修正だけでなく、従業員にとってメリットがあることを伝えると、合意が得られやすくなります。例えば、「機密情報を適切に管理することが、将来的なキャリアにおいて信頼を得るためにも役立つ」などの説明を加えると、納得しやすくなるでしょう。
法的アドバイスの重要性
誓約書をめぐる問題は、労働法や契約法と密接に関わるため、企業側としても適切な法的知識を持つことが重要です。誓約書の作成や交渉の際には、必要に応じて弁護士や社労士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
法的リスクの回避
不適切な誓約書を作成すると、後々の法的トラブルの原因になります。特に、競業避止義務の制約が強すぎる場合、裁判で無効と判断される可能性もあります。法的に有効な誓約書を作成することで、企業のリスクを最小限に抑えることができます。
従業員とのトラブルを未然に防ぐ
従業員が誓約書に不満を持ったまま退職すると、労働基準監督署への相談や訴訟に発展する可能性があります。法的アドバイスを受けながら適切な対応を取ることで、従業員の理解を得ながらスムーズに退職手続きを進めることができます。
柔軟な解決策の提案
弁護士や社労士は、法的な視点から企業にとって最適な解決策を提案できます。例えば、競業避止義務の期間を短縮する代わりに退職金を増額する、秘密保持契約(NDA)を別途締結するなど、双方にとって納得のいく形を模索することが可能です。
誓約書なしでの退職手続きの進め方
退職時に誓約書への署名を求める企業は多いものの、法的にサインを義務付ける規定はありません。従業員が誓約書を拒否した場合でも、企業は適切な方法で退職手続きを進める必要があります。
誓約書がないからといって、企業側が退職を認めない、あるいは退職金を支払わないといった対応は違法となる可能性があります。そのため、誓約書なしでも円満に退職手続きを完了させる方法を検討することが重要です。
代替措置の検討
誓約書なしでの退職手続きを進める場合、企業としては機密情報の保護や競業避止を確保するために、代替措置を検討することが重要です。以下のような方法が考えられます。
機密保持契約(NDA)の締結
誓約書の代わりに、**機密保持契約(Non-Disclosure Agreement, NDA)**を締結する方法があります。NDAは機密情報の保護に特化した契約であり、退職後も機密情報の漏洩を防ぐための法的効力を持つため、誓約書なしでも一定の安全性を確保できます。
NDAを活用するメリットとしては、
- 機密保持の範囲が明確になり、トラブルを防げる
- 退職後に機密情報を不正利用された場合、法的措置を取りやすい
- 誓約書と異なり、従業員が納得しやすい
このようなものが挙げられます。
退職面談での口頭確認
誓約書がなくても、退職面談を実施し、退職者と口頭で確認することで、一定の合意形成を図ることが可能です。
特に以下の点を明確に伝えることで、退職後のトラブルを防ぐことができます。
- 企業の機密情報を持ち出さないこと
- 取引先や顧客情報の不正使用を行わないこと
- 競業避止義務が必要な場合、その合理的な範囲について話し合う
面談の際には、議事録を作成し、双方が合意した事項を記録として残すことも有効です。
退職時の誓約を記録する「確認書」の活用
誓約書の代わりに、簡単な「退職時確認書」を作成し、企業の情報や資産を適切に取り扱うことを確認する書面を交わすのも一つの方法です。
この確認書には、以下のような内容を記載するとよいでしょう。
- 会社のPC、資料、備品を返却したことの確認
- 退職後、企業の機密情報を第三者に開示しないことの確認
- 取引先への対応方法や社外からの問い合わせ対応に関するルール
このような確認書を作成することで、誓約書がなくても一定の法的根拠を持たせることができます。
退職手続きの円滑な進行のためのポイント
誓約書がない場合でも、企業側が円滑に退職手続きを進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
退職までのスケジュールを明確にする
退職者との間で、最終出勤日や退職日、引継ぎ期間などを明確に設定することが重要です。スムーズな退職を実現するために、以下の点を事前に決めておきましょう。
- 業務の引継ぎ期間(通常2週間~1ヶ月程度)
- 最終出勤日と退職日の明確化
- 退職金や有給休暇の消化についての取り決め
また、退職日までに必要な書類(離職票、源泉徴収票など)の準備を進めることで、スムーズに手続きを完了できます。
貸与物の回収を徹底する
誓約書なしでの退職手続きを進める場合、会社のPCやスマートフォン、社員証、顧客リストなどの資産が適切に返却されるよう管理することが重要です。
チェックリストを作成し、退職前に以下の項目を確認するとよいでしょう。
- PCや業務用スマホの返却
- 社員証、入館証の回収
- 業務用アカウント(メール、クラウドストレージ)の削除
- 退職者が持ち出した資料やデータの有無の確認
万が一、機密情報を持ち出した疑いがある場合は、退職後でも調査し、必要に応じて適切な対応を取ることが求められます。
退職後の関係を良好に保つ
退職者との関係を悪化させると、企業の評判や今後の採用活動にも影響が出る可能性があります。そのため、退職時には円満に手続きを終え、退職後も良好な関係を維持することが重要です。
具体的には
- 退職者の今後のキャリアを応援する姿勢を示す
- 退職後の問い合わせに適切に対応する
- 企業の悪評が広がらないよう、退職者と円滑な関係を築く
このような対応を取ることで、元従業員が転職先や業界内で企業の評判を下げるリスクを抑えることができます。
まとめ:誓約書拒否時の適切な対応
退職時の誓約書にサインを求めても、従業員が拒否するケースは珍しくありません。企業としては、誓約書の強制ではなく、従業員との対話や法的に適切な対応を重視することが求められます。
従業員が誓約書へのサインを拒否する背景には、不明確な契約内容、不公平な条項、競業避止義務への懸念など、さまざまな理由が考えられます。
したがって、企業はまず従業員の拒否理由を丁寧にヒアリングし、その懸念に寄り添う姿勢を見せることが重要です。
誓約書を拒否された際に無理にサインを強要すると、かえって従業員とのトラブルを引き起こし、企業側に不利益をもたらす可能性があります。そのため、企業としては適切な対応を取りながら、従業員と合意を形成し、円滑な退職手続きを進めることを意識しましょう。
退職者とのトラブルを未然に防ぐためにも、「サインを拒否されたらどうするか?」ではなく、「誓約書なしでもリスクを抑えるにはどうすればよいか?」という視点を持つことが、企業にとって最善の選択となるでしょう。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
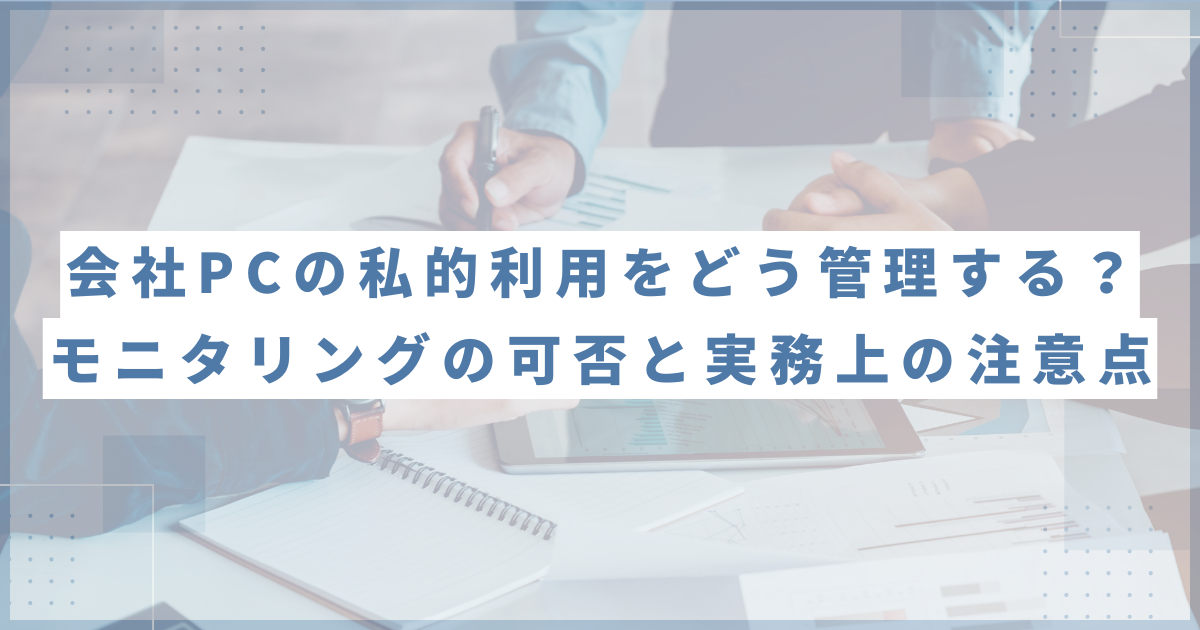 ニュース一覧2026.02.11会社PCの私的利用をどう管理する?モニタリングの可否と実務上の注意点
ニュース一覧2026.02.11会社PCの私的利用をどう管理する?モニタリングの可否と実務上の注意点 ニュース一覧2026.02.09社会保険の随時改定とは?条件・タイミング・注意点を社労士が解説
ニュース一覧2026.02.09社会保険の随時改定とは?条件・タイミング・注意点を社労士が解説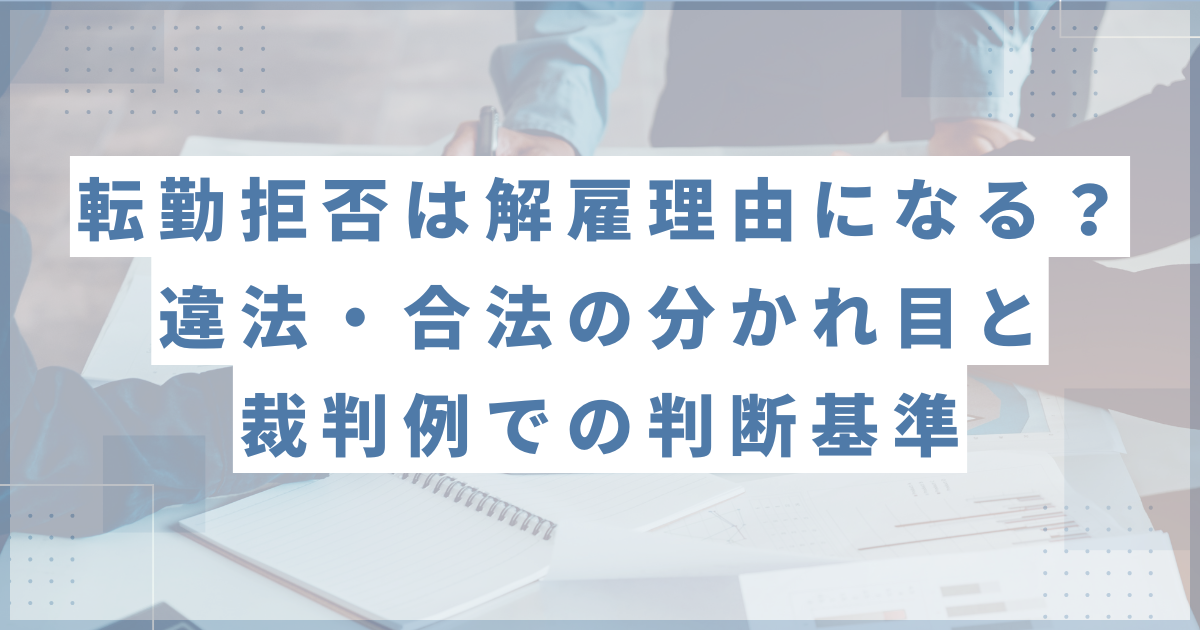 ニュース一覧2026.02.05転勤拒否は解雇理由になる?違法・合法の分かれ目と裁判例での判断基準
ニュース一覧2026.02.05転勤拒否は解雇理由になる?違法・合法の分かれ目と裁判例での判断基準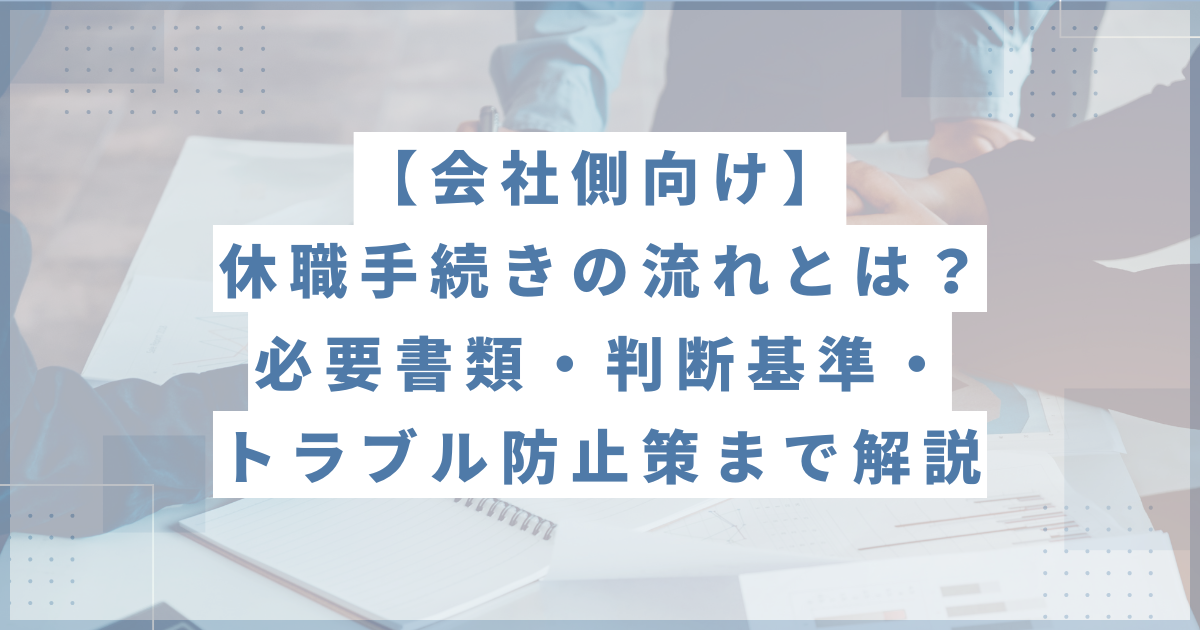 ニュース一覧2026.02.03【会社側向け】休職手続きの流れとは?必要書類・判断基準・トラブル防止策まで解説
ニュース一覧2026.02.03【会社側向け】休職手続きの流れとは?必要書類・判断基準・トラブル防止策まで解説
