新しく採用した従業員に対して設けられる「試用期間」。
なんとなく雇用する前の“お試し期間”というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、実はこの制度には法律的な意味や、運用上の重要なポイントが数多く存在します。
本記事では、正社員はもちろん、パート・アルバイトにも関係する「試用期間」の意味や設定期間、解雇・本採用の判断基準、トラブル回避のための注意点などを、労務の専門家の視点でわかりやすく解説します。
採用後のミスマッチを防ぎ、安心して人材を活かすためにも、試用期間の正しい知識を身につけておきましょう。
試用期間とは何か?基本的な理解
新しく採用された従業員が、すぐに「本採用」となるわけではないことをご存じでしょうか?
多くの企業では、まず「試用期間」という評価期間を設け、その間に業務の適性や勤務態度などを確認したうえで、正式な雇用継続を判断しています。これは、企業・従業員の双方にとってミスマッチを防ぐための重要なプロセスです。
ただし、試用期間という言葉の解釈は企業や人によって異なることもあるため、正確な意味を知ることがトラブルの予防につながります。この章では、試用期間の本来の定義や、似た言葉との違いを専門家の視点からわかりやすく解説します。
試用期間の定義と目的
試用期間とは、「本採用を前提にしつつ、労働者の適性を見極めるための一定期間」を意味します。企業と従業員の間では、すでに雇用契約は結ばれているものの、従業員の適正を判断する期間として設けられることが多い制度で、一般的に、試用期間の主な目的は以下の3つに集約されます。
- 業務遂行能力の確認:指示を正しく理解し、適切に業務を進められるかどうか。
- 職場環境への適応力:チームとの協調性や、会社の風土に馴染めるか。
- 勤務態度や責任感の評価:遅刻・欠勤の有無、基本的なマナーの遵守など。
企業側にとっては、リスク回避の手段として活用される制度ですが、労働者にとっても自分の働き方や社風との相性を見極める貴重な時間です。この「見極めの機会」が双方にあることが、試用期間制度の大きな意義といえるでしょう。
試用期間と研修期間の違い
試用期間と研修期間を混同している企業や従業員は少なくありませんが、この2つには明確な違いがあります。簡単にいえば、試用期間は「評価を目的」とし、研修期間は「教育を目的」としている点が異なります。
| 区分 | 試用期間 | 研修期間 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 適性の評価 | 業務スキルの習得や知識の習得 |
| 雇用契約 | 労働契約の一環 | 同上(明確な契約下で行う) |
| 本採用との関係 | 評価結果により本採用の可否を判断 (ただし、本採用の拒否自体はハードルが高い) | 原則、本採用を前提にした教育期間 |
研修期間中であっても、労働契約がある以上、給与の支払いや労働時間の管理、社会保険の加入義務などは発生します。企業が「研修中だから最低賃金以下でよい」などと誤解することは、重大な違法行為につながります。
また、研修中であっても解雇や契約終了を行う場合には、正当な理由や手続きが必要になります。目的や名称に関係なく、「働かせる以上は労働法が適用される」という基本を押さえておきましょう。
試用期間の一般的な期間と設定方法
企業が新たに従業員を採用する際、試用期間をどれくらいの長さに設定すればよいのか、またその法的な根拠や制限について迷うことは少なくありません。試用期間の設定には「自由度」がある一方で、誤った運用はトラブルの原因にもなり得ます。
この章では、試用期間の一般的な長さの目安から、設定時に注意すべき法律上のポイント、さらには延長を行う場合の正しい手続きについて、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
試用期間の一般的な長さ
多くの企業では、試用期間を「3か月」と設定しているケースが一般的です。これは、労働者の適性を見極めるにはある程度の実務経験が必要であること、かつ過度に長くなると労働者の不安を招きやすいことからバランスの取れた期間とされているためです。
ただし、業種や職種によって以下のような違いも見られます。
- 一般事務・営業職:1~3か月程度
- 製造業・技能職:3~6か月程度
- 専門性の高い職種(エンジニアや研究職など):6か月以上を設定する場合もある
なお、期間について法律上の明確な上限は定められていませんが、実務上は6か月以内が適正とされるケースが多く、あまりにも長期間の試用は「実質的な本採用の先延ばし」と見なされる恐れがあります。
試用期間の設定に関する法的留意点
試用期間の設定は企業の自由裁量に委ねられている部分もありますが、労働契約の一環である以上、法律上のルールに従って運用する必要があります。以下の点は必ず押さえておくべきポイントです。
- 労働条件通知書への明記が必須
- 就業場所・賃金・契約期間・社会保険などと同様に、試用期間の有無とその長さは明記が必要です。
- 社会保険・雇用保険の適用対象
- 試用期間中であっても、労働時間や賃金の条件を満たせば、正社員と同様に各種保険の加入義務があります。
- 解雇手続きの簡略化は不可
- 試用期間中であっても、解雇には「客観的に合理的な理由」が必要です。14日を超えて雇用する場合は解雇予告も求められます。
「試用期間中だから、すぐに辞めさせられる」という誤解は企業・労働者双方に根強く残っていますが、現実には正社員同様の法的保護がある点を正確に理解しておくことが重要です。
試用期間の延長とその手続き
業務の性質や本人の評価によっては、「あと少し様子を見たい」という理由で試用期間を延長するケースもあります。しかし、延長には明確な理由と、適切な手続きが求められます。
試用期間を延長する際の注意点は以下の通りです。
- 延長理由が客観的に説明できること(例:業務の習熟度が不足している、出勤日数が少なく十分な評価ができない等)
- 本人に書面で説明・同意を得ること
- 延長期間も合理的な範囲内(原則として数週間~1か月程度)
また、採用時の労働条件通知書に「必要に応じて延長することがある」といった記載があれば、トラブルを未然に防ぐことができます。
企業側の「評価期間をもう少し確保したい」という気持ちは理解できますが、理由も手続きも曖昧なまま延長することは、労働者との信頼関係を損なう大きなリスクとなります。試用期間の延長は、あくまでも慎重に、そして誠実に対応すべき事項です。
試用期間中の労働条件と雇用契約
「試用期間中だから、まだ本採用ではない」と考える企業も多い一方で、法律上はすでに労働契約が成立しており、従業員としての権利と義務が発生しています。この点を正しく理解していないと、思わぬトラブルや法的リスクを招くことになりかねません。
ここでは、試用期間中の労働契約の法的性質や、給与・社会保険の取り扱い、そして有給休暇の付与や労働条件の通知義務について、実務の観点から詳しく解説します。
解約権留保付労働契約とは?
試用期間中の雇用は、「解約権留保付労働契約」と呼ばれる特別な契約形態とされています。
これは、企業が一定期間内に労働者の勤務状況を評価したうえで、本採用を最終判断するという前提の契約です。
ただし、この契約においても、労働者はすでに法的に「雇用されている」状態であり、企業側は自由に契約を打ち切れるわけではありません。
解約権留保が有効とされるための要件は次の通りです。
- 解約権の留保が労働契約書や就業規則に明記されていること
- 客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性があること
- 評価・判断の基準が明確で、本人にも共有されていること
試用期間中でも解雇の判断には慎重さが求められ、単に「雰囲気が合わない」「思ったよりできない」といった抽象的理由だけでは不当解雇とされるおそれがあります。解約権の濫用があれば、法的責任を問われる可能性があることを、企業側は十分に認識しておくべきです。
試用期間中の給与・社会保険の取り扱い
試用期間中であっても、労働者としての地位はすでに確立しているため、給与の支払いと社会保険の加入義務は基本的に本採用後と同様に扱う必要があります。
【給与に関する取り扱い】
- 試用期間中の給与を本採用時より低く設定すること自体は可能
- ただし、最低賃金法を下回ってはならない
- 差を設ける場合は、合理的な説明が求められる
【社会保険に関する取り扱い】
- 労働時間が所定の基準を満たす場合、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入させる義務がある
- 試用期間を理由に保険加入を先延ばしにするのは違法
つまり、「試用期間だから保険は後で」という運用は原則として認められておらず、適切な初期対応が求められます。
試用期間中の有給休暇と労働条件の明示
有給休暇の発生についても、試用期間中だからといって無関係というわけではありません。労働基準法では、「雇入れ日から6か月継続勤務し、かつ所定労働日の8割以上出勤した労働者」に対して年次有給休暇の付与義務があると定めています。
つまり、試用期間中もこのカウントに含まれるため、6か月後に付与されるかどうかは、入社日からの通算で判断されます。
会社のルールとして「入社時に有給休暇を前倒しして付与する場合」には、
- 労働者から申請があれば、原則として有給は取得可能
- 雇用契約時に「試用期間中は有給が使えない」としている場合でも、法的効力は限定的
上記のような形になる点、注意しておきましょう。
さらに、労働条件の明示義務についても気を付けなければなりません。試用期間中であっても、以下の項目は労働条件通知書等により明示しなければなりません。
- 労働契約の期間
- 勤務地・業務内容
- 労働時間・休日
- 賃金の決定方法・支払日
- 社会保険の有無
- 試用期間の有無および期間
これらが明記されていない、または曖昧にされていると、労働トラブルの温床となります。入社時点でしっかりと明示し、説明することが企業の信頼にもつながります。
試用期間中の解雇と本採用拒否
「試用期間だから、気に入らなければいつでも解雇できる」と考えていると、思わぬ法的トラブルに発展しかねません。試用期間中であっても、労働者はすでに法律上の保護対象であり、解雇や本採用拒否には厳格なルールが求められます。
この章では、試用期間中に解雇が認められる具体的なケース、解雇手続きと予告期間のルール、そして本採用を見送る場合の法的リスクについて、実務で注意すべきポイントを専門的視点から整理していきます。
試用期間中の解雇が認められるケース
試用期間中とはいえ、解雇は「無条件」に行えるわけではありません。解雇が適法と認められるためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。
代表的な解雇が認められるケースは次のとおりです。
- 重大な経歴詐称(学歴・資格・職歴などの虚偽申告)
- 著しい勤務態度の不良(無断欠勤や職場内トラブルの常習)
- 明らかな能力不足(業務遂行に必要な最低限の能力が欠如している)
- 指示命令に従わない、業務放棄がある場合
これらに該当する場合でも、企業は記録や証拠をもとに、合理的な判断であったことを説明できる必要があります。
単に「期待外れだった」「相性が悪い」というような主観的な理由だけでは、労働審判や訴訟で不当解雇と認定される可能性が高くなります。
解雇手続きと予告期間の注意点
試用期間中の労働者に対しても、解雇の際には正社員と同様に解雇予告義務が適用されます。これは、労働基準法第20条によって規定されており、「14日を超えて雇用されている場合」は、以下のいずれかが必要です。
- 解雇日の30日前までに予告する
- 30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)
注意点ですが、試用開始から14日以内であれば、予告なしで即時解雇が可能な一方で就業規則や雇用契約書の規定に基づくことが前提となります。
また、社会的に妥当とされる対応でなければ、後に法的責任を問われるリスクがあることは忘れてはいけません。また、労働者にとっては試用期間中の突然の解雇は精神的にも大きな打撃となるため、「解雇に至る前の注意指導」や「評価基準の明示」といった事前措置も非常に重要です。
本採用拒否とその法的リスク
「試用期間が終わったが、本採用は見送る」という判断は、企業にとって重要な権限の一つですが、その扱いは解雇と同様に慎重でなければなりません。
実務上、本採用拒否も「解雇」に相当する行為とみなされるため、法的には以下のようなリスクが伴います。
- 解雇と同等の理由が必要(合理性と社会的相当性)
- 不当と判断された場合は、損害賠償や復職命令の可能性あり
- 労働審判や裁判に発展するリスクがある
対応すべきポイントですが、評価基準をあらかじめ明示しておく(雇用契約書・就業規則など)ことは前提となります。また、評価結果を本人にフィードバックし、記録を残したり、正当な理由がない場合は安易に本採用拒否をしないことが大切です。
また、面談や書面で「なぜ不採用としたのか」を丁寧に説明することも、後のトラブル回避につながります。本採用拒否は「企業の選択」であると同時に「解雇と同義」であることを意識した対応が求められます。
試用期間に関するよくある誤解と注意点
試用期間はあくまで「見極めのための期間」であり、特別な立場にあるようでいても、法的には通常の労働契約と同様の保護を受ける制度です。にもかかわらず、「試用期間だから自由に解雇できる」「本採用までは労働者の権利は弱い」といった誤解は今なお根強く残っています。
この章では、そうした誤解に基づくリスクやトラブルを避けるために、試用期間中における労働者の基本的な権利・義務、実際に起こりがちなトラブル事例とその対処法、さらに企業が制度を設ける際に留意すべきポイントについて、わかりやすく整理して解説します。
試用期間中の労働者の権利と義務
試用期間中の従業員であっても、すでに法的には「雇用された労働者」としての地位が認められており、以下のような基本的権利が保障されています。
- 最低賃金・労働時間・割増賃金などの労働基準法の保護
- 社会保険・雇用保険への加入(基準を満たす場合)
- 有給休暇の付与対象となるための勤務期間のカウント
- 不当解雇からの保護(合理的理由のない解雇は無効)
一方、労働者には義務も伴います。遅刻・欠勤の多発や業務命令への不従順などがあると、「本採用にふさわしくない」と判断されるリスクがあるため、基本的な労働マナーの順守が重要です。
試用期間中のトラブル事例と対処法
試用期間中は、「評価」という性質がある分、トラブルも発生しやすい時期です。以下に代表的な事例と対処のポイントを紹介します。
【トラブル事例1】
突然の解雇通告により労働者が労基署へ申告
→ 解雇理由の説明が不十分だったり、評価記録がなかったりすると「不当解雇」とみなされる。
【トラブル事例2】
試用期間中という理由で社会保険に加入させていなかった
→ 基準を満たす労働者に未加入のまま就労させていた場合、後日追徴保険料や指導対象に。
【トラブル事例3】
労働条件が明示されておらず、給与の認識にズレがあった
→ 労働条件通知書や雇用契約書に明記しておらず、支払額や支払方法を巡ってトラブルに。
適切な対応方法としては
- 雇用契約時に条件を明示する(書面での交付)
- 試用期間中も評価の記録を残す
- 解雇を検討する場合は、本人への事前説明と是正機会の提供を行う
試用期間であっても、上記労務管理は心がけましょう。
試用期間を設ける際の企業側の注意点
試用期間は企業にとって重要な「人材評価の機会」ですが、運用を誤ると法的責任や評判リスクを伴います。以下の点を押さえて制度を設計・運用することが求められます。
【導入時の注意点】
- 就業規則や雇用契約書に「試用期間の有無・期間・延長の可能性」を明記
- 評価項目や本採用判断の基準を明確化
- トラブル回避のために、入社時に口頭ではなく書面で説明
【運用時の注意点】
- 試用期間中も正当な理由なしに解雇はできない
- 延長する場合は、必ず労働者本人に説明し、同意を得る
- 一貫性のある評価と、業務改善の機会提供が重要
特に、試用期間が終わった後に本採用とする場合、「黙示の本採用」とみなされることも多いため、合否の意思決定は期間内に明確に伝えることが望まれます。
パート・アルバイトにおける試用期間の取り扱い
正社員と同様に、パートタイム労働者やアルバイト従業員に対しても、試用期間を設けるケースは多く見られます。しかし、非正規雇用者だからといって法的保護が弱くなるわけではなく、むしろ正確な知識と運用が企業に求められます。
この章では、パート・アルバイトに試用期間を適用する際の基本的な考え方、労働条件の設定方法、そして解雇・不採用といった判断を行う際の注意点について詳しく解説します。
非正規雇用者への試用期間の適用
パート・アルバイトであっても、採用時点から労働契約は成立しており、試用期間を設けることは可能です。むしろ、業務適性や勤務態度を事前に見極める意味では、非正規雇用であっても試用期間を活用する意義は大きいといえます。
ただし、以下のような誤った運用はトラブルのもととなるため注意が必要です。
- 「試用期間中は労働契約がない」と誤解し、雇用契約書を交付しない
- 社会保険に加入させないまま労働させる
- 試用期間満了時に理由を示さず一方的に契約終了とする
非正規労働者にも、法的保護は正社員と同様に及ぶため、「短時間だから」「パートだから」といった軽視は許されません。
パート・アルバイトの試用期間中の労働条件
パート・アルバイトに試用期間を設ける際も、労働条件通知書の交付は必須です。試用期間中の時給、勤務日数、社会保険の有無などを明記し、本人に内容を十分説明する必要があります。
【労働条件で注意すべき点】
- 試用期間中に時給を下げる場合は、その理由を明確に説明
- 試用期間であっても、労働時間や日数によっては社会保険加入が必要
- 業務内容や評価のポイントを明確にし、本人にも伝える
また、有期契約(たとえば3か月契約のアルバイト)であっても、試用期間を設ける場合は「契約期間内に試用期間を含む」旨を明記しておくことが重要です。
解雇・本採用拒否の際の注意点
パートやアルバイトに対しても、試用期間中の「契約終了」や「本採用拒否」は、事実上の解雇として扱われます。特に、社会保険に加入していた場合や、雇用が継続的であると見なされるようなケースでは、正社員と同様の厳しい基準が適用されます。
【注意すべきポイント】
- 試用期間中の契約終了にも合理的な理由と説明が必要
- 解雇予告義務は、14日を超えて雇用していた場合に発生
- 合理性のない不採用判断は、不当解雇として争われる可能性あり
たとえば「初日の印象が悪かった」「指導しなくてもできると思っていた」といった理由では、客観性や社会的妥当性を欠き、不適切と判断されることがあります。非正規雇用であっても、雇用関係を終了させる際には正社員と同じく、適切な評価・記録・説明が求められるのです。
試用期間に関するQ&A
試用期間は、労使双方にとって「見極めの期間」ではありますが、その運用や法的な扱いに対しては多くの疑問や不安がつきまとうものです。特に、労働者側にとっては「退職の自由はあるのか」「評価基準はどうなっているのか」など、入社後すぐに確認しづらい点も少なくありません。
ここでは、試用期間中によく寄せられる代表的な質問に対し、実務的かつ法律的な視点でわかりやすく回答していきます。
試用期間中に退職したい場合は?
結論から言えば、試用期間中であっても、退職は可能です。
労働者は、正当な理由がなくても「2週間前に退職の意思を示すことで自由に退職できる」と民法で定められています(民法627条)。この原則は、試用期間中でも適用されます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 就業規則や雇用契約に「1か月前に申し出」などと記載がある場合には、2週間前の退職の意思表示ではなく会社のルールをできるだけ遵守する
- 無断欠勤や即日退職などはトラブルの原因になるため、事前に書面や口頭での連絡が望ましい
- 退職理由は義務ではないが、引き継ぎや関係者への配慮として最低限の説明をするのがマナー
「もう辞めたいけれど、試用期間だからできないのでは…」と悩む必要はありません。法律は労働者にも自由を認めています。
試用期間中の評価基準は?
試用期間中の評価基準は、企業ごとに異なりますが、一般的には以下の3つの要素が中心になります。
- 業務遂行能力:仕事の理解力、作業スピード、正確性など
- 勤務態度:遅刻・欠勤の有無、マナーや報連相など基本行動
- 組織適応力:社風との相性、周囲との協調性、柔軟性
これらの評価項目は、面接時に確認したポテンシャルとは異なり、「実際の職場でどう動いているか」を重視されます。
企業としても、評価基準は明確に伝えるべき内容です。もし試用期間中に不安がある場合は、「どの点を改善すべきか」を率直に上司や人事に尋ねるのも一つの手段です。
逆に、評価項目がまったく提示されずに「なんとなく不採用」になる場合は、労働者側も法的措置を検討できる余地があります。
試用期間後に本採用されないことはある?
あります。試用期間はあくまでも「本採用を前提としたお試し期間」であり、評価によっては本採用が見送られるケースも正当に存在します。
ただし、以下のようなルールを守らない「本採用拒否」は、法律上無効とされるおそれがあります。
- 評価内容や基準を事前に明示していない
- 本人へのフィードバックが一切なかった
- 恣意的・感情的な判断による拒否
法的には、本採用拒否も「解雇」に近い意味合いを持つため、客観的合理性と社会的相当性が求められます。企業が「なんとなく合わないから」という理由だけで不採用にすると、不当解雇と認定され、損害賠償などのリスクを抱えることになります。
労働者側としては、試用期間中から「評価されるポイント」を把握し、自分の課題を改善する努力を見せることが、本採用への近道となります。
まとめ:試用期間を有効に活用するために
試用期間は、企業と従業員の双方にとって「ミスマッチを防ぐための貴重な機会」です。適切に設定・運用することで、人材の定着や業務の安定につながる一方、誤った対応はトラブルや法的リスクを招く可能性があります。
本記事では、試用期間の定義や目的、法的な留意点、設定方法からトラブル事例、非正規雇用での対応まで幅広く解説してきました。企業としては、単に制度を導入するだけでなく、実務に即した運用ルールを整備し、評価や契約に関する透明性を高めていくことが重要です。
もし、試用期間の設計や運用、採用後の評価基準づくりに不安や課題を感じている場合は、労務管理の専門家である社会保険労務士法人ステディまでお気軽にご相談ください。実情に即した制度設計と運用サポートで、御社の採用・定着力を強化いたします。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
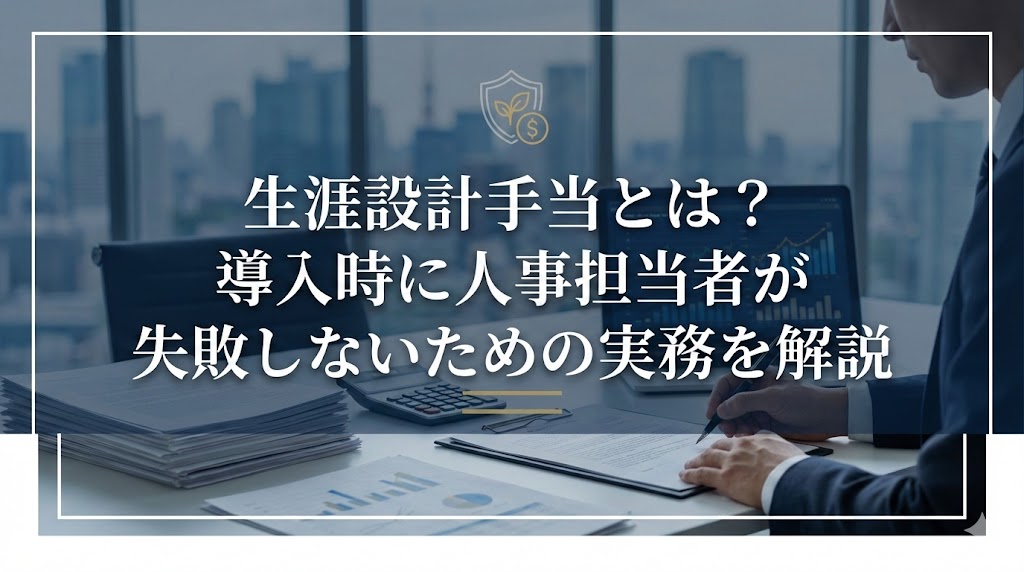 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説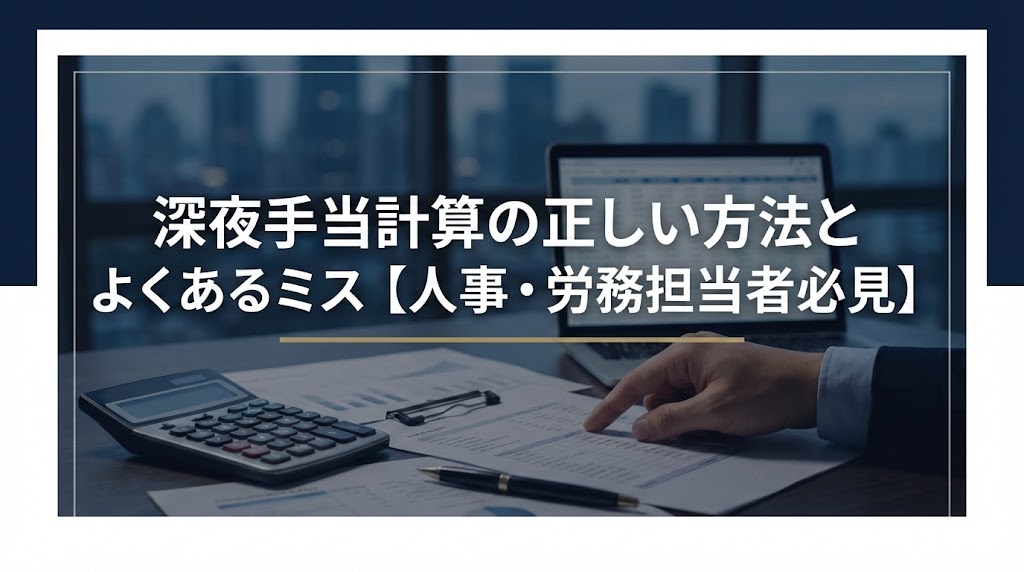 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】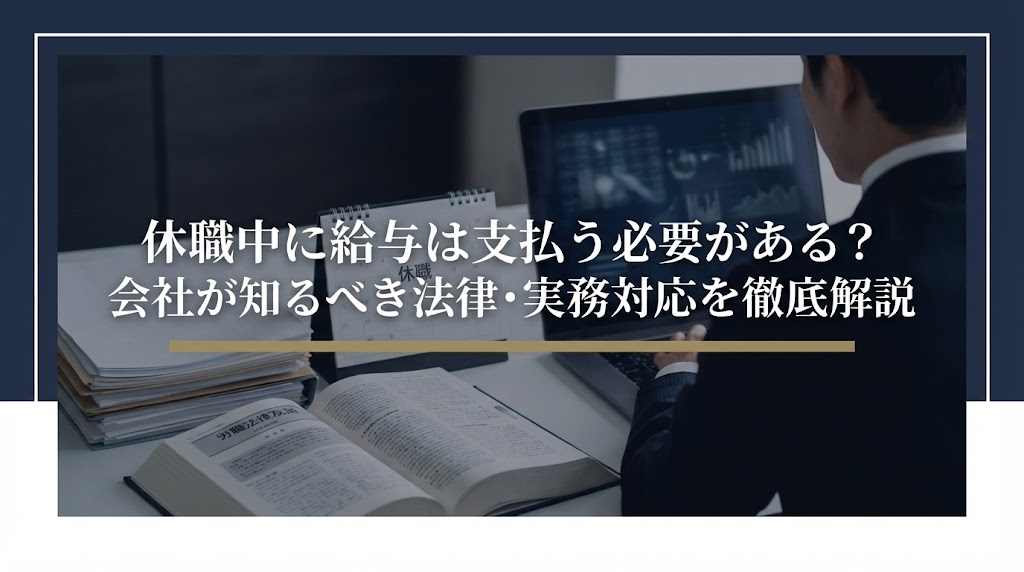 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説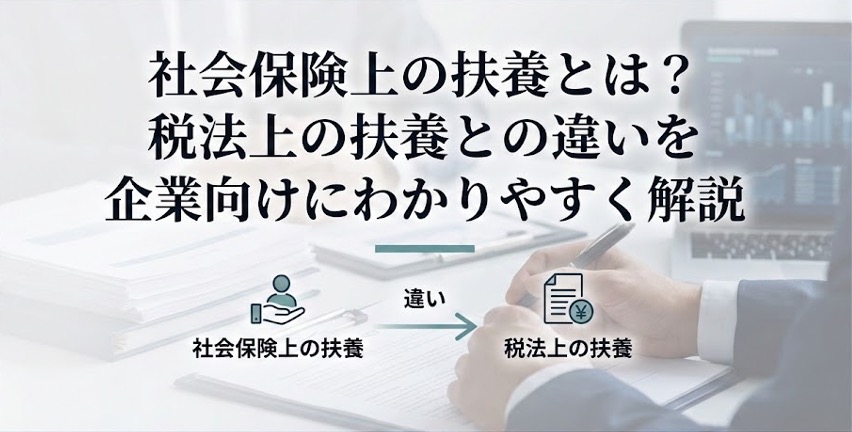 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説

