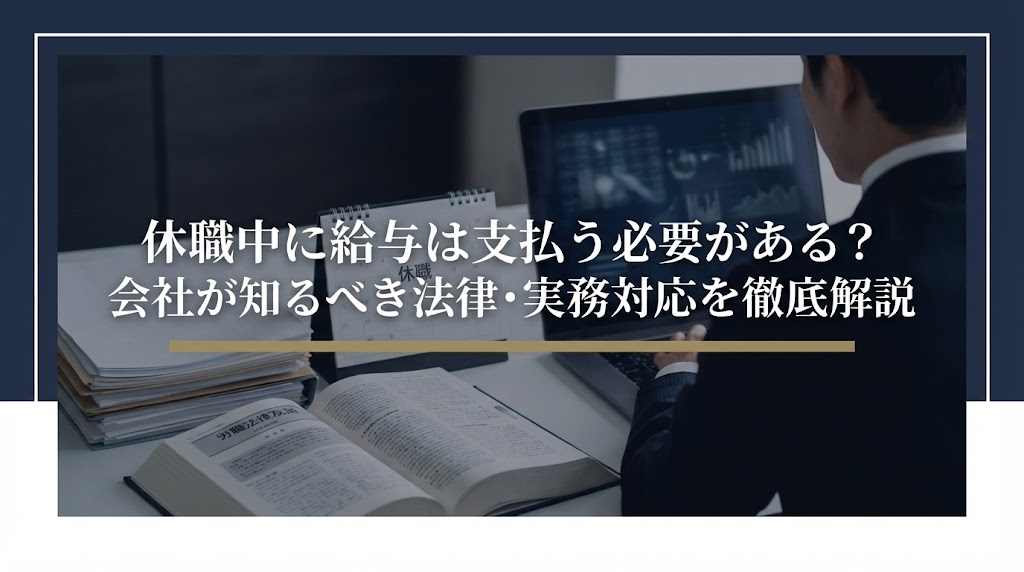従業員が病気やメンタル不調などを理由に休職した場合、「休職中の給与は支払う必要があるのか?」という点は、多くの企業担当者が直面する重要なテーマではないでしょうか。
誤った対応は、労使トラブルや法的リスクに発展する可能性がある一方、正しい理解と実務対応ができていれば、企業としての信頼性向上にもつながります。
本記事では、休職中の給与支払い義務の有無を中心に、関連する法律の考え方や実務上押さえるべきポイントを整理し、会社側が知っておくべき対応策をわかりやすく解説していきますので、ぜひご一読ください。
そもそも休職中の給与は支払う必要があるのか
休職中の給与支払いについては、「法律で必ず支払わなければならない」と誤解されがちですが、実際には休職の性質や就業規則の内容によって結論が大きく異なります。
この章では、まず休職の基本的な位置づけを整理したうえで、法律上の考え方や、規定が存在しない場合の実務対応について順を追って解説します。
休職の定義と会社都合・従業員都合の違い
休職とは、従業員が一定期間にわたり労務を提供できない場合に、雇用関係を維持したまま就労義務を免除する制度を指します。重要なのは、休職は法律で義務付けられた制度ではなく、あくまで会社が任意に設ける制度である点です。
実務上、休職は主に以下の2つに分類して考えられます。
- 従業員都合による休職
病気やケガ、メンタルヘルス不調など、従業員本人の事情により就労が困難となるケースが典型例です。この場合、原則として「労務の提供ができない状態」と評価されます。 - 会社都合による休職(実質的な就業不能)
配置転換の失敗や職場環境の問題など、会社側の要因が背景にある場合は、単なる従業員都合とは言い切れないケースも存在します。
この違いは、後述する賃金支払い義務の有無を判断するうえで非常に重要な視点となります。形式上は「休職」であっても、その原因がどこにあるのかを丁寧に見極める必要があるでしょう。
労働基準法における休職中の賃金の考え方
労働基準法では、「労働の対価として賃金を支払う」というノーワーク・ノーペイの原則が採られています。そのため、従業員が労務を提供していない休職期間中については、原則として賃金支払い義務は発生しないと考えられます。
ただし、注意すべきポイントもあります。
- 会社の責に帰すべき事由により労務提供ができない場合
いわゆる「使用者責任」が認められるケースでは、休職という形式をとっていても、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払い義務が生じる可能性があります。 - 就業規則や労働契約で賃金支払いが定められている場合
法律上の義務がなくても、社内ルールで給与支給を約束していれば、その内容が優先されます。
このように、法律だけを見て「支払わなくてよい」と即断するのは危険であり、休職に至った経緯や社内規程との整合性を総合的に判断する姿勢が求められます。
就業規則に定めがない場合の対応
就業規則に休職中の給与や取扱いが明記されていない場合、会社としては判断に迷う場面が多くなるでしょう。しかし、規定がないからといって、完全に自由な対応が許されるわけではありません。
実務上は、以下の点を意識した対応が重要になります。
- 過去の運用実態との整合性を保つこと
これまで同様のケースで給与を支払っていた場合、突然無給とするのはトラブルの原因になりやすいです。 - 個別事情を踏まえた慎重な判断
病状や休職に至る経緯、復職の見込みなどを考慮せず、一律対応を行うのはリスクが高いといえます。 - 早期に規程整備を検討すること
曖昧な状態を放置せず、休職制度・給与取扱いを明文化することで、将来的な紛争リスクを大幅に軽減できます。
結論として、就業規則に定めがない場合でも「支払わなくてよい」と単純に割り切るのではなく、法的観点と実務上の影響を踏まえた慎重な対応が不可欠だといえるでしょう。
また、重ねてになりますが「会社の責に帰すべき事由により労務提供ができない場合」については、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払い義務がある点には注意しておきましょう。
休職理由別に見る給与支給の扱い
休職中の給与支給は、「休職している」という事実だけで一律に判断できるものではありません。実務では、休職に至った理由によって法的評価や会社の対応が大きく異なります。
この章では、代表的な休職理由ごとに、給与支給の考え方と注意点を整理します。
私傷病による休職の場合の給与対応
私傷病休職とは、業務とは無関係の病気やケガを理由に、従業員が就労できなくなった場合の休職を指します。
最も一般的な休職形態であり、多くの企業がこのケースを前提に制度設計をしているでしょう。
結論から言えば、私傷病による休職中は、原則として給与支払い義務はありません。ただし、その根拠を正しく理解しておくことが重要です。
ノーワーク・ノーペイ原則との関係
私傷病休職における無給の根拠としてよく挙げられるのが、「ノーワーク・ノーペイ原則」です。これは、労働の提供がない以上、賃金も発生しないという労務管理の基本原則を指します。
私傷病の場合、
- 労務を提供できない原因が従業員本人にある
- 会社が就労を拒否しているわけではない
という構造になるため、ノーワーク・ノーペイ原則がそのまま適用されると考えられます。その結果、就業規則に特別な定めがない限り、休職期間中は無給とする扱いが一般的でしょう。
傷病手当金との違い
私傷病休職では、会社から給与が支払われない代わりに、健康保険から傷病手当金が支給される可能性があります。この点を混同している担当者も少なくありません。
両者の違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 給与 | 傷病手当金 |
|---|---|---|
| 支給主体 | 会社 | 健康保険 |
| 支給義務 | 就業規則・契約次第 | 法律上の制度 |
| 支給額 | 規程による | 原則として標準報酬日額の約2/3 |
会社が給与を支払わないこと自体は違法ではありませんが、従業員に対して傷病手当金の存在や手続きについて適切に案内することは、実務上きわめて重要だといえるでしょう。
メンタルヘルス不調による休職の扱い
うつ病や適応障害など、メンタルヘルス不調による休職も、法的には私傷病休職として扱われるのが原則です。そのため、基本的な給与の考え方は私傷病の場合と同様になります。
ただし、メンタルヘルス不調の場合は、以下の点に特に注意が必要です。
- 長時間労働やハラスメントなど、会社要因が関与していないか
- 産業医の意見や医師の診断内容と会社判断に齟齬がないか
- 休職命令の出し方が一方的・強制的になっていないか
もし、メンタル不調の原因が会社の管理体制や職場環境にあると判断されれば、労災の可能性も生じますので、注意しなければなりません。形式だけで私傷病と決めつけるのは、非常にリスクが高い対応といえるでしょう。
業務上疾病・労災休職の場合
業務上疾病や労働災害による休職は、私傷病とはまったく異なる扱いとなります。この場合、就労できない原因が業務に起因しているため、ノーワーク・ノーペイ原則はそのまま適用されません。
実務上のポイントとしては、以下が挙げられます。
- 労災認定を受けた場合、休業補償給付が支給される
- 会社は療養中および休業中の解雇が原則禁止される
- 就業規則上の休職制度とは切り分けて考える必要がある
特に注意すべきなのは、業務上疾病にもかかわらず、安易に私傷病休職として処理してしまうケースです。このような対応は、後に労災トラブルや損害賠償請求に発展するおそれがあり、企業にとって大きなリスクとなります。
休職理由を正確に見極め、それに応じた給与・補償の整理を行うことが、適切な労務管理の第一歩だといえるでしょう。
休職中に利用できる公的給付と会社の関与
休職中の従業員に対して会社が直接給与を支払わない場合でも、公的制度によって一定の生活保障が図られる仕組みが用意されています。
企業担当者としては、「会社はどこまで関与すべきか」「給与との関係はどう整理するのか」を正確に理解しておくことが重要です。この章では、実務で特に関わることの多い傷病手当金を中心に、会社の立場から押さえておくべきポイントを解説します。
健康保険の傷病手当金の概要
傷病手当金は、業務外の病気やケガによって働くことができず、かつ給与の支払いを受けられない場合に、健康保険から支給される公的給付です。私傷病休職における生活保障の中核を担う制度といえるでしょう。
主な支給要件は、以下のとおりです。
- 業務外の病気やケガであること
- 療養のために労務不能であること
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
- 休業期間中に給与の支払いがない、または著しく少ないこと
支給額は、原則として標準報酬日額の約3分の2で、支給期間は最長1年6か月とされています。会社が独自に設ける休職制度とは異なり、全国共通の公的制度である点が特徴です。
傷病手当金と休職給与の併給可否
実務でよく問題になるのが、「休職中に会社から一定額を支給している場合、傷病手当金はどうなるのか」という点です。
原則として、給与と傷病手当金の満額併給はできません。具体的には、以下のような整理になります。
- 会社から給与が全額支給されている場合
→ 傷病手当金は支給されません。 - 給与が一部支給されている場合
→ 傷病手当金との差額分が支給されます。
たとえば、会社が見舞金的に一定額を支給している場合でも、それが「賃金」と評価されれば、傷病手当金の調整対象になります。就業規則上の名称だけで判断するのではなく、その実質が問われる点には注意が必要でしょう。
企業としては、休職中の給与支給方針と傷病手当金との関係を事前に整理し、従業員に誤解を与えない説明を行うことが重要です。
傷病手当金の申請に対して会社が実施するサポート
傷病手当金の申請は従業員本人が行うものですが、実務上は会社の協力が不可欠です。特に、人事・労務担当者が関与する場面は少なくありません。
会社が担う主な役割としては、次のようなものがあります。
- 事業主記入欄(休業期間・賃金支給状況等)の正確な記載
- 申請書類の提出方法やスケジュールの案内
- 休職期間・給与支給状況の管理と記録の整合性確保
ここで注意したいのは、申請を「代行する義務」までは会社にないという点です。ただし、実務上では会社が主体となって書類を進めるケースが多いです。これは、記入ミスや情報不足によって支給が遅れれば、従業員の生活に直接的な影響があるためです。したがって、傷病手当金の申請の支援をしない場合には会社への不満や不信感につながるケースも珍しくありません。
法的義務の有無とは別に、円滑な申請をサポートする姿勢は、労務トラブルの予防や職場の信頼関係維持という観点からも、実務上きわめて重要だといえるでしょう。
休職期間中の社会保険・税金の取り扱い
休職中は給与支給の有無だけでなく、社会保険料や税金をどのように扱うかも、企業実務において非常に重要な論点となります。
対応を誤ると、未納トラブルや従業員からの不満につながりやすいため、制度の基本構造を正しく理解しておく必要があります。この章では、休職期間中の社会保険料と税金の取り扱いについて、実務目線で整理します。
社会保険料の会社負担・本人負担
健康保険・厚生年金保険といった社会保険は、休職中であっても被保険者資格が継続している限り、保険料の納付義務が発生します。
これは「実際に働いているかどうか」ではなく、「被保険者であるかどうか」で判断されるためです。
そのため、休職中であっても原則として、
- 会社負担分:従来どおり会社が負担
- 本人負担分:従業員が負担
という構造自体は変わりません。
無給休職であっても、会社負担分の社会保険料が免除されるわけではない点は、経営・人事双方にとって重要なポイントでしょう。
給与が出ない場合の保険料徴収方法
休職中に給与が支給されない場合、本人負担分の社会保険料をどのように徴収するかが実務上の課題となります。代表的な対応方法としては、以下が考えられます。
- 会社が立替え、復職後にまとめて控除する方法
- 毎月、従業員から直接振込みを受ける方法
- 賞与支給時に調整する方法(可能な場合)
いずれの方法を採る場合でも重要なのは、事前に本人へ十分な説明を行い、合意を得ておくことです。説明不足のまま立替えや一括控除を行うと、「聞いていなかった」「そんなに引かれるとは思わなかった」といったトラブルに発展しやすくなります。
また、就業規則や休職規程に社会保険料の取り扱いを明記しておくことで、実務対応をスムーズに進めやすくなるでしょう。
住民税・所得税の取り扱い
税金についても、休職中は通常勤務時とは異なる整理が必要です。
まず所得税については、給与支給がなければ源泉徴収自体が行われません。そのため、無給休職期間中に所得税を天引きすることは基本的にありません。
一方で注意が必要なのが住民税です。
住民税は前年の所得を基準に課税されるため、当年に無給であっても納税義務が消えるわけではありません。
住民税の徴収方法としては、
- 給与支給がある間は特別徴収
- 無給期間中は普通徴収に切り替え、本人が納付
といった対応が一般的です。
特別徴収から普通徴収への切替手続きが必要になるため、自治体への届出漏れがないよう注意が求められます。
休職中の社会保険・税金の取り扱いは、給与以上に複雑に感じられがちですが、基本原則を押さえたうえで丁寧な説明と事前調整を行うことが、実務トラブルを防ぐ最大のポイントだといえるでしょう。
休職制度を就業規則にどう定めるべきか
休職をめぐるトラブルの多くは、就業規則の記載が曖昧であることに起因します。
休職制度は法律で義務付けられたものではないからこそ、会社がルールを明確に設計し、文書として定めておくことが極めて重要です。この章では、実務上とくに重要となる就業規則の定め方について解説します。
休職期間・延長・復職条件の明確化
まず最優先で整理すべきなのが、休職期間に関するルールです。ここが不明確だと、「いつまで休めるのか」「復職できるのか」といった点で紛争が生じやすくなります。
就業規則には、少なくとも以下の事項を明記しておくことが望ましいでしょう。
- 休職を命じることができる事由(私傷病、その他やむを得ない事情など)
- 休職期間の上限(例:勤続年数に応じて6か月・1年など)
- 休職期間の延長可否と、その判断基準
- 復職の可否を判断する方法(主治医意見書、産業医面談など)
- 復職できない場合の取り扱い(自然退職・解雇との関係)
特に重要なのは、「休職=必ず復職できる制度ではない」という点を、規程上も明確にしておくことです。復職条件が曖昧なままだと、会社の判断が恣意的だと受け取られやすく、後の紛争リスクを高める要因になります。
休職中の給与・手当の規定例
休職中の給与については、「支給しない」のであれば、その旨を明確に記載しておく必要があります。記載がない場合、従業員側が「支払われると思っていた」と主張する余地を与えてしまいます。
一般的な規定例としては、以下のような書き方が考えられます。
- 休職期間中は原則として無給とする
- 法令または会社が特に認めた場合を除き、賃金は支給しない
- 社会保険・公的給付については別途定める
もし、見舞金や独自の休職手当を支給する制度を設ける場合は、
- 支給対象者
- 支給期間・金額
- 傷病手当金との調整有無
といった点まで踏み込んで定めておくことが重要です。
「善意」で設けた制度が、後に義務として固定化されてしまうケースも少なくありません。
トラブルを防ぐための記載ポイント
就業規則に休職制度を定める際は、単に条文を置くだけでなく、紛争予防の視点を持つことが不可欠です。実務上、特に意識したいポイントを整理します。
- 抽象的な表現を避け、判断基準をできる限り具体化する
- 会社の裁量が及ぶ部分については、その範囲を明示する
- 他の規程(懲戒、解雇、復職基準)との整合性を確保する
- 実際の運用とかけ離れた内容にしない
就業規則は「作って終わり」ではなく、「運用される前提」で設計する必要があります。現場で実行できない厳しすぎる規定や、逆に甘すぎる規定は、いずれ会社自身の首を絞める結果になりかねません。
休職制度は、従業員を守るための制度であると同時に、会社を守るための制度でもあります。だからこそ、法的視点と実務感覚の両立を意識した就業規則の整備が不可欠だといえるでしょう。
休職から復職・退職までの実務
休職制度は、休職に入った時点で終わりではありません。実務上は、復職できた場合の給与再開や、復職に至らなかった場合の退職処理・賃金精算まで含めて、一連の流れとして整理しておく必要があります。この章では、人事・労務担当者が特に判断に迷いやすい給与実務のポイントを解説します。
復職時の給与再開タイミング
復職が決定した場合、次に問題となるのが「いつから給与を支払うのか」という点です。結論としては、実際に労務の提供が再開された日から給与支払い義務が発生します。
実務では、次のようなケースが考えられます。
- フルタイムでの通常復職
→ 出勤開始日から通常どおり給与支給 - 時短勤務・段階的復職(リワーク)
→ 実際の勤務時間・勤務内容に応じて賃金を支給 - 試し出勤・慣らし勤務期間
→ 就業規則で賃金の扱いを定めていない場合、無給扱いが争点になりやすい
特に注意したいのが「復職判定は出ているが、実際には勤務していない期間」です。この期間を有給・無給のどちらとするかは、事前にルール化しておかなければトラブルの原因となります。復職に関する給与の扱いも、休職規程や復職規程の中で明確にしておくことが望ましいでしょう。
復職できない場合の自然退職・解雇の扱い
休職期間満了時点で、従業員が復職できない場合、その後の雇用関係をどう整理するかは非常にデリケートな問題です。
多くの企業では、就業規則に「休職期間満了による自然退職」を定めています。
この場合の給与実務上のポイントは以下のとおりです。
- 休職期間満了日までは無給(または規程どおりの支給)
- 自然退職日以降は賃金支払い義務は発生しない
- 解雇予告手当が不要とされるケースが多い(規程と運用が適正な場合)
ただし、休職満了=当然退職が常に有効とは限りません。復職可能性の判断が不十分だったり、会社側の配慮義務が尽くされていない場合には、退職や解雇の有効性が争われるリスクもあります。
そのため、給与を支払わない判断そのものだけでなく、退職に至るプロセス全体の合理性が問われる点には十分注意が必要でしょう。
退職時の未払い賃金・精算対応
休職中または復職直後に退職となった場合、最後に重要となるのが賃金や各種金銭の精算です。ここを曖昧にすると、退職後の紛争に直結します。
退職時に確認すべき主な項目は、次のとおりです。
- 最終勤務日までの未払い賃金の有無
- 残っている有給休暇の取り扱い(買上げ可否)
- 社会保険料の本人負担分の清算
- 会社立替分(保険料・貸付金等)の精算
無給休職期間が長期に及んでいる場合、社会保険料の立替額が高額になるケースも珍しくありません。退職時に一括請求するのか、分割対応とするのかについても、事前の説明と合意が不可欠です。
休職から復職、あるいは退職に至るまでの給与実務は、単なる計算処理ではなく、法的妥当性と従業員への説明責任が強く求められる分野です。最後まで丁寧な対応を心がけることが、不要なトラブルを防ぐ最大のポイントだといえるでしょう。
休職給与をめぐる会社側のよくあるトラブル
休職中の給与対応は、法律・就業規則・個別事情が複雑に絡み合うため、企業側が想定していなかったトラブルに発展しやすい分野です。とくに対応を誤ると、労使関係の悪化だけでなく、労基署対応や訴訟といった深刻な問題に発展する可能性もあります。この章では、実務で頻発するトラブルと、その予防策を整理します。
給与不支給をめぐる従業員との紛争
最も多いトラブルが、「休職中は無給と聞いていなかった」「給与が出ると思っていた」という認識のズレによる紛争です。会社側としては当然の無給対応でも、従業員側に十分な説明がなされていないと、不信感が一気に高まります。
典型的な紛争パターンとしては、以下が挙げられます。
- 就業規則に無給と書かれているが、説明や周知が不十分だった
- 過去の休職者には給与や手当を支給していた
- 休職命令が事実上の「会社都合」と主張される
特に注意したいのは、過去の運用実績です。就業規則上は無給であっても、これまでの慣行で支給していた場合、従業員から「黙示の合意」があったと主張されるリスクがあります。規程と実態が乖離していないか、定期的な点検が欠かせません。
メンタル不調者対応で注意すべき点
メンタルヘルス不調による休職は、給与問題と同時に「会社の安全配慮義務」が厳しく問われる分野です。対応を誤ると、単なる給与トラブルでは済まなくなります。
実務上、特に注意すべきポイントは次のとおりです。
- 休職理由が本当に私傷病といえるかを慎重に検討する
- 長時間労働やハラスメントの有無を形式的に否定しない
- 医師意見を軽視した会社独自判断をしない
メンタル不調者に対して「働けないのだから無給で当然」といった姿勢を示すと、後に「会社の対応が症状を悪化させた」と主張されるリスクがあります。給与の支給有無だけでなく、対応プロセス全体の合理性と丁寧さが重要だといえるでしょう。
労基署・訴訟リスクを避けるための対策
休職給与をめぐるトラブルが深刻化すると、労働基準監督署への申告や、最悪の場合は訴訟に発展することもあります。これを防ぐためには、事後対応ではなく、事前の制度設計と運用が何より重要です。
具体的な対策としては、以下が有効です。
- 就業規則・休職規程に給与の扱いを明確に記載する
- 休職開始時に、書面で給与・社会保険・給付制度を説明する
- 休職理由や経緯を記録として残しておく
- 判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談する
「法律上は問題ない」という一点だけで判断するのは危険です。実務では、説明不足や配慮欠如が原因で紛争に発展するケースが非常に多く見受けられます。
休職給与をめぐるリスクを最小限に抑えるためには、ルールの明確化・丁寧な説明・一貫した運用を徹底することが、会社側にとって最大の防御策になるといえるでしょう。
会社が押さえるべき休職給与対応のポイント
休職中の給与対応は、法律知識だけでなく、日々の運用や従業員とのコミュニケーションが結果を大きく左右します。場当たり的な判断を避けるためにも、会社として「何を確認し、いつ見直すべきか」を整理しておくことが重要でしょう。ここでは、人事・労務担当者が実務で意識すべきポイントをまとめます。
人事・労務担当者が確認すべきチェックリスト
休職対応が発生した際、まず確認すべき事項をチェックリストとして整理しておくと、判断のブレを防ぎやすくなります。
- 就業規則・休職規程に休職要件、期間、給与の定めがあるか
- 休職理由が私傷病・業務上・会社都合のいずれに該当するか
- 休職開始時に、給与・社会保険・公的給付について説明しているか
- 過去の同様事案と取り扱いに不整合がないか
- 記録(医師意見書、面談記録、説明書面)を適切に残しているか
これらを都度確認することで、「知らなかった」「前例と違う」といったトラブルを未然に防ぎやすくなります。特に給与不支給に関する説明は、口頭だけで済ませず、書面で残すことが望ましいでしょう。
社労士・専門家に相談すべきケース
休職給与の判断は、会社単独で抱え込むほどリスクが高まります。以下のようなケースでは、早めに社労士や弁護士などの専門家へ相談するのが賢明です。
- メンタルヘルス不調で、会社要因の有無が争点になりそうな場合
- 休職期間満了後の自然退職・解雇を検討している場合
- 過去の運用と就業規則の内容が食い違っている場合
- 従業員から賃金請求や労基署申告を示唆されている場合
「まだ問題化していない段階」での相談ほど、選択肢は広がります。事後的な対応よりも、予防的な専門家活用の方が、結果的にコストや労力を抑えられるケースが多いといえるでしょう。
休職制度を見直すタイミング
休職制度は、一度作って終わりにすべきものではありません。社会情勢や働き方の変化に応じて、定期的な見直しが求められます。
見直しを検討すべき主なタイミングとしては、次のような場面が挙げられます。
- メンタルヘルス休職が増加してきたとき
- 実際の運用で判断に迷うケースが頻発しているとき
- 労務トラブルや指導を受けた経験があるとき
- 就業規則を長期間改定していないとき
休職制度の見直しは、「従業員を厳しく管理するため」ではなく、「無用なトラブルを防ぎ、双方が納得できるルールを作るため」に行うものです。給与対応を含めた休職制度全体を定期的に点検することが、安定した労務管理につながるといえるでしょう。
まとめ|休職中の給与対応は「ルール設計」と「説明」がすべて
休職中の給与を支払う必要があるかどうかは、一律に決まるものではなく、休職理由・法律の考え方・就業規則の定め・過去の運用などを総合的に判断する必要があります。
私傷病休職では原則無給とされる一方で、メンタルヘルス不調や業務起因性が疑われるケースでは、会社側の対応次第で法的リスクが高まる点には特に注意が必要でしょう。
また、給与だけでなく、傷病手当金・社会保険料・税金の扱い、復職や退職時の精算まで含めて整理しておかなければ、後々大きなトラブルに発展しかねません。その意味で、就業規則における休職制度の明確化と、休職開始時の丁寧な説明は、会社を守るための重要な実務対応だといえます。
休職対応に少しでも不安がある場合や、
- 就業規則の内容が実態と合っていない
- メンタルヘルス休職が増えてきている
- 給与不支給をめぐり従業員との認識差を感じている
といった状況がある場合は、早めに専門家へ相談することが有効な選択肢となります。
休職制度や給与対応を見直すことは、トラブル防止だけでなく、企業としての信頼性向上にもつながります。この機会に、自社の休職制度・就業規則が現状に即した内容になっているか、一度立ち止まって確認してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人ステディでは、休職・復職の制度設計から、傷病手当金の申請サポートとった実務面までサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
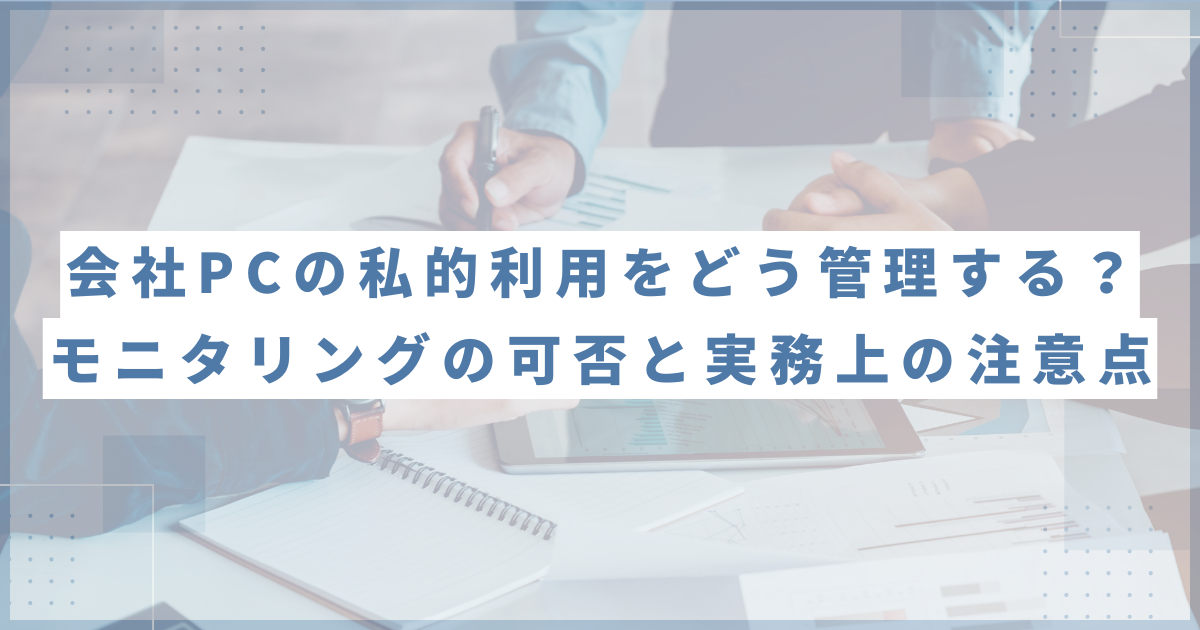 ニュース一覧2026.02.11会社PCの私的利用をどう管理する?モニタリングの可否と実務上の注意点
ニュース一覧2026.02.11会社PCの私的利用をどう管理する?モニタリングの可否と実務上の注意点 ニュース一覧2026.02.09社会保険の随時改定とは?条件・タイミング・注意点を社労士が解説
ニュース一覧2026.02.09社会保険の随時改定とは?条件・タイミング・注意点を社労士が解説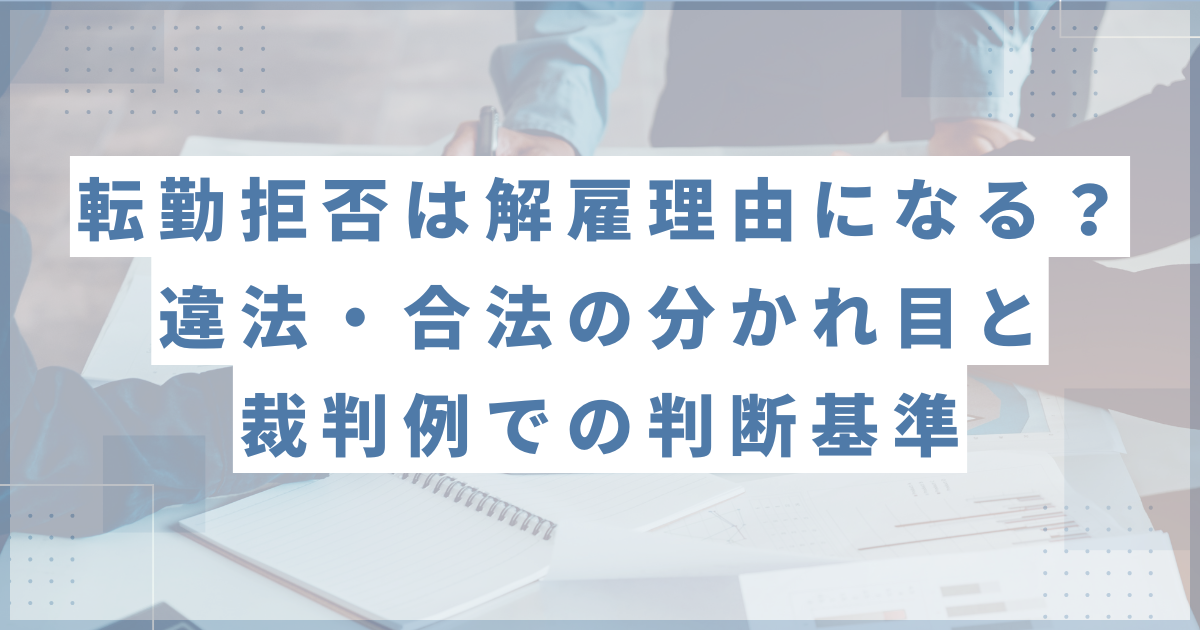 ニュース一覧2026.02.05転勤拒否は解雇理由になる?違法・合法の分かれ目と裁判例での判断基準
ニュース一覧2026.02.05転勤拒否は解雇理由になる?違法・合法の分かれ目と裁判例での判断基準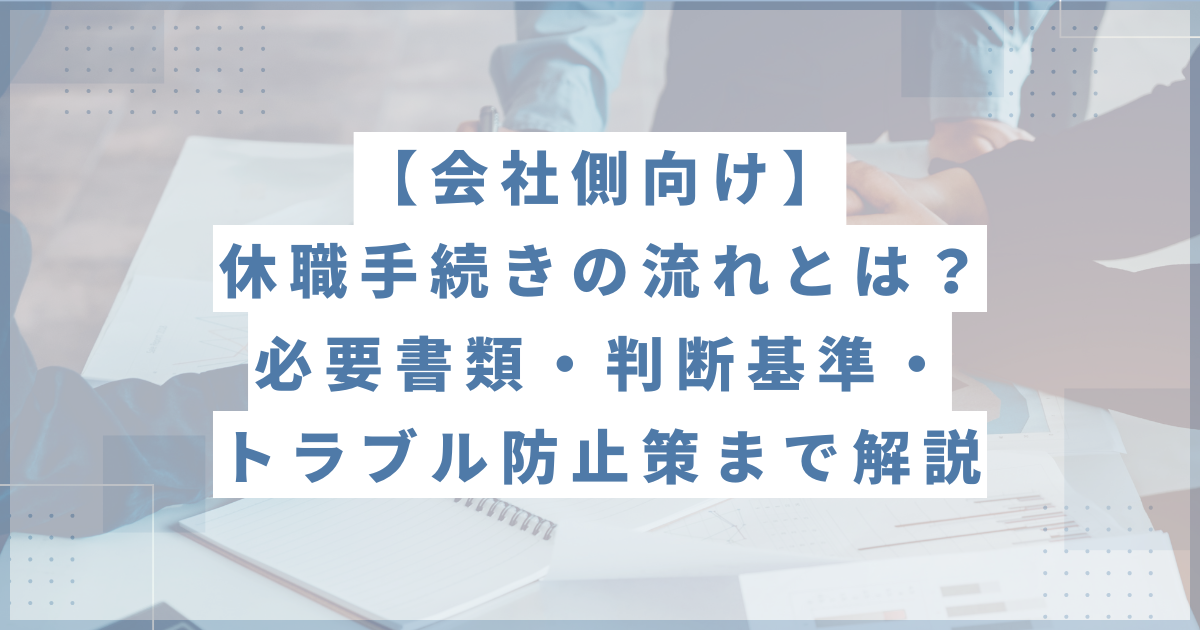 ニュース一覧2026.02.03【会社側向け】休職手続きの流れとは?必要書類・判断基準・トラブル防止策まで解説
ニュース一覧2026.02.03【会社側向け】休職手続きの流れとは?必要書類・判断基準・トラブル防止策まで解説