従業員から休職の申し出があったとき、会社側は「何から対応すべきか」「どこまで判断してよいのか」と迷いがちではないでしょうか。
休職は法律で一律に定められた制度ではないため、対応を誤るとトラブルや紛争につながるおそれもあります。一方で、制度を理由に機械的な対応をしてしまえば、職場の信頼関係を損ねかねません。
そこで、本記事では、会社側の実務に焦点を当て、休職手続きの全体像を流れに沿って整理してお伝えいたします。
必要書類の考え方、休職を認める際の判断基準、そして人事・総務が事前に押さえておきたいトラブル防止のポイントまで、実務にそのまま活かせる形で解説しますので、参考になれば幸いです。
休職制度とは?会社側が理解しておくべき基本知識
従業員から休職の申し出があった際、会社側の対応は就業規則や社内ルールに強く左右されます。にもかかわらず、「休職は当然認めなければならない」「法律で決まっている制度」と誤解したまま対応してしまうケースは少なくありません。
まずはこの章では、休職手続きを進める前提として、会社側が必ず押さえておきたい休職制度の基本的な考え方を見ていきましょう。
休職と欠勤・休業の違い
まず混同されやすいのが、「休職」「欠勤」「休業」の違いです。
これらは似た言葉に見えますが、会社側の法的義務や実務対応は大きく異なりますので、注意が必要です。
欠勤は、労働契約が継続したまま、労務提供が一時的に行われない状態を指しており、多くの場合、無給扱いとなり、勤怠管理の延長線上で処理されます。
一方、休業は、会社側の都合や法令に基づいて労務提供を停止するものです。代表例としては、育児休業や介護休業、業務上の災害による休業などが挙げられ、法律上の制度として整備されています。
これに対して休職は、労働契約を維持したまま、労務提供義務を一時的に免除する「会社独自の制度」となります。多くは私傷病やメンタル不調など、従業員の事情によって一定期間就労が困難な場合に適用されますが、法律で一律に定められている制度ではありません。
休職制度は法律上の義務ではない
会社側が特に注意すべき点は、休職制度そのものは法律上の義務ではないという点です。
労働基準法をはじめとする労働関係法令には、「休職を設けなければならない」という規定はありません。
つまり、休職を認めるかどうか、どのような条件で認めるかは、原則として会社の就業規則や社内規程によって決まります。就業規則に休職制度が定められていない場合、会社が必ず休職を認めなければならないわけではありません。
ただし、制度がないからといって一切配慮なく対応してよいわけではなく、対応を誤ると安全配慮義務違反や不当な取り扱いを問われるリスクがあります。そのため、制度の有無と実務対応は切り分けて考える必要があるでしょう。
就業規則における休職規定の役割
休職手続きを進めるうえで、会社側の判断基準となるのが就業規則です。
就業規則には、一般的に以下のような事項が定められています。
・休職を認める事由(私傷病、精神疾患など)
・休職期間の上限
・休職中の給与や社会保険の扱い
・復職の条件や手続き
・休職期間満了時の取り扱い
これらが明確に定められていることで、会社側は恣意的な判断を避け、従業員に対しても説明責任を果たしやすくなります。
逆に、休職規定が曖昧なまま運用していると、「あの人は休職できたのに、なぜ自分は認められないのか」といった不公平感につながり、後々の労務トラブルの原因になりがちです。
休職手続きは、個別対応になりやすいテーマだからこそ、まずは制度の位置づけとルールを会社側が正確に理解しておくことが、実務を円滑に進める第一歩となります。
休職の申し出があった際に会社側が最初にやること
従業員から「休職したい」「しばらく働けないかもしれない」といった相談を受けたとき、会社側の初動対応はその後の手続き全体を左右します。
この段階で対応を誤ると、不要なトラブルや紛争に発展することもあるため、感情的・場当たり的な判断は避け、冷静に事実確認を行うことが重要です。
本人からの申出内容を正確に確認する
最初に行うべきは、本人の申し出内容をできるだけ正確に把握することです。
ただ、ここで確認しておきたいのは、単に「休みたい」という意思だけではありません。
たとえば、以下の点は初期段階で整理しておく必要があります。
・就労が困難な理由(私傷病、精神的不調など)
・いつ頃から働けない状態なのか
・一時的な欠勤なのか、一定期間の休職を希望しているのか
・医療機関の受診状況
この時点では、休職を認めるかどうかの判断を急ぐ必要はありません。まずは事実関係を丁寧に聞き取り、「会社として確認が必要な事項」を整理することが目的です。
また、上司が最初の窓口になるケースも多いため、人事・総務へ速やかに情報共有する体制を取ることも重要になります。
診断書・申請書の提出を求める際の注意点
休職手続きに進む可能性がある場合、会社側は診断書や休職申請書の提出を求めることになります。
ただし、この伝え方には注意が必要です。
診断書は、休職の要否や期間を判断するための重要な資料ですが、提出を強く迫るような言い方をすると、従業員との信頼関係を損ねるおそれがあります。
そのため「就業規則上、休職の判断には診断書が必要になる」といった形で、制度上の必要性として説明することが望ましいでしょう。
また、診断書の内容についても、「病名の開示」を過度に求めることは避けるべきです。会社側が確認すべきなのは、就労可否や必要な配慮の有無であり、詳細な病状そのものではありません。
安易に受理・拒否しないための初動対応
休職の申し出があった際、「とりあえず休ませておこう」「前例がないから認めない」といった判断はリスクを伴います。
休職は、会社の制度と就業規則に基づいて判断すべきものであり、その場の雰囲気や担当者の主観で決めるものではありません。
初動対応として重要なのは、次のスタンスを明確にすることだと考えられます。
・その場で結論を出さない
・就業規則を確認したうえで判断する
・必要書類が揃ってから正式に検討する
このように段階を踏んで対応することで、会社側としても判断の根拠を明確にでき、後から「言った・言わない」の問題が生じにくくなります。
休職手続きは、この最初の対応次第で円滑にも紛糾にもなります。
だからこそ、会社側は「まず確認すべきこと」「今は判断しないこと」を意識しながら、慎重に初動対応を進める必要があるでしょう。
休職を認めるか判断する際の会社側の実務
休職の申し出に対し、必要書類が揃った段階で会社側は「休職を認めるかどうか」を判断することになります。この判断は、人事・総務の実務の中でも特に慎重さが求められる場面です。
結論だけを急ぐのではなく、就業規則と事実関係を照らし合わせながら、段階的に検討する姿勢が欠かせません。
就業規則に基づく判断フロー
休職の可否を判断する際、最初に確認すべきものは就業規則です。
多くの会社では、休職に関して以下のような要件が定められています。
・対象となる事由(私傷病、精神疾患など)
・休職を認める前提条件(一定期間の欠勤が継続していること等)
・休職期間の上限
・必要書類(診断書の提出など)
これらの要件に該当しているかを一つずつ確認し、規定に沿って判断することが基本です。
「前例ではこうだった」「本人が大変そうだから」といった理由だけで例外的な判断をすると、後のトラブルにつながりやすくなるため、避けるべきでしょう。
また、規定が複数のパターンに分かれている場合は、どの条文を適用するのかを明確にし、判断の根拠を社内で共有しておくことも重要です。
休職要件(期間・理由・対象者)の確認
就業規則を確認する際は、休職の「理由」だけでなく、「期間」や「対象者」の条件にも目を向ける必要があります。
たとえば、私傷病による休職であっても、無制限に認められるわけではなく、勤続年数に応じて休職期間の上限が定められているケースがあります。また、契約社員やパートタイム労働者が休職制度の対象外となっている場合もあります。
こうした条件を見落としたまま休職を認めてしまうと、後になって制度との整合性が取れなくなり、是正が難しくなります。
会社側としては、「誰に」「どの条件で」「どれくらいの期間」休職を認めるのかを、制度面から冷静に整理することが求められます。
判断時にトラブルになりやすいポイント
休職の判断を巡っては、会社側が意図せずトラブルを招いてしまう場面も少なくありません。特に注意したいのは、次のようなケースです。
・診断書の内容を過度に疑い、休職を認めない
・説明が不十分なまま休職を却下する
・判断基準を本人に伝えず、結果だけを通知する
休職を認めない判断をする場合であっても、その理由と根拠を丁寧に説明することが不可欠です。「会社としては認められない」という結論だけを伝えると、不公平感や不信感を生みやすくなります。
判断結果を伝える際は、就業規則の該当条文や判断プロセスを示し、「どの点が要件を満たしていないのか」を明確にすることが、無用な紛争を避けるための実務上のポイントです。
休職を認めるかどうかの判断は、会社側の裁量がある一方で、その裁量には合理性と一貫性が求められます。
制度に基づいた判断を積み重ねることが、結果的に会社と従業員双方を守ることにつながります。
休職決定後に会社側で行う具体的な手続き
休職を認める判断をした後は、速やかに社内手続きを進める必要があります。
この段階での対応が曖昧だと、休職期間中の認識違いや、復職時のトラブルにつながりかねません。ここでは、休職決定後に会社側が行うべき実務を、順を追って整理します。
休職発令通知書・辞令の作成と交付
休職を正式に決定したら、その内容を文書で明確にすることが重要です。
口頭での合意だけでは、「いつから休職なのか」「どの条件で認められているのか」といった点が曖昧になりやすく、後々の紛争の原因になります。
一般的には、休職発令通知書や休職辞令を作成し、本人に交付する流れです。この文書には、少なくとも以下の事項を記載しておくべきです。
・休職開始日と終了予定日
・適用される休職事由
・休職中の就労義務が免除されること
・復職に関する基本的な考え方
書面で正式に通知することで、会社側・従業員双方の認識を揃えることができます。
休職期間・復職条件の明確化
休職手続きにおいて特に重要なのが、「休職期間」と「復職条件」を明確にしておくことです。この点を曖昧にしたまま休職に入ると、期間満了時に判断が難航するケースが多く見られます。
休職期間については、就業規則で定められた上限を踏まえたうえで、今回の休職がどこまで認められるのかを明示します。また、延長の可能性がある場合は、その条件や再提出が必要な書類についても説明しておくとよいでしょう。
復職条件についても、「主治医の診断書の提出」「通常業務が可能であること」など、判断基準を事前に共有しておくことが重要です。
休職中ではなく、開始時点で説明しておくことで、会社側の判断が一方的だと受け取られるリスクを下げることができます。
社会保険・給与・勤怠管理の処理
休職に入ると、給与や社会保険、勤怠管理の取り扱いも通常とは異なります。これらは人事・総務が連携して対応すべき実務といえるでしょう。
多くの会社では、休職期間中は無給または一部支給とし、健康保険の傷病手当金の対象となるケースもあります。そのため、給与の支給有無や社会保険料の控除方法について、本人に事前に説明しておくことが望ましいと思います。
また、勤怠管理上も「欠勤」ではなく「休職」として処理する必要があります。処理を誤ると、勤続年数や賞与算定、評価制度への影響が生じることもあるため、社内ルールに沿った対応が欠かせません。
休職決定後の手続きは事務的な作業が中心になりますが、この段階での丁寧な対応が、休職期間中の混乱や不信感を防ぐ土台になります。
休職期間中の会社側の対応と管理実務
休職が開始すると、会社側の役割は一旦終わるように感じられるかもしれません。しかし実際には、休職期間中の対応こそが、その後の復職判断やトラブル防止に大きく影響します。
過度に干渉することなく、かつ放置もしない。そのバランスを意識した管理が求められます。
本人との連絡頻度と情報管理の考え方
休職期間中、本人とどの程度連絡を取るべきかは、会社側が悩みやすいポイントです。
頻繁な連絡は本人の負担になる一方、まったく連絡を取らない状態が続くと、状況把握ができず、復職判断が難しくなります。
一般的には、就業規則や社内ルールに基づき、一定の間隔で状況確認を行う運用が望ましいとされています。たとえば、「月に1回、状況報告を受ける」「期間満了が近づいた段階で連絡を取る」など、あらかじめ方針を決めておくことで、双方の認識を揃えやすくなります。
また、連絡内容についても注意が必要です。業務上の指示や復帰を急かすような発言は避け、体調や就労可否に関する事実確認にとどめることが重要です。
やり取りの内容は、後から確認できるよう記録として残しておくと、管理面でも安心です。
診断書の再提出・状況確認の実務
休職期間中は、必要に応じて診断書の再提出を求めることがあります。これは、会社側が回復状況や就労可能性を把握し、今後の対応を検討するためのものです。
再提出を求めるタイミングや頻度については、就業規則に定めがあるかを必ず確認してください。規定がない場合でも、「一定期間ごとに提出を求める」といった運用ルールを設けておくと、対応が属人的になりにくくなります。
なお、ここでも重要なのは、診断書の内容を過度に詮索しないことです。
確認すべきなのは、就労の可否や必要な配慮の有無であり、詳細な病状や私的な情報まで踏み込む必要はありません。
休職期間満了が近づいた際の対応
休職期間の満了が近づいたら、会社側は次のステップを見据えた対応を進める必要があります。
具体的には、「復職が可能か」「休職期間を延長するのか」「規定に基づき次の措置を取るのか」を検討する段階です。
この時点で慌てないためにも、満了日の少し前に本人へ連絡を取り、診断書の提出期限や今後の流れを説明しておくことが重要でしょう。
事前の案内がないまま満了日を迎えると、「聞いていなかった」「突然決められた」といった不満につながりやすくなります。
休職期間中の管理は目立ちにくい業務ですが、会社側の姿勢が問われる場面でもあります。
適切な距離感を保ちながら、制度に基づいた対応を継続することが、円滑な復職やトラブル防止につながります。
復職・復帰判断で会社側がやること
休職期間が終了に近づくと、会社側は「復職を認めるかどうか」という判断を行うことになります。この場面は、休職対応の中でも特にトラブルが生じやすい局面です。
判断基準や手続きを曖昧にしたまま進めると、従業員との認識のズレが顕在化しやすくなるため、制度と実務の両面から慎重に対応する必要があります。
復職可否の判断基準と診断書の扱い
復職判断の基本となるのは、就業規則に定められた復職要件。
多くの場合、「通常業務に耐えられる状態であること」「主治医による復職可能の診断書が提出されていること」などが基準として設けられています。
ここで重要なのは、診断書が提出されたからといって、必ず復職を認めなければならないわけではない点です。
会社側は、診断書の内容を踏まえつつ、業務内容や職場環境を考慮し、実際に就労可能かどうかを総合的に判断します。
一方で、医学的な判断を会社側が独自に否定することは避けるべきです。
復職を認めない判断をする場合は、「業務上必要な能力との関係」や「就業規則上の要件」を根拠として整理し、感覚的な理由にならないよう注意してください。
試し出勤・配置転換の検討
復職判断に迷う場合や、いきなり通常業務に戻すことが不安な場合には、段階的な復帰を検討することもあります。
代表的な方法が、いわゆる試し出勤や、業務内容を限定した形での復職です。
試し出勤を行う場合は、「正式な復職ではない期間」であることを明確にし、賃金の扱いや評価への影響を事前に整理しておく必要があります。
また、配置転換や業務量の調整を行う際も、本人の希望だけでなく、職場全体への影響を踏まえた判断が求められます。
これらの措置は、あくまで復職を円滑に進めるための手段であり、無期限に続けるものではありません。期間や目的を明確にしたうえで運用することが、会社側の実務上のポイントです。
復職不可の場合の対応と注意点
検討の結果、復職が困難と判断されるケースもあります。
その場合でも、会社側は感情的な対応を避け、制度に基づいた手続きを踏むことが不可欠です。
復職不可とする理由、判断に至った経緯、今後の取り扱いについては、本人に対して丁寧に説明する必要があります。
説明が不十分なまま次の措置に進むと、不当解雇や不利益取扱いを主張されるリスクが高まります。
また、休職期間満了後の取り扱いについては、就業規則の規定に従うことが前提となります。
会社側としては、「制度上どうなるのか」「どこまで配慮したのか」を説明できる状態を整えておくことが重要です。
復職判断は、会社と従業員の今後の関係を大きく左右します。だからこそ、結論だけでなく、そのプロセスを重視した対応が求められます。
休職手続きを巡る会社側のよくあるトラブルと防止策
休職対応は制度に沿って進めていても、判断や伝え方次第でトラブルに発展することがあります。
特に、「休職を認める・認めない」「期間をどう扱うか」といった局面では、会社側の説明不足や対応のばらつきが問題になりがちですので、ここでは、実務上よく見られるトラブルと、その防止策を整理します。
休職を認めなかった場合のリスク
休職の申し出に対して、会社側が「制度上認められない」と判断すること自体は珍しくありません。ただし、その判断の伝え方や根拠が不十分だと、後に大きな問題へと発展する可能性があります。
たとえば、就業規則を確認せずに口頭で休職を拒否したり、「前例がない」「忙しいから」といった理由だけを伝えたりすると、本人から不当な取り扱いだと受け取られやすくなります。
防止策として重要なのは、次の点です。
・就業規則の該当条文を根拠に判断する
・なぜ要件を満たさないのかを具体的に説明する
・書面や記録として判断過程を残す
結論だけでなく、プロセスを説明できる状態を整えておくことが、会社側のリスク低減につながります。
休職期間の延長・打ち切りを巡るトラブル
休職期間が満了に近づいた際、「もう少し休ませてほしい」という相談を受けるケースも少なくありません。このとき、対応を曖昧にするとトラブルになりやすくなります。
特に問題になりやすいのが、明確な基準を示さないまま延長を認めたり、逆に突然打ち切ったりするケースです。
本人としては「前回は認めてもらえたのに」「急に方針が変わった」と感じ、不信感を抱きやすくなります。
こうした事態を防ぐためには、以下の点を徹底することが重要です。
・休職期間の上限を事前に明示する
・延長の可否や条件を就業規則に基づいて判断する
・満了前に十分な説明と案内を行う
一貫したルール運用ができていれば、判断結果に対する納得感も高まりやすくなります。
人事・総務が事前に整備しておくべき体制
休職対応のトラブルは、個別案件の問題というより、社内体制の未整備が原因となっていることも少なくありません。
担当者ごとに対応が異なったり、上司任せになっていたりすると、判断基準がぶれやすくなります。
そのため、人事・総務としては、次のような体制を整えておくことが望ましいでしょう。
・休職対応の基本フローを社内で共有する
・判断や説明を人事部門が一元的に管理する
・就業規則と実務運用のズレを定期的に見直す
休職は突発的に発生することが多いテーマです。
だからこそ、事前にルールと対応方針を整理しておくことで、いざというときにも落ち着いて対応でき、不要なトラブルを防ぐことができます。
休職対応を円滑に進めるために会社側が意識すべきこと
休職手続きは、単なる事務処理ではなく、会社側の判断力と運用姿勢が問われる実務です。
制度の理解が不十分なまま対応すると、従業員との信頼関係を損ねたり、後の労務トラブルにつながったりする可能性があります。
本記事で見てきたとおり、休職制度は法律で一律に義務付けられているものではなく、就業規則に基づいて運用される会社独自の仕組みです。だからこそ、申し出の段階から復職判断に至るまで、一貫して「規則に基づく対応」が求められます。
特に重要なのは、次の3点です。
まず、初動対応では結論を急がず、事実確認と制度確認を優先することです。
その場の印象や感情で判断せず、「確認が必要な事項」と「今は判断しない事項」を切り分ける姿勢が、後の混乱を防ぎます。
次に、休職決定後や休職期間中も、放置せず、過干渉にもならない適切な距離感を保つことです。
連絡頻度や診断書の扱いをルール化し、対応を属人化させないことで、会社側の説明責任を果たしやすくなります。
そして、復職や期間満了の場面では、判断結果だけでなく、そのプロセスを丁寧に伝えることが欠かせません。
復職可否や次の措置について、就業規則を根拠に説明できる状態を整えておくことが、会社側のリスク管理につながります。
休職対応は、どの会社でも突然直面する可能性があります。
だからこそ、個別対応に頼るのではなく、制度と実務の両面から準備を整え、誰が対応しても同じ判断ができる体制を作っておくことが、安定した労務管理の土台となります。
社会保険労務士法人ステディでは、経営者のお考えや会社の方針に沿った休職・復職制度の導入を支援していますので、もしお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
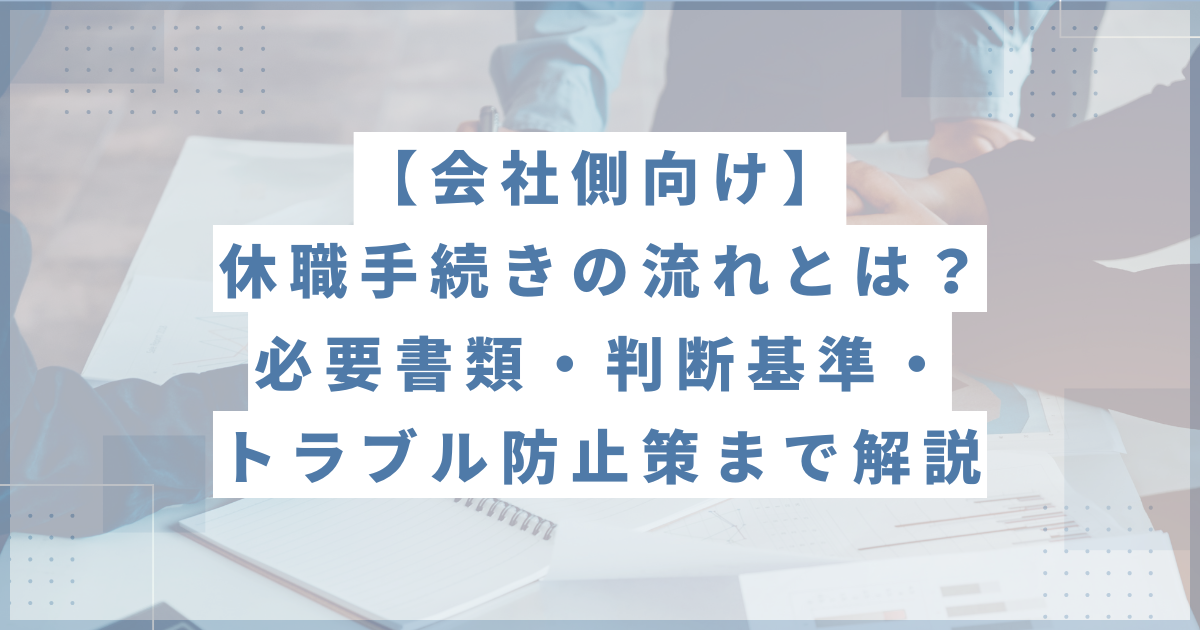 ニュース一覧2026.02.03【会社側向け】休職手続きの流れとは?必要書類・判断基準・トラブル防止策まで解説
ニュース一覧2026.02.03【会社側向け】休職手続きの流れとは?必要書類・判断基準・トラブル防止策まで解説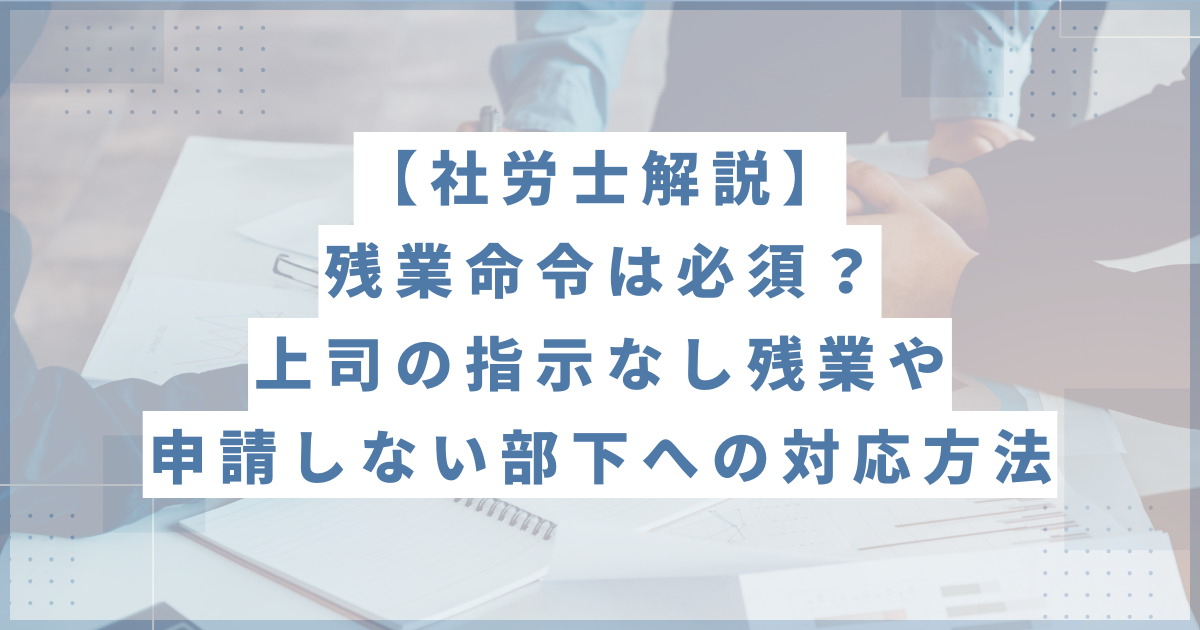 ニュース一覧2026.02.02【社労士解説】残業命令は必須?上司の指示なし残業や申請しない部下への対応方法
ニュース一覧2026.02.02【社労士解説】残業命令は必須?上司の指示なし残業や申請しない部下への対応方法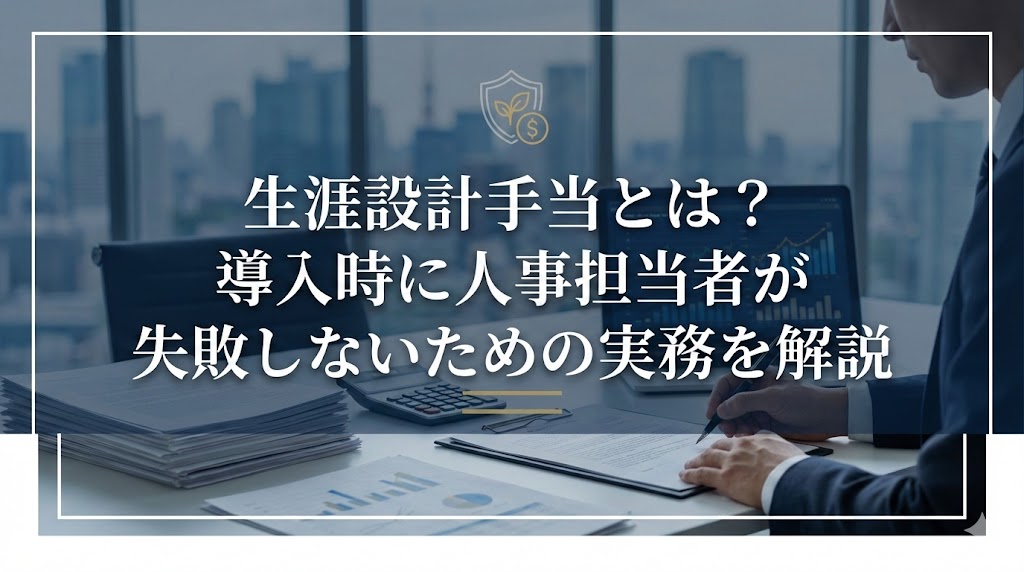 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説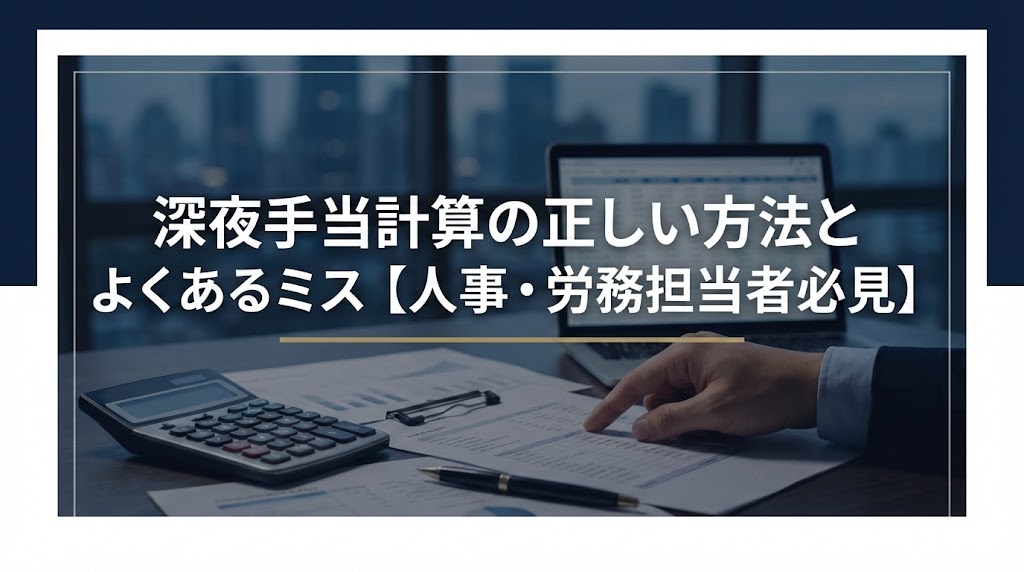 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
