「法定休日ってそもそも何?」「所定休日とはどう違うの?」「休日出勤したら本当に35%の割増賃金が必要なの?」
このような疑問を抱える経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。
お客様から「土日を休みとしている完全週休2日制度ですが、この場合は土曜日に出社した場合も休日出勤として割増賃金が必要ですか?」といったご相談もございます。
本記事では「法定休日」の基本から実務上の注意点までを専門家の視点でわかりやすく解説します。
労働基準法で定められた最低限の休息日である法定休日は、適切に理解し管理しなければ、思わぬ労務トラブルや割増賃金の支払いミスにつながりかねません。
所定休日との違い、割増賃金のルール、振替休日や代休の取り扱いも含めて、今すぐ現場で活用できる知識をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
法定休日とは?基本の定義と法的根拠
働き方改革や労働時間の適正化が叫ばれる中、「法定休日」は企業と従業員の双方が正しく理解しておくべき重要な制度です。
単なる「会社が決めた休み」ではなく、法律に基づき必ず設けなければならない休みの日を意味します。
まずは、法定休日の定義と、それがなぜ必要なのかという背景を、専門家の視点も交えてわかりやすく解説します。
労働基準法第35条に基づく法定休日の定義
法定休日は、労働基準法第35条で明確に定められた制度であり、「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定されています。
(休日)
e-GOV「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」より
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
この条文のポイントは以下のとおりです。
- 週に1回の休日を原則とする
- 変形労働時間制を採用している場合でも、4週間に4日以上の休日を与えることが必要
この規定により、最低限の休息時間が法律で保障されており、これを満たさない雇用契約や労働実態は違法となります。
なお、法定休日は「最低限の義務」として定められているものであり、それ以上の休日(いわゆる所定休日)は企業が自由に定めることができます。
例えば、完全週休2日制の場合、多くの企業では「日曜日を法定休日」「土曜日を所定休日」として設定しているケースが多いです。どちらが法定でどちらが所定かを明記しておくことが、後々のトラブル回避につながります。
法定休日の目的と企業の義務
法定休日制度の目的は、労働者に十分な休息を与え、過重労働による健康被害やモチベーションの低下を防ぐことです。特に長時間労働が問題視されている日本において、法定休日は「健康を担保するための最低限の休息日」として位置していると言えるでしょう。
企業に課せられている主な義務は以下の通りです。
- 週1回以上の休日の確保
- これは法的義務であり、違反した場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 法定休日の特定と管理
- 労務管理上、就業規則やカレンダーに「どの日が法定休日か」を明示しておくことが重要です。曖昧なままだと、休日出勤時の割増賃金の計算根拠が不明確になり、労使トラブルの原因にもなります。
- 休日労働に対する割増賃金の支払い
- 法定休日に労働させた場合には、通常賃金の35%以上の割増賃金を支払う必要があります。これは所定休日の労働とは区別されるべきで、賃金の扱いも異なります。
企業が法定休日を軽視すると、単なるコンプライアンス違反にとどまらず、従業員のモチベーション低下や採用難につながる可能性もあります。持続的な組織運営のためにも、法定休日の適正な管理と運用は欠かせません。
法定休日と所定休日の違いを理解しよう
「休日出勤をしたら割増賃金がもらえる」とよく聞きますが、実は「どの休日に働いたか」によって、その割増率や企業の義務は大きく異なります。重要なポイントは「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」の違いの理解です。この章では、それぞれの定義と、給与や労務管理における具体的な違いをわかりやすく解説します。
所定休日(法定外休日)とは何か
所定休日とは、企業が独自に定める休日のことを指し、法定休日とは区別されます。
たとえば、労働基準法で義務づけられているのは「週に1回以上の休日」(=法定休日)のみですが、週休2日制を採用している企業の多くは、法定休日に加えてもう1日を所定休日として設定しています。
例:週休2日制(月〜金が勤務日、土日休み)
- 日曜日:法定休日
- 土曜日:所定休日(=法定外休日)
所定休日は、労働基準法によって義務付けられているものではないため、企業が自由に決定できる反面、法的保護の範囲外となる部分もあるため注意が必要です。
法定休日と所定休日の割増賃金の違い
「休日出勤に対してどれだけの割増賃金が必要か」は、出勤日が【法定休日】か【所定休日】かによって異なります。
| 区分 | 割増率 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 法定休日出勤 | 35%以上(法定休日の労働時間全てが対象) | 労働基準法第37条 |
| 所定休日出勤 | 25%以上(1週40時間・1日8時間を超える部分のみ) | 労働基準法第37条 |
法定休日に労働させた場合には、休日労働とみなされ、所定労働時間を超えていなくても35%以上の割増賃金が必要です。一方で、所定休日に出勤した場合は、通常の労働時間として扱われるため、1日8時間を超えたり、週40時間を超えた労働に対して、割増率が25%以上となります。
また、以下のような違いもあります。
- 法定休日出勤:原則として36協定(休日労働の同意)と割増賃金の支払いが必須
- 所定休日出勤:労働時間の合計次第では、通常賃金のみで済むケースもある
企業としては、就業規則や勤務カレンダー上で「どの日を法定休日とするか」を明確にすることが重要です。それにより、休日出勤の際の賃金トラブルを未然に防ぐことができます。
法定休日の特定とその必要性
法定休日は「週に1日以上の休み」として法律で定められていますが、実務においてはその「特定」が非常に重要です。
特定せずに運用を続けていると、割増賃金の計算や労使トラブルの原因になりかねません。この章では、法定休日をあらかじめ明示しておくことのメリットとリスク、そして就業規則での適切な記載方法について解説します。
法定休日を特定するメリットとリスク
法定休日を明確に定めておくことには、以下のようなメリットがあります。
- 休日出勤時の割増賃金計算が明確になる
- 「法定休日に出勤したのか、それとも所定休日に出勤したのか」が明確になるため、35%以上の割増が必要かどうか判断しやすくなります。
- 労使トラブルを予防できる
- 「どの日が法定休日か」の認識のズレによって、割増賃金の未払いや説明不足が起こるケースは少なくありません。事前に特定しておくことで、認識の統一が図れます。
- 監督署対応がスムーズになる
- 労働基準監督署からの調査時に、休日の扱いが明確であるかどうかは確認項目の一つです。法定休日が特定されていれば、法令遵守の観点からもプラスに働きます。
一方、特定しないことによるリスクも存在します。
- 休日労働の取り扱いが曖昧になる
- 法定休日の特定がないと、「この日が法定休日かどうか」が後から争点になる場合があり、結果として割増賃金の支払い義務を巡るトラブルが発生します。
- 結果として企業が不利な立場に立たされる可能性
- 法定休日を曖昧にしていると、労働者側に有利な解釈がなされるケースが多く、過去の出勤分について追加支払いを求められるリスクもあります。
就業規則への法定休日の記載方法
就業規則には、休日に関する項目を設けることが義務付けられています。その中で「法定休日」と「所定休日」を明確に区別して記載することが、実務上非常に重要です。
(休日)
第○条 会社の休日は、原則として次のとおりとする。
(1)土曜日
(2)日曜日
(3)国民の祝日
2.前項に定める休日のうち法定休日は、日曜日とする。
このように、具体的な曜日や日付を記載することで、誰が見ても分かりやすく、管理や対応もしやすくなります。また、業務の性質上、曜日を固定できない場合は、「シフト表により定める日」などと記載して柔軟に運用することも可能です。
さらに、変形労働時間制や交代制勤務の場合は、「4週4日制により、あらかじめシフトにより法定休日を設定する」などの文言を追記すると、制度上の整合性も保たれます。
このように、就業規則での記載は形式的なものではなく、トラブル予防・法令遵守の観点からも極めて重要な役割を果たします。
法定休日に関する労働のルールと割増賃金
企業の業務都合や人手不足などの理由により、やむを得ず法定休日に従業員を出勤させることがあります。しかし、その場合には事前に法的な手続きを踏み、適正な割増賃金を支払う必要があります。この章では、法定休日に労働させる際に必要となる「36協定(サブロク協定)」と、割増賃金の具体的な計算ルールについて解説します。
法定休日に労働させる際の36協定の必要性
労働基準法第36条では、労働者を「時間外」または「休日」に労働させる場合、労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。
つまり、法定休日に従業員を働かせる場合でも、事前に36協定が締結されていないと、その労働自体が違法となります。
【36協定のポイント】
- 誰に適用するか(対象者)
- どのような業務で、どれくらいの時間働かせるか(内容)
- 協定期間と署名捺印(有効期間)
特に、36協定には「休日労働をさせる可能性があること」も明記する必要があります。
時間外労働のみを記載していても、休日労働には適用されません。対象となる業務や上限時間なども、できる限り具体的に設定しておくことが重要です。
なお、36協定を結ばずに法定休日に出勤させると、労働基準法違反として行政指導や罰則の対象になりますので、企業にとってもリスクが高い行為です。
法定休日労働時の割増賃金の計算方法
法定休日に労働させた場合には、通常の賃金に加えて35%以上の割増賃金を支払うことが労働基準法で義務付けられています。
【計算式の例】
通常時給:1,200円
法定休日の労働時間:8時間
割増率:35%
割増賃金 = 1,200円 × 1.35 × 8時間 = 12,960円
ここで注意すべきポイントは、時間外労働とは別枠での割増となる点です。所定労働時間内であっても、法定休日であれば必ず割増が発生します。
よくある誤解としては、
- 「月の所定労働時間を超えていないから割増は不要」→ 法定休日なら必ず割増が必要
- 「代休を与えれば割増は不要」→ 代休を与えても割増賃金の支払い義務は残る
企業としては、法定休日労働を例外的なものと位置づけ、あらかじめ労働者に説明し、36協定の締結と運用を適正に行うことが求められます。また、就業規則や給与規程にも割増賃金の取り扱いを明記しておくと、トラブル防止にもつながります。
振替休日と代休の違いとその取り扱い
法定休日に従業員を出勤させた場合、その代わりに他の日を休ませる「振替休日」や「代休」という制度がありますが、この2つには法律上・実務上の明確な違いがあります。特に割増賃金の要否や就業規則上の取り扱いに大きく影響するため、正しく理解しておくことが重要です。この章では、それぞれの定義と割増賃金の違いについて詳しく解説します。
振替休日とは?適用条件と割増賃金の有無
振替休日とは、あらかじめ予定されていた法定休日を他の日に移す制度のことです。たとえば、日曜日が法定休日である会社で、日曜に出勤が必要となった場合、前もって水曜日を法定休日としておけば、その日は「振替休日」となります。
【振替休日の適用条件】
- 法定休日に出勤させる「前に」、事前に振替日を指定すること
- 振替先は、直近の労働日(1週間以内など)であることが望ましい
- 会社の就業規則や労使協定に、振替休日制度が明記されていること
振替休日における割増賃金の扱いは、振替休日を事前に正しく設定した場合、出勤した日(本来の法定休日)は労働日扱いになるため、休日労働の割増賃金(35%)は不要となります。
ただし、振替の手続きを怠った場合には「代休」と見なされ、割増賃金の支払い義務が生じます。制度の運用には十分な注意が必要です。
代休とは?取得条件と割増賃金の扱い
代休とは、法定休日に出勤した後に、その代わりとして別の日に休みを与える制度です。振替休日と異なり、「事前に休日の振替を設定していない」ケースで適用されます。
【代休の特徴】
- 法定休日に出勤した「後に」与えられる休み
- 労働義務がすでに発生しているため、出勤日の割増賃金は発生する
- 休日労働を帳消しにする性質はなく、休息の機会を与えるにとどまる
代休における割増賃金の扱いは、代休を与えた場合でも、法定休日に出勤した分の割増賃金(35%以上)の支払い義務は残ります。
例えば、日曜日に8時間出勤(法定休日)→水曜日に代休を付与した場合、日曜日の勤務分には割増賃金が必要になります。水曜日の休みはあくまで休息の提供であり、賃金の支払い義務には影響しません。
このように、「振替休日」は事前対応で割増賃金を抑えることができる一方、「代休」は事後対応のため、原則として休日労働分の割増賃金が発生します。企業としては、就業規則等で制度の定義や手続きを明文化し、運用ルールを社内で徹底しておくことが不可欠です。
法定休日に関するよくある質問(FAQ)
法定休日について調べていると、「祝日との違いは?」「特定しないとどうなるの?」といった素朴な疑問が生まれることがあります。ここでは、実務で頻繁に寄せられる質問を取り上げ、わかりやすく解説します。正しい知識を持つことで、労務管理の精度が高まり、トラブル防止にもつながります。
法定休日は祝日と同じですか?
結論からいうと、法定休日と祝日はまったくの別物です。
| 項目 | 法定休日 | 祝日(国民の祝日) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 労働基準法 第35条 | 国民の祝日に関する法律 |
| 法的義務 | 毎週1日以上の休日を付与義務 | 休みにするかは会社の裁量 |
| 休業の強制力 | あり(企業に付与義務あり) | なし(企業判断による) |
| 割増賃金 | 出勤時は35%以上の割増賃金が必要 | 出勤しても通常の労働時間扱い (割増義務は原則なし) |
たとえば「日曜日が法定休日、月曜日が祝日(成人の日)」というケースでは、日曜は法律で定められた必須の休み、祝日は企業が休みにしていれば休日、という扱いになります。
つまり、祝日が自動的に法定休日になるわけではなく、企業がどの日を法定休日と定めているかによって対応が変わるのです。そのため、就業規則等で「法定休日と祝日の関係」をきちんと明記しておくことが望ましいでしょう。
法定休日を特定しないとどうなりますか?
法定休日を特定していない企業は、思わぬリスクを抱えることになります。主なリスクとしては
- 休日出勤時に割増賃金の根拠が不明確になる
- 法定休日が明示されていないと、「この日の出勤は法定休日労働に該当するのか?」という判断があいまいになり、割増賃金の計算や支払いに誤りが生じやすくなります。
- 従業員とのトラブルの原因になる
- 「法定休日に出勤したと思っていたので、休日手当が支給されると思っていた」等の従業員との認識のずれが生じやすく、不満や苦情、場合によっては未払賃金の請求につながることもあります。
- 労働基準監督署からの是正指導の対象になる
- 監査や調査の際に、休日管理の不備が指摘され、改善指導や罰則を受けるリスクも否定できません。
このように、法定休日を曖昧にしていると、労務管理の根幹に関わる問題に発展しかねません。特定することで、企業は休日出勤のルールを明確にでき、従業員側も自らの労働条件を正しく理解しやすくなります。
そのため、「就業規則や勤務表などで、どの曜日を法定休日とするかを明示しておく」ことが、安定した人事労務運営の第一歩といえるでしょう。
まとめ:法定休日の理解は労務トラブル防止の第一歩
本記事では、法定休日の基本的な定義から、所定休日との違い、割増賃金の考え方、そして振替休日・代休の取り扱いまでを網羅的に解説しました。特に、法定休日を「特定しているかどうか」が実務における重要な分かれ道であり、就業規則への明記や36協定の整備は、企業リスクの軽減に直結します。
正確な知識を持ち、法定休日を適切に運用することは、従業員の満足度向上と、企業の信頼性向上にもつながります。
もし現在、就業規則の整備や休日の取り扱い、割増賃金の算定などでお悩みの点がありましたら、どうぞお気軽に弊社までご相談ください。労務の専門家として、貴社の状況に合わせた最適なアドバイスをご提供いたします。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
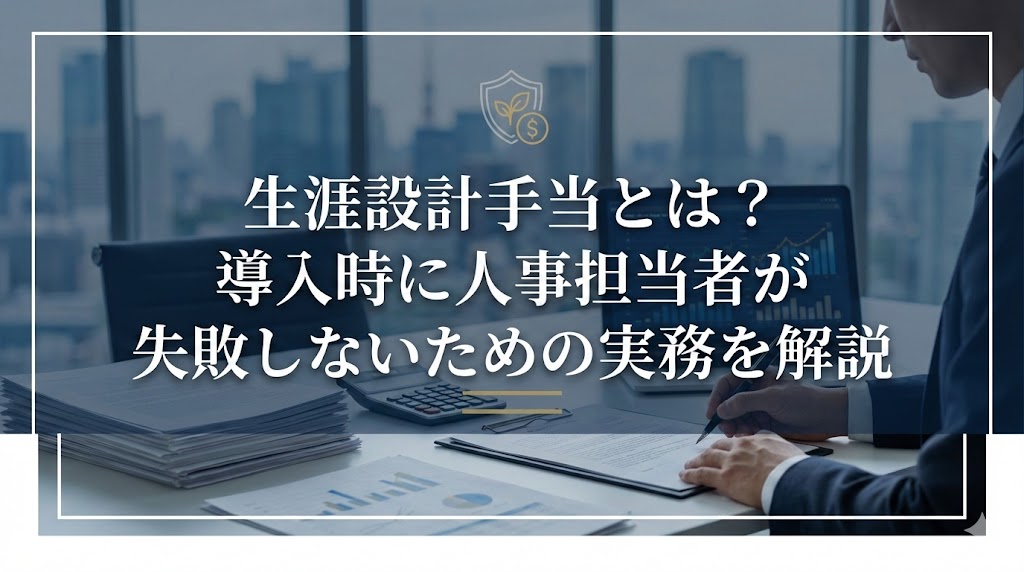 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説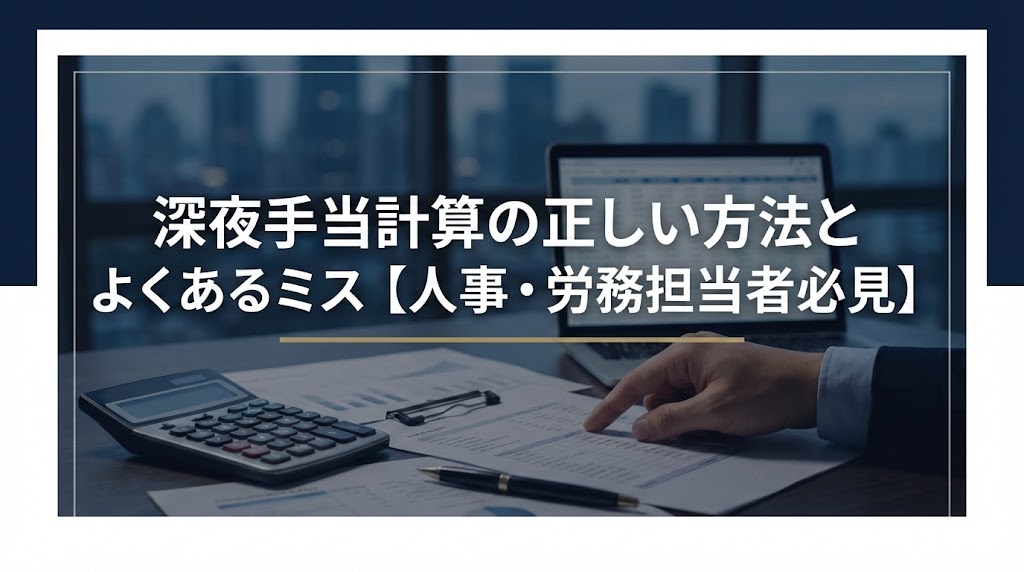 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】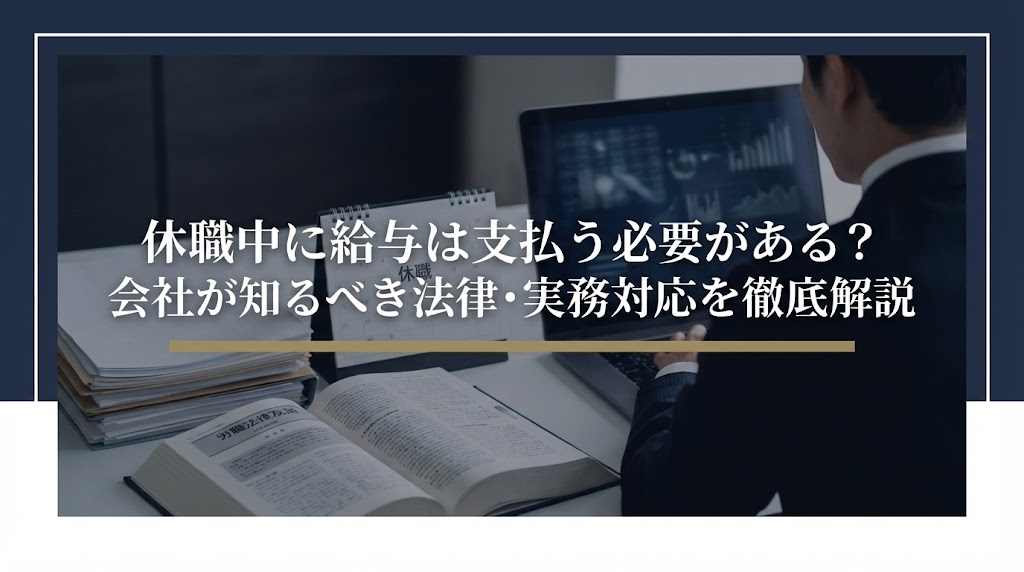 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説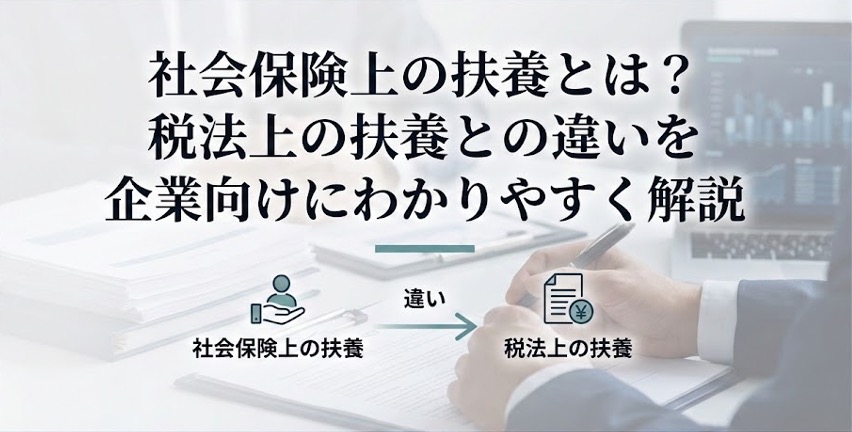 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説

