「役員に有給休暇はあるのか?」
経営者の方からいただくことがあるこの質問ですが、明確に答えられる方は意外と少ないかもしれません。労働者には当然のように付与される年次有給休暇ですが、役員という立場になると、その扱いは一変します。ただし、すべての役員が一律に対象外というわけではありません。
本記事では、
- 取締役などの一般的な役員
- 使用人兼務役員
- 執行役員
- 名ばかり役員
といったさまざまなケースごとに、有給休暇の法的取り扱いや労働者性の判断基準、企業として注意すべき実務ポイントをわかりやすく解説します。
制度の正しい理解と、リスクを回避するための社内対応のヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。
役員に有給休暇は原則なし?その理由と例外とは
会社で働く従業員には「年次有給休暇」が与えられますが、これが「役員」にも適用されるのかどうかは意外と迷われる方もおられるのではないでしょうか。
とくに中小企業では、家族経営や代表者自らがプレイヤーを兼ねるケースも多く、役員が「有給を取っていいのか」といった疑問を持つことも少なくありません。本章では、役員と有給休暇の関係について、制度上の位置づけとその背景を詳しく解説します。
労働基準法と役員の関係性
労働基準法は、「労働者」の保護を目的とした法律です。
ここでいう「労働者」とは、会社と雇用契約を結び、指揮命令のもとで働く人を指します。一方で、「取締役」や「監査役」などの役員は、会社との関係が「委任契約」にあたるため、法律上は労働者とは見なされません。
つまり、労働基準法の保護対象外である役員は、原則として年次有給休暇などの制度の適用を受けることがないのです。これにより、「会社の役員である以上、有給は使えない」とされるのが基本的なルールです。
ただし、後述の「使用人兼務役員」のように、実質的に労働者と同様の勤務実態が認められる場合には、労働基準法の適用が一部認められる可能性もあります。したがって、役員といってもその勤務形態や契約内容によって、法律上の取り扱いが異なる点に注意が必要です。
役員に有給休暇が付与されない理由
役員に有給休暇が付与されない理由は、端的にいえば「雇用契約が存在しないから」です。
年次有給休暇は、一定の勤務日数や勤続年数を満たした【労働者】に対して、法律に基づき会社が付与する義務を負うものです。
しかし、役員は一般的に会社の経営を担う立場であり、その勤務に関する自由度も高く、「労働時間の管理」や「雇用の指揮命令関係」が明確ではない場合がほとんどです。
そのため、以下のような点が理由となり、役員は有給休暇制度の対象外とされています。
- 雇用契約ではなく、委任契約である
- 勤務時間や業務内容が自己裁量に委ねられている
- 前提として労働基準法上の「労働者」に該当しない
企業の実務においても、「役員に有給を付与してもよいのか」と迷う場面はあるかもしれませんが、法律上は“原則として認められない”と理解しておくことが大切です。
ただし、役員報酬の支給形態や役員規程によって独自に「休暇制度」を設けることは可能であり、それが社内制度として運用されている企業も存在します。
こうした判断には、役員の実態や契約形態、就業規則との整合性などを含めて検討する必要があります。「形式」ではなく「実態」に基づいた判断を行い、法令遵守と実務のバランスを取る視点が求められる場面といえるでしょう。
使用人兼務役員の有給休暇の取り扱い
「役員には有給休暇がない」という原則の中で、例外的に有給休暇の対象となりうるのが「使用人兼務役員」です。
この立場は、経営者であると同時に、現場の業務に従事する“従業員”としての側面も持ち合わせているため、扱いが複雑です。ここでは、「使用人兼務役員とは何か」から、「有給休暇の付与が認められる条件」や「企業が取るべき実務対応」について、専門家の視点も交えて詳しく解説します。
使用人兼務役員とは何か?
使用人兼務役員とは、会社の取締役などの役員でありながら、現場で従業員としての業務も行っている人物を指します。
たとえば、取締役でありながら営業部長として営業成績に責任を持つような場合が該当します。
このような兼務が認められるのは、以下のような実態がある場合です。
- 業務内容が他の一般従業員と同様である
- 勤務時間や勤務場所などの労働条件が明確に管理されている
- 指揮命令系統の中で業務を遂行している
- 業務報酬が「役員報酬」と「給与」に区分されている
このような兼務役員は、法的には「労働者性」が認められる可能性があるため、労働基準法に基づく有給休暇の付与対象となる場合があります。
有給休暇付与の判断基準と実務対応
使用人兼務役員に有給休暇を付与すべきかどうかは、その「労働者性」がどこまで認められるかがカギです。具体的には、次のような点を基準に判断されます。
- 指揮命令関係があるか
- 労働時間の管理がされているか
- 業務の遂行が会社の指示に基づいているか
- 給与の支給形態が、役員報酬と明確に区分されているか
これらを総合的に見て、労働者としての実態が認められれば、通常の従業員と同じく年次有給休暇の付与が必要です。
実務的な観点としては、兼務の事実を社内で明確にし、職務分掌や雇用契約書、役員規程などに記載しておくことで「役員」「使用人兼務」のどちらに該当するのか明確になり、トラブルも防止できるでしょう。また、給与と役員報酬を明確に分けて支給し、源泉徴収区分も整理しておきましょう。
従業員としての立場がある場合には、勤怠管理システムを利用して労働時間を記録したり、有給休暇の取得履歴を他の従業員と同様に管理することが求められます。
企業としては、「役員だから有給は関係ない」と一括りにせず、使用人兼務役員としての勤務実態に即して、就業規則や労務管理の体制を整えておくことが法的リスクの回避にもつながります。
社会保険労務士の立場としても、こうした線引きは労働基準監督署の調査や、万が一の労務トラブルにおいて重要な論点になるため、早期に見直しや整備を行うことを推奨しています。
執行役員の有給休暇の取り扱い
近年、多くの企業が導入している「執行役員制度」ですが、この立場にある人が有給休暇を取得できるかどうかについては、誤解されやすいポイントです。
特に、執行役員が「労働者」なのか「経営者」なのかによって、労働基準法の適用範囲が大きく異なります。本章では、執行役員の法的な位置づけを整理した上で、有給休暇の取扱いについて実務の視点から解説します。
執行役員の法的立場と労働者性
執行役員とは、会社法上の役員(取締役、監査役など)ではなく、社内の業務執行に特化した役職として、多くの企業が独自に設けているポジションです。
法的には「会社法上の役員」ではないため、実態によっては「労働者」として取り扱われるケースも存在します。
一般的に、執行役員の労働者性が問われる際には、以下のような要素が考慮されます。
- 雇用契約が締結されているか
- 指揮命令下にあるか(役員としての独立性の有無)
- 勤務時間や就業場所が明確に定められているか
- 他の従業員と同様に給与や賞与が支払われているか
これらの要素を総合的に判断し、労働者性が強いと認められる場合、労働基準法上の保護対象となり、有給休暇の付与も必要になります。一方で、執行役員であっても経営的な意思決定や人事権を有するような場合は、労働者性が否定されることもあり得ます。
有給休暇の付与と取得義務の有無
執行役員に対して有給休暇を付与すべきかどうかは、「労働者性」が判断の軸になります。労働者と認められる場合には、以下のように通常の従業員と同様の対応が必要です。
- 雇用開始から6ヶ月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を10日付与
- 10日以上付与される場合には有給休暇の取得義務化(年間5日の取得)も適用対象となる
一方で、執行役員が経営に携わる立場で、労働者性が認められない場合は、会社に有給休暇の付与義務はありません。ただし、このようなケースでも福利厚生として任意の「休暇制度」を整備する企業もあり、企業独自の裁量で制度設計を行う余地も残されています。
執行役員に関する実務上の注意点
執行役員の労務管理はグレーゾーンが多く、企業の管理体制によって判断が分かれやすい分野です。そのため、下記のポイントはあらかじめ整理しておくことを推奨いたします。
- 就業規則や雇用契約書において、執行役員の立場を明確にしておく
- 勤怠管理の有無や給与体系が、他の従業員と明確に異なる場合は、労働者性が否定されやすい
- 労務トラブルを防ぐために、執行役員への対応は“実態”に即して個別に判断することが重要
事前にリスクを見据え、契約や制度設計を整備することが、トラブル回避の鍵となるでしょう。
名ばかり役員と労働者性の判断基準
「役員だから有給休暇はない」と一括りにされがちですが、現場の実態を見てみると、肩書きだけが“役員”であって、実際には一般社員とほとんど変わらない働き方をしているケースも少なくありません。
このような立場にある人を「名ばかり役員」と呼びます。本章では、名ばかり役員の具体像と、労働者性が認められる場合の有給休暇の取り扱いについて解説します。
名ばかり役員とは?
名ばかり役員とは、会社の登記上は取締役や役員などの肩書きを有していても、実際には会社の経営には関与しておらず、労働者としての業務に従事している人物を指します。典型的には、以下のような特徴があります。
- 勤務時間や業務内容が他の従業員と同じである
- 指揮命令を受けて働いている
- 経営判断や意思決定への関与がほとんどない
- 報酬が固定的な給与として支払われている
このような場合、「役員」という肩書きだけでは労働者性を否定することはできません。労働基準法においては、「実態」に基づいて判断されるため、たとえ取締役であっても、労働者性が強く認められると法律の保護対象となるのです。
労働者性が認められる場合の有給休暇の取り扱い
名ばかり役員であっても、その実態が労働者であれば、会社には年次有給休暇の付与義務が生じます。具体的には、通常の労働者と同様に、以下の条件を満たすことで有給休暇が発生します。
- 入社から6ヶ月が経過していること
- その間の出勤率が8割以上であること
さらに、有給休暇の取得義務(年5日取得)も適用対象となるため、企業としては名ばかり役員に対しても、正しく労働者として管理する必要があります。
名ばかり役員のトラブルを防ぐ実務上のポイント
名ばかり役員問題は、未払い残業や労災、社会保険の適用など、他の労務トラブルにもつながりやすいリスクを含んでいます。したがって、最低限下記3つについては押さえておきましょう。
- 登記上の肩書きだけで労働者性を判断しない
- 勤怠管理・給与体系・指揮命令関係などの実態を総合的に確認する
- 名ばかり役員と判断されうるポジションには、明確な職務区分や業務委任の根拠を整備しておく
形式だけで判断せず、常に「実態を基準に評価する」姿勢が求められます。
役員就任前後の有給休暇の取り扱い
従業員から役員へ、あるいは役員から従業員へと立場が変わる場合、有給休暇の取り扱いにも注意が必要です。
特に、退職・再雇用を伴わないケースや、実態としての労働者性が残るようなケースでは、制度上の理解と実務上の整理を誤るとトラブルに発展する可能性もあります。本章では、立場変更のタイミングでの有給休暇の扱い方について、具体的な対応例とともに解説します。
従業員から役員に就任する際の有給休暇の消化・買取
従業員から取締役などの役員に就任する場合、原則として労働者としての地位を喪失するため、それまでに付与されていた有給休暇の権利も消滅します。そのため、就任前にどのように有給休暇を処理するかが重要になります。
基本的な対応方法は以下の2つです。
- 有給休暇の事前消化:役員就任前に可能な限り有給を消化してもらう
- 会社都合での有給買取:業務の都合等で消化できない場合は、会社の判断で買い取る
なお、有給休暇の買取は原則として禁止されていますが、退職や労働者性の喪失などで今後行使ができなくなる場合に限っては、例外的に認められています。つまり、従業員から役員になる場合は、実質的に「退職」と同様の取り扱いがされるため、買取についても会社の判断で行うことは可能です。
実務的なアドバイスとしては
- 有給休暇が残っている場合は、役員就任日の前に計画的に取得を促す
- 有給の買取を実施する場合は、金額計算方法や税務上の取扱いを事前に確認する
- 社内文書(異動通知書や役員登記書類など)で就任日を明確にしておく
上記3つの観点は押さえておきましょう。
役員から従業員に転換した場合の有給休暇の付与
逆に、役員を退任して従業員として再雇用されるケースでは、有給休暇の付与に関して「勤続年数」の考え方がポイントとなります。役員としての期間は「労働者」としての勤続には該当しないため、原則として新たにカウントし直すことになります。
ただし、以下のような例外的な対応が可能です。
- 役員時代も労働者性が認められる実態があった場合:その期間を勤続年数に通算できる可能性あり
- 会社が任意に過去の勤続を考慮して有給を付与するケース:就業規則や雇用契約書に基づく
従業員としての再雇用が「継続勤務」とみなされない限り、有給休暇は新たに発生することになります。つまり、入社から6ヶ月後、出勤率8割以上であれば10日の付与という、通常のルールが適用されます。
トラブルを防止するためには、
- 再雇用後の就業条件を明文化し、雇用契約書を新たに作成する
- 勤続年数の取り扱いについては、就業規則の記載と照らして整合性を確認
- 実態に応じて「再雇用」か「新規採用」かを整理しておくことが重要
このような取り組みを推進しましょう。
立場の変更は、法的な地位や労働条件の変化を伴うため、有給休暇のような権利に関しても慎重な判断が求められます。特に社会保険や税務処理にも影響するため、事前に専門家と相談しながら対応を決めることが望ましいでしょう。
有給休暇取得義務化と役員の関係
2019年4月に施行された「年次有給休暇の取得義務化」は、多くの企業にとって大きな制度改革となりました。この制度により、企業は対象となる従業員に対して、年5日の有給休暇を“確実に取得させる”義務を負うことになります。
しかし、「役員」や「執行役員」「使用人兼務役員」のような立場の人にも、この義務は適用されるのでしょうか?ここでは、有給休暇取得義務の基本と、役員への適用可否について詳しく見ていきます。
有給休暇取得義務化の概要
働き方改革の一環として導入された「年5日の有給休暇取得義務」は、従業員の心身の健康保持や労働環境の改善を目的とした制度です。
制度のポイントは
- 年間10日以上の有給休暇が付与される労働者が対象
- 付与から1年以内に5日分の有給を確実に取得させる義務が会社に課される
- 違反した場合は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金対象
これらは忘れてはいけません。
この制度では、単に「有給休暇を与えればよい」のではなく、「計画的に取得させる義務」が企業に生じるため、労務管理体制の強化が求められます。
ただし、この制度の適用対象は“労働者”に限られます。よって、役員や使用人兼務役員、執行役員などについては、その労働者性の有無によって取り扱いが異なります。
使用人兼務役員や執行役員への適用範囲
役員であっても、「労働者性」が認められる場合には、有給休暇の付与はもちろん、取得義務の対象にもなります。特に注意が必要なのが、以下の2つの役職です。
使用人兼務役員は年次有給休暇の取得義務の対象?
使用人兼務役員は、役員でありながら、従業員としての勤務実態も併せ持つ立場です。この場合、労働者性が強く、以下のような実態がある場合は、取得義務の対象とされます。
- 雇用契約が存在し、労働時間が管理されている
- 他の従業員と同じように勤怠管理が行われている
- 有給休暇が実際に付与されている
これらの条件を満たす使用人兼務役員については、年5日の有給休暇を取得させる義務も、他の一般従業員と同様に発生します。
執行役員は年次有給休暇の取得義務の対象?
執行役員については、会社法上の役員ではないため、雇用契約があれば“労働者”として扱われる可能性があります。業務内容や勤務形態によっては、労働者性が認められ、次のような対応が求められます。
- 有給休暇の付与と取得義務の適用
- 年5日の取得管理(計画付与・管理簿の整備)
使用人兼務役員や執行役員に対する実務上の留意点
誤って「役員だから対象外」と判断してしまうと、労働基準監督署からの是正指導や指摘を受けるリスクもあります。
下記3つのポイントについて、自社でどのような管理ができているのか確認してみましょう。
- 使用人兼務役員・執行役員の労働者性の有無を社内で明確に判断しておく
- 就業規則や職務規程で、役職ごとの労働条件を整理しておく
- 労働者性がある場合は、通常の従業員と同様に「取得義務」の対応を忘れずに
特に使用人兼務役員はグレーゾーンになりやすいため、専門家の助言を受けながら慎重に管理することが大切です。
企業が注意すべき実務上のポイント
役員と有給休暇の関係は、表面的な肩書きではなく「労働者性の有無」によって大きく左右されます。
特に、使用人兼務役員や執行役員など、実質的に労働者としての勤務実態がある場合には、労働基準法の適用対象となり、企業側にとっても労務管理や規程整備の重要性が増します。本章では、役員の労働者性の判断基準と、企業が取るべき実務上の整備ポイントを解説します。
役員の労働者性の判断とリスク管理
企業がまず把握すべきは、「誰が労働者性を持ち、法令上の保護対象に該当するのか」という点です。肩書きが「取締役」や「執行役員」であっても、実際の業務内容や勤務形態によっては、労働者と判断されるケースがあります。
労働者性の主な判断ポイントとして
- 雇用契約が存在するか
- 指揮命令系統の中で業務を行っているか
- 勤務時間や就業場所が会社によって管理されているか
- 給与が役員報酬とは別に「給与」として支払われているか
これらの要素を複合的に見て判断されるため、「名ばかり役員」や「使用人兼務役員」などは、労働者性が強いと判断される可能性が高いです。
リスク管理の観点から重要な対応
企業としては、「肩書き」に頼るのではなく、「実態」に即した判断を行い、事前に社内体制を整備しておくことが、最も重要なリスクヘッジとなります。
- 労働者性があると判断される役員に対して、有給休暇や残業代など労基法上の管理を適切に行う
- 実態と異なる運用が継続されると、労働基準監督署からの是正勧告や労務トラブルに発展する恐れがある
- 特に退職時の未払賃金(未取得有給の買取など)に関しては、金銭トラブルに発展しやすい
労務管理の状況によっては、知らないうちにトラブルの種が発生していることもありますので、ご注意ください。
就業規則や役員規程の整備
労務リスクを防ぐためには、社内ルールの整備が欠かせません。特に、役員に関する規程や就業規則の記載があいまいなままだと、判断が属人的になり、対応の一貫性が保てなくなります。
整備すべき主な社内文書としては
- 就業規則:使用人兼務役員が労働者として勤務する際の条件や労働時間、有給休暇などの取扱いを明記
- 役員規程(または取締役規程):役員報酬、職務内容、労働者性を持たないことの明記など
- 雇用契約書(該当する場合):給与・勤務形態・業務内容の具体的な定義
上記への対応が必須です。
特に、役員と従業員が重複するポジションについては、「就業規則+役員規程+雇用契約書」の3点セットで整合性のある管理を行うことが望まれます。
社内のルールや実態が明確であれば、仮に労基署の調査や訴訟トラブルに発展した場合でも、企業側にとって有利な証拠となります。だからこそ、ルール整備は「備え」として欠かせない実務対応なのです。
まとめ:役員と有給休暇の関係は「肩書き」でなく「実態」で判断を
役員には原則として有給休暇は認められない――これは労働基準法上のルールですが、使用人兼務役員や執行役員、名ばかり役員のように“実質的に労働者と同様の働き方”をしている場合には、労働者性が認められ、有給休暇の付与や取得義務の対象となるケースがあります。
本記事では、以下のようなポイントを解説してきました。
- 役員が原則として労働基準法の適用外である理由
- 使用人兼務役員や執行役員に対する有給休暇の取り扱い
- 名ばかり役員の判断基準と実務対応
- 役員就任前後の有給休暇の消化・買取ルール
- 有給休暇取得義務化の対象者と企業対応の注意点
- 実態に即した社内規程や管理体制の整備
役員の労務管理は、法的な判断に加え、社内制度や運用ルールとの整合性が問われる領域です。「肩書き」にとらわれず、「実態」を踏まえた適切な対応が、トラブルの未然防止と健全な組織運営につながります。
もし現在、役員の労働時間や有給管理、社内規程の整備などにお悩みの点がありましたら、ぜひ一度、社会保険労務士法人ステディまでお気軽にご相談ください。専門家が、貴社の実情に合わせた最適な対応をご提案いたします。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
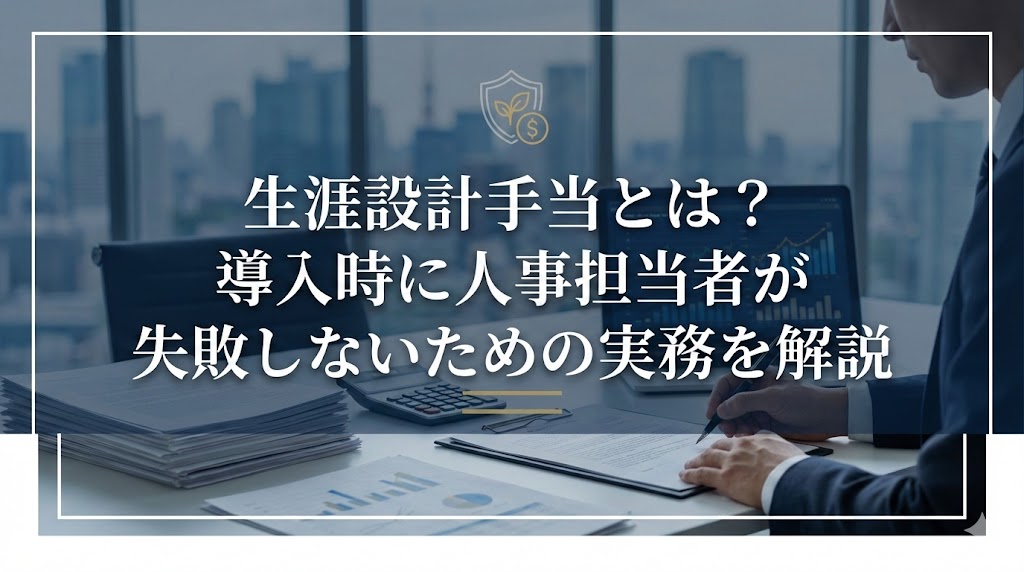 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説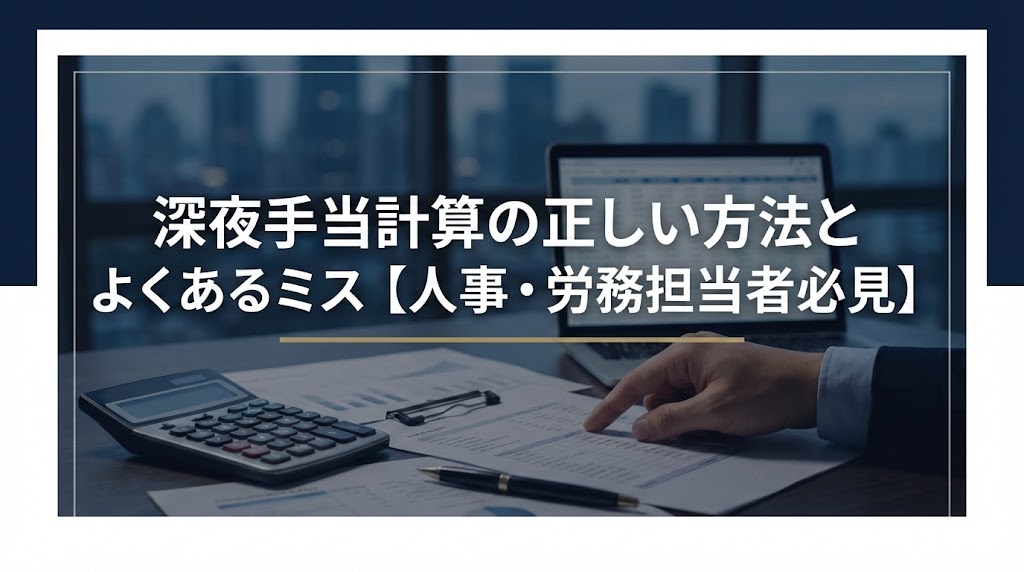 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】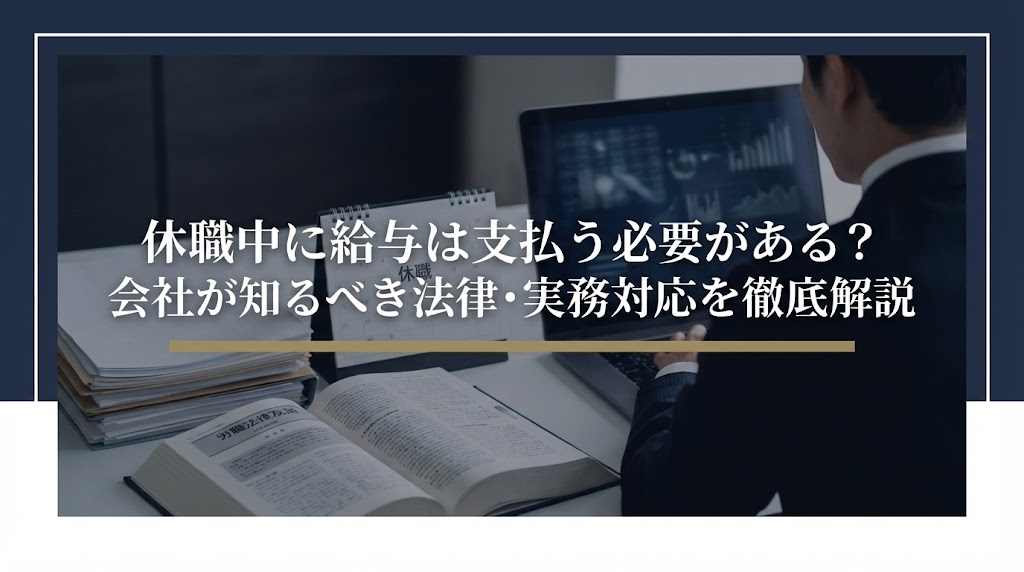 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説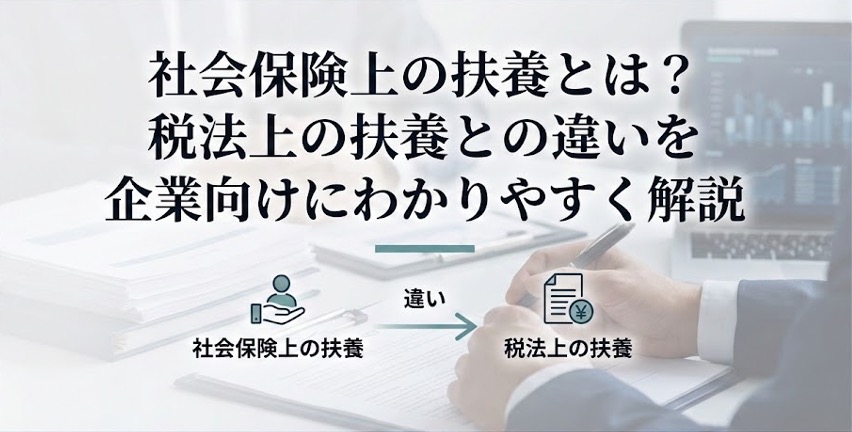 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説

