「代休」と「振休」、どちらも“休みの振替”に関する制度ですが、その意味や運用ルールには大きな違いがあります。取得タイミングや割増賃金の有無、労働基準法との関係など、正しく理解しておかないと、知らぬ間に法令違反や賃金トラブルにつながる可能性もあります。
本記事では、社会保険労務士の視点から、代休と振休の基本的な定義から、実務での使い分け方、管理方法までを網羅的に解説。制度の違いをしっかり理解し、職場での適正な運用に役立てていただける内容となっています。
代休と振休の違いとは?まずは基本の定義から
「代休」と「振休」は、どちらも出勤の代わりに休みを取得する制度ですが、その仕組みや法律上の位置づけには明確な違いがあります。
制度の違いを正しく理解していないと、労務トラブルや割増賃金の未払いといった問題につながる可能性も。ここでは、それぞれの定義と基本的な適用条件について、わかりやすく解説します。
振替休日(振休)の定義と適用条件
振休とは、もともと休日であった日に出勤する代わりに、事前に別の労働日を休日として振り替える制度です。あらかじめ「この日は働いて、その代わりにこの日を休みにする」と決めておくのが特徴です。
この制度は、労働基準法上の「法定休日」における割増賃金の発生を避けるためにも重要な役割を果たします。正しく運用すれば、休日労働にはあたらないため、割増賃金の支払い義務も発生しません。
振休の適用条件としては
- 振替は事前に行う必要がある
- 振替先の日は、本来の労働日でなければならない
- 振替休日制度が就業規則等に明記されていることが必要
上記ルールが守れているのか、確認する必要があります。
たとえば、業務の都合で土曜日に出勤してもらい、事前に水曜日を休みにしておくようなケースが該当します。
振休の運用で注意すべきは、「週に1回の法定休日」が守られているかどうかです。振休によって週内の休日がなくなってしまうと、法定休日労働とみなされて割増賃金の支払い義務が発生する恐れがあります。
代休の定義と取得条件
一方の代休は、休日に出勤した「後」に、その代わりとして休みを与える制度です。
振休と違い、事前の計画ではなく、結果として出勤が発生したことへの対応として「後日、別日に休みを与える」仕組みです。
この点が大きなポイントであり、代休の場合、休日労働がすでに成立しているため、たとえ代わりの休みを与えたとしても、割増賃金の支払いは原則として必要です。
代休の適用条件は
- 実際に休日に労働が行われたこと
- その代わりとして、一定期間内に休暇を取得すること
- 代休制度が就業規則等で整備されていること
これらの対応ができているのか確認しましょう。
たとえば、「休みである祝日に出勤した社員に対し、翌週の金曜日に代休を付与する」といったケースがこれに該当します。
また、代休の取得期限を設けていないと、未消化のまま時効を迎える可能性があり、結果として法的トラブルに発展する恐れもあります。そのため、代休制度の運用には「取得期限の明示」「管理台帳の整備」などが欠かせません。
法律と労働時間制度における位置づけの違い
「代休」と「振休」はどちらも勤務の代わりに取得する休暇制度ですが、法律上の取り扱いや労働時間制度との関係性には大きな違いがあります。特に、労働基準法や36協定といった法的枠組みを理解することで、適切な運用やトラブルの予防につながります。ここでは、それぞれの制度が法律上どのように位置づけられているのかを解説します。
労働基準法における振休と代休の扱い
まず、振休と代休は労働基準法の中で明確に区分されておらず、どちらも「休日の取り扱い」として企業側の就業規則や労使慣行によって運用されるものです。ただし、実務上は明確な違いが存在します。
振休(振替休日)の法的扱い
振休は、事前に休日と労働日を入れ替えることで、法定休日労働とみなされず、割増賃金の支払いも不要となります。
ただし、「週に1日の法定休日」を守らなければ、労働基準法第35条に違反する恐れがあります。
代休の法的扱い
代休は、休日にすでに労働が行われているため、労働基準法上の「休日労働」に該当します。
そのため、法定休日に勤務させた場合は、休日手当として35%以上の割増賃金の支払いが必要です。
代休を与えたとしても、割増賃金の支払い義務は消滅しません(代休≠割増賃金の代替ではない)。
36協定や就業規則との関係性
振休・代休の運用には、企業ごとの36協定や就業規則との整合性も欠かせません。
特に時間外労働や休日出勤が日常的に発生する職場では、これらの制度を適切に整備しておくことで、法的トラブルを未然に防ぐことができます。
振休と36協定や就業規則との関係性
振休は、事前に労働日と休日の振替が決定されているため、36協定による休日労働の許可は原則不要です。
ただし、振替によって結果的に週の労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働として36協定の範囲内で行う必要があります。
代休と36協定や就業規則との関係性
代休は、休日労働がすでに発生しているため、36協定によって事前に休日労働が認められていることが前提となります。
また、代休制度を導入する場合は、就業規則への明記が必須であり、取得ルールや有効期限、賃金処理の方針も定めておくべきです。
このように、振休と代休はいずれも就業規則と法令の両面から制度設計が求められます。形だけ制度を置いても、実態と合っていなければ違法となる可能性もあるため、専門家の監修を受けたうえでの整備が望ましいでしょう。
振休と代休の比較表
振休と代休は一見似ている制度ですが、実際の取得方法や給与処理、管理の仕方には明確な違いがあります。
労働者の権利を守りつつ、企業が適正に制度運用を行うためには、その違いを正確に理解することが不可欠です。ここでは、比較しやすいよう表形式も交えながら、両者の違いをわかりやすく整理します。
取得タイミングと発生条件の違い
振休と代休の最大の違いは、いつ取得が決まるか(事前 or 事後)という点にあります。
| 項目 | 振休(振替休日) | 代休 |
|---|---|---|
| 取得タイミング | 出勤前に振替日を設定 | 出勤後に休暇を付与 |
| 発生のきっかけ | あらかじめ休日と労働日を入れ替える | 実際に休日に出勤した場合に発生 |
| 労働の前提 | 原則として労働前に振替を通知 | 実際の休日労働が発生した後に対応 |
| 法的な割増対象外か | 該当(法定休日労働とならない) | 該当せず(法定休日労働とみなされる) |
このように、「事前に計画された休日の移動=振休」、「事後の補償としての休暇=代休」という構図を理解することが大切です。
割増賃金の支払有無とその理由
制度の違いは、賃金の取り扱いにも大きく影響します。
- 振休
- 事前に休日と労働日を入れ替えるため、休日労働とはみなされず、割増賃金の支払いは不要です。
- ただし、結果的に週40時間を超える場合は時間外労働として扱われます。
- 代休
- 実際に休日に労働しているため、法定休日労働として35%以上の割増賃金が必要になります。
- 代休を与えたとしても、割増賃金の支払い義務が免除されることはありません。
上記のポイントは必ず押させておきましょう。整理しますと、次のようにまとめることができます。
| 項目 | 振休 | 代休 |
|---|---|---|
| 割増賃金の必要性 | 不要(法定休日労働とならない場合) | 必要(法定休日労働に該当) |
| 賃金の支払い処理 | 通常通りの賃金計算 | 割増賃金(1.35倍以上)の支払いが必要 |
このように、「割増賃金が発生するか否か」が振休と代休の大きな分かれ目となります。
振休と代休の記録・管理方法の違いや注意点
制度の違いは、勤怠管理や帳票の記録方法にも表れます。
振休については、事前に振替日を設定・記録しておく必要があり、勤務予定表や勤怠システムへの反映が不可欠となります。そのため、振替日の設定忘れや記録漏れがあると、休日労働と誤解される可能性につながってしまいます。
一方で代休は、実際に勤務した日と、後日取得する代休の日の両方を正確に記録する必要があります。代休の有効期限を設けている企業が多く、未消化リスクへの注意しましょう。
まとめると、次のようになります。
| 項目 | 振休 | 代休 |
|---|---|---|
| 記録タイミング | 事前に設定・反映 | 勤務後に発生、代休日も別途記録が必要 |
| 勤怠管理のポイント | 週の法定休日の確保 | 有効期限と消化状況の把握が重要 |
| トラブル回避の工夫 | 振替手続きの文書化と明文化 | 代休台帳の整備・申請フローの標準化 |
特に中小企業では、口頭でのやりとりに頼るケースも多いため、就業規則でのルール明記と、運用ルールの徹底がカギとなります。
振休・代休の正しい使い分けと実務対応
制度として存在する「振休」と「代休」ですが、現場では従業員からの申請や業務の都合によって柔軟な判断が求められる場面も少なくありません。特に、繁忙期や急なシフト変更が発生した際には、法令遵守と職場運用のバランスをとる必要があります。ここでは、実務上の使い分けと現場での対応ポイントを整理します。
従業員からの希望があった場合の対応方法
従業員が「振休にしてほしい」「代休を取得したい」と申し出た場合、まず確認すべきはその出勤予定日の性質(法定休日かどうか)と事前の振替手続きの有無です。
実務上のポイントとしては、
- 振休として対応するには、事前に振替を決定しておくことが絶対条件
- 休日勤務の前に書面やシステム上で振替日を確定させる必要があります。
- すでに休日出勤が発生している場合は、代休として処理するのが原則
- 後から「これは振休だった」という扱いはできません。
上記の対応を進めましょう。
また、従業員からの希望がある場合でも、業務の繁忙や人員体制に応じて調整が必要です。一方的に希望を拒否するのではなく、代替案を提示するなど労使の対話を重ねることがトラブル防止につながります。
業務繁忙期における労使の調整ポイント
繁忙期に振休・代休をどのように扱うかは、会社の柔軟な制度設計が問われる場面です。人員不足を避けながら、従業員の権利も尊重する必要があります。
実務対応の工夫
- 代休の取得希望日を一定期間内で制限し、部署単位での取得調整を行う
- 振休については、週内に必ず1日法定休日を確保できるようにシフト編成を管理
- 事前に「代休は繁忙月を避けて取得する」旨のルールを明記しておく
このように、制度としてのフレームを固めておけば、個別対応の負担も軽減されます。
期限切れ代休の対応と代替措置
代休は「事後的な休暇」のため、消化せずに失効してしまうケースも見受けられます。未取得のまま有効期限を過ぎた場合、賃金精算が必要かどうかが問題になります。
一般的には、代休を与えることで休日労働の割増賃金の支払い義務は免除されないため、有効期限を過ぎた場合、未取得分については改めて休日出勤手当を支給する必要があると考えられます。
就業規則には、代休の取得期限と期限超過時の取扱い(賃金精算の有無)を明記しておくことが望まれます。
振休予定日の変更は可能か?
一度設定した振休でも、業務都合や個人事情によって「やはりその日は出勤したい(あるいは別日にしたい)」という相談が寄せられることがあります。
振休の変更は、以下の条件を満たすことで原則可能とされます。
- 振休の前日までに労使双方が同意のうえで変更する
- 振替先の日も本来の労働日であること
- 週の中で1回は法定休日が確保されるようにスケジューリングする
ただし、繰り返しの変更や直前の変更が続くと、勤怠記録の整合性がとれなくなるため、文書での確認やシステム入力の徹底が求められます。
よくある質問Q&A:労務管理で困らないための実践知識
振休や代休は制度として理解していても、実際の現場運用では「これってどうなるの?」という細かな疑問がつきものです。ここでは、企業担当者や従業員から寄せられることの多い質問をQ&A形式で整理し、実務にすぐ活かせる知識としてご紹介します。
代休と振休は有給扱いになるのか?
結論から言うと、代休・振休はいずれも「有給休暇」とは別枠の休暇制度です。つまり、年次有給休暇の残日数を消化するわけではなく、会社が与える「特別な休み」として扱われます。
振休は、もともとの休日と労働日を入れ替える制度であるため、出勤扱いとなった日も、休みにした日も賃金は通常どおり支給されます。
代休も、休日出勤に対する代替休暇として付与されるため、その取得日については賃金控除はされません。
ただし、就業規則で「代休は無給」と規定していたり、未整備で判断に迷うようなケースも見受けられます。社内制度としての明確化と周知が重要です。
半日単位・時間単位での取得は可能?
振休・代休ともに、制度としては半日単位や時間単位での取得も可能です。ただし、これが認められるかどうかは就業規則や社内規程の整備状況によります。
実務上のポイントとして、下記を確認しましょう。
- 会社が明確に「半日代休制度」「時間単位振休制度」などを定めていれば、取得は問題なし
- 管理が煩雑になるため、勤怠システムや管理ルールの整備が前提となる
- 法定休日の労働に対する代休を「時間単位」で分割する場合、割増賃金の取扱いに注意
このように、可能かどうかは「制度としての設計次第」です。運用ルールを整えずに実施すると、労使トラブルにつながる恐れもあります。
振休・代休が取れなかった場合の賃金精算方法
やむを得ない事情で代休・振休が取得できなかった場合の処理も、事前にルールを定めておくことが重要です。特に代休の場合、取得しないまま放置すると、休日出勤に対する割増賃金が未払いとなるリスクがあります。
- 振休が取れなかった場合
- 原則として事前に振替していれば休日出勤とは扱われないが、振休の設定が無効とされると割増賃金が必要になるケースも
- 代休が取れなかった場合
- 休日労働が成立しているため、割増賃金(通常1.35倍以上)の支払いが必要
- 賃金精算で対応するか、遅れてでも代休を付与するかを、就業規則で定めておくことが望ましい
また、「代休取得の期限を過ぎた場合の取り扱い(消滅 or 賃金支払い)」についても、ルールを就業規則に明記しておくことで、トラブルを回避できます。
勤怠管理やシステム運用に役立つ管理方法とは?
振休・代休の適切な運用は、労務トラブルの予防だけでなく、従業員の満足度や生産性向上にも直結します。そのためには、取得状況やルールに基づいた正確な記録が欠かせません。特に近年は、クラウド型勤怠管理システムを活用して効率化を図る企業も増えています。ここでは、実務に活かせる具体的な管理方法をご紹介します。
代休・振休の履歴管理とシステム連携
振休や代休の運用においては、誰がいつ取得したか、何を根拠に付与されたのかを正確に把握することが求められます。手書きや口頭管理ではミスや漏れが発生しやすく、法的リスクも高まります。
- 勤怠システムで「出勤予定の振替」「代休付与履歴」「有効期限」を自動で管理
- 休日出勤の記録と連動させて、代休の自動付与設定が可能
- 有効期限のリマインド通知や、未取得分の一覧表示で対応漏れを防止
主要な勤怠管理クラウド(例:ジョブカン、KING OF TIME、freee勤怠など)では、代休や振休のステータス管理に対応しており、給与計算や労働時間管理と連動させることも容易です。
これにより、総務・人事担当者の負担を軽減し、制度の透明性・公平性を担保することができます。
中小企業におすすめの管理方法と運用フロー
中小企業では、「手間をかけずに管理したい」「高額なシステムは導入できない」という声も少なくありません。とはいえ、制度が形骸化していたり、取得履歴が曖昧になっていると、後々大きなリスクにつながります。
- テンプレート活用でルールを明文化
- 代休申請書・振休届などをエクセルやGoogleフォームで簡易運用
- フォーマット内に「取得理由」「希望日」「取得期限」「承認欄」を明記
- カレンダー・台帳で一元管理
- Googleカレンダーやスプレッドシートで、付与日と取得日を記録
- 社内で共有しておけば、重複申請や未取得の可視化がしやすい
- 月次での残数チェックと上長確認
- 毎月の給与計算タイミングで未消化分を一覧化し、所属長に共有
- 有効期限が近いものは、早めの取得勧奨を行う
- 就業規則で取得期限・精算方法を明記
- トラブルを未然に防ぐため、「取得は◯日以内」「未取得時は割増賃金支払い」などを明文化
このように、高機能なシステムがなくても、工夫次第で適切な管理体制は構築可能です。制度の信頼性を高めるためにも、ルールの整備と運用の徹底を進めましょう。
まとめ:振休と代休の違いを理解し、トラブルのない職場運用を
本記事では、「振替休日(振休)」と「代休」の違いについて、法律上の扱いや賃金処理、実務運用まで幅広く解説しました。両者は似て非なる制度であり、取得タイミングや割増賃金の有無など、適切に区別することが労務リスクの軽減につながります。
とくに、就業規則の整備や勤怠管理体制の構築は、企業の信頼性と従業員満足度の向上に直結します。「なんとなく」で運用していると、思わぬトラブルや未払い賃金のリスクに発展しかねません。
制度の見直しや労務体制に課題を感じている企業様は、ぜひ一度、当社までお気軽にご相談ください。
専門家が貴社の実情に合わせた制度設計・運用改善をサポートいたします。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
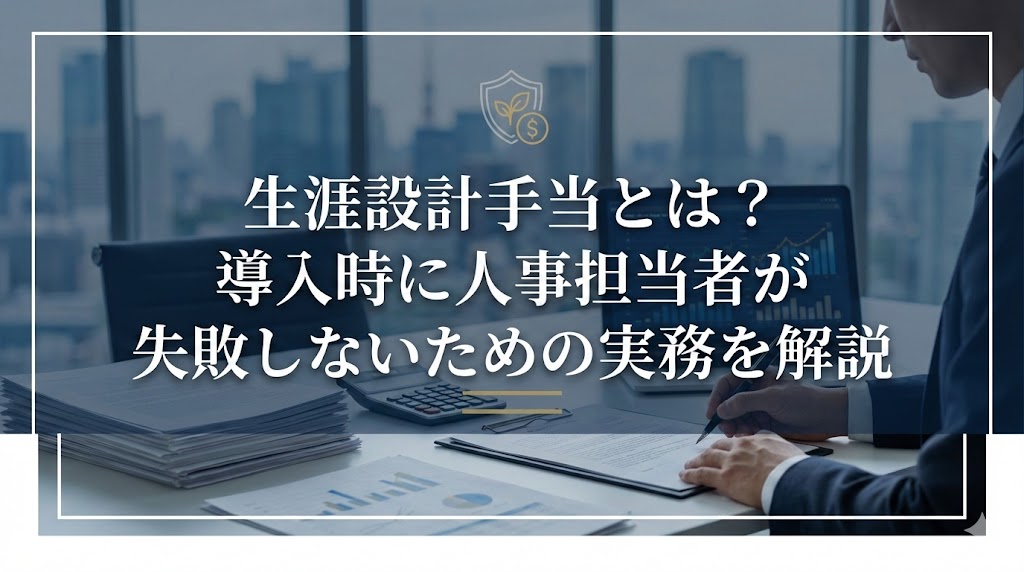 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説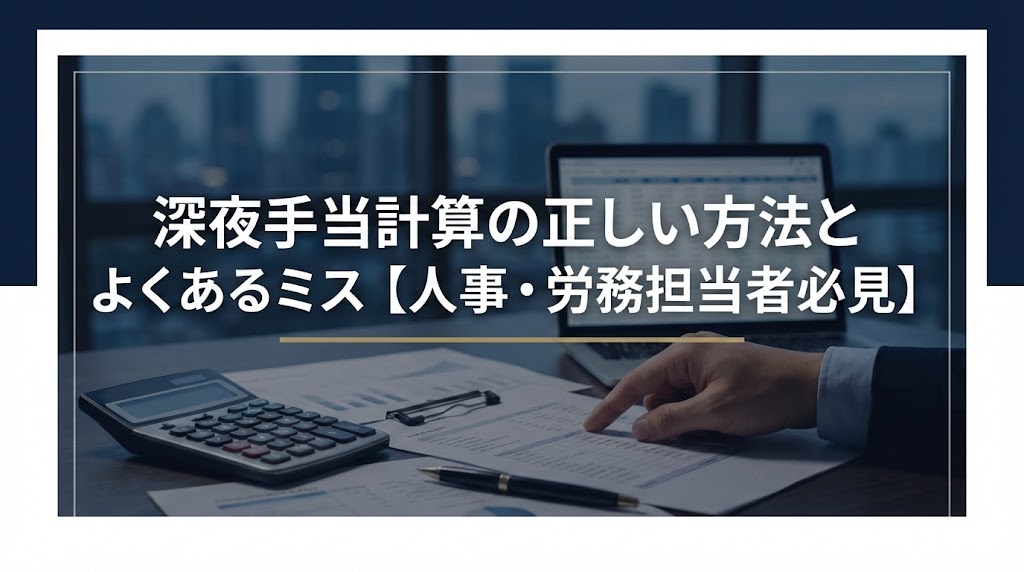 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】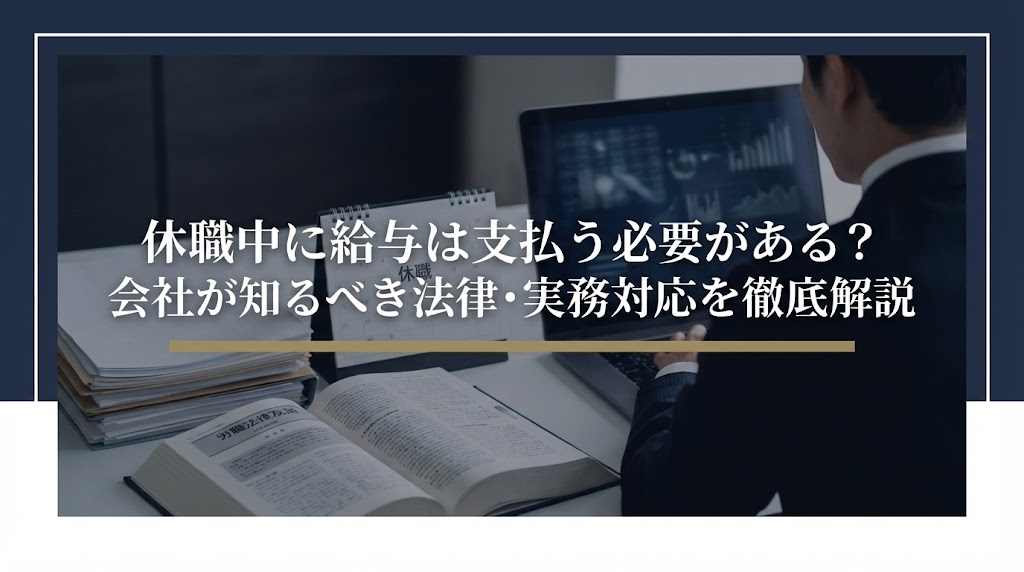 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説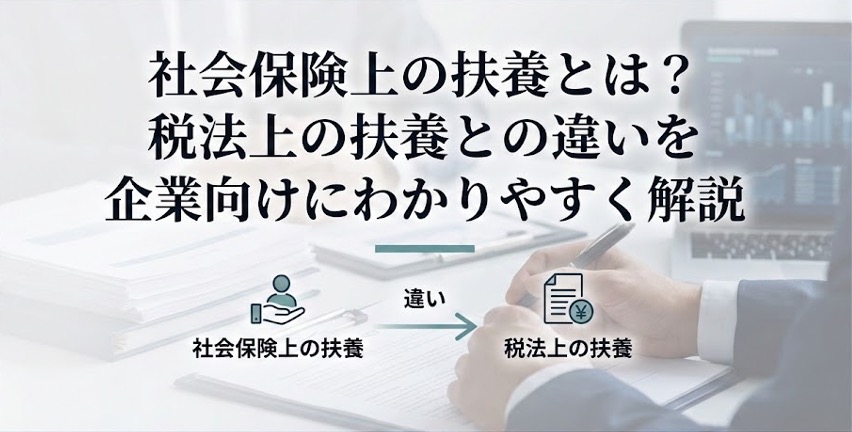 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説

