就業規則を作成・変更する際に必要となる「意見書」。しかし、実際に記入する立場になると、「何を書けばいいの?」「記入例が見つからない」「異議があるときはどう表現すれば?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、就業規則意見書の基本的な書き方から、異議なし・異議ありの具体的な記入例、労働者代表の選出方法、記入時の注意点までを網羅的に解説します。
また、社会保険労務士としての現場経験をもとに、単なるテンプレートの紹介にとどまらない「実務で本当に役立つポイント」や「よくある誤解」についてもお伝えしますので、ご参考になれば幸いです。
意見書作成の必要性と法的背景
就業規則の作成や変更にあたって、労働者代表からの「意見書」を添付することは、単なる形式的な義務ではありません。労働者の権利を守るうえでも、会社と従業員の信頼関係を築くうえでも、非常に重要な役割を担っています。この章では、意見書がなぜ必要なのか、どのような法的根拠があるのかを、専門家の視点からわかりやすく解説します。
意見書は「労使対話」の第一歩
就業規則は、企業のルールブックとも言える存在であり、従業員の労働条件や職場でのルールを明文化したものです。これを会社側だけで一方的に作成・変更することは、労使トラブルの火種になりかねません。
そこで登場するのが、労働者代表の「意見書」です。これは、労働者の立場から就業規則の内容に対して意見を述べる正式な手段であり、企業が労働者の声に耳を傾けていることを示す「証拠」でもあります。
労働基準法第90条が根拠
意見書の提出は、労働基準法第90条により明確に義務付けられています。同条では、就業規則を作成または変更する際には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取し、その意見書を労働基準監督署に提出しなければならないとされています。
ここで注意すべきなのは、「同意」ではなく「意見の聴取」であるという点です。つまり、労働者代表が就業規則のすべてに賛成する必要はなく、異議がある場合にはその旨を記載することができます。それでも、会社はその意見を無視して就業規則を届け出ることが可能です。しかしながら、実務上は異議が出た場合、労使間での対話を重ねて調整を行うことが望ましく、後のトラブル予防にもつながります。
社会保険労務士の視点:意見書はどのような価値?
社労士として多くの企業現場を見てきた経験から言えば、意見書の作成プロセスこそが、労使間の信頼を築く最も重要なタイミングです。単に「異議なし」と書いてもらうための手続きとして済ませてしまう企業もありますが、実際にはこのプロセスを通じて、労働者が会社の方針や規則の背景を理解し、納得感を持って働くことができるようになります。
企業が持続的に成長していくには、「形だけの同意」ではなく、「実質的な合意と理解」が欠かせません。そのためにも、意見書は単なる添付書類ではなく、「対話と信頼構築のツール」として活用していただきたいと考えています。
意見書の記載事項と記入例
就業規則の意見書は、書式がシンプルな分、「どこまで書けばいいのか?」「表現に迷った場合はどうする?」と不安を感じる方も多いものです。特に、労働者代表の立場であっても専門知識があるとは限らず、何を書けばよいか悩んでしまうのは当然です。
この章では、意見書に記載すべき基本事項を整理したうえで、実際に使える記入例(異議なし・異議ありの2パターン)をご紹介します。実務に役立つよう、必要最小限でありながら、法的にも整合性のある記述を意識した内容になっています。
意見書に記載すべき基本項目
意見書は、労働基準監督署に提出される正式な書類です。したがって、以下の基本事項を漏れなく記載する必要があります。
- 作成日:意見書を作成した日付
- 宛名:会社名および代表者名(例:「株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 様」)
- 意見聴取日:就業規則について意見を求められた日付
- 意見の内容:「異議なし」または「異議あり」の意見と、その具体的な内容
- 労働者代表の氏名・職名:意見を述べた労働者代表の名前と役職
- 労働者代表の選出方法:過半数労働者代表の選出方法(例:全従業員による投票)
これらの項目は、労働基準監督署での確認に必要な情報であるため、形式的であっても正確に記載することが求められます。
異議なしの場合の記入例
以下は、就業規則の内容に特に異議がない場合の記載例です。

このように、特に問題がなければ「特に意見はありません」という一文で完結できます。ポイントは、簡潔であると同時に、日付・選出方法などの法的に必要な情報は抜けなく記載することです。
異議ありの場合の記入例
就業規則の内容に対して労働者代表が何らかの懸念や意見を持っている場合は、それを正直に書くことが大切です。以下はその記載例です。

異議がある場合でも、表現は冷静かつ建設的に書くのが基本です。「反対」や「抗議」ではなく、「要望」や「希望」などの言葉に置き換えることで、労使間の信頼関係を保ちながら意見を伝えることができます。
労働者代表の選出方法と注意点
就業規則意見書の作成にあたり、非常に重要なのが「労働者代表の選出方法」です。実は、意見書そのものよりもこの選出方法に不備があることで、労働基準監督署から受理されなかったり、就業規則の届け出が無効とみなされたりするケースがあります。
この章では、法令に準拠した正しい選出方法や、実務上でよくある間違い、そしてその対策について詳しく解説します。
労働者代表に求められる要件とは?
まず、就業規則に対する意見書を提出できる「労働者代表」には、以下の要件が求められます。
- 管理監督者でないこと(課長・部長クラスの役職者は対象外)
- 従業員の過半数を代表していること
- 会社側が一方的に指名していないこと
つまり、会社が「この人に頼んでおこう」と独断で選んだり、管理職が代表としてサインするのは法的に認められません。あくまで、従業員全体の意思を反映した選出である必要があります。
選出方法の具体例と実務でのポイント
労働者代表は、次のような手続きで選出するのが望ましいとされています。
- 全従業員に選出のお知らせをする
- メール、社内掲示板、回覧などで通知を行い、「〇〇の件について労働者代表を選出します」と周知します。
- 立候補または推薦を募る
- 立候補制、もしくは同僚からの推薦制など、自由な意思に基づく選出が望ましいです。
- 無記名での投票、もしくは過半数の署名による同意を得る
- 特定の人物に決定する際は、簡易なアンケート方式や署名簿などでも対応可能です。
記録として「労働者代表選出の経緯を残しておくこと」が重要です。例えば、選出のお知らせ文書や投票結果一覧をPDFや紙で保存しておけば、万が一監督署から問い合わせがあった際にも安心です。
よくあるNGケースとそのリスク
以下のような選出方法は、労働基準法の趣旨に反するため注意が必要です。
- 会社側が役職者に「とりあえずお願い」と依頼して代表にする
- 過半数に満たない従業員で勝手に代表を決める
- 従業員への事前通知なしに代表を決定する
こうしたケースは、「適正な労働者代表が選ばれていない」と判断され、就業規則の届出そのものが受理されない可能性があります。
特に小規模な会社では「選出手続きが面倒」と感じることもあるかもしれませんが、簡略化しすぎて法的な手続きを欠くと、後々大きなトラブルにつながる恐れがあります。
意見書作成時の注意点と専門家からのアドバイス
就業規則意見書は、形式的な一枚の書類に見えるかもしれませんが、その記載内容や手続きの正確さが問われる、非常に重要な文書です。ちょっとした不備が「受理されない」「手続きやり直し」といったトラブルにつながることもあるため、細部まで気を配る必要があります。
ここでは、意見書を作成・提出する際に見落とされやすいポイントと、実務経験をふまえた専門家としてのアドバイスをお伝えします。
注意すべき3つのチェックポイント
意見書を作成する際は、以下の3点に特に注意しましょう。
労働者代表の記載と選出方法の明記
前章でも述べたとおり、労働者代表の選出方法が不適切な場合、就業規則の届出そのものが認められません。選出方法(例:全従業員の投票による)を必ず記載し、正当性が担保されていることを明示しましょう。
記載日と宛名の間違いに注意
意外と多いのが「作成日」や「宛名」のミスです。代表者名や社名に誤記があると、監督署での指摘対象になります。特に法人名や代表者の肩書きが変更された直後などは要注意です。
押印・署名の要否はケースバイケース
現在、意見書の押印や署名は法的には不要とされています(※2021年の行政手続き見直しによる)。ただし、企業によっては、形式的な署名や押印を求めるケースもあります。提出先や社内規定に合わせて、あらかじめ確認しておくのがベターです。
トラブルを防ぐために「一言コメント」を活用しよう
意見書は「異議なし」でも「異議あり」でも、内容をただ形式的に埋めるだけではもったいないと感じています。
たとえば、「異議なし」の場合でも
「特に異議はありません。内容については全従業員に説明が行き届いており、納得しています。」
といった一言を加えるだけで、単なる形式処理ではなく、労使の信頼関係がきちんと機能していることの証拠になります。労働基準監督署の調査が入った場合でも「きちんと説明・共有された就業規則」として受け止めてもらえる可能性が高まります。
意見書は“届け出書類”であると同時に、“信頼構築ツール”でもある
意見書を単なる「お役所への提出書類」として扱ってしまうと、手続きは済んでも、社内には何も残りません。しかし、労働者に丁寧に説明し、意見を取りまとめたうえで作成された意見書は、企業にとっても財産となります。
「きちんと対話してくれる会社だ」と思ってもらえることが、採用や定着率の向上にもつながるのです。
社労士として現場を多数見てきた経験上、「意見書の扱い方」でその会社の労務コンプライアンスレベルが垣間見えることも少なくありません。面倒な手続きこそ、誠実に対応することで企業価値を高めるチャンスにもなるのです。
まとめ
就業規則の意見書は、見た目はシンプルな書類ですが、その背景には労働基準法に基づいた正当な手続きと、会社と従業員の信頼関係の証明という重要な役割があります。
特に気をつけるべきポイントは、以下の4つです。
- 労働者代表を適切に選出すること
- 法定項目を漏れなく記載すること
- 異議あり・異議なしにかかわらず丁寧な記載を心がけること
- 記録(選出方法の証拠など)を残しておくこと
また、社会保険労務士の視点からもお伝えしたとおり、意見書は単なる「届け出用の紙」ではなく、職場の健全性やコンプライアンス意識を可視化するツールとして活用する価値があります。
これから就業規則を作成・改訂しようとしている方は、ぜひこの記事を参考に、形式だけでなく内容面でも誠実で意味のある意見書作成を心がけていただければ幸いです。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
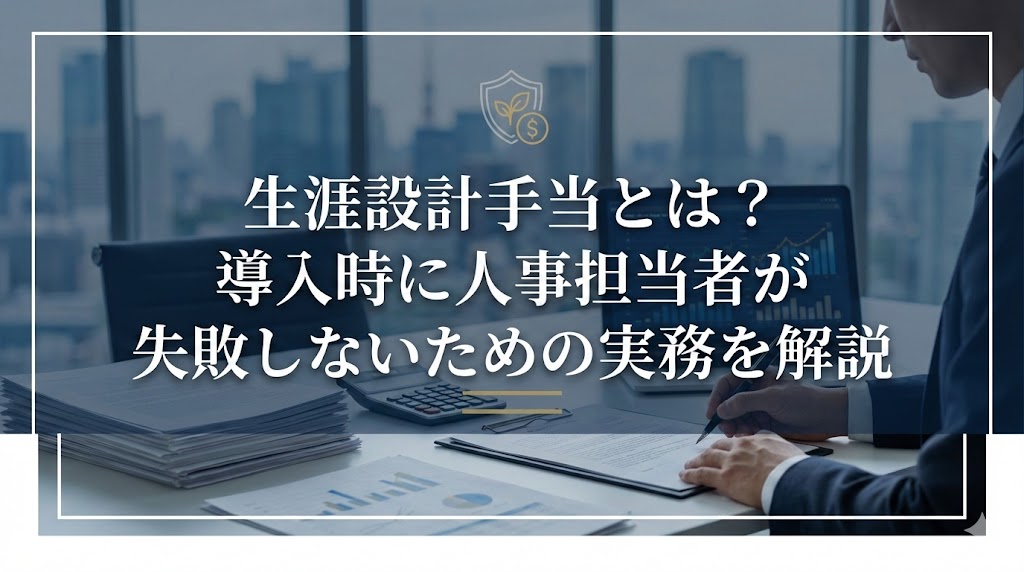 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説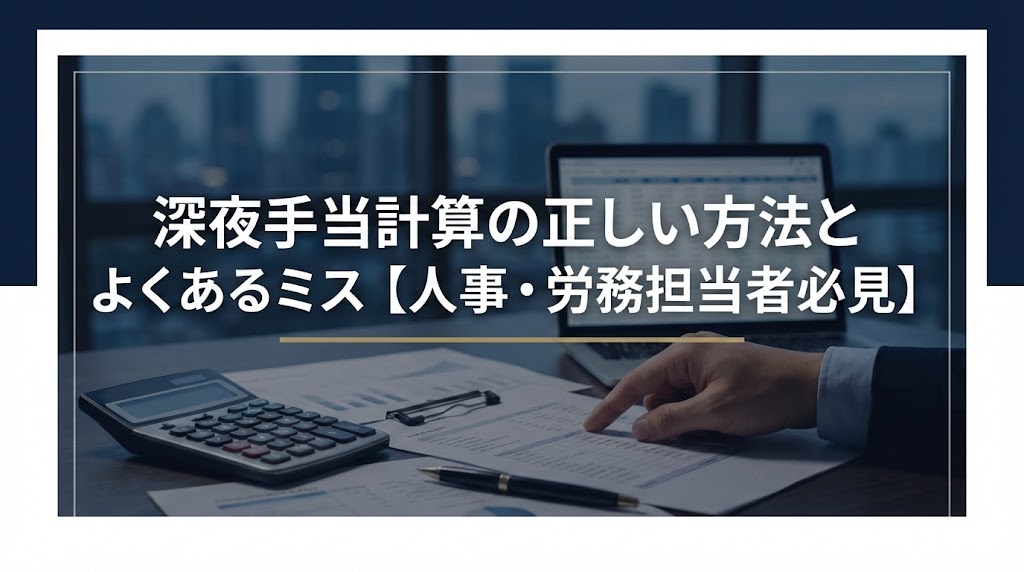 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】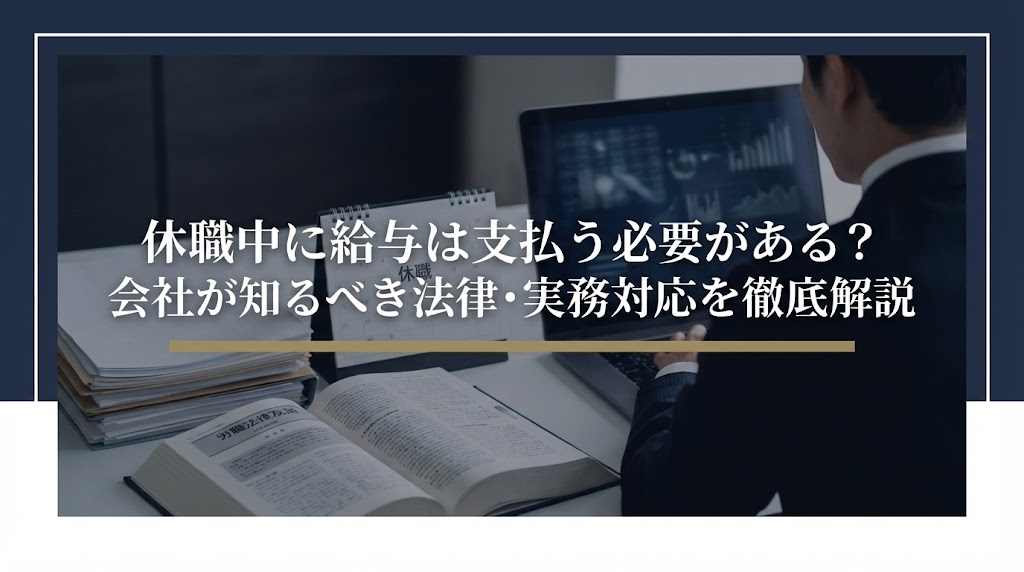 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説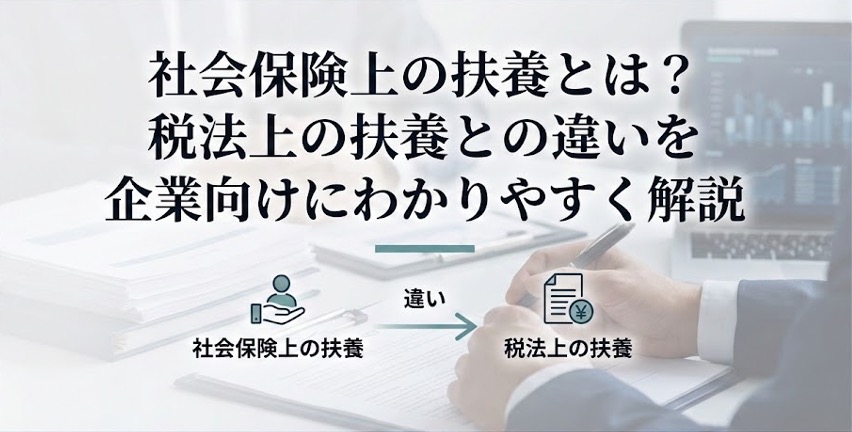 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説

