働き方改革が進む中で、企業にとって「メンタルヘルス対策」は避けて通れないテーマとなっています。2015年に義務化された「ストレスチェック制度」は、従業員の健康管理の上で大切な施策です。労働者50人以上の事業場には、毎年1回のストレスチェック実施が法律で義務づけられており、企業が従業員の心の健康を守るために果たすべき責任が明確になりました。
このストレスチェック制度について、厚生労働省は2024年9月において「全ての企業に対して義務付ける方針」を明らかにしたのです。
そのため、労働者数が50人未満の中小企業においてもストレスチェック制度の内容や対応のポイントを正しく理解していないと、単なる「形式的なチェック」で終わってしまい、逆にリスクを高める結果になりかねません。
本記事では、「ストレスチェック 義務」というキーワードで検索される方のために、制度の概要から、対象事業場・義務の範囲、具体的な実施方法、活用のポイント、さらには罰則やトラブル回避のための実践的アドバイスまでを、専門家の視点でわかりやすく解説します。
企業の人事・労務担当者、産業医や保健スタッフ、そして従業員の健康管理に関心のある方々にとって、今すぐ実務に役立つ内容を網羅しています。ぜひ最後までお読みいただき、メンタルヘルス対策を「義務」から「価値ある取り組み」へと変えていく第一歩にしていただければ幸いです。
ストレスチェック制度とは?
働く人々のメンタルヘルス不調が社会問題として深刻化するなか、企業に求められる「心の健康管理」が注目を集めており、その中で制度化されたのが「ストレスチェック制度」です。
単なる検査としてではなく、組織全体の働きやすさやパフォーマンス向上に寄与する仕組みとして、この制度の目的や仕組みを正しく理解することが求められます。
ここではまず、ストレスチェック制度の概要と、その背景にある社会的課題について、専門家の視点を交えて解説します。
制度の概要と目的
ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法の改正により、2015年12月から50人以上の労働者がいる事業場に対して義務付けられた制度です。
主な目的は、労働者自身が自身のストレス状態に気づき、必要に応じて医師の面接指導などを受けることで、メンタルヘルス不調の早期発見・予防につなげることにあります。
ストレスチェック制度の特徴は以下のとおりです。
- 対象者は常時50人以上の労働者がいる事業場
→ 現在は労働者50人未満の事業場には努力義務とされていますが、将来的には50人未満の企業に対しても義務化される方針となっています。 - 年1回以上の定期実施が義務
- 実施者は医師(産業医)・保健師などの専門職
- 本人の同意がない限り、結果は事業者に提供されない
この制度の意義は、単に「ストレスがあるかどうか」を測るだけではなく、職場環境そのものの改善を促すことにあります。
たとえば、集団ごとの結果を分析し、部署ごとにストレス要因を洗い出すことで、働きやすい職場づくりへの一歩となるのです。
ストレスチェック義務化の背景:メンタルヘルス不調の現状
制度が義務化された背景には、年々深刻化する「職場のメンタルヘルス問題」があります。厚生労働省の調査によれば、精神障害を原因とする労災請求件数はここ10年以上高水準で推移しており、働く人の心の不調が「見えない労働災害」として広がっている現状があります。
特に以下のような課題が社会的に問題視されてきました。
- 長時間労働や人間関係のストレスによる「うつ病」や「適応障害」の増加
- 精神疾患による労災認定や訴訟の増加
- 職場のメンタル不調が原因の「パフォーマンス低下」や「離職率の上昇」
こうした問題に対し、企業として“心の安全配慮義務”を果たす必要があるという流れの中で、ストレスチェック制度は生まれました。
制度の導入により、企業は「問題が起こる前」に兆候を察知し、対応できる体制づくりが可能になります。これは、単にリスク回避の観点からだけでなく、「従業員の幸福度=企業の生産性」という視点に立った、現代的な人事戦略の一環とも言えるでしょう。
ストレスチェックの実施義務
「うちの会社も義務なのか?」「何をすればいいのかわからない」といった声は、実際の現場でもよく耳にします。ストレスチェック制度はすべての企業に同じ義務があるわけではなく、従業員数によって実施義務の有無や内容が異なります。このセクションでは、義務の対象となる事業場や、努力義務となるケースについて詳しく解説します。
対象となる事業場と労働者
ストレスチェックの実施が法的に義務付けられているのは、「常時使用する労働者が50人以上いる事業場」です。
ここで注意すべきポイントは「企業単位」ではなく「事業場単位」であるという点です。たとえば、本社と支店がある企業であっても、それぞれの拠点が独立した事業場として機能している場合、それぞれで労働者数をカウントする必要があります。
【対象事業場のチェックポイント】
- 事業場ごとの労働者数が50人以上か?
- 常時使用されているパート・アルバイトもカウント対象か?
- 派遣労働者や業務委託は含まれるのか?
また、対象となる「労働者」には、正社員だけでなく、週30時間以上働く契約社員やパートタイマーも含まれるため、見落としがちな点にも注意が必要です。
最初は「自社は50人もいない」と思っていたが、契約社員や育児復帰後の短時間勤務社員を含めると実は義務対象だった、というケースもございます。まずは正確な人数の把握が制度対応の第一歩です。
50人未満の事業場における努力義務から義務化へ
一方、常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、ストレスチェックの実施は「努力義務」とされていました。しかしながら、政府は2025年3月14日に、従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施義務化についての労働安全衛生法の改正案を閣議決定しており、今後はすべての企業が対応しなければならりません。
中小企業でも負担が増える決定内容ですが、ストレスチェック自体には以下のようなメリットがあるため、職場環境の改善につなげていく必要があるでしょう。
- メンタル不調の“予防”による人材の定着・離職防止
- 職場環境の課題を見える化し、早期に対応できる
- 「社員を大切にする会社」としての企業ブランディング効果
「50人未満だからやらなくて良かったのに」と考えるのではなく、「今こそ体制づくりのチャンス」と捉えることをおすすめします。
ストレスチェックの具体的な実施方法
ストレスチェック制度は、単に「検査を受けさせれば終わり」というものではありません。検査項目の選定から、評価の仕方、高ストレス者への対応まで、実施にはいくつかのステップと配慮が求められます。
この章では、実際にストレスチェックを実施する際に知っておくべき基礎知識を、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。
検査項目と評価基準
ストレスチェックの調査票は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を基に作成されることが一般的です。これは科学的根拠に基づいた内容で、以下の3つの尺度に分かれています。

- 心理的なストレス反応(例:イライラする、気分が落ち込む)
- 仕事のストレス要因(例:仕事量が多い、裁量がない)
- 周囲からの支援(例:上司や同僚に相談できる環境か)
この3つのバランスを総合的に評価し、労働者が「現在どの程度ストレスを感じているか」「どのようなストレス要因が存在するか」を可視化することが可能です。
高ストレス者の判定基準と対応策
検査結果に基づき、「高ストレス者」と判定された従業員には、ストレスチェックを実施した方から医師による面接指導の機会を提供する必要があります。この判定基準も厚労省のガイドラインに準拠していますが、実務では以下のような状況が判断材料となります。
- ストレス反応が非常に高い(精神的疲労、睡眠障害など)
- ストレス要因が過剰で、職場の支援がほとんど得られていない
- 明らかに労働環境が本人のキャパシティを超えている状態
ただし、従業員が高ストレス者であることがどうか、会社が勝手に知ることはできません。原則、ストレスチェックの結果は本人の同意なく会社が結果を閲覧することが禁止されています。
そのため、会社としてはストレスチェックの結果を知るためには「本人の信頼を得られる体制」が整っているかどうかがポイントになります。
面接指導の流れと注意点
高ストレス者から面接希望の申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を速やかに実施しなければなりません。面接の主な流れは以下の通りです。
- 本人からの申出を受ける(書面が望ましい)
- 産業医など医師との面接日程を調整
- 医師が勤務状況・心理状態などを総合的に評価
- 医師の意見を踏まえ、必要に応じて就業措置を検討
ここで注意すべき点は、「医師の意見を聞いたあと、就業措置を講じるかどうかは事業者の判断に委ねられている」という点です。
たとえば、労働時間の短縮や配置転換などが必要とされた場合、企業側がそれをどう受け止め、対応できるかが重要になります。
また、医師が見立てた内容が曖昧だったり、企業の実情とそぐわなかったりすることも少なくありません。そうした場合には、産業医との連携強化やセカンドオピニオンの導入も視野に入れると良いでしょう。
実際の労務支援でも、「医師のコメントが抽象的で困った」という相談を受けることがありますが、その際は制度を「杓子定規」に運用するのではなく、「本人の安全・職場の対応可能性・就業規則との整合性」を丁寧に検討する姿勢が求められます。
ストレスチェック結果の活用
ストレスチェック制度は、単なる「実施して終わり」の仕組みではありません。制度本来の目的は、得られたデータを活用して、職場環境の改善やメンタルヘルス不調の予防につなげることにあります。
特に重要なのが、「集団分析による組織全体の傾向の把握」と、「個人へのフィードバックによる早期対応」です。この章では、それぞれの活用方法と注意点を詳しく解説します。
集団分析による職場環境の改善
ストレスチェックの結果は、一定の条件を満たす場合に限り、個人を特定しない形で集団ごとの傾向を把握する「集団分析」に活用することが可能です。これは、部署単位や職種別などでストレス要因の分布を把握し、職場全体の課題を浮き彫りにする強力なツールとなります。
集団分析の活用で得られるメリット
- 高ストレス部署の早期発見と対策立案
- 上司・同僚間の支援体制の見直し
- 業務負荷の偏りや不公平感の是正
- 人事施策(配置転換、教育、研修)の根拠づくり
たとえば、ある企業では「ある部署だけ高ストレス率が異常に高い」ことが集団分析で判明し、上司のマネジメントスタイルを見直すきっかけになったという事例もあります。単なる“従業員の問題”として片づけるのではなく、組織構造そのものに目を向ける視点が求められます。
なお、集団分析を実施するには、集計・分析の単位として「10人以上の従業員の回答があること」などの条件があるため、分析対象の範囲設定にも注意が必要でしょう。
個人結果のフィードバックとプライバシー保護
ストレスチェック結果は、労働者本人にフィードバックされることで、初めて“自分のストレス状態に気づく”という価値を発揮します。ただし、ここで最も重要なのは本人のプライバシー保護です。
法律上、本人の同意がなければ事業者は結果を知ることができません。このルールを軽視した運用は、制度そのものの信頼性を損ねるだけでなく、従業員との関係悪化にもつながります。
【フィードバックの実施時に押さえておくべきポイント】
- 結果は本人に直接・個別に通知する(紙またはWeb)
- 産業医・保健スタッフによる丁寧な説明・フォローを行う
- 結果を人事評価や異動に絶対に使用しない旨を周知する
- 同意取得や面接希望は本人の自主的判断に委ねる
企業によっては、フィードバックを「結果のスコアだけで通知して終わり」にしてしまっているケースもありますが、それでは本人の理解が深まらず、実質的な自己ケアにもつながりません。専門家が結果を読み解き、必要に応じてアドバイスを行う仕組みが望まれます。
義務違反時の罰則とリスク
ストレスチェック制度は「やった方がいい」だけでなく、一定の条件下では「やらなければならない」法的義務です。制度を軽視していると、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、労働トラブルや損害賠償リスクにつながる可能性もあります。
このセクションでは、ストレスチェック制度における法的義務違反がもたらすリスクと、企業として注意すべきポイントを詳しく解説します。
労働安全衛生法に基づく罰則
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10で明文化された義務です。これに違反した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
- 労働者50人以上の事業場で未実施の場合
- 労働安全衛生法違反として行政指導の対象
- 改善勧告や命令に従わない場合、罰金刑(50万円以下)が科される可能性も
ただし、現時点で「未実施だから即罰則」というケースは多くありません。行政としてもまずは指導・助言を優先する傾向にあります。しかし、是正勧告を無視し続けた場合や、重大な健康被害につながったケースでは、企業の責任が厳しく問われることになります。
また、労働基準監督署が行う調査の一環として、ストレスチェック制度の実施状況が確認されることもあります。とくに安全衛生委員会の記録や、面接指導の有無なども確認対象となるため、形式だけでなく中身のある運用が重要でしょう。
安全配慮義務違反の可能性とその影響
企業が最も注意すべきリスクは、労働者がメンタル不調を訴えた際に、「適切な予防措置を怠った」と判断されることです。これは、ストレスチェックそのものの未実施に限らず、実施後の対応が不十分だった場合も含まれます。
たとえば、以下のようなケースでは「安全配慮義務違反」に問われる可能性があります。
- 高ストレス者の申出を放置し、面接指導を行わなかった
- 面接結果を無視し、業務負荷を軽減しなかった
- 集団分析で問題が見つかっていたのに、環境改善を行わなかった
このような対応の不備は、企業イメージの低下につながる重大な問題です。とくに最近は、従業員の健康管理や職場環境への関心が高まっていることもあり、「メンタルヘルスへの取り組み」が企業の信頼性を測る一つの指標となっています。
社労士の視点ですと「ストレスチェック=年に1回の行事」ではなく、職場全体の健康リスクを未然に防ぐ“安全管理の柱”であるという視点です。万が一のトラブルを防ぐためにも、法令順守だけでなく、実効性のある対応体制の整備が不可欠です。
効果的なストレスチェックのためのアドバイス
ストレスチェック制度は「やればよい」というものではなく、いかに効果的に活用するかが問われる時代になっています。制度を形骸化させないためには、実施者のスキルと体制、そしてストレスチェック後の対応を「継続的な仕組み」として確立することが重要です。社労士の目線から、ストレスチェックを有効に活用するための考え方をお伝えいたします。
実施者の選定と教育
ストレスチェックの実施にあたっては、医師、保健師、または適切な研修を受けた看護師・精神保健福祉士などが実施者となることが求められています。
形式的に資格を持っているだけでなく、「職場環境や働き方に対する理解があること」も極めて重要なポイントです。
【実施者を選定する際のポイント】
- ストレスやメンタルヘルスに関する十分な知識・経験があるか
- 労働者と信頼関係を築けるコミュニケーション力があるか
- 結果の分析・説明が論理的かつ配慮あるものであるか
また、産業医がいる場合でも、「実施を丸投げ」にせず、企業側との連携や報告体制をしっかり構築することが大切です。
実務の中で、「担当者が制度の目的を理解していなかったため、面接希望の労働者対応が遅れた」といった事例もあるでしょう。
担当者や管理職に対しても、制度の概要や対応マナーを周知する研修機会を設けることで、現場の対応力を高めることができます。
継続的なメンタルヘルス対策の重要性
ストレスチェックはあくまで気づきのきっかけに過ぎません。制度を本当に意味あるものにするためには、チェック後のフォローアップや、組織としての継続的な取り組みが必要不可欠です。
【継続的な取り組みの具体例】
- ストレスチェック結果に基づいた職場改善計画の策定・実行
- 年2回以上の定期的なヒアリングや満足度調査の実施
- 管理職向けのメンタルヘルス研修・ラインケア研修
- 「相談できる空気」を作る社内コミュニケーション施策
さらに、従業員の自主的なケアを促す風土づくりも大切です。たとえば、社内報やイントラネットを活用して、セルフケアに関する情報提供を定期的に行う企業も増えています。
制度を「やること自体」が目的になってしまっている企業ほど、効果が実感できずに形骸化する傾向にあります。逆に、職場の声に耳を傾け、小さな改善を積み重ねている企業は、離職率低下・生産性向上など、目に見える成果を実感しています。
ストレスチェックは「制度」ではなく、従業員とのコミュニケーションと環境改善の入口です。制度をうまく使いこなすことで、組織も人も、より健やかに成長することができるのです。
ストレスチェック制度の運用や仕組み化にお困りの方へ
「制度は知っているけれど、正しく実施できているか不安…」
「面接指導や集団分析の対応が追いつかない」
「労務トラブルを未然に防ぐために、専門家のサポートがほしい」
そのようなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひお気軽に弊社までご連絡ください。社会保険労務士として多数の企業のストレスチェック制度運用を支援してきた実績があり、貴社の職場環境改善に向けたサポートをいたします。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
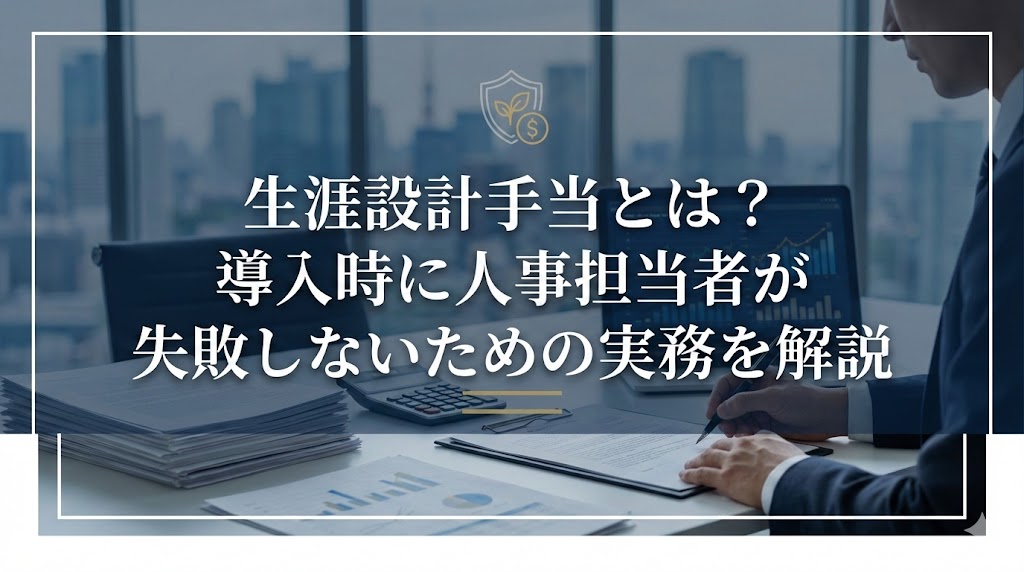 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説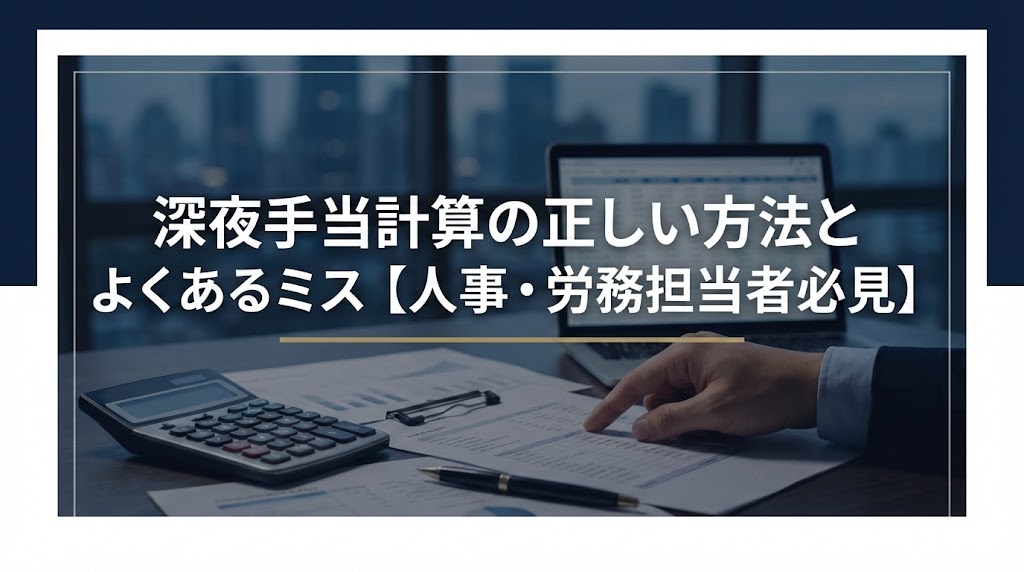 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】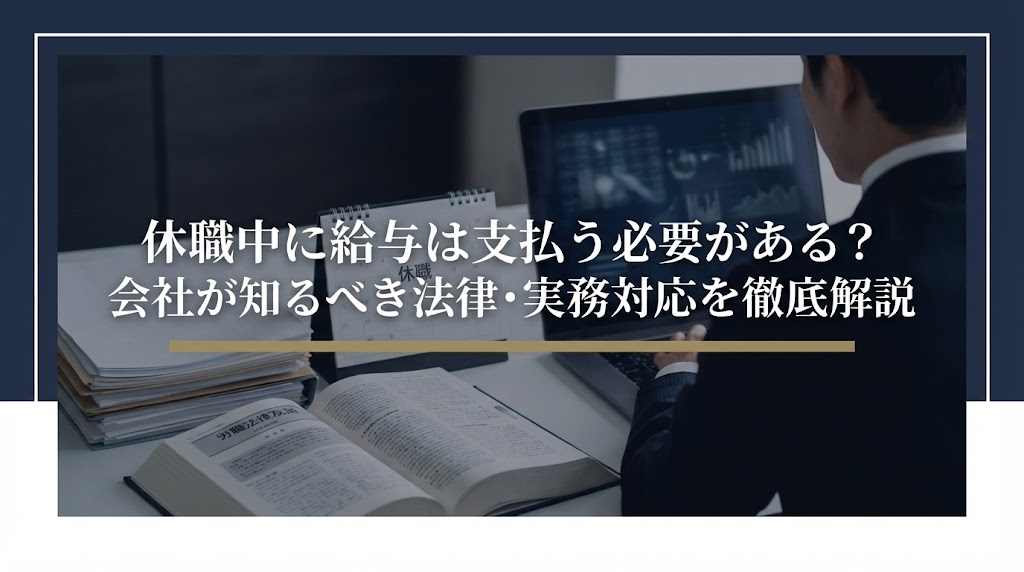 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説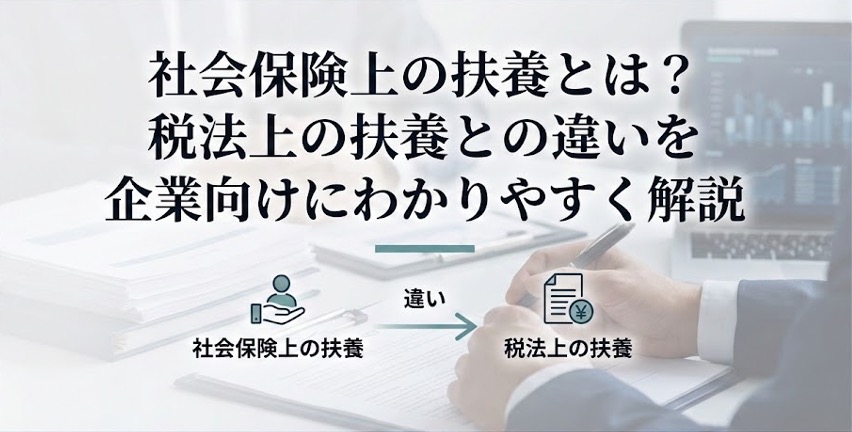 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説


