企業にとって、社員が蓄積したノウハウや顧客情報は、まさに「知的財産」とも言える貴重な資産です。しかし、退職後に元社員が同業他社へ転職し、競合となるビジネスを始めたとしたら……?
こうしたリスクを回避するために存在するのが「競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」です。
この義務は、雇用契約や誓約書などを通じて、在職中または退職後の一定期間において、社員が同業他社で働いたり、自ら競合ビジネスを立ち上げたりする行為を制限するものです。とはいえ、むやみに制限をかければ「職業選択の自由」や「労働者の権利」に抵触するおそれもあるため、慎重な対応が求められます。
本記事では、競業避止義務の基本的な意味から、実際にどのようなケースで問題になるのか、違反した場合のリスク、そして企業・従業員双方が気をつけるべきポイントまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
「競業避止義務」という言葉に初めて触れる方にも、実務でトラブルを未然に防ぎたい方にも役立つ内容を網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。
競業避止義務の基本事項とその重要性
企業と従業員の関係は、単なる雇用契約にとどまらず、企業秘密やノウハウ、顧客との信頼関係といった“目に見えない資産”の共有によって成り立っています。
そのような中で、社員が同業他社に転職したり、独立して同様のビジネスを始めたりすると、企業の利益が直接的に脅かされる可能性があります。
このような事態を防ぐために設けられているのが「競業避止義務」です。企業にとっては、事業上のリスクを最小限に抑える“防衛策”であり、一方で従業員にとっては、自由な職業選択とのバランスを考慮しながら向き合うべき“契約上のルール”でもあります。
本章では、まず競業避止義務が何を意味するのか、そしてどのような場面で問題になりやすいのかを、わかりやすく解説していきます。
競業避止義務の定義と目的
競業避止義務とは、従業員が在職中または退職後に、会社と競合する事業を行わないよう制限する義務のことを指します。
これは民法上の「信義則」や「忠実義務」に基づくものであり、企業が社員に対して当然に求めることのできる一定の行為規範とされています。
主な目的は次のようなものがあります。
- 企業の利益やノウハウの流出を防ぐこと
- 同業他社への過度な人材流出を防止すること
- 取引先との関係や営業秘密を守ること
とくに近年では、IT技術やノウハウの移転が容易になっているため、従業員一人の離職が企業にとって大きな損失となることもあります。
そのため、競業避止義務は単なる“制限”ではなく、企業の健全な運営を守るための“予防的なリスク管理”の一環として位置付ける必要があります。
適用される場面と対象者
競業避止義務が問題になるのは、特に以下のようなケースがあります。
- 営業職や技術職など、機密性の高い情報にアクセスできる社員の退職時
- 独立して元の会社と類似する事業を立ち上げる場合
- 在職中に副業で競合サービスを始めた場合
これらのケースに共通するのは、「企業の利益を損なう可能性がある行為」であるという点です。
また、競業避止義務が適用される“対象者”は、必ずしも全社員に一律で課されるわけではありません。
裁判例では、競業避止義務の有効性について「地位や役割」「アクセスできる情報の重要度」「代償措置の有無」などが重視されています。
たとえば、以下のような社員が対象となりやすい傾向にあります。
- 経営幹部や管理職
- 技術開発部門に在籍し、製品のコア技術を扱っていた社員
- 営業で主要な顧客情報にアクセスしていた社員
企業側は、誰にどのような競業制限を課すべきかを慎重に見極め、契約書や誓約書の内容を明確にすることが極めて重要です。
一方、従業員側も、自身がどのような立場にあり、退職後にどのような制限が課される可能性があるのかをあらかじめ把握しておくことが、将来的なトラブル回避に繋がります。
競業避止義務が適用される具体的なケース
競業避止義務は、理論上のルールにとどまらず、実際のビジネスシーンで頻繁に問題になります。特に企業秘密を扱う職種や、顧客と直接関わる職種においては、在職中・退職後ともに競業リスクが常につきまといます。
本章では、企業と従業員の双方にとって実務上の注意点となる「在職中の競業行為」と「退職後の競業行為」それぞれについて、具体的なケースとポイントを解説していきます。
在職中の競業行為とその制限
在職中の従業員は、雇用契約に基づいて会社の利益に貢献する義務を負っています。そのため、会社と利益が相反する行為、すなわち競業行為は基本的に認められていません。
代表的な競業行為の例としては、下記のようなものがあります。
- 勤務時間外に、同業他社の業務を副業として行う
- 勤務中に自身のビジネスの立ち上げ準備をする
- 会社の顧客や仕入先に自ら営業をかける
これらの行為は、就業規則や雇用契約の内容に関わらず「信義則違反」として懲戒処分や損害賠償請求の対象になる可能性があります。
近年、政府が副業・兼業を推進する流れの中で、「在職中の副業」はある程度社会的に容認されつつあります。しかし、副業の内容が競合他社であったり、自社と利害がぶつかる場合には競業行為に該当しうるため、企業は就業規則で明確なガイドラインを定めることが不可欠でしょう。
従業員側も、「副業OK」とされていても、その中身が競業にならないかを事前に確認しておくべきです。
退職後の競業行為に関する制約
退職後の競業制限は、在職中と異なり、法律上は必ずしも義務とはされていません。そのため、多くの企業では、誓約書や退職時契約で「退職後○年間、競業他社に就職しない」などの取り決めを行っています。
ただし、退職後の競業避止義務は「職業選択の自由」を制限するものでもあるため、制限が妥当でなければ無効とされるリスクもあります。
有効とされるための条件(裁判例に基づくポイント)ですが、
- 制限期間が合理的である(一般的には1〜2年程度)
- 対象となる業種・業務内容が明確かつ限定されている
- 地理的な制限が妥当である
- 代償措置(競業避止の対価としての金銭支払い等)がある
このような内容は押さえておきましょう、
特に代償措置は裁判所でも重視される要素であり、企業が競業制限を設ける以上、「何らかの対価」を提示することが必要です。
実務上の注意点
企業側は、退職時に慌てて誓約書を書かせるのではなく、入社時や在職中からルールを明確にし、従業員に十分説明した上で同意を得ることが望ましいです。
従業員側も、退職後のキャリア形成に影響を与える可能性があるため、自分が署名した誓約書の内容を再確認し、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。
競業避止義務違反のリスクと法的措置
競業避止義務は単なる“お願い”ではなく、明確な契約上の義務として位置づけられるケースが多くあります。そのため、これを違反した場合には、企業側が法的措置を講じることも珍しくありません。
また、違反を放置すれば、企業の営業秘密や顧客が流出し、深刻な損害に発展するリスクもあります。
本章では、競業避止義務に違反した場合に企業が取り得る対応策、そして実際の判例に見るトラブル事例とその影響について、実務に即した観点からわかりやすく解説します。
違反時に企業が取り得る対応策
競業避止義務に違反する行為が発覚した場合、企業ができる対応にはいくつかの段階があります。重要なのは、感情的な対処ではなく、法的根拠に基づく冷静かつ戦略的な対応を取ることです。
主な対応策は次の4つの点を確認してください。
- 退職者への是正要求(内容証明郵便などによる警告)
まずは、退職者本人に対して競業行為の中止を求める文書を送付します。ここで誓約書や契約書をもとに、具体的な競業制限の内容と違反行為を指摘します。 - 損害賠償請求
競業行為によって明確な損害が発生した場合、民事訴訟により損害賠償を請求することが可能です。ただし、損害額の立証には高いハードルがあるため、事前に証拠収集を丁寧に行う必要があります。 - 差止請求
継続的な競業行為が続いている場合は、裁判所に対して差止請求を行い、競業活動の中止を法的に求めることができます。 - 元従業員を採用した競合企業への対応
元従業員を採用した会社に対しても、場合によっては損害賠償や営業妨害の差止を求めることが可能です。ただし、過度な介入は不当な営業妨害と見なされる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
競業避止義務の違反を主張する際には、「どのような契約内容で、どのような行為が違反にあたるのか」を客観的に立証できるかが極めて重要です。
そのため、企業は退職時の誓約書だけでなく、業務範囲や取り扱った情報の内容を明確に記録に残しておくことが、将来の法的対応力を大きく左右します。
過去の判例から学ぶ違反事例とその影響
競業避止義務に関する裁判は、実務においても数多く争われており、判例は企業がどのように制度設計すべきかを考える上での貴重なヒントとなります。
代表的な判例の一例:IT企業 vs 元従業員
IT企業の元営業社員が、退職後すぐに同業他社へ転職し、元の勤務先の顧客にアプローチをかけていた事例です。
この判例では、競業避止義務を明記した誓約書が有効とされ、一定期間の同業他社での勤務禁止が適用されました。ただし、「代償措置がなかったこと」「職務内容が限定的であったこと」などが加味され、賠償額は限定的なものにとどまりました。
判例から学べる実務的な教訓として
- 競業避止義務の有効性は、「制限の合理性」と「代償措置の有無」がカギ
- 契約内容だけでなく、実際の業務範囲や影響の有無が裁判所で検討される
- 誓約書の記載だけでは不十分で、従業員の同意と理解を得ておくことが重要
実務においては、判例がすべてを解決してくれるわけではありません。
同じように見えるケースでも、契約内容や事実関係の違いによって判断が分かれることが多くあります。
そのため、過去の判例を“絶対的なルール”として扱うのではなく、「どのように裁判所が判断する傾向にあるか」という視点で、制度設計や契約書作成に活かすことが大切です。
競業避止義務を定める際のポイントと注意点
競業避止義務は、企業の機密情報や営業基盤を守るうえで重要な契約条項のひとつです。しかし、その内容が不適切であったり、従業員に不利すぎる場合は、裁判で無効と判断されるリスクがあります。
そのため、単に「競業を禁止する」と記載するだけでは不十分で、法律上の有効性や公平性、実務上の説得力を持たせる必要があります。
本章では、実際に有効な競業避止義務契約を締結するために押さえておきたい3つの要件について、専門的な観点から解説していきます。
有効な競業避止義務契約の要件
競業避止義務の契約が法的に有効と認められるためには、「企業利益を正当に守る目的」であり、「従業員の権利とのバランス」が取れていることが不可欠です。
これを実現するために特に重視されるのが、以下の3つの要件です。
守るべき企業利益の明確化
まず第一に必要なのは、「なぜ競業を避ける必要があるのか」という企業側の正当な理由を明確にすることです。
裁判では、「抽象的な企業利益」ではなく、「営業秘密」「重要な顧客情報」「技術ノウハウ」など、具体的かつ合理的な利益を守るためであることが求められます。
たとえば、次のような場合には、競業避止義務が正当と判断されやすくなります。
- 研究開発職が、未発表の技術を扱っていた
- 営業職が、主要顧客の情報や契約内容に精通していた
- 経営幹部が、会社の戦略方針を決定する立場にあった
専門家の視点:競業避止義務は「誰にでも課せるもの」ではありません。従業員の役割や業務内容に応じて、守るべき利益を具体的に示すことが、契約の信頼性を高めます。
制限の範囲(期間・地域・業務内容)の適切な設定
競業避止義務が無効とされる主な理由のひとつが、「制限の範囲が過度である」という点です。したがって、どこまで制限するのかを合理的な範囲に限定することが求められます。
具体的には以下のような視点で範囲を検討しましょう。
- 期間:一般的には「1〜2年以内」が目安。3年以上となると無効と判断される可能性が高まります。
- 地域:全国一律の制限は不合理とされることも。事業展開地域に限定するなど、実情に即した範囲設定を。
- 業務内容:完全な「同業他社への転職禁止」ではなく、「同種の製品開発・営業活動の制限」など、職務に沿った内容に。
たとえば、「東京都内における、○○業界の新規開拓営業への従事を1年間禁止する」といったように、制限対象を具体的に明文化することで、裁判での有効性も高まりやすくなります。
従業員への適切な代償措置の提供
競業避止義務は、従業員の「職業選択の自由」に制限をかけるものです。そのため、その制限に見合う代償措置を講じることが不可欠です。
この点は、裁判所も契約の有効性判断において非常に重視する項目です。
代償措置の例としては、以下のようなものがあります。
- 競業禁止期間中の金銭補償(競業避止手当)
- 退職金への加算や特別支給
- 在職中の給与への反映(競業リスクのある業務への手当)
重要なのは、「明示された形で支払われていること」です。あとから「退職金に含めていた」という主張は、裁判で認められにくい傾向があります。
専門家の視点:代償措置は、企業にとっては一見「コスト」に見えるかもしれませんが、それにより契約の実効性を担保し、自社の重要資産を守る“保険料”として考えるべきです。
競業避止義務を巡るトラブルを防ぐために
競業避止義務は、企業と従業員双方にとって非常にデリケートなテーマです。企業側は「事業の防衛線」として、従業員側は「職業選択の自由とのバランス」として、どう向き合うかが問われます。
トラブルが発生する多くのケースで共通しているのは、「認識のズレ」や「契約内容の曖昧さ」です。誤解や不十分なコミュニケーションが、法的紛争にまで発展してしまうことも少なくありません。
この章では、実務に携わる専門家の立場から、企業と従業員それぞれが取るべき具体的な予防策についてアドバイスをまとめました。トラブルを未然に防ぎ、健全な雇用関係を築くためのヒントとしてご活用ください。
企業が講じるべき予防策と従業員教育の重要性
企業が競業避止義務に関するトラブルを回避するためには、「契約書を用意すること」だけでは不十分です。むしろ、従業員との認識を一致させ、ルールを定着させるプロセスそのものがリスク管理の要になります。
実務的な予防策としては、下記3つの方法が考えられます。
- 制度設計の明文化と見直し
競業避止義務に関するポリシーや誓約書の内容を定期的に見直し、現場の実態に合ったものにすることが大切です。
特に新規事業や人事制度の変更時にはアップデートが必要です。 - 従業員への丁寧な説明と同意の取得
入社時や異動時などのタイミングで、競業避止義務の内容と理由をわかりやすく説明し、書面で同意を得ること。
ただの署名ではなく、説明責任を果たすことがトラブル予防に繋がります。 - 従業員教育の実施
「誓約書を書いたから安心」と思わず、eラーニングや研修で定期的に競業避止義務や営業秘密の取り扱いに関する教育を実施することが望まれます。
企業は、契約や制度の整備と同じくらい、「従業員にどう伝え、どう納得してもらうか」という点に力を入れるべきです。誤解のない状態をつくることで、法的リスクだけでなく、組織の信頼性や定着率の向上にもつながります。
従業員が理解しておくべき自身の権利と義務
従業員側も、「競業避止義務は企業が一方的に決めるもの」と誤解してしまうことがあります。
しかし実際には、自分の将来のキャリアにも大きく影響する契約であるため、内容をしっかり理解し、自身の立場や権利についても正しく把握することが重要です。
理解しておくべきポイントとしては
- 競業避止義務の範囲と期間
契約書や誓約書には、自分にどのような制限が課されるのか明示されています。業務内容や地域、期間が現実的かどうか、自身で確認することが必要です。 - 代償措置の有無
競業制限に見合った補償が用意されているかどうかを必ず確認しましょう。特に退職後に影響が出る可能性があるため、口約束ではなく、明文化された内容を把握することが大切です。 - 不明点があれば専門家に相談を
もし契約内容に疑問や不安がある場合は、労働問題に詳しい社会保険労務士や弁護士に早めに相談するのが賢明です。トラブルになる前の相談が、将来のリスク回避につながります。
上記の取り組みを参考にしてください。
競業避止義務は、企業の防衛策であると同時に、従業員のキャリア設計や独立に直接関わる問題でもあります。自分自身の将来を守るためにも、「知らなかった」「聞いていない」で済まされない契約であるという意識が必要です。
まとめ:競業避止義務を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐために
競業避止義務は、企業の利益を守るための重要な手段であり、同時に従業員のキャリアや権利にも大きく関わるデリケートなテーマです。
制度を設ける側・守る側のどちらにとっても、「どのような内容が妥当であり、どのように合意を得るか」が極めて重要なポイントとなります。
本記事では、競業避止義務の基本的な考え方から、具体的な適用ケース、違反時のリスク、契約を有効にするための要件、トラブルを防ぐための実践的な対策までを解説してきました。
繰り返しになりますが、最も避けるべきは「知らなかった」「説明していなかった」ことによる紛争です。制度を導入・運用する企業側は、契約書の整備だけでなく、従業員への丁寧な説明と理解促進を重視すること。
そして従業員側も、自身の権利と義務をしっかりと認識したうえで、必要に応じて専門家のサポートを受けることが大切です。
もし、競業避止義務の制度設計や契約書の内容に不安がある場合は、ぜひ一度弊社(社労士事務所)までご相談ください。
労務の専門家として、企業の立場・従業員の立場双方を踏まえた実践的なアドバイスをご提供いたします。
トラブルを未然に防ぎ、健全な雇用関係を築くための第一歩として、お気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
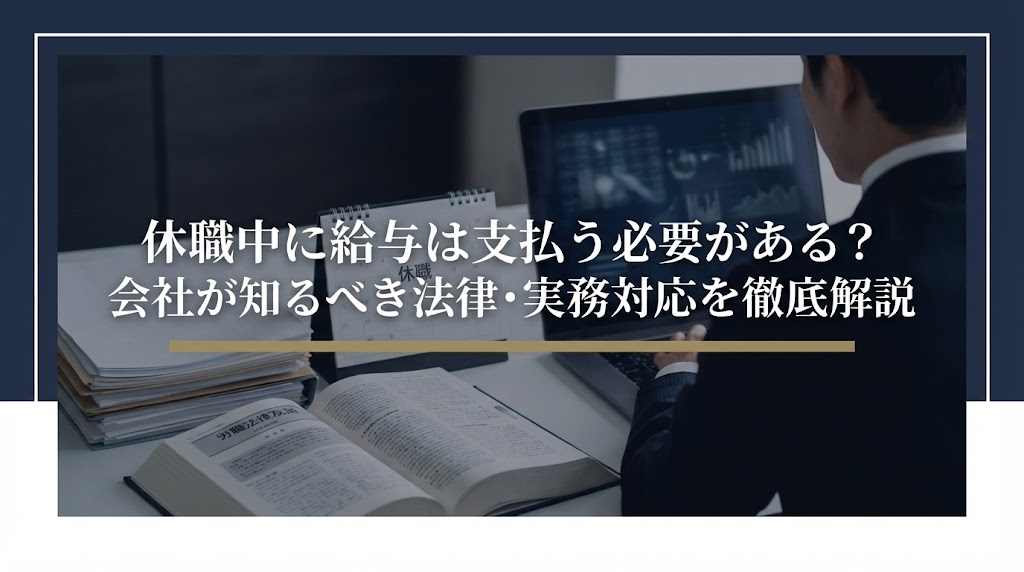 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説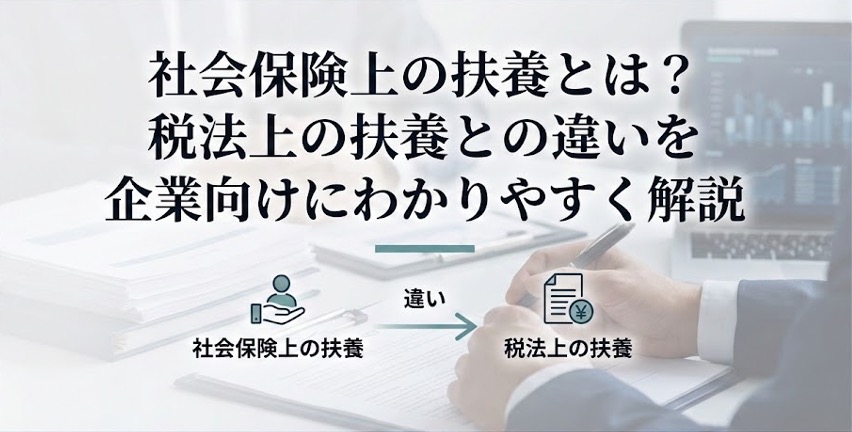 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説 ニュース一覧2026.01.08【重要】助成金に関する不正リスクについて
ニュース一覧2026.01.08【重要】助成金に関する不正リスクについて ニュース一覧2025.12.12顧問社労士に“ミスが多くて不満”と感じたときに会社が取るべき5つのステップ
ニュース一覧2025.12.12顧問社労士に“ミスが多くて不満”と感じたときに会社が取るべき5つのステップ

