「無断欠勤14日で自然退職?」という言葉に戸惑いを感じている人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
従業員の突然の無断欠勤は、企業運営に大きな支障をきたす可能性があります。
しかし、安易に自然退職として扱うことはトラブルの種となりかねません。今回の記事では、無断欠勤が続く従業員への適切な対応方法や、自然退職扱いの際の注意点、さらには労働問題を回避するためのポイントを詳しく解説します。
人事労務担当者として知っておくべき法的知識や実務上の対策を網羅的に紹介しますので、従業員との良好な関係を維持しつつ、会社のリスクを最小限に抑える方法を学んでいきましょう。
無断欠勤と自然退職の基本知識
無断欠勤と自然退職は、企業の人事労務管理において重要な考え方です。
無断欠勤と自然退職という考え方に馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、従業員の勤怠管理や退職手続きに深く関わるため、人事担当者や経営者の方にはぜひ確認をいただきたいです。
まずは無断欠勤と自然退職の定義、法的根拠、そして実務上の取り扱いについて詳しく解説します。
無断欠勤とは?
無断欠勤とは、従業員が事前の連絡や許可なく、勝手に仕事を休むことを指します。
具体的には、以下のような状況が無断欠勤に該当いたします。
- 出勤予定日に連絡なく出社しない
- 勤務時間中に無断で職場を離れる
- 休暇申請をせずに休む
このような無断欠勤は、単なる遅刻や欠勤とは異なり、労働契約上の義務違反となる可能性が高い状況といえます。
企業にとっては、業務の遂行に支障をきたすだけでなく、他の従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼす可能性があるため、適切な対応が求められます。
自然退職の定義と法的根拠
自然退職とは、従業員や企業の明示的な意思表示がなくても、特定の事由により自動的に労働契約が終了することを指します。
一般的には次のような場合が自然退職に該当します。
- 定年退職
- 従業員の死亡
- 長期無断欠勤
- 休職期間満了後の復職不能
自然退職には、労働基準法上の明確な規定はありません。しかし、就業規則に自然退職に関する条項を設けることで、法的な根拠を持たせることができます。
企業は、自然退職の条件を就業規則に明記し、従業員に周知することが重要であり、例えば、「14日間以上の無断欠勤が続いた場合、自然退職とみなす」といった規定を設けることで、無断欠勤に対する対応を明確にすることができます。
無断欠勤が14日続いた場合のルールと実務上の取り扱い
無断欠勤が14日続いた場合、会社としては該当の従業員を雇用を継続することは難しいといえます。そのため、無断欠勤が続いた場合のルール策定を行うことが一般的です。
これは、労働行政の実務指針から生まれた慣行といえるのですが、その由来は、昭和23年11月11日付けの基発1637号通達にさかのぼります。この通達では、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」を、労働者の責に帰すべき事由による解雇の一例として挙げています。
この観点から、実務上では、無断欠勤が14日続いた場合のルールとしては下記のような内容で策定することが多いと考えられます。
- 解雇検討の目安:14日以上の無断欠勤は、解雇を検討する一つの基準となります。
- 自然退職の基準:多くの企業が就業規則に14日以上の無断欠勤を自然退職の条件として定めています。
- 労使トラブル防止:14日という期間は、従業員の状況確認や連絡を試みるのに十分な時間とされ、拙速な判断を避ける役割を果たします。
ただし、無断欠勤の14日ルールは絶対的なものではありません。
個々の状況や企業の就業規則、そして従業員との関係性を考慮して判断する必要があります。
例えば、精神疾患が原因の場合や、企業側に無断欠勤の原因がある場合は、14日を超えても即座に解雇や自然退職とすることは適切でない可能性があるため注意が必要です。
無断欠勤と自然退職に関する知識は、適切な労務管理を行う上で不可欠です。企業は、これらの考え方を正しく理解し、公平かつ適切な対応を心がけることが重要なのです。
無断欠勤が14日続いた場合の対応手順
無断欠勤が14日間続く事態は、企業にとって深刻な問題です。
この状況に適切に対応するためには、段階的な対応が必要です。初期対応から14日経過後の対応、そして就業規則への明記まで、具体的な手順について確認しましょう。
初期対応:連絡と安否確認
まず、無断欠勤が発生した場合に最優先すべきは従業員の安否確認です。以下の手順で対応しましょう。
- 電話やメールで本人に連絡を試みる。複数回、異なる時間帯で連絡を取ろうとすることが重要です。
- 本人と連絡が取れない場合、緊急連絡先や家族に連絡を取りましょう。
- 周囲の従業員から近況や様子を聞き取ることも忘れてはいけません。
- 状況に応じて、自宅訪問を検討しましょう。
- 事故や災害の可能性も考慮し、必要に応じて警察や病院に問い合わせることも手段として必要です。
安否確認の過程では、従業員のプライバシーに配慮しつつ、必要な情報のみを収集するよう心がけましょう。
無断欠勤が14日した場合の対応
14日間の無断欠勤が続いた場合、企業は以下の2つの選択肢を検討することになります。
自然退職扱いの手続き
多くの企業では、14日以上の無断欠勤を自然退職の条件として就業規則に定めています。自然退職扱いとする場合の手順は以下の通りです。
- 就業規則の確認:自然退職に関する規定を再確認する。
- 書面による通知:従業員に自然退職扱いとなることを書面で通知する。
- 退職手続きの実施:社内システムの更新、社会保険の手続きを行う。
- 記録の保管:一連の対応や通知の記録を保管する。
解雇を選択する場合の注意点
自然退職ではなく解雇を選択する場合は、次の5つの点に注意が必要です。
- 解雇予告:原則として30日前に解雇予告を行う必要があるります。
- 解雇理由の明確化:無断欠勤の経緯や指導の記録を整理し、解雇理由を明確にしましょう。
- 解雇通知書の作成:解雇の理由、通知日、解雇予定日を明記した書面を作成します。
- 弁明の機会:連絡が取れるのでれば、従業員に弁明の機会を与えましょう。
- 法的リスクの検討:解雇が不当とされるリスクを考慮し、必要に応じて専門家に相談してください。
就業規則への明記と従業員への周知
無断欠勤に関する対応を明確にするため、以下の点を就業規則に明記し、従業員に周知しなければなりません。
- 無断欠勤の定義:何をもって無断欠勤とするかを明確に定義する。
- 連絡方法:欠勤時の正式な連絡手段を明記する。
- 自然退職の条件:何日間の無断欠勤で自然退職扱いとするかを明記する。
- 懲戒処分の基準:無断欠勤に対する懲戒処分の種類と基準を明確にする3。
- 安否確認の方法:会社が行う安否確認の手順を明記し、従業員の同意を得ておく1。
これらの規定を従業員に周知し、定期的に確認することで、無断欠勤に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
また、従業員とのコミュニケーションを密にし、無断欠勤が発生しにくい職場環境づくりに努めることも重要です。
自然退職と解雇の違いと選択のポイント
自然退職と解雇は、従業員の退職に関する重要な概念ですが、その性質や法的影響に大きな違いがあります。
自然退職と解雇の違いと、企業が選択する際のポイントについて詳しく解説します。
自然退職のメリットとデメリット
自然退職には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
自然退職として扱うメリット
- 法的リスクの低減: 自然退職は就業規則に基づいて行われるため、法的トラブルのリスクが比較的低くなります。
- 手続きの明確さ: 就業規則に沿った手続きを踏むことで、プロセスが明確になり、従業員の納得も得やすくなります。
- 企業イメージの維持: 解雇と比べて、企業イメージへの悪影響が少ないです。
自然退職として扱うデメリット
- 適用の限定性: 私傷病か業務上の傷病かによって適用可否が変わり、紛争の原因となる可能性があります。
- 復職判断の難しさ: 特に精神疾患の場合、復職可能かどうかの判断が困難な場合があります。
- 従業員との信頼関係への影響: 自然退職の適用が不適切だと従業員が感じた場合、信頼関係が損なわれる可能性があります。
解雇を選択する場合のリスクと対策
解雇を選択する場合、以下のようなリスクと対策があります。
解雇を選択するリスク
従業員を解雇する場合、手続きが適切でない場合、解雇が無効となり、慰謝料請求のリスクがあります。また、解雇は「会社都合」での退職となり、企業イメージに悪影響を与える可能性があることを忘れてはいけません。
最終的に、従業員から「不当な解雇だ」として紛争に発展することも考えられますので、慎重に進めるべき方向性といえるでしょう。
トラブルにならない対応策
従業員とのトラブルを避けるためには、まずは解雇となる理由を明確に伝えることからはじめましょう。無断欠勤の経緯や指導の記録を整理し、解雇理由を明確にしておきます。
続いて、適切な手続きとして解雇の予告(解雇日の30日前)もしくは解雇予告手当の支払いなど、労働基準法に則った対応が重要です。
法的リスクを最小限に抑えるためには、必要に応じて社労士に相談されることをおすすめいたします。
労働問題を回避するための留意点
労働問題を回避するために、以下の6点に留意することが重要です。
- 就業規則の整備: 自然退職や解雇に関する規定を明確に定め、従業員に周知します。
- コミュニケーションの重視: 従業員との対話を重視し、問題の早期発見と解決に努めます。
- 公平性の確保: 全ての従業員に対して公平な対応を心がけ、差別的な扱いを避けます。
- 記録の保管: 無断欠勤や業務遂行状況、指導の経緯などを適切に記録し保管します。
- 健康管理への配慮: メンタルヘルスケアを含む従業員の健康管理に注意を払い、問題の予防に努めます。
- 法令遵守の徹底: 労働基準法をはじめとする関連法令を遵守し、適切な労務管理を行います。
これらの点に注意を払うことで、自然退職や解雇に関する労働問題のリスクを軽減し、より健全な労使関係を構築することができます
無断欠勤の予防と職場環境改善
無断欠勤は企業にとって深刻な問題ですが、適切な予防策と職場環境の改善により、その発生リスクを大幅に低減することができます。
ここでは、無断欠勤の主な原因を分析し、メンタルヘルスケアの重要性、そしてコミュニケーション改善と信頼関係構築について詳しく解説します。
無断欠勤の主な原因分析
無断欠勤の背景には様々な要因が存在します。主な原因を理解することで、効果的な予防策を講じることができます。
- 自己管理の不足:寝坊や二日酔いなど、個人の自己管理能力の欠如が原因となることがあります。
- 職場環境の問題:ハラスメントや人間関係の悩みが無断欠勤のきっかけとなる場合があります。
- メンタルヘルスの問題:うつ病や適応障害などの精神疾患が原因で、連絡ができない状況に陥ることがあります。
- 突発的な事故や病気:予期せぬ事故や急病により、連絡が取れなくなる場合もあります。
- 仕事への不満や責任感の欠如:配属先や業務内容への不満、あるいは仕事に対する責任感の不足が無断欠勤につながることがあります。
これらの原因を把握し、適切な対策を講じることが無断欠勤の予防には不可欠です。
メンタルヘルスケアの重要性
従業員のメンタルヘルスケアは、無断欠勤の予防において極めて重要な役割を果たします。主に次の5つの対応策は、従業員のメンタルヘルスケアにおいて重要な役割を果たしますので、ご参考ください。
- ストレスチェックの実施:定期的なストレスチェックを行い、従業員のメンタル状態を把握します。
- 相談窓口の設置:従業員が気軽に相談できる窓口を設け、早期の問題発見と対応を可能にします。
- 産業医との連携:メンタルヘルスの専門家である産業医と連携し、適切なケアを提供します。
- 休暇取得の促進:有給休暇の取得を奨励し、従業員のリフレッシュを支援します。
- 長時間労働の是正:過度な残業を抑制し、ワークライフバランスの改善を図ります。
メンタルヘルスケアを重視することで、従業員の心身の健康を維持し、無断欠勤のリスクを軽減することができます。
コミュニケーション改善と信頼関係構築
良好なコミュニケーションと信頼関係は、無断欠勤の予防に大きく寄与します。
- オープンな対話の促進:上司と部下、同僚間でのオープンなコミュニケーションを奨励します。
- 定期的な面談の実施:上司と部下の間で定期的な面談を行い、業務上の課題や個人的な悩みを共有する機会を設けます。
- チームビルディング活動:部署やチーム単位でのイベントや活動を通じて、従業員間の信頼関係を強化します。
- フィードバック文化の醸成:建設的なフィードバックを日常的に行い、相互理解を深めます。
- 透明性の確保:会社の方針や決定事項を適切に共有し、従業員の不安や疑問を解消します。
- 多様性の尊重:個々の従業員の個性や価値観を尊重し、インクルーシブな職場環境を創出します。
これらの取り組みにより、従業員が安心して働ける環境を整え、無断欠勤のリスクを大幅に減少させることができます。
無断欠勤の予防と職場環境改善は、単に罰則を設けるだけでは達成できません。従業員の心身の健康に配慮し、オープンで信頼関係に基づいた職場文化を醸成することが、長期的かつ持続可能な解決策となります。
無断欠勤・自然退職に関する法的知識
無断欠勤と自然退職に関する法的知識は、人事労務管理において非常に重要です。これらの概念を正しく理解し、適切に対応することで、労使間のトラブルを防ぎ、円滑な職場運営を実現することができます。
労働基準法における無断欠勤の扱い
労働基準法では、無断欠勤に関する明確な規定はありませんが、行政通達により一定の指針が示されています。
- 無断欠勤の定義:労働者が事前の連絡や許可なく勝手に仕事を休むことを指します。
- 懲戒解雇の基準:行政通達では、「原則として2週間以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」を懲戒解雇に相当する事由としています。
- 解雇の有効性:無断欠勤の期間が2週間未満の場合、解雇が不当と判断される可能性が高くなります。例えば、6日間程度の無断欠勤で解雇した場合、不当解雇と判断された裁判例があります。
裁判例から学ぶ自然退職の有効性
自然退職の有効性については、以下の裁判例から重要な示唆を得ることができます。
- 就業規則の重要性:自然退職を有効に成立させるためには、就業規則にその旨の規定が必要です。
- 正当な理由の考慮:無断欠勤が続いている場合でも、その原因がうつ病などの精神疾患である場合、正当な理由のない欠勤とは言えない可能性があります。
- 会社の対応義務:約40日間の欠勤を理由に諭旨退職処分とした事例で、会社は精神科医による健康診断や必要な治療の勧奨、休職などの対応を検討すべきだったとして、懲戒処分が無効とされた判例があります。
- 休職理由と就労不能の判断:休職理由に含まれない事情を根拠に就労不能と判断して自然退職扱いにすることは認められません。
これらの法的知識を踏まえ、無断欠勤や自然退職に関する対応を行う際は、就業規則の整備、従業員への周知、適切な手続きの遵守が重要です。また、個々の事案に応じて慎重に判断し、必要に応じて専門家に相談することが望ましいでしょう。
まとめ:適切な無断欠勤対応で労務リスクを軽減
無断欠勤への適切な対応は、企業の労務リスク軽減に直結します。
最後に、これまでの内容を踏まえ、無断欠勤が14日続いた場合に対するルールの正しい運用、従業員ケアと職場環境改善の重要性、そして専門家への相談の必要性について整理しましたので確認していきましょう。
無断欠勤14日ルールの正しい運用
無断欠勤14日ルールを適切に運用することは、労務管理の要となります。
- 就業規則への明記:14日ルールを就業規則に明確に定め、従業員に周知することが重要です。
- 段階的な対応
- 1-3日目:電話やメールで連絡を試みる
- 4-7日目:緊急連絡先や家族への連絡
- 8-13日目:自宅訪問や警察への相談を検討
- 14日目以降:自然退職や解雇の手続きを検討
専門家への相談と適切な対応の必要性
無断欠勤や自然退職に関する問題は、法的リスクを伴う複雑な案件となる可能性があります。そのため、専門家への相談と適切な対応が重要です。
適切な無断欠勤対応は、単に罰則を設けるだけでなく、従業員のケアと職場環境の改善、そして専門家の知見を活用した総合的なアプローチが必要です。これにより、労務リスクを軽減し、健全で生産性の高い職場環境を実現することができます。
弊社ではトラブルを防止するための就業規則・社内ルールの策定支援を行っていますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
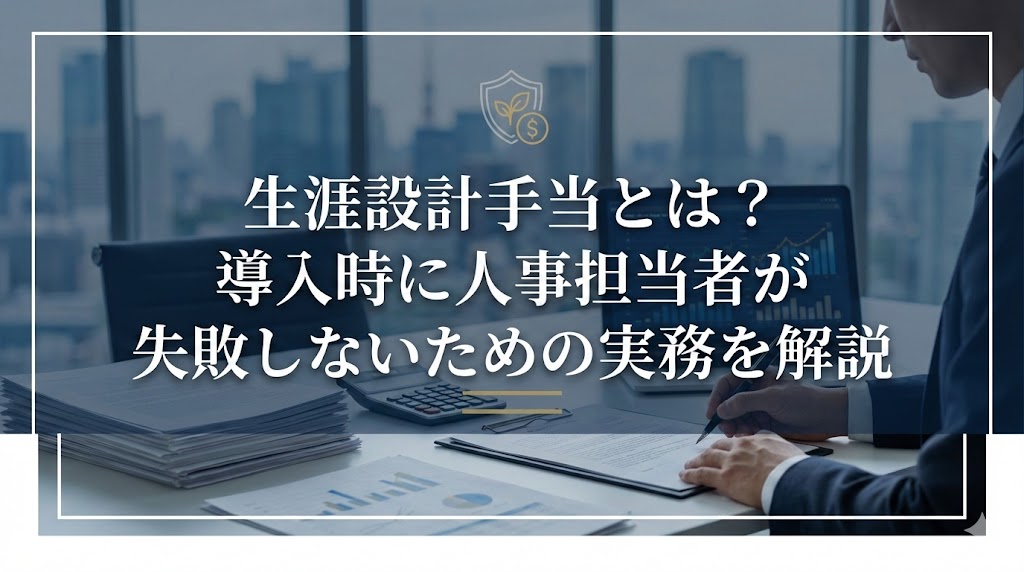 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説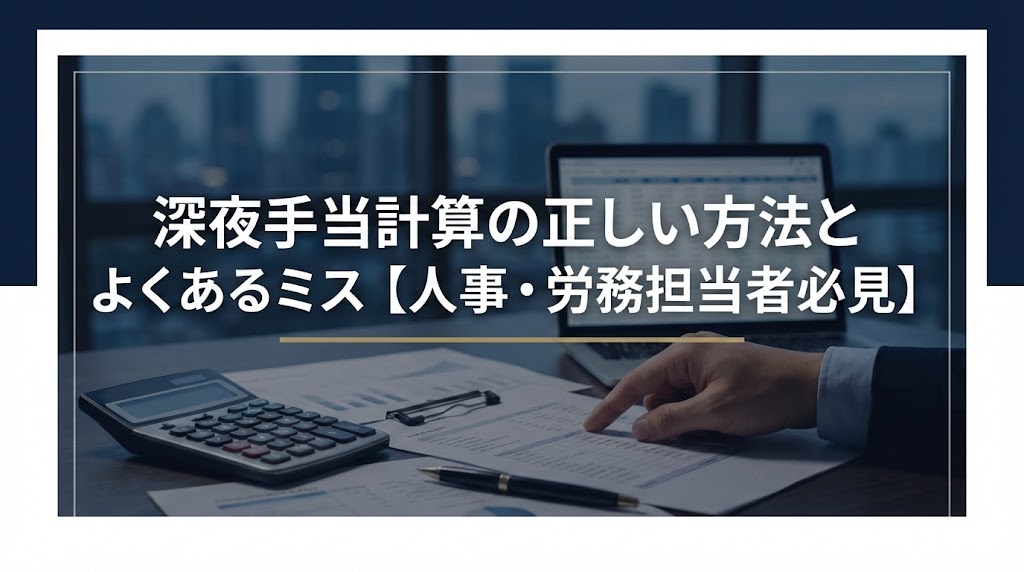 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】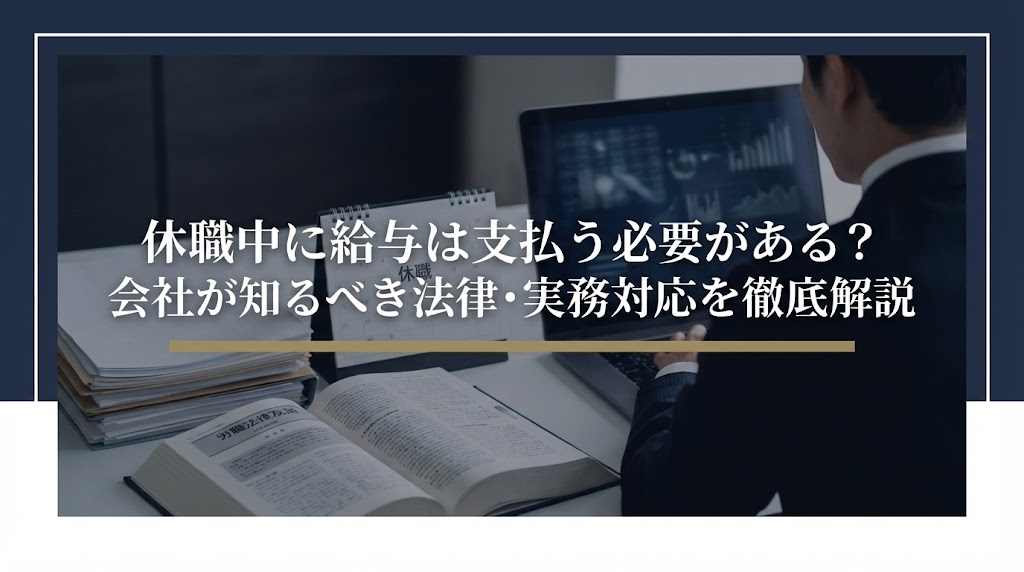 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説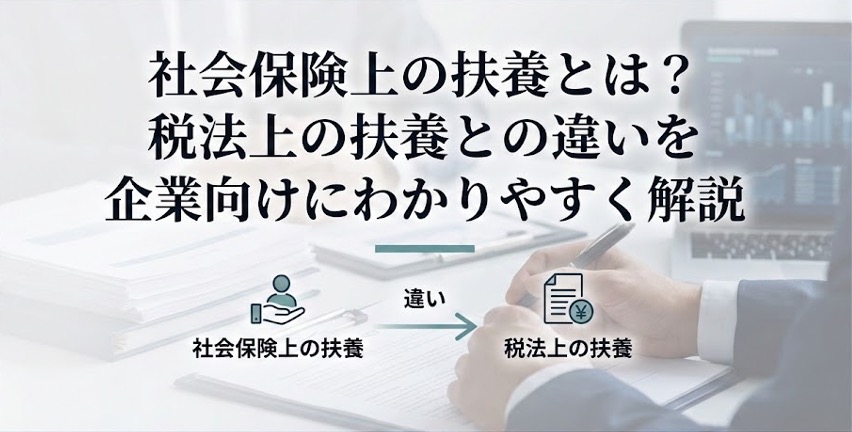 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
