会社を経営する中で、従業員を新しく役員や執行役員に登用することがあります。このとき「今までは従業員として雇用していたため、有給休暇を与えていたけど、役員にすると必要ないのか?」と疑問に思われる経営者の方もおられるのではないでしょうか。
実際顧問先の経営者の方より
- 新しく登用した役員から有給休暇の申請があるのだが、どうしたら良いのか?
- 執行役員にも有給休暇を与えるべきなのか?
こういったご相談をいただくことがあります。結論、役員は原則として「労働者ではないため、労働基準法が適用されない」ため、有給休暇の付与も必要ありません。
しかしながら「役員」として契約しているにも関わらず労働者としての性質がある場合や「執行役員」については注意が必要になります。
今回のコラム記事では、役員や執行役員に対して有給休暇の付与が必要なのか詳しく解説いたします。
役員に有給休暇は必要?
役員に有給休暇は必要かどうかは、会社経営者や人事労務担当者の方で議論されることがあります。
結論、役員は労働者ではありませんので、労働基準法が適用されないことから、有給休暇が付与されないのが原則です。
一方で実務上では役員にも有給休暇を付与したほうが良いのでは?というご相談をいただくことがあります。まずは役員と一般の労働者の違いについて確認していきましょう。
役員と労働者の違い
役員と労働者の間には
- 雇用契約の有無
- 労働基準法の適用範囲
大きく2つの違いがあります。
雇用契約の有無
通常、労働者は会社と雇用契約を結びます。これは会社から労働者に対して、労働力の提供を請負わせる契約ですので、会社は労働者に労働をさせる権利を持ち、労働者は、使用者に対して労働を提供する義務を負います。
一方で委任契約とは、委任者から受任者に対して、一定の事務を委託する契約です。委任者は、受任者に事務の遂行を依頼し、受任者は、委任者の指示に従って事務を遂行します。
役員は雇用契約ではなく「委任契約」を結ぶことになりますので、会社に雇用されている労働者とは異なるのです。
労働基準法の適用範囲
役員は、労働基準法が適用されません。一方、労働者は労働基準法が適用されます。そのため下記表のように、労働基準法で定められたルールの適用有無が、役員と労働者には発生することになります。
| 項目 | 役員 | 労働者 |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 適用されない | 適用される |
| 労働時間 | 定めはない | 1日8時間・1週40時間等 |
| 残業時間 | 定めはない | 月45時間・年360時間等 |
| 休日 | 定めはない | 1週1休・4週4休等 |
| 休暇 | 定めはない | 年次有給休暇・育児休暇等 |
| 賃金 | 役員報酬 | 基本給、諸手当 |
役員に有給休暇が付与されない理由
重ねてになりますが、役員に有給休暇が付与されない理由は、以下の2つです。
- 役員は労働者ではない
- 役員は経営判断を行う立場にある
役員は労働者ではないから
役員は、会社と委任契約を結んでいるため、労働者ではありません。労働基準法は、労働者に適用される法律です。そのため、労働者ではない役員には、労働基準法が適用されることがありません。
役員は経営判断を行う立場にあるから
役員は、会社の経営判断を行う立場にあります。そのため、常に会社のために働く必要があると考えられています。
役員に有給休暇を付与するメリット
ここまで「役員は労働者ではないから有給休暇が付与されない」と解説をいたしましたが、便宜上役員にも有給休暇を付与している会社はあります。
特に
有給休暇取得義務への対応をリードするため
2019年4月以降、働き方改の一環として年次有給休暇が年間10日付与される労働者に対して、会社は年間5日間は有給休暇を取得させる義務を負うことになりました。
有給休暇の取得を促進させるために、経営者層が自ら率先して休暇を取得することで、組織風土の改善・向上が期待できます。
役員のモチベーションアップ
役員にも有給休暇を付与することで、役員のモチベーションアップにつながります。
役員は、労働者ではないため、労働基準法の適用は受けません。しかし委任契約の内容をどのようにするのか、会社と役員の間で協議することになりますので、有給休暇を与えることは可能です。
有給休暇を付与することで、役員のモチベーションアップを図ることができます。
企業のブランディング向上
役員にも有給休暇を付与することで、企業のブランディング向上につながります。
有給休暇は、労働者の権利として認知されています。そのため、役員にも有給休暇を付与することで、企業が労働者の権利を尊重していることをアピールすることができます。
使用人兼務役員には有給休暇が付与される?
使用人兼務役員とは、役員として会社経営に携わる一方で、従業員として労働契約を締結している者のことを指します。
取締役兼営業部長や取締役兼工場長などがこれにあたります。
使用人兼務役員の有給休暇の取り扱い
使用人兼務役員は、労働者としての要素が強いと認められる場合には、労働基準法が適用されます。そのため、有給休暇の付与や取得義務などの労働基準法上の権利が認められます。
具体的には、使用人兼務役員の有給休暇の取り扱いは、以下のとおりです。
- 有給休暇の付与:労働基準法に基づき、6か月以上継続勤務した場合には10日以上の有給休暇が付与され、その後も法律上の付与がされます。
- 取得義務:労働基準法に基づき、年次有給休暇は、労働者の請求により与えなければなりません。
使用人兼務役員に有給休暇を付与するかどうかは、その者の労働者としての要素の強弱によって判断されます。労働者としての要素が強いと認められる場合には、有給休暇を付与することが一般的です。
前述の「役員」に対しても、使用人兼務役員と同様に「労働者としての性質」が認められる場合には、労働基準法の適用対象となる可能性があります。
そのため、例え委任契約を結んでいる役員であっても、実態が労働者であれば有給休暇を付与しなければならないケースも考えられますので、注意をしましょう。
まとめ
今回のコラム記事では「役員や執行役員に有給休暇は必要?法律や実務上の考え方を解説」として、役員や執行役員に対する有給休暇の考え方を解説いたしました。
役員は、労働基準法が適用されないため、原則として有給休暇は付与されません。しかし、使用人兼務役員の場合は、労働基準法が適用されるため、有給休暇を付与するかどうかを検討する必要があります。
労務管理は、企業経営において重要な要素です。役員や執行役員に対してどのような契約を結ぶのか、判断が難しい場合もあると思います。弊社では、トラブルを未然に防止するための雇用契約や委任契約の制度設計に強みがありますので、お気軽にお問い合わせください。
労務管理に関する豊富な知識と経験を持つ専門家が、お客様の状況に応じた最適なご提案をさせていただきます。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
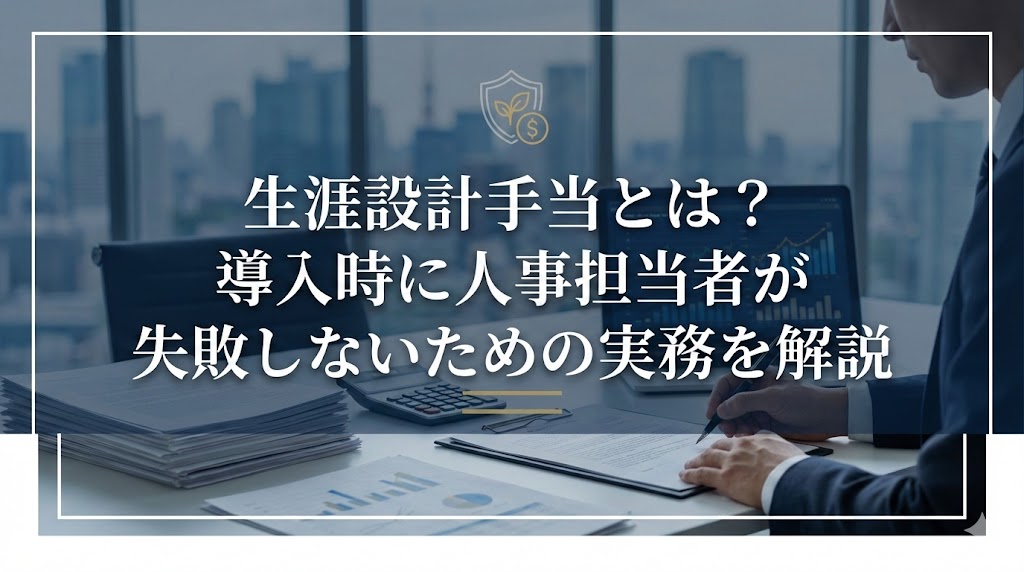 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説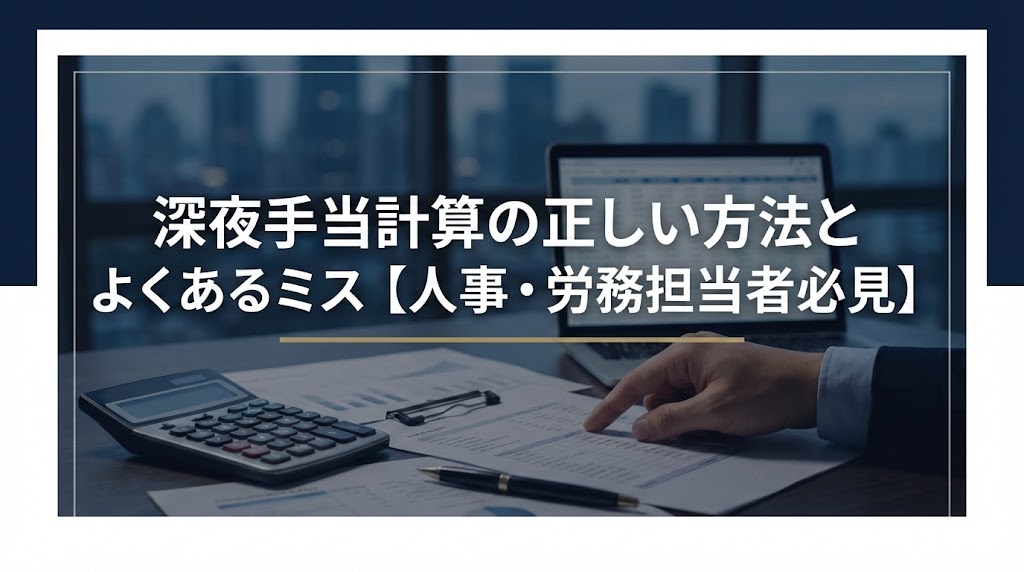 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】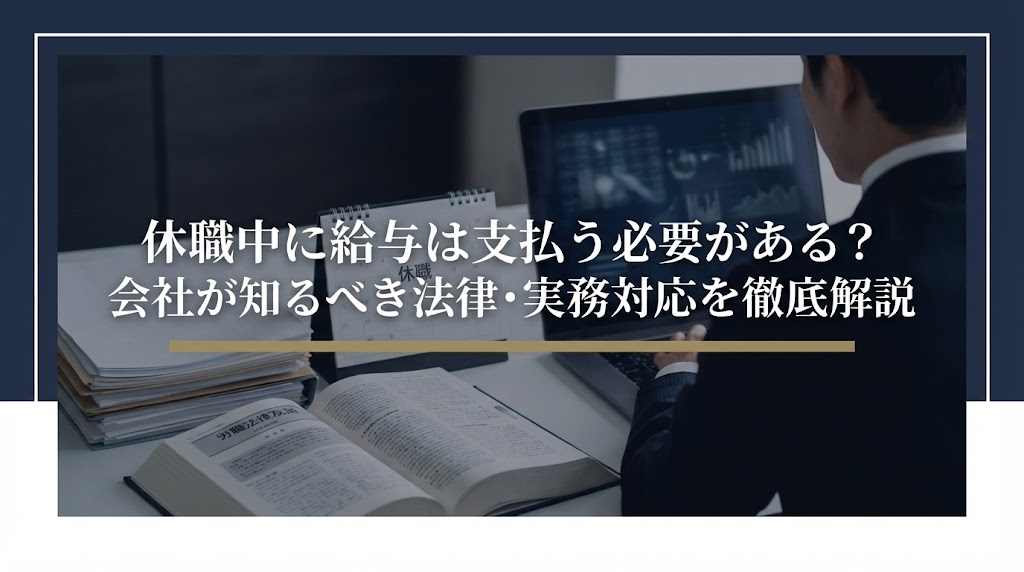 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説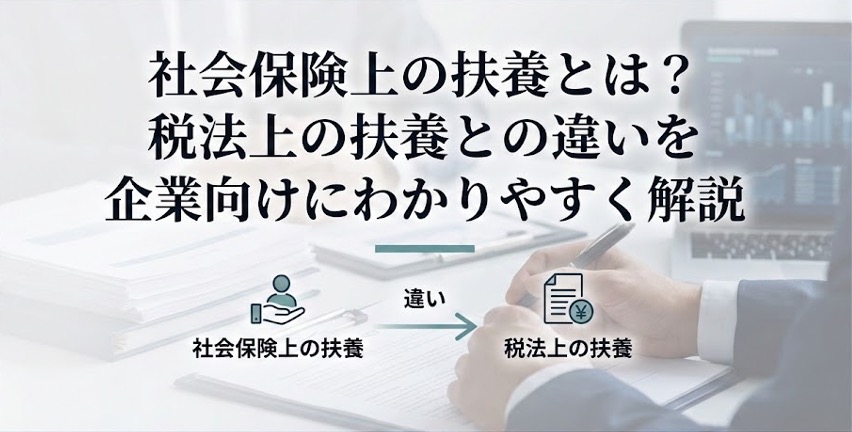 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
