2019年より順次施行された働き方改革の法律。その中でもとくに経営者の頭を悩ませる種になっているのが「年次有給休暇取得義務化」ではないでしょうか?
弊社の顧問先様からも「有給休暇が取得できない場合は何かリスクがあるのか?」というお問い合わせは、法改正から数年経った今でもいただいております。
今回は「有給休暇の取得義務化を徹底解説:5日取得できなかった場合のリスクとは」と題しまして、有給休暇の取得が未達だった際のリスクや罰則、人的リソースの観点から対応が難しい中小企業での取るべきアクションについてわかりやすく解説いたします。
会社経営者、人事労務担当者の方は本記事を参考に、有給休暇取得促進にチャレンジいただけますと幸いです。
年次有給休暇の5日取得義務化とは?
日本における労働基準法では、
- 雇入れの日から6か月継続勤務
- 全労働日の8割以上出勤
という条件を満たすと、正社員、パート問わず年次有給休暇が一定数与えられます。この年次有給休暇が一年間で10日以上発生する従業員については「5日間を取得義務化させる」法律が2019年4月に施行されました。
この法律の背景には、従業員の健康とワークライフバランスの保護、そして生産性の向上を目的として導入されたものになります。
5日の有給休暇、いつからいつまでの期間を指す?
「5日の有給休暇」は、従業員が有給休暇の権利を得てからの1年間に、最低5日を取得することが求められる制度を指します。
例えば正社員の場合、雇用されてから6ヶ月後に10日の年次有給休暇が付与されますので、この付与日から1年経過するまでの間に、5日間は有給休暇を利用させる必要があるのです。
中小企業における有給休暇義務化の実際
中小企業においても、有給休暇の取得義務は例外なく適用されます。
しかし、実際には多くの中小企業で有給休暇が取得されていないという課題があります。一因として、
- 人的リソース不足(労働力が足りず、有給休暇を利用できる環境ではない)
- コンプライアンス意識の低さ(法令遵守の意欲が低い)
こういったものが考えられます。
しかしながら、有給休暇の取得義務化については労働基準法に基づく制度になりますので、守らなかった場合は罰則が存在しています。また、有給休暇取得を促進するための取り組みが不足していると労働基準監督署に判断された場合には行政指導の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
有給休暇を取得できなかった場合のリスクと罰則
2019年の法改正以降、有給休暇の取得は少しずつ進んでいますが、実態として法令遵守ができていないケースもあります。
会社側が取得促進をしていても、従業員が自ら取得しなかった場合も実は会社側が責任を負うリスクもありますので、有給休暇を取得しなかった場合のリスクや罰則、それに関連する具体的な事例や対策を詳しく解説します。
具体的な罰則実例:有給休暇の5日未取得時に何が起きる?
結論、有給休暇が5日取得できなかった場合、労働基準監督署の行政指導を受けることになります。特に、年次有給休暇を巡るトラブルは多く
- 特に理由がないのに有給休暇の申請を拒否している
- 有給休暇の申請はあったが、承認をしていないので欠勤扱いにしていた
- 年5日間の有給取得義務を守らない
- 年次有給休暇の管理簿を作っていないため管理ができていない
こういった場合、労働基準監督署から重点的に指摘される可能性があります。そして「5日取得義務化」が守れていない場合、法的措置として「書類送検」や「罰金」が科せられることもあるなど、注意をしなければなりません。
直近の具体的な事例として、茨城県の飲食店や、愛知県の食品会社が送検されています。
茨城・龍ヶ崎労働基準監督署(大畠成明署長)は、年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして、飲食業の(有)とむとむ(茨城県北相馬郡)と同社代表取締役を、労働基準法第39 条(年次有給休暇)違反の疑いで水戸地検土浦支部に書類送検した。同社は、平成31 年4 月1 日~令和4 年3 月31 日の期間において、年10 日以上の年休が付与される労働者全員に対して時季指定を怠り、年5 日間を取得させていなかった疑い。労働者2 人が退職前に申請・取得した年休について、賃金を支払わなかったとして、同法第24 条(賃金の支払い)違反の疑いでも立件した。
労働新聞社「年休の時季指定怠り送検 労働者全員が未取得 龍ヶ崎労基署」より引用
罰金は従業員一人あたりで計算される
年次有給休暇の5日取得義務が守れていない場合、労働基準法違反となりますので30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
これは守れていない従業員一人あたりに発生しますので、10人の違反時には300万円と増えてしまいます。
退職時、5日分の有給が取れなかった場合は?
退職時に5日取得できていない従業員がいたとしても、すぐさま問題になることは考えられません。ただし、退職時にトラブルになり「有給休暇を申請したが、会社から断られてしまった」と労働基準監督署に通報されるリスクもあります。
そのため、退職時に最低5日を満たすように有給休暇を取得してもらい、法的観点はクリアしておくことが望ましいといえます。
会社の立場で考える:有給休暇義務化の「バレない」対策はある?
有給休暇の取得を奨励するための取組みは、企業の社会的責任として重要です。そのため有給休暇の取得状況を隠し、「バレない対策」をとるのは法的にリスクが伴います。有給休暇の取得ができるように、現場の状況を改善するなどを行い、従業員の健康管理・モチベーション向上を目指すことがベストといえます。
具体的には、取得しやすい環境の整備や、上司や経営者からのメッセージ発信、育児や介護といったライフイベントへの対応を考慮した取得プランの提案などが考えられます。
中小企業と有給休暇の現状
中小企業の経営者や人事担当者は、大手企業とは異なる課題があります。中でも「人的リソースの確保が難しい」というお声はよくお聞きします。
中小企業における有給休暇の取得の現状や、義務化について猶予があるのか確認してみましょう。
中小企業での有給休暇の取得実態
中小企業における有給休暇の取得実態は、業界や地域、経営状況などによって大きく異なりますが、一般的には大手企業と比べて取得率が低い傾向にあります。
厚生労働省「令和4年就労条件総合調査」によると、
- 1,000人以上:平均付与日数が18.5日に対して、平均取得日数は11.7日
- 300~999人:平均付与日数が17.8日に対して、平均取得日数は10.2日
- 100~299人:平均付与日数が17.1日に対して、平均取得日数は9.5日
- 30~ 99人:平均付与日数が16.7日に対して、平均取得日数は8.9日
と、従業員規模が小さくなるにつれて平均取得日数も減少している実態があります。この背景には、人手不足や業務の繁忙、そして労働者の取得意識の低さなどが影響していると考えられます。
取得しづらい文化や風土が根付いている場合も多く、それを変えるための取組みや改善策の導入が求められています。
中小企業には有給休暇義務化の猶予はあるのか?
有給休暇の義務化に関する法律は、中小企業に対して特別な猶予期間を設けているわけではありません。そのため2019年4月以降は、年次有給休暇が10日以上付与される従業員を雇用している限り、大企業や中小企業、個人事業主問わず法律が適用されます。
企業の状況や特性を考慮して、有給休暇が取得できるように「計画的付与」や「会社からの時季指定」といったアプローチが必要になります。
有給休暇が取れない場合の企業・従業員に対する悪影響
有給休暇の取得義務化は、従業員の健康やワークライフバランスを考慮して制定されている制度です。取得をさせずに放置してしまうと、することなく放置される場合も残念ながらあります。
法的観点では「罰金」や「行政指導」の対象と解説しましたが、それ以上に悪影響につながる恐れもありますので、従業員・会社の双方の立場で考えてみましょう。
従業員側から見た有給休暇未取得の悪影響
有給休暇を取らないことで従業員に及ぼす悪影響は、健康上の問題が主となります。
連続的な勤務は、肉体的・精神的疲労を蓄積させ、ストレスや過労からくる健康トラブルの原因となります。また、継続的な労働はモチベーションの低下や業務の効率の低下を引き起こし、キャリアアップの妨げとなることもあるでしょう。
企業側から見た有給休暇未取得のリスクと対策
企業側にとって、労働者の有給休暇の未取得は様々なリスクをはらんでいます。過労やモチベーションが下がることで生産性の低下や退職、最悪のケースとして過労死を起こすことも考えられます。
また、近年ではSNSサービスの流行により、ブラック企業として社名が広まってしまうと会社のイメージは悪化することになります。
単なる法令違反、ではなく、会社全体に悪影響を及ぼす可能性もありますので、有給休暇が未取得を問題・課題として受け取る必要があります。
会社としては、以下のような点を考慮することをご検討ください。
- 有給休暇取得推進の社内制度の導入:例えば、一定期間内に取得しない場合には自動的に取得する日を設定するなど。
- 社内文化の醸成:上層部からのメッセージや啓発活動を行い、有給取得の重要性を従業員に伝える。
- 情報提供:有給休暇の取得状況や未取得日数を定期的に公開し、取得を促す。
まとめ
今回は
- 有給休暇取得義務化の基本的な内容
- 5日取得ができなかった場合の法的リスクや悪影響
の内容を解説いたしました。法改正からしばらく経過していますが、実際の企業運営・人事労務の現場では頭を悩ませることもあるかと思います。特に中小企業様では、細やかな対応や柔軟な運営が求められることも少なくありません。
「具体的なケースでの対応はどうすればよいのか」「会社の現状に合わせた有給休暇の取得推進方法を知りたい」など、さらなる詳細や具体的なアドバイスが必要な場合は、お気軽に社会保険労務士法人ステディまでお問い合わせください。専門のスタッフが一つ一つお悩みを解消し、最適な対応策をご提案いたします。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
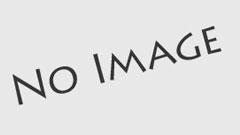 お知らせ2024.07.09夏季休業のお知らせ
お知らせ2024.07.09夏季休業のお知らせ ニュース一覧2024.06.02社会保険の加入条件とは?30時間を超えたり超えなかったりする場合の対応を解説
ニュース一覧2024.06.02社会保険の加入条件とは?30時間を超えたり超えなかったりする場合の対応を解説 ニュース一覧2024.06.02社会保険調査は厳しい? その理由と調査の流れを解説!
ニュース一覧2024.06.02社会保険調査は厳しい? その理由と調査の流れを解説!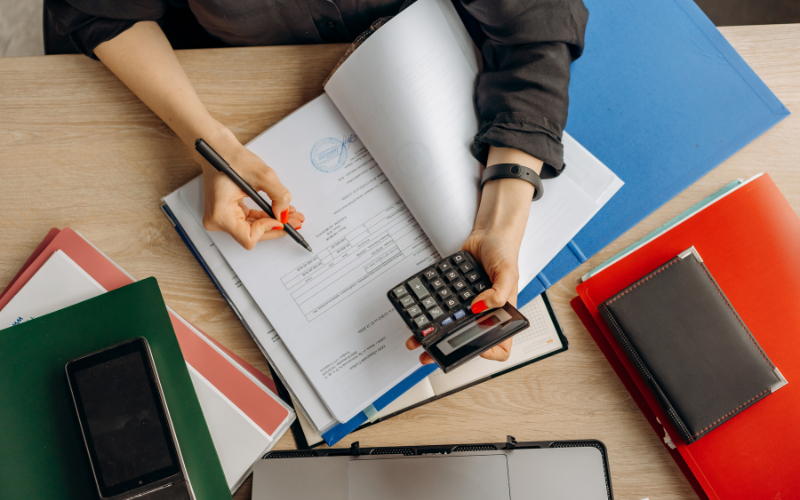 ニュース一覧2024.05.03キャリアアップ助成金(正社員化コース)は審査が厳しい?申請までの注意点を社労士が解説
ニュース一覧2024.05.03キャリアアップ助成金(正社員化コース)は審査が厳しい?申請までの注意点を社労士が解説
