所定時間外労働という言葉を耳にしても、「残業」との違いや正確な意味を理解している方は意外と少ないかもしれません。
実は、労働時間の考え方には「所定労働時間」「法定労働時間」「時間外労働」など、複数の区分が存在し、それぞれに異なるルールと対応が求められます。
本記事では、所定時間外労働の定義から法定労働時間との違い、残業代の計算方法、さらには36協定や割増賃金のルールまでを、社労士の視点でわかりやすく解説します。
労務トラブルを未然に防ぎ、適切な時間管理と賃金対応を行うために、ぜひ最後までご覧ください。
所定時間外労働とは何か?
企業で働くうえで「労働時間」は非常に重要なポイントですが、その中でも特に混同しやすいのが「所定時間外労働」と「法定時間外労働」の違いでしょう。
労務管理を適切に行うためには、まずこれらの用語を正しく理解することが不可欠です。まずは、企業の担当者や人事労務担当者が押さえておくべき基礎知識として、「所定労働時間」と「法定労働時間」の違い、そして「所定時間外労働」と「法定時間外労働」の定義について、専門的な観点からわかりやすく解説します。
所定労働時間と法定労働時間の違い
「所定労働時間」と「法定労働時間」は似ているようで、法律上の意味合いや管理方法が異なります。以下の内容を正しく理解することで、労働時間に関する誤解を防ぐことができます。
所定労働時間とは
所定労働時間とは、企業と従業員の間で就業規則や雇用契約書に定めた、1日または1週間あたりの基本的な労働時間のことを指します。たとえば、9:00~17:00(休憩1時間)の勤務であれば、1日7時間が所定労働時間です。
所定労働時間を整理すると、
- 従業員が働くべき労働時間を会社が定めている
- 就業規則や雇用契約に明記されている
- 法定労働時間より短いこともある
上記のような特徴があります。
法定労働時間とは
法定労働時間とは、労働基準法によって定められた、原則として労働者が1日または1週間に働くことができる上限時間のことです。
- 原則:1日8時間・1週40時間(労働基準法第32条)
- これを超える場合は、原則として残業扱いとなる
- 業種や特例措置によって異なる場合あり
所定労働時間は「会社独自の基準」、法定労働時間は「法律上の基準」と理解しておくと良いでしょう。
所定時間外労働と法定時間外労働の定義
残業という言葉の中には、実は「所定時間外労働」と「法定時間外労働」という2種類の意味合いが含まれています。それぞれの違いを明確にすることが、適切な割増賃金の支払いや36協定の締結判断にも関わってきます。
所定時間外労働とは
所定時間外労働とは、就業規則などで定められた所定労働時間を超えて働く労働のことを指します。ただし、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えていない限り、法的には「時間外労働」とは扱われません。
たとえば、「所定労働時間が1日7時間の企業で、8時間勤務した場合」この1時間は「所定時間外労働」であり、まだ「法定時間外労働」には該当しません。
法定時間外労働とは
法定時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働く時間を指します。この時間には、労基法に基づいた「割増賃金の支払い」と「36協定の締結」が必要となります。
具体的には、
- 1日8時間を超えて労働した時間
- 週40時間を超えて働いた合計時間
上記のように判断していきます。
所定時間外労働と、法定時間外労働を比較すると、次のようになります。
| 種別 | 対象となる時間 | 割増賃金 | 36協定の必要性 |
|---|---|---|---|
| 所定時間外労働 | 所定労働時間を超え、法定労働時間内 | ○(会社による) | ✕(原則不要) |
| 法定時間外労働 | 法定労働時間を超える労働時間 | ◎(必須) | ◎(必須) |
所定時間外労働は企業独自の時間設定に基づくため、割増賃金の支払い義務がないケースもありますが、労使トラブル防止の観点からも、一定の配慮や制度設計が望まれます。
所定時間外労働の具体例と計算方法
「所定時間外労働」という言葉だけではイメージしづらい方も多いかもしれませんが、実際には多くの企業で日常的に発生しています。
特に所定労働時間が法定労働時間よりも短い企業では、労働時間の区分や残業代の支払いに関して正確な理解が求められます。この章では、所定時間外労働が実際にどのようなケースで発生するのかを具体例を交えて解説するとともに、「法定内残業」と「法定外残業」の違いにも触れながら、計算の考え方をわかりやすく紹介します。
所定労働時間が7時間の場合の残業時間の考え方
企業によっては、1日7時間労働を基本とするところも少なくありません。このような場合、1日8時間までの労働は「法定内」に収まるものの、会社が定めた所定時間を超えているため、いわゆる「残業」として扱われることがあります。
具体例
- 所定労働時間:9:00〜17:00(休憩1時間)=実働7時間
- 実際の勤務時間:9:00〜18:00(休憩1時間)=実働8時間
この場合、17:00〜18:00の1時間が「所定時間外労働」にあたります。
ただし、法定労働時間(1日8時間)はまだ超えていないため、法律上の「時間外労働」には該当しません。
注意すべきポイント
- 就業規則で「所定時間外労働にも割増賃金を支払う」としている場合、企業にはその支払い義務が生じます。
- 一方で、特に割増賃金の規定がない場合は、通常の賃金を支払うのみで違法とはなりません。
労働者にとっては「残業している」感覚があるため、処遇に関する不満や誤解を防ぐには、明文化されたルールが重要になります。
法定内残業と法定外残業の違い
「残業」とひとくちに言っても、法的な区分では「法定内残業」と「法定外残業」に分けられます。労働時間の管理や賃金計算を適切に行うためには、この違いを正確に理解しておく必要があります。
法定内残業とは
- 所定労働時間を超えているが、法定労働時間(1日8時間・週40時間)には達していない労働時間
- 例:所定7時間→8時間働いた場合の1時間
- 割増賃金の支払いは法的義務ではないが、会社の就業規則により支払うこともある
法定外残業とは
- 法定労働時間を超える時間の労働
- 例:1日8時間を超えた分、または週40時間を超えた分
- 原則として、25%以上の割増賃金の支払いが必要(労基法第37条)
- 実施には36協定の締結が必要
法定内残業と法定外残業の比較
| 区分 | 労働時間の範囲 | 割増賃金の支払い義務 | 36協定の必要性 |
|---|---|---|---|
| 法定内残業 | 所定労働時間超~法定労働時間内 | 任意(会社の定めによる) | 不要 |
| 法定外残業 | 法定労働時間超 | 必須(25%以上) | 必須 |
企業としては、残業の区分ごとに賃金ルールを明確にし、従業員に周知徹底することが重要です。曖昧な運用が続くと、未払い残業代や労使トラブルのリスクを高めることになります。社労士などの専門家と相談しながら制度を整備しておくと安心です。
所定時間外労働に関する法律と36協定
所定時間外労働が発生する場合、企業には法令に基づいた対応が求められます。
特に「36協定(さぶろくきょうてい)」の締結は、時間外労働や休日労働を行わせる際に必要不可欠な手続きです。また、近年では時間外労働の上限規制が強化され、違反に対して行政指導や罰則も科されるようになっています。この章では、所定時間外労働を適法に行うために知っておくべき36協定の概要や、上限規制・割増賃金のポイントを専門家の視点でわかりやすく解説します。
36協定の概要と締結の必要性
労働基準法第36条に基づき、企業が労働者に法定労働時間を超えて働かせるには、労使間で「時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)」を締結し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
36協定のポイントとしては、
- 対象:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働、および休日労働
- 手続き:労働者代表と書面で協定を締結し、労基署へ届け出る
- 効果:協定があることで、法律上の「残業命令」が可能になる
上記を把握しておけると企業の労務管理が適法に繋がります。
所定時間外労働が法定労働時間を超える場合は、この36協定がなければ違法な時間外労働と判断される可能性があります。つまり、企業が従業員に残業を依頼する際の“土台”となるのが36協定です。
時間外労働の上限規制と特別条項付き36協定
2019年の法改正により、時間外労働には明確な「上限」が設けられました。これにより、従来よりも厳格な労働時間管理が求められるようになっています。
原則の上限
- 月45時間、年360時間まで
- 原則として、これを超える時間外労働は禁止
特別条項付き36協定
業務の繁忙期などで上限を超える可能性がある場合、「特別条項付き36協定」を締結することで例外的に上限を引き上げることが可能です。ただし、以下の条件をすべて守る必要があります。
- 年720時間以内(時間外労働のみ)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
- 2〜6か月平均で月80時間以内(休日労働を含む)
- 原則月45時間を超えるのは年6か月まで
違反があれば労働基準監督署から是正勧告や企業名の公表、さらには罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)も科されることがあるため、注意が必要です。
割増賃金の計算方法と注意点
所定時間外労働に対して支払う賃金は、時間帯や労働時間の区分に応じて、割増賃金の支払い義務が発生することがあります。正しく計算しないと未払いが発生し、トラブルや是正勧告に発展する恐れもあるため、正確な理解が求められます。
割増率の基本
- 法定時間外労働(8時間超):25%以上の割増
- 深夜労働(22時~翌5時):25%以上の割増
- 休日労働(法定休日):35%以上の割増
- 複合(例:法定外×深夜):50%以上の割増
計算式の例
1時間あたりの通常賃金が1,500円の場合は、次のように算出しなければなりません。
- 時間外労働(25%):1,500円 × 1.25 = 1,875円
- 深夜労働(25%):1,500円 × 1.25 = 1,875円
- 休日労働(35%):1,500円 × 1.35 = 2,025円
なお、企業によっては「みなし残業」「固定残業」制度を導入している場合がありますが、みなしている時間を超えた残業(超過分)は追加で支払う義務がありますので、注意しましょう。また、固定残業代の内訳や根拠を就業規則・雇用契約に明記していないと、無効とされる可能性もあります。
社労士などの専門家と連携し、システム導入による自動計算なども活用することで、リスクの最小化を図りましょう。
所定時間外労働に関するよくある質問
所定時間外労働に関する理解が深まるにつれ、現場ではさまざまな実務上の疑問が生じます。特に、サービス残業や変形労働時間制の取り扱い、管理監督者の残業代の扱いなどは、誤解されがちでありながらトラブルに直結することの多いテーマです。この章では、労務の専門家としての視点から、よくある質問に対して具体的かつ実務的に役立つ回答をまとめました。
サービス残業は違法か?
結論から言えば、サービス残業は明確に「違法」です。
労働基準法では、使用者は労働者に実際に労働させた時間に応じて、適切な賃金を支払う義務があります。たとえ上司が「つけなくていいよ」と言ったとしても、労働実態がある限り、賃金を支払わなければなりません。
サービス残業のよくある例
- 「自主的に残っていただけ」として残業記録をつけさせない
- タイムカードを先に打刻させてから作業を続けさせる
- 始業前にメールチェックや掃除などを“業務”として行わせる
このような対応は、労働時間の隠蔽にあたり、労働基準監督署の調査対象になる可能性があります。従業員から未払い残業代を請求されれば、過去5年(当面の間は3年)の遡及請求が認められます。
変形労働時間制やフレックスタイム制の場合の対応はどうすればいいですか?
変形労働時間制やフレックスタイム制といった柔軟な働き方が増える一方で、それに伴う所定時間外労働の取り扱いには注意が必要です。これらの制度を導入していても、「働いた時間」と「制度上の時間」とが適切に連動していなければ、違法な残業とされることがあります。
変形労働時間制の注意点
- 1か月単位・1年単位などの形態がある
- 所定労働時間は日によって変動する
- 「期間平均で法定時間内に収まる」設計が必要
例えば、1ヶ月の変形労働時間制度の場合、ある週に45時間働いたとしても、他の週で35時間に抑え、1か月の平均が40時間以内であれば法定内となります。ただし、計画外の残業が発生した場合は、36協定と割増賃金の対象になります。
フレックスタイム制の注意点
- コアタイムの有無に関わらず、1か月の総労働時間で評価
- 清算期間(原則1か月)を超えた労働時間は時間外扱い
- 清算期間中に法定労働時間を超えた分には割増賃金が必要
いずれの制度も、就業規則での明確な定義と、日々の労働時間の適切な管理が不可欠です。導入時には制度設計のミスや説明不足が原因でトラブルが起きやすいため、専門家と連携して運用ルールを整備しましょう。
管理監督者に残業代支払い義務はありますか?
「管理職だから残業代は不要」と思っている企業も多いですが、法律上の“管理監督者”に該当しなければ、残業代の支払い義務があります。名ばかり管理職問題として、過去には裁判でも企業側が敗訴した事例が数多くあります。
管理監督者と認められる要件
- 会社経営に関する重要な決定に関与している
- 勤務時間を自ら決定できる裁量がある
- 給与・待遇が一般職に比べて明確に優遇されている
この3つの要件を満たしていなければ、たとえ「課長」「部長」といった肩書きがあっても、法的には管理監督者とは認められません。
実務上の注意点
- 名ばかり管理職に時間外労働を命じると、未払い残業代のリスクあり
- 管理監督者でも「深夜労働」には割増賃金が必要(22時~翌5時)
- 就業規則での定義と実態が一致しているかを定期的に確認する
制度を正しく理解せずに「管理職だから残業代は不要」としてしまうと、会社側にとって大きな法的リスクになります。特に中小企業では、待遇面での優遇が曖昧なケースも多いため、慎重な判断が求められます。
まとめ|所定時間外労働の正しい理解と実務対応が、企業経営の安定につながる
所定時間外労働は、単なる「残業」とは異なり、法的区分や賃金対応、労使協定の有無など、複数の視点からの正確な管理が必要です。誤った運用は、未払い残業代や是正勧告などのリスクにつながりかねません。
もし「うちは大丈夫だろうか?」と少しでもご不安があれば、専門家として状況を確認させていただきます。適正な制度設計や見直しをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
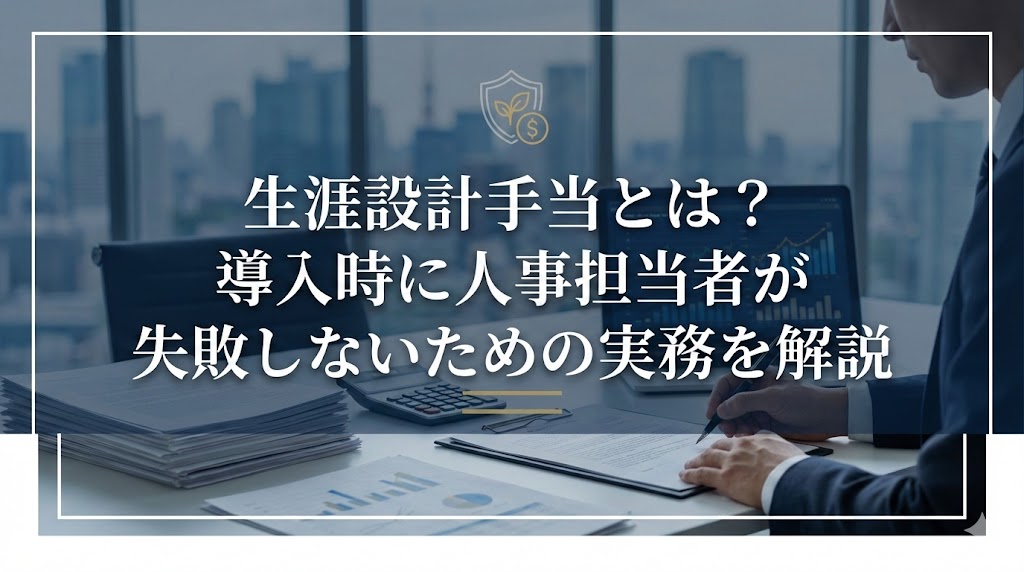 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説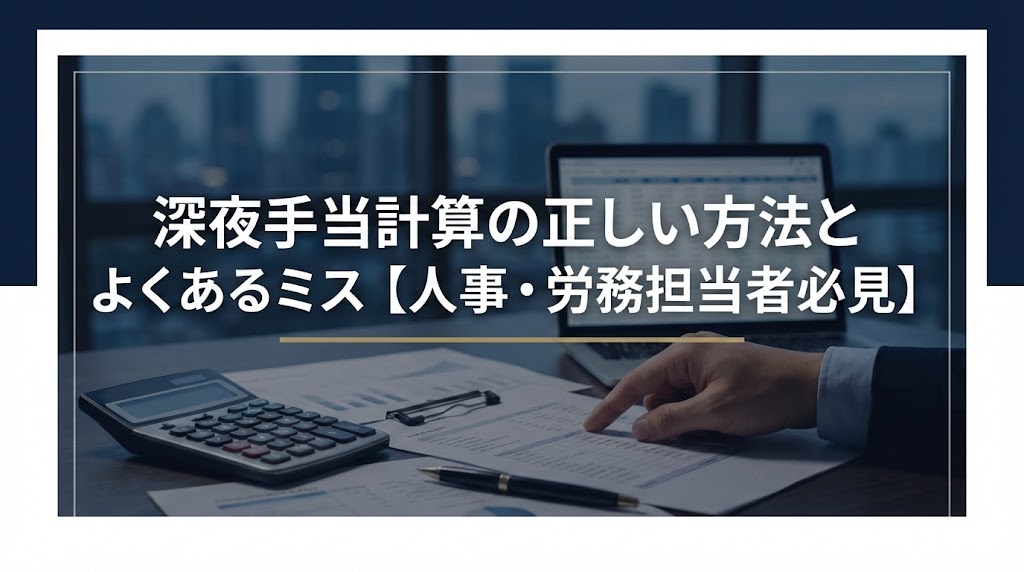 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】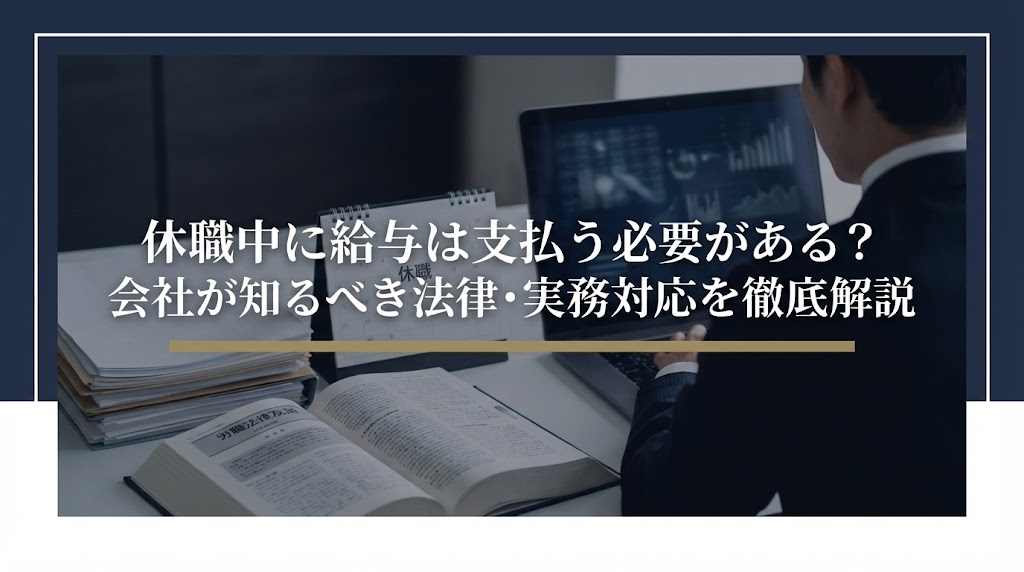 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説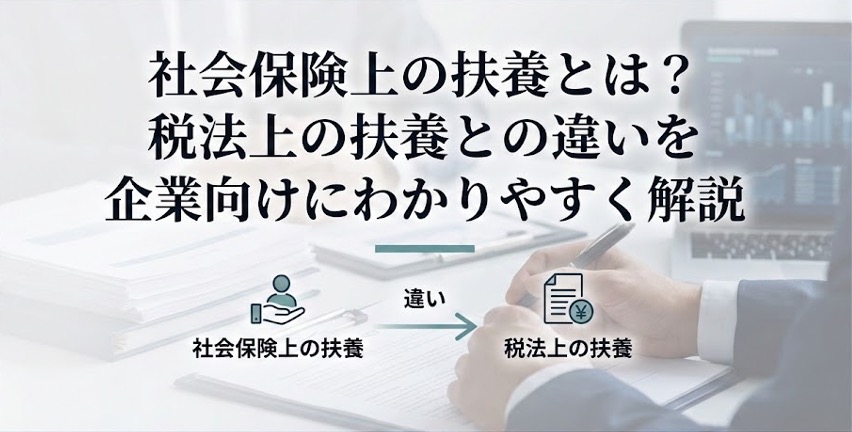 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説

