近年、多くの企業で業務委託契約から正社員への登用が検討されています。フリーランスや契約社員として活躍する優秀な人材を、より安定した形で確保することで、組織の強化を図る企業も増えています。しかし、業務委託と正社員では雇用形態が大きく異なるため、適切なプロセスを踏まないと、トラブルに発展する可能性もあります。
例えば、「正社員登用を打診したものの、条件が合わず辞退されてしまった」や「登用後に期待していた働きをしてもらえなかった」といったケースは珍しくありません。また、登用の進め方によっては、労務管理上のリスク(偽装請負の疑い、社会保険の適用漏れなど)が発生することもあります。
そこで本記事では、業務委託から正社員登用を検討する経営者や担当者に向けて、登用を成功させるためのメリット・デメリット、具体的なプロセス、トラブルを回避するためのポイントを解説します。
優秀な人材を確保し、組織の成長につなげるために、どのような準備が必要なのか。経営者や人事担当者が知っておくべき重要なポイントを詳しくご紹介します。
業務委託から正社員登用を考える背景とは?
業務委託契約を結んでいる人材を正社員として迎え入れることを検討している経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは、単なる雇用形態の変更ではなく、企業の成長戦略やリスクマネジメントの観点からも重要な選択肢となっています。
特に、長期間にわたり同じ業務を委託している人材や、専門性が高く企業の競争力を高める貴重な存在である人材を、より安定した関係のもとで雇用することは、企業にとって大きなメリットをもたらします。
しかし、業務委託のままにしておくことで発生するリスクもあるため、正社員登用を戦略的に進めることが求められます。ここでは、企業が業務委託から正社員登用を検討する主な理由と、業務委託契約のままで起こり得るリスクについて詳しく解説します。
企業が業務委託を正社員に登用する理由
優秀な人材を確保し、組織の安定性を高めるため
業務委託契約の人材は、専門スキルを持ち、即戦力として企業の業務に貢献しているケースが多いです。しかし、契約期間が決まっているため、企業側の都合で「長く働いてもらいたい」と思っても、そのままでは他社に移籍されるリスクがあります。
正社員登用を行うことで、
- 企業のノウハウを継続的に蓄積できる
- 業務の属人化を防ぎ、組織全体の生産性を向上させる
- 企業文化に馴染み、組織への帰属意識を持ってもらえる
といったメリットを得ることができます。
業務の安定化と長期的な人材戦略の一環
業務委託契約では、受託者側の都合で契約が終了する可能性があります。そのため、事業の中核となる業務を担う人材を安定して確保するためには、正社員として迎え入れることが有効です。
特に、経営戦略に直結する業務や顧客対応を行う人材であれば、突然契約終了となるリスクを避けるためにも、長期的な雇用形態への移行が望ましいでしょう。
コンプライアンスリスクを回避するため
近年、労働基準監督署が業務委託契約の実態を厳しくチェックする傾向が強まっています。特に、業務委託としながらも、
- 指揮命令系統が正社員と同様である
- 勤務時間や業務の進め方を細かく指示している
- 企業の備品やシステムを利用させている
といった状況にある場合、「偽装請負」とみなされ、企業側に罰則が科される可能性があります。
こうしたリスクを回避するためにも、業務実態に即した適切な雇用形態への移行を検討することが重要です。
業務委託のままでは発生するリスク
業務委託契約を継続することで、企業が抱える可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。
偽装請負と見なされるリスク
業務委託契約の本来の趣旨は、「独立した事業者として業務を遂行する」ことにあります。しかし、実際には「正社員と同じように働いている」と判断されるケースが増えており、企業側が偽装請負として指摘を受けるリスクが存在します。
労働基準監督署が偽装請負と判断した場合、
- 契約の見直しや罰則を受ける
- 過去に遡って雇用契約とみなされ、社会保険料や残業代の支払いを求められる
といった問題が発生する可能性があります。
人材の流出リスク
業務委託契約では、契約期間が満了すれば、契約者側の判断で契約終了が可能です。そのため、企業にとって重要な業務を担当している人材が、突然離脱するリスクがあります。
特に、
- 競合他社へ転職・業務委託先を変える
- 独立して同じ業界で事業を立ち上げる
といったケースは、企業の事業運営に大きな影響を与えます。長期的な視点で考えると、優秀な人材を囲い込むための施策として、正社員登用を検討する価値は十分にあるでしょう。
労務トラブルや訴訟リスク
業務委託契約のまま、長期間にわたって勤務していると、契約者が**「実質的に雇用されている」と主張し、トラブルに発展するケース**があります。
具体的には、
- 契約終了時に「解雇された」と主張される
- 業務内容に変更があった際に「労働条件の不利益変更」とされる
- 報酬未払い・不当な業務増加の訴えが起こる
といった問題が発生する可能性があります。
特に、企業が契約を終了させたい場合でも、相手が納得しない場合には法的トラブルにつながることがあるため、事前に正社員登用や契約の見直しを検討することがリスクヘッジとして有効です。
業務委託から正社員登用のメリット・デメリット
業務委託から正社員への登用は、企業にとって組織の安定化や人材確保の手段として魅力的な選択肢です。しかし、登用にはメリットだけでなく、企業側にとっての負担やリスクも伴います。
例えば、「登用後に期待した成果が出なかった」「固定費の増加により経営に負担がかかった」といった失敗例もあります。こうした課題を事前に理解し、適切な対応策を講じることで、正社員登用の成功率を高めることができます。
ここでは、業務委託から正社員登用を行うことで企業が得られるメリットと、考慮すべきデメリットについて詳しく解説します。
正社員登用のメリット(企業側視点)
1. 優秀な人材を確保し、組織の安定性を高められる
業務委託契約の人材は、すでに業務内容を理解し、即戦力として活躍していることが多いため、採用リスクを大幅に軽減できます。
一般的な新卒採用や中途採用では、面接や試験では分からない「実際の仕事ぶり」を判断するのが難しいですが、業務委託として一定期間働いてもらった後であれば、能力や社風との相性を見極めた上で登用を判断できます。
さらに、
- 長期的な雇用を前提とすることで、企業の成長戦略に沿った人材育成が可能
- ノウハウの蓄積が進み、業務の属人化リスクを軽減できる
- 優秀な人材が流出するリスクを防ぐことができる
といった利点もあります。
2. 組織の一体感が生まれ、生産性が向上する
業務委託として働く人材は、契約上、企業の指揮命令を直接受けず、独立した立場で業務を遂行します。しかし、実際には社員と同じ業務を担当しているケースも多く、企業文化に溶け込むことが求められる場面が増えているのが現状です。
正社員として登用することで、
- 企業のビジョンや経営方針に共感しやすくなる
- チームワークを重視した業務遂行が可能になる
- 責任感が生まれ、業務へのモチベーションが向上する
といった効果が期待できます。特に、社員間の連携が必要な業務では、正社員として組織の一員になることで、より円滑なコミュニケーションが生まれるでしょう。
3. コンプライアンスリスクを低減できる
近年、労働基準監督署による業務委託契約の実態調査が強化されています。
特に、
- 指揮命令を受けて働いている
- 業務内容が社員とほぼ同じである
- 企業の設備やシステムを利用して業務を行っている
といった場合、業務委託契約が「偽装請負」と判断されるリスクがあります。
正社員として正式に雇用することで、法的リスクを回避し、企業の信頼性を向上させることができるのも大きなメリットです。
正社員登用のデメリット(企業側視点)
1. 固定費(人件費・社会保険負担)の増加
業務委託契約では、労働時間に関わらず報酬を支払う契約形態が多いため、固定費を抑えることが可能です。しかし、正社員として雇用すると、毎月の給与だけでなく、社会保険や各種福利厚生のコストが発生します。
例えば、
- 雇用保険・厚生年金・健康保険の負担増
- ボーナスや退職金の考慮が必要
- 福利厚生費の増加(通勤手当、住宅手当など)
といった要素が加わり、企業の経営状況によっては大きな負担となることがあります。
そのため、正社員登用を検討する際には、長期的な人件費シミュレーションを行い、経営計画に基づいた判断をすることが重要です。
2. 業務の柔軟性が低下する可能性がある
業務委託契約では、プロジェクト単位や繁忙期に応じて、必要なときだけ人材を活用できるという利点があります。しかし、正社員として登用すると、業務量が減ったとしても一定の給与を支払う必要があるため、柔軟なリソース調整が難しくなる場合があります。
特に、
- 業務量に波がある業種(IT・クリエイティブ・コンサルティング業など)
- プロジェクトベースで人材を起用している企業
においては、登用後の業務設計を慎重に行う必要があります。
3. 登用後のパフォーマンスや適応度の問題
業務委託の際は、比較的成果ベースで業務を遂行していることが多いですが、正社員になると業務範囲の拡大や社内ルールの順守が求められるため、戸惑うケースも少なくありません。
具体的には、
- 会社の評価制度や勤務時間の制約に馴染めない
- 自由な働き方ができなくなり、モチベーションが低下する
- 期待していたスキルが発揮されず、成果が上がらない
といった課題が発生する可能性があります。
そのため、正社員登用を成功させるためには、登用前にしっかりと本人の意向を確認し、企業と候補者の間で期待値のすり合わせを行うことが不可欠です。
正社員登用の流れと成功のポイント
業務委託の人材を正社員として登用する際には、事前準備をしっかり行い、適切なプロセスを踏むことが成功の鍵となります。
「この人は優秀だから、ぜひ正社員になってほしい」と思っても、本人がそれを望んでいなかったり、企業の準備が整っていなかったりすると、期待通りの成果を得ることができません。また、登用の進め方を間違えると、労務トラブルや契約変更に関する問題が発生することもあります。
本章では、正社員登用の前に確認すべきポイントと、具体的な進め方(ステップ)について詳しく解説します。
登用の前に確認すべきポイント
1. 企業の人員計画と財務状況のチェック
正社員登用を行うことで、企業には給与の支払い義務、社会保険負担、福利厚生のコストが発生します。そのため、登用を決定する前に、以下の点を確認することが重要です。
- 登用後の人件費は経営的に持続可能か
- 今後の事業計画と整合性が取れているか
- 既存社員との給与バランスに問題はないか
特に、給与水準が既存社員と極端に異なる場合は、不満が生じる可能性があるため慎重に調整する必要があります。
2. 本人のキャリア志向を確認する
企業側が登用を望んでいても、本人がフリーランスとしての自由な働き方を希望している場合、正社員登用の話がスムーズに進まないことがあります。
そこで、事前に以下の点を確認しましょう。
- 長期的に会社で働く意欲があるか
- 正社員としての雇用条件(給与・勤務時間・福利厚生)に納得できるか
- 会社のビジョンや文化に共感し、一緒に成長する意志があるか
また、登用の打診をする際は、単に「正社員になりませんか?」と聞くのではなく、本人のキャリアプランを尊重しながら丁寧に話を進めることが大切です。
3. 適切なポジションと役割の設定
業務委託として働いていた人材を正社員にする場合、単に契約形態を変更するのではなく、適切な役割を設計することが重要です。
例えば、
- 業務内容はそのままでも、責任の範囲が変わるのか
- 新たな役職やリーダーシップの役割を期待するのか
- 他の正社員との業務のすみ分けはどうするのか
といった点を明確にしないと、登用後に「思っていた働き方と違う」と本人が不満を感じ、モチベーション低下や離職につながる可能性があります。
登用後にスムーズに活躍してもらうためにも、業務の再設計や役割分担の整理を行い、本人と合意を取っておくことが不可欠です。
正社員登用の進め方(ステップ解説)
ステップ1:候補者との面談・ヒアリング
まず、登用を検討する業務委託の方と面談を行い、本人の意向をしっかりと確認します。
面談時に確認すべきポイント
- 現在の業務への満足度
- 正社員登用に対する興味・意向
- キャリアプランとの整合性
- 雇用形態の変更に対する不安や懸念点
ここで無理に登用を進めようとすると、逆に本人のモチベーションが下がることもあるため、相手の意思を尊重しながら、双方にとって最適な形を模索する姿勢が重要です。
ステップ2:契約条件の調整(給与・待遇・業務内容)
本人の意向を確認し、登用が可能と判断したら、具体的な給与・待遇・業務内容の調整を行います。
調整時に考慮すべきポイント
- 現在の業務委託報酬と比較して適正な給与設定を行う
- 社会保険・福利厚生を適用する際のコストを試算する
- 既存社員との給与バランスを考慮する
- 業務内容に変更がある場合は、事前に本人と合意を取る
特に、業務委託の方は報酬が「成果ベース」で決まっていたケースが多いため、固定給の設定に慎重になる可能性があります。そのため、給与テーブルの設計やインセンティブの仕組みなども含めて検討するのが望ましいでしょう。
ステップ3:登用計画の策定と試用期間の設定
登用を成功させるためには、いきなり本採用とするのではなく、試用期間を設けるのが効果的です。
試用期間の活用ポイント
- 正社員としての働き方に適応できるか確認する
- 業務範囲の拡大に問題がないかチェックする
- チームとの相性を見極める
通常、試用期間は3~6ヶ月程度が一般的ですが、業務委託としての実績がある場合、短めに設定することも可能です。
ステップ4:労務・法務手続きの実施
契約変更に伴い、以下の手続きを進めます。
✅ 雇用契約書の締結(業務内容・勤務時間・報酬などの明文化)
✅ 社会保険・雇用保険の加入手続き
✅ 社内規則の説明(就業規則・評価制度・給与体系など)
この段階で不備があると、後々のトラブルにつながる可能性があるため、専門家(社労士・人事担当)と連携しながら進めるのが望ましいでしょう。
ステップ5:登用後のフォローアップと評価
登用後は、定期的な面談を行い、本人の適応状況を確認することが重要です。
特に、
- 業務委託時との働き方の違いに戸惑っていないか
- 給与や待遇に不満はないか
- チームにスムーズに馴染めているか
といった点をしっかりフォローし、必要に応じてサポートを行うことで、長期的に活躍してもらえる環境を整えることができます。
登用時の注意点とトラブルを防ぐための対策
業務委託から正社員に登用する際、適切なプロセスを踏まなければ、給与・待遇の不満、契約のトラブル、定着率の低下など、さまざまな問題が発生する可能性があります。特に、給与の決定や契約の見直し、労務リスクの管理が不十分な場合、企業と登用者の間で認識のズレが生じ、結果的に退職や法的トラブルに発展することも考えられます。
そこで本章では、給与・待遇の適正な設定、法的リスクを回避するポイント、登用後の定着率を高めるための施策について解説し、トラブルを未然に防ぐ方法を紹介します。
給与・待遇の適正な設定
1. 業務委託時の報酬と正社員給与のバランスを考慮する
業務委託の報酬体系と正社員の給与体系は大きく異なります。そのため、登用時には適正な給与水準を設定することが不可欠です。
考慮すべきポイントとしては
✅ 業務委託時の報酬と比較し、大幅な減額にならないか
✅ 企業の給与テーブルと整合性が取れているか
✅ 年収換算した際に、登用者が納得できる金額になっているか
例えば、業務委託時に月50万円の報酬を受け取っていた人が、登用後に年収500万円(ボーナス込み)では大幅な減収となる可能性があります。この場合、
- 固定給+インセンティブ制度を導入する
- 賞与やストックオプションなどの報酬形態を工夫する
といった方法で、登用者が納得できる条件を提示することが重要です。
2. 社会保険や手当の適用を考慮する
正社員になることで、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する必要があります。これにより、企業側のコストが増えるだけでなく、登用者側の手取り額が減る可能性があるため、事前にしっかり説明しておくことが大切です。
また、通勤手当・住宅手当・福利厚生など、業務委託時には適用されていなかった手当が追加される場合もあります。これらを加味して、総合的な報酬パッケージを提示することが求められます。
法的リスクを回避するためのポイント
1. 雇用契約書を適切に作成し、契約内容を明確にする
業務委託から正社員に移行する際、最も重要なのが雇用契約書の適切な作成です。口頭での合意や曖昧な契約内容は、後々トラブルの原因になります。
契約書に明記すべき事項は次のような内容が必須となります。
✅ 職務内容と業務範囲(業務委託時と異なる点を明確化)
✅ 給与・賞与・手当の詳細(支給条件、評価制度など)
✅ 労働時間・残業規定(フレックスタイム制の有無など)
✅ 試用期間の有無と期間(3〜6ヶ月が一般的)
✅ 退職時のルール(競業避止義務の有無など)
特に、「雇用契約書を締結せずに業務委託から正社員に移行させる」ことは、労働基準法違反となる可能性があるため、必ず書面で合意を取るようにしましょう。
2. 残業代・労働時間の取り扱いに注意する
業務委託の人材は、基本的に労働時間の制約を受けず、成果報酬型で働くケースが多いですが、正社員になると労働基準法に基づいた労働時間の管理が必要になります。
✅ 固定残業制(みなし残業制度)を導入するか
✅ フレックスタイム制や裁量労働制を適用するか
✅ 実労働時間と給与のバランスをどう設定するか
こうした点を事前に検討し、登用者が「思っていた働き方と違う」とならないように配慮する必要があります。
登用後の定着率を高めるために
1. 研修・サポート体制を整える
業務委託から正社員になると、業務範囲や責任が変わるため、スムーズに適応できるよう研修やサポート体制を整備することが重要です。
具体的なサポート施策
✅ オンボーディングプログラムの実施(社内ルールや業務フローの説明)
✅ メンター制度の導入(既存社員がサポート役となる)
✅ 1on1ミーティングの実施(月1回程度、適応状況を確認)
登用直後は「何を期待されているのか分からない」「正社員になったことで働き方が変わった」と感じるケースが多いため、適切なフォローを行い、不安を払拭することが大切です。
2. キャリアパスを明確にする
「正社員になったものの、今後どのように成長できるのか分からない」と感じると、モチベーションが低下し、早期離職につながる可能性があります。
そのため、登用後のキャリアパスを明確に提示し、長期的な視点で成長できる環境を整えることが求められます。
✅ 昇進・昇給の基準を明確化する(どのような成果が求められるか)
✅ スキルアップ支援を行う(研修・資格取得補助など)
✅ 評価制度を透明化する(成果に応じたフィードバックを実施)
登用者に対し、単に「雇用形態を変更しただけ」ではなく、今後のキャリア形成をサポートする姿勢を示すことが、定着率向上につながります。
専門家のアドバイス:正社員登用を成功させるために
業務委託から正社員登用を進める際、多くの企業が「どうすればスムーズに移行できるか」「トラブルを避けるために何をすべきか」といった課題に直面します。給与の設定や法的リスクの管理、登用後の定着施策など、考慮すべきポイントは多岐にわたります。
特に、労務管理や就業規則の整備を怠ると、労働基準監督署からの指摘や、登用者とのトラブルにつながる可能性があるため、事前のルールづくりが重要です。
本章では、労務管理の専門家の視点から、正社員登用を成功させるための具体的なポイントや、適切なルールづくりの方法について解説します。
専門家目線での「成功する正社員登用のポイント」
「登用の基準」を明確にする
業務委託から正社員へ移行する際、企業側の判断基準が曖昧なままでは、登用が成功しにくいだけでなく、既存社員との不公平感が生まれる原因にもなります。
登用基準を定める際のポイントとして
✅ スキル・業務経験(正社員として期待するレベルに達しているか)
✅ 企業の価値観・文化への適応度(チームワークや社風との相性)
✅ 責任感・コミットメント(長期的に貢献する意志があるか)
✅ 契約条件の適合性(給与体系・労働時間の変更に納得できるか)
このような基準を社内で統一し、誰が見ても納得できる形にしておくことで、登用後のミスマッチを防ぐことが可能になります。
登用のプロセスを制度化し、統一する
登用の判断をケースバイケースで行っていると、企業全体での一貫性が失われ、従業員間で不公平感が生じる可能性があります。
そのため、登用プロセスを明確にし、社内ルールとして統一することが重要です。
登用プロセスの例としては
- 業務委託者との評価面談を実施(登用の意向確認・業務実績の評価)
- 社内で登用基準と照らし合わせて審査(人事・経営層が判断)
- 登用条件の提示と交渉(給与・待遇・業務範囲の確定)
- 試用期間の設定(3〜6ヶ月の適応期間を設ける)
- 正式登用とフォローアップ(登用後の評価とサポート体制の強化)
この流れを事前に整備しておくことで、登用の判断がブレにくくなり、組織としての安定性が向上します。
既存社員との公平性を考慮する
正社員登用が進むと、既存の社員から「業務委託の方が優遇されているのでは?」という不満が生まれることがあります。
特に、給与・待遇面での違いが大きいと、社内の士気低下や離職リスクの増加につながる可能性があります。
そのため、
- 登用者の給与が既存社員と適正なバランスを取るよう調整する
- 社内で登用の目的や基準をしっかり説明し、透明性を確保する
- 既存社員にもキャリアアップの機会を提供し、不公平感を払拭する
といった対応を行うことが、組織の安定化にとって重要です。
正社員登用におけるルールづくり・就業規則の整備
就業規則の変更・適用範囲の明確化
業務委託から正社員登用を行う際、就業規則を適用できるように整備することが必須です。
✅ 正社員と業務委託の違いを明確に記載(雇用形態の明文化)
✅ 登用基準を就業規則の中に明記する(昇進・昇格基準と統一)
✅ 試用期間中の扱いや給与体系を整備する(登用後の条件を明確に)
特に、「業務委託時と業務内容が変わらないのに、契約形態だけが変わる」といった場合は、就業規則上の曖昧さがトラブルの原因となるため、事前にルールを整備しておくことが大切です。
評価・給与制度の調整
登用後の評価制度が整備されていないと、給与や昇進の不透明さが原因で早期退職につながるリスクがあります。
そのため、
- 評価の基準を明確にし、成果に応じた給与体系を設ける
- 業務委託時の報酬との比較を行い、適正な報酬バランスを設計する
- キャリアアップの仕組みを整え、登用後の成長機会を提供する
といった施策を導入することで、登用者のモチベーションを維持し、長期的に活躍できる環境を作ることが可能です。
労務トラブルを防ぐための社内研修の実施
登用後に「労働時間の扱いが変わった」「残業代のルールが違う」といった問題が発生しないよう、登用者向けの社内研修を実施することも効果的です。
✅ 労働時間・休暇制度の説明(業務委託時との違いを明確に)
✅ 給与・賞与・福利厚生の詳細を共有(どのような支給条件があるか)
✅ 会社の評価制度・キャリアパスの説明(成長の機会を明確化)
これらの研修を登用直後に行うことで、登用者が新しい働き方にスムーズに適応できるようになります。
まとめ:業務委託から正社員登用を成功させるには
業務委託から正社員登用を進めることは、企業にとって優秀な人材の確保、組織の安定化、法的リスクの回避といった多くのメリットをもたらします。しかし、登用プロセスを適切に設計しないと、給与・待遇のミスマッチ、登用後のパフォーマンス低下、社内の不満増加といった課題が発生する可能性があります。
本記事では、業務委託から正社員登用を行う際のメリット・デメリット、適切な進め方、トラブルを防ぐための対策について詳しく解説してきました。最後に、経営者・担当者が押さえておくべき重要なポイントを整理し、スムーズな登用を実現するために下記ポイントはあらかじめ押さえておきましょう。
✅ 登用の目的とメリット・デメリットを理解する
✅ 給与や待遇を適正に設定し、登用者の納得感を得る
✅ 法的リスクを回避し、雇用契約の適正化を図る
✅ 登用後のフォローを徹底し、定着率を高める
✅ 社内の公平性を保ち、既存社員とのバランスを取る
これらのポイントを押さえることで、登用者と企業双方にとって有益な登用プロセスを構築でき、長期的な組織の成長につなげることが可能になります。
正社員登用を検討している企業は、単なる契約変更ではなく、組織戦略の一環として登用を進めることを意識することで、より効果的な人材確保と組織の強化を実現できるでしょう。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
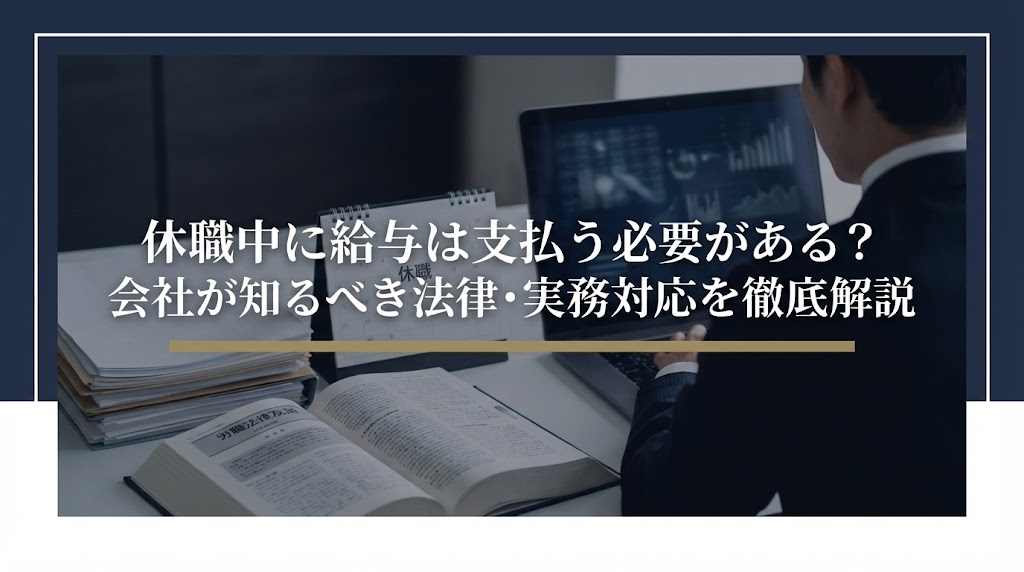 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説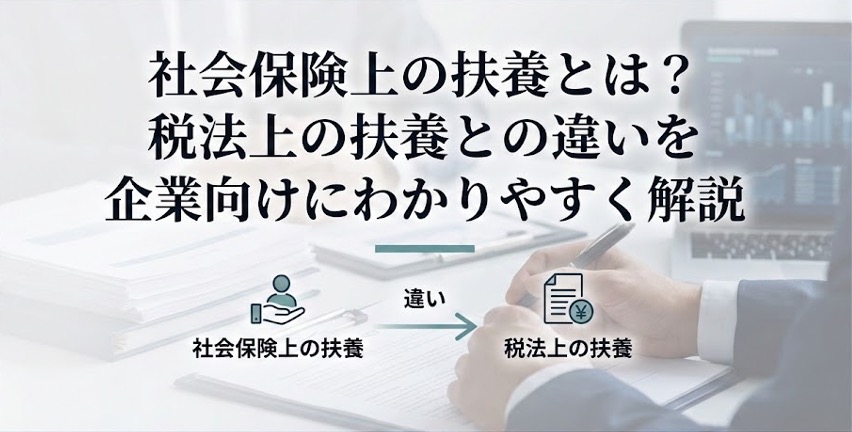 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説 ニュース一覧2026.01.08【重要】助成金に関する不正リスクについて
ニュース一覧2026.01.08【重要】助成金に関する不正リスクについて ニュース一覧2025.12.12顧問社労士に“ミスが多くて不満”と感じたときに会社が取るべき5つのステップ
ニュース一覧2025.12.12顧問社労士に“ミスが多くて不満”と感じたときに会社が取るべき5つのステップ
