「6時間勤務でも休憩は必要なのか?」と疑問に感じたことはありませんか?
労働基準法では、労働時間に応じた休憩の付与が定められていますが、6時間勤務の場合はその“境界線”に位置するため、企業担当者や現場の管理者にとっては判断に迷うポイントでもあります。
この記事では、労働基準法上のルールをわかりやすく解説するとともに、6時間勤務における休憩時間の実務的な対応方法や注意点を社労士の視点から詳しく紹介します。
制度の正しい理解と、労使トラブルを防ぐためのヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。
6時間勤務時における休憩時間の基本ルールは?
6時間勤務は、フルタイム勤務よりも短時間であるため、「休憩時間が本当に必要なのか?」と疑問に思う方も少なくありません。
しかし、労働基準法では勤務時間に応じた休憩の付与が明確に定められており、企業としては法令を順守した対応が求められます。
まずは、6時間勤務時における休憩の取り扱いについて、法的根拠と実務の観点から見ていきましょう。
労働基準法第34条に基づく休憩時間の規定
労働基準法第34条では、労働時間に応じて、以下のような休憩時間の最低基準が定められています。
(休憩)
e-Gov:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)より
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
つまり、
- 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分の休憩を与えること
- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩を与えること
条文から上記がルールになっていることが明らかなように、6時間ちょうどの勤務であれば、休憩の付与義務は発生しません。ただし、6時間「を超えた時点」で、企業は45分以上の休憩を与える義務が生じます。
また、同条では休憩の「一斉付与」「途中付与」「自由利用」といった原則も示されています。これらの原則に沿わない運用を行う場合には、就業規則の整備や労使協定の締結が求められます。
6時間勤務の場合の休憩時間の必要性
労働基準法上、6時間ぴったりの勤務であれば休憩は「義務」ではありません。しかし、実務においては以下の理由から、任意で休憩を設けるケースも多く見られます。
- 勤務時間が6時間1分になると休憩が必要なためあらかじめ休憩を付与したい
- 業務の効率を維持するために小休憩を挟みたい
- 労働者の健康や集中力の維持を図るため
- 他の社員と休憩時間をそろえることでチーム内の連携を保つため
特に職場によっては「6時間超」にギリギリかかるケースもあり、1日の中で不規則な業務が発生しがちな業種(例:飲食・介護・警備など)では、余裕をもった休憩の設定が望まれます。
また、就業規則やシフト表に「一律で◯分の休憩を設ける」と明記しておくことで、後々の労使トラブルを回避する効果も期待できます。
社労士としては、6時間勤務の取り扱いを形式的な法令順守にとどめず、現場の実態と労働者のニーズを踏まえた柔軟な対応を検討することを推奨します。
労働時間別の休憩時間の違いと注意点
労働時間に応じた休憩時間の取り扱いは、企業のコンプライアンス対応の中でも見落とされがちなポイントです。
労働基準法では明確なルールが定められていますが、実際の運用では職種や勤務形態によって柔軟な対応が求められる場面もあります。ここでは、労働時間別にどのような休憩時間の取り扱いが必要になるのかを整理し、企業が注意すべき実務対応について解説いたします。
5時間勤務の場合の休憩時間の取り扱い
前述の通り、休憩時間は労働時間が「6時間を超える場合」に与える義務が生じます。
そのため、5時間以内であれば、労働基準法上、休憩時間の付与は義務付けられていません。したがって、5時間勤務のパート・アルバイトなどには休憩を与えなくても違法ではないのです。
しかしながら、現場では次のような理由から任意の休憩を設ける企業も多くあります。
- 肉体的・精神的な負担軽減のため
- 労働者の満足度や定着率の向上を図るため
- 近隣他社との労働条件比較における競争力確保のため
就業規則で「5時間勤務でも15分の休憩を与える」といった制度を整備することで、従業員にとって働きやすい職場環境の構築にもつながります。
6時間を超える勤務時間の場合の休憩時間の付与義務
6時間を「超える」勤務時間になると、労働基準法第34条の規定により、休憩時間の付与が義務となります。この場合、企業は最低45分以上の休憩を与える必要があります。
ここで重要なのは、「6時間ちょうど」では休憩義務がない点です。
たとえば「6時間10分」や「6時間半」のようにわずかでも超過している場合は、45分以上の休憩を確実に設定しなければ法違反となります。
また、以下の点にも注意が必要です。
- 休憩は原則として労働時間の途中に与える必要がある
- 勤務シフトの変更により6時間を超える日がある場合には、都度適切な休憩設定が求められる
- 労働時間が延びる可能性がある業務(例:残業前提のシフト)では、事前に休憩の調整ルールを設けておくことが望ましい
勤務時間の境界線が曖昧になりがちな職場こそ、明確なルール作りと従業員への周知が必要となるでしょう。
8時間勤務やそれ以上の場合の休憩時間の設定
8時間を超える勤務時間の場合は、労働基準法により最低1時間の休憩が義務づけられています。
この「1時間」は労働時間の途中に与える必要があり、かつ原則として自由に利用できる時間である必要があります。
実務上のポイントは次のとおりです。
- 8時間を1分でも超えれば1時間の休憩が必要、また労働時間が9時間や10時間であっても1時間で可
- 分割して休憩を与える場合には、トータルで1時間以上になるよう注意
- 交替制勤務や夜勤では、休憩時間のタイミングや場所の確保も重要
また、労働時間が長くなればなるほど、休憩の質や取り方もパフォーマンスや健康管理に直結します。勤務時間が8時間を超える職場では、制度としての休憩だけでなく、業務上の「小休止」や「仮眠」も含めた柔軟な設計が望まれます。
経営者としては、労働法上の最低ラインを守るだけでなく、従業員のパフォーマンス向上と離職防止の視点からも休憩制度を見直すタイミングと捉えるとよいでしょう。
休憩時間の付与に関する3つの原則と実務上の注意点
休憩時間は単に「与えればよい」ものではなく、労働基準法上、いくつかのルールに従って適正に付与する必要があります。
なかでも重要なのが「途中付与」「自由利用」「一斉付与」の3つの原則です。
これらは実務において誤解されやすく、労使間のトラブルに発展するケースも少なくありません。以下では、各原則の内容と注意点を詳しく解説します。
①途中付与の原則:休憩は労働時間の途中に与える
労働基準法第34条では、休憩は「労働時間の途中に与えること」が定められています。
これは、勤務開始から終了までの間のどこかで、業務の合間に休憩を挟む必要があるという意味です。
たとえば、次のような休憩の与え方は原則違反となります。
- 始業直後に「1時間の休憩」を与える
- 終業後に「まとめて休憩時間をとったことにする」
このような運用は休憩の本来の目的(労働負担の軽減)を果たさず、違法と判断されるリスクがあります。実務上は、午前と午後を分けるような形で昼休憩を配置するのが一般的であり、交替制勤務など特殊なケースを除き、休憩時間は原則として中間に配置することが良いのではないでしょうか。
②自由利用の原則:休憩時間の過ごし方の自由
休憩時間は「労働者が自由に使える時間」として与えなければなりません。
つまり、企業が一方的に休憩中の行動を制限したり、業務命令を出したりすることは、法的に問題があります。
具体的には、次のような対応は避けるべきです。
- 休憩時間中の電話当番を命じる
- 社内に留まるよう強制する
- 昼休み中に研修やミーティングを入れる
ただし、業種によっては「持ち場を離れられない」などの制約が発生する場合もあります。その場合、休憩時間の自由利用が困難な実情に対応することが求められますので、形式だけでなく、実態として自由が確保されているかどうかを常に意識することが重要です。
③一斉付与の原則とその例外
原則として、同一の事業場で働く労働者には「一斉に休憩を与える」ことが求められます。
これが「一斉付与の原則」です。たとえば、全員が12時〜13時の1時間を休憩とする、といった形が該当します。
このルールには以下のような目的があります。
- 業務の一斉中断によって業務効率のメリハリがつく
- 労働者同士の不公平感やトラブルを防ぐ
一方で、以下のケースでは例外として個別に休憩を与えることが認められます。
- 運輸業や医療、サービス業など、業務を止められない業種
- 労使協定を締結して個別付与を認める場合
企業が一斉付与を行わず、交代制などで個別に休憩を与える場合は、「休憩時間の一斉付与の例外に関する協定(労使協定)」を締結し、労働基準監督署への届出は不要ですが、就業規則等に明記して運用ルールを明確化することが望まれます。
特に近年は柔軟な働き方の導入が進むなかで、休憩の付与タイミングにも多様性が求められています。制度と実態の乖離が生じないよう、企業ごとの運用実態を確認しながら見直しを図ることが大切です。
実務における休憩時間の設定と勤怠管理のポイント
労働基準法に準拠した休憩時間の設定は、企業にとって最低限の義務ですが、それだけでは十分とはいえません。
職場の運用に合わせた柔軟な管理や、勤怠システムによるトラブル防止の仕組みも不可欠です。本章では、休憩時間の分割運用やシステム活用のポイント、さらに実際に起きがちなトラブルとその防止策について、実務目線で解説します。
休憩時間の分割や柔軟な運用の可否
原則として、休憩時間は一括して与えることが望ましいとされていますが、業務の都合上、分割して与えるケースも現場ではよく見られます。たとえば「30分×2回」など、小休憩を分けて与える運用です。
このような分割休憩が許容されるためには、以下の点を確認する必要があります。
- 合計で法定時間(45分または1時間)を満たしていること
- 労働者が実質的に休息できる時間として確保されていること
- 分割方法が一貫しており、従業員への周知・同意があること
また、短時間勤務のパートや、交替制勤務の現場では、柔軟な休憩設定が労働環境の改善にもつながります。企業は就業規則や労使協定を通じて、運用の根拠を明確にしておくと安心です。
勤怠管理システムを活用した休憩時間の適正管理
近年ではクラウド型の勤怠管理システムの導入が進み、休憩時間の記録・集計も自動化されつつあります。これにより、手作業によるミスや集計漏れといったリスクを大幅に軽減できます。
システム導入時に意識すべきポイントは以下のとおりです。
- 「休憩自動控除」機能の有無と運用ルールの明確化
- 実際の休憩取得状況と自動集計結果に齟齬がないかのチェック
- 管理者による定期的なログの確認と修正機能の活用
たとえば、休憩時間を自動で差し引く設定になっているにもかかわらず、実際には従業員が休憩を取れていなかったという場合、未払い賃金や労使トラブルに発展する恐れがあります。
システムに頼りきるのではなく、「現場の実態」と「システムの設定」が一致しているかを定期的に確認することを強く推奨します。
休憩時間に関するトラブル事例とその防止策
適切な休憩管理がなされていない場合、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。代表的な事例を以下に挙げます。
- 未払い賃金トラブル:実際には休憩を取っていないのに自動で差し引かれていた
- 自由利用の侵害:休憩中にもかかわらず電話対応や来客対応を強いられた
- 不公平感の訴え:同じ業務時間でも人によって休憩時間の扱いが異なる
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、以下のような対策が有効です。
- 休憩時間の取得ルールを明文化し、従業員に周知徹底する
- 勤怠記録の見直しを定期的に実施し、実態との乖離をチェックする
- トラブルが起きた際の相談窓口や改善フローをあらかじめ整備しておく
実務においては、「形式的に休憩を与えた」ではなく、「実質的に休憩が機能しているかどうか」が重要です。
制度と運用、そして記録管理が連動して初めて、休憩時間の適正な付与と勤怠管理が実現します。
休憩時間に関してよくある質問(FAQ)
6時間勤務における休憩時間の取り扱いは、法律上の基準がある一方で、実際の現場では「これってOKなの?」と迷う場面が多々あります。
ここでは、企業担当者や従業員からよく寄せられる疑問に対して、社労士の視点から明確かつわかりやすく回答します。
6時間勤務で休憩を取らせないと違法になるのか?
結論から言うと、労働時間が「6時間ちょうど」であれば、休憩を取らせなくても違法にはなりません。
これは労働基準法第34条に基づく規定で、休憩の付与が義務付けられるのは「6時間を超える」勤務時間からです。
ただし、注意したいのは以下のようなケースです。
- 実際には6時間を少し超えてしまうことが多い
- 始業前・終業後の準備や片付け時間が労働時間に含まれている
- 従業員に不満が生じている
このような場合、形式的には「6時間以内」でも、実態として休憩を与えないことがトラブルにつながる可能性がありますので、経営者としては、実情を踏まえた柔軟な対応が求められます。
休憩時間を業務の合間に分割して与えることは可能か?
はい、休憩時間を分割して与えること自体は法的に可能です。ただし、いくつかの条件を満たしている必要があります。
- 合計で法定の休憩時間(45分または1時間)を満たしていること
- 実質的に休息の効果が得られるような時間であること
- 労働者に周知されており、運用ルールとして一貫していること
たとえば、「15分×3回」「30分+15分」などのパターンが考えられます。
特に交替制勤務や集中力の維持が求められる業務では、分割休憩の方が実情に即している場合もあります。
休憩を分割する場合でも就業規則に記載し、従業員への説明と同意を得ることを推奨いたします。
休憩時間中に業務連絡をすることは問題ないのか?
原則として、休憩時間中は労働者が自由に過ごせる時間であるため、業務連絡や指示をすることは望ましくありません。たとえば、以下のような行為は「休憩の自由利用」の原則を損なう可能性があります。
- 昼休みに電話やチャットで業務連絡を送る
- 休憩中に会議や報告を求める
- 一部の従業員にだけ業務対応をさせる
もちろん、業務上の緊急対応などでどうしても連絡が必要な場合もありますが、そのような状況が常態化している場合には、休憩が休憩として機能していないと判断される恐れがあります。
実務上は、以下のような配慮が望まれます。
- 休憩時間中の業務連絡を極力避ける
- 緊急対応が必要な場合は、事前に対応手当の支給やローテーション体制を整える
- 就業規則に「休憩中の業務連絡に関するルール」を明記しておく
労使トラブルや未払い賃金のリスクを避けるためにも、休憩時間の自由利用が確保されているかどうかを定期的に見直すことが大切です。
まとめ|6時間勤務における休憩時間のルールと実務対応のポイント
6時間勤務では、法律上の休憩付与義務が発生しない場合でも、実務ではトラブルを避けるための工夫が欠かせません。労働時間の境界にあるからこそ、制度の理解と柔軟な運用が必要です。
自社の勤怠管理や休憩時間の設定に不安がある、あるいは休憩制度の見直しを検討している場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。労働時間・休憩時間に関する制度設計から就業規則の整備まで、専門家がサポートいたします。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
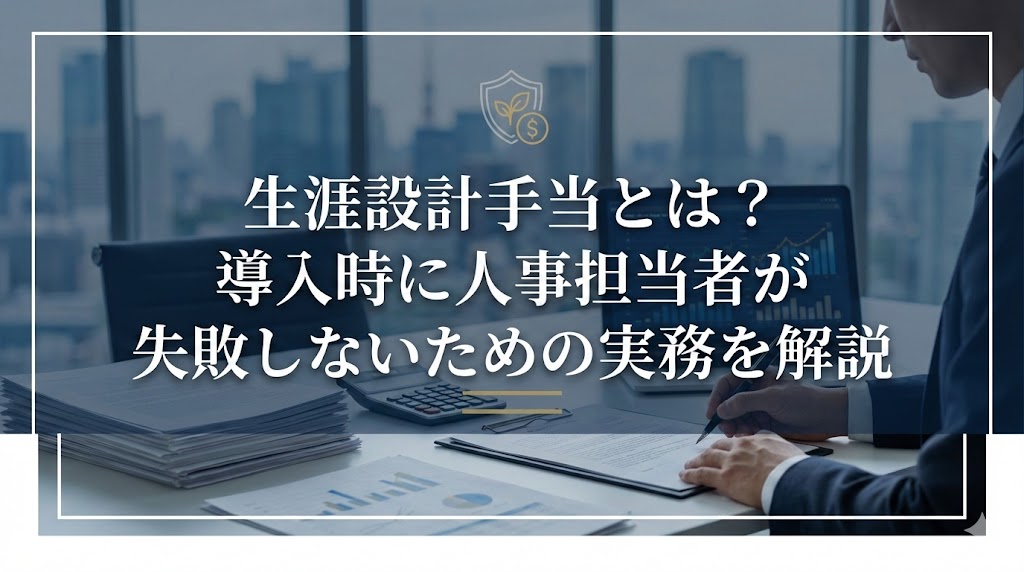 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説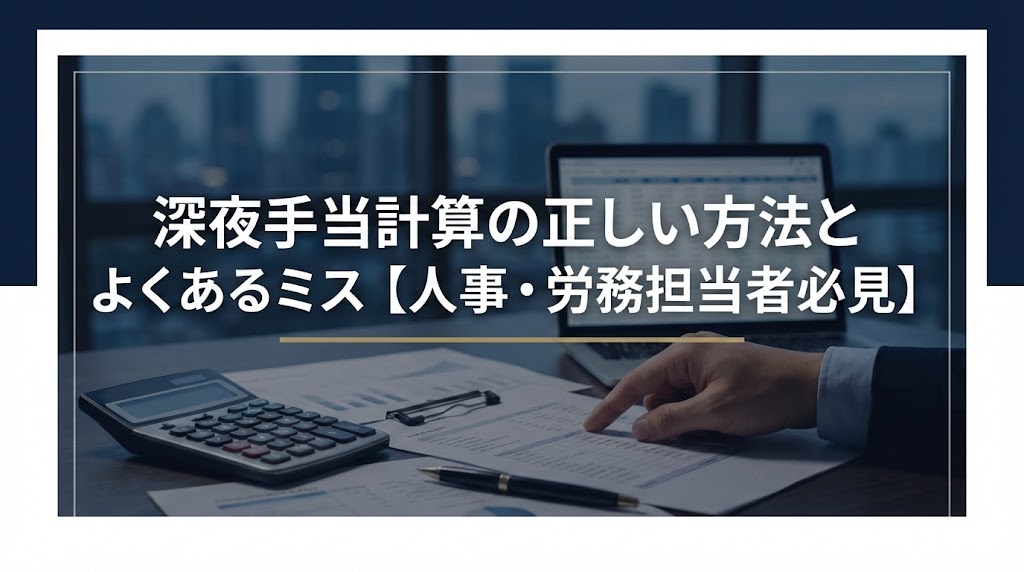 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】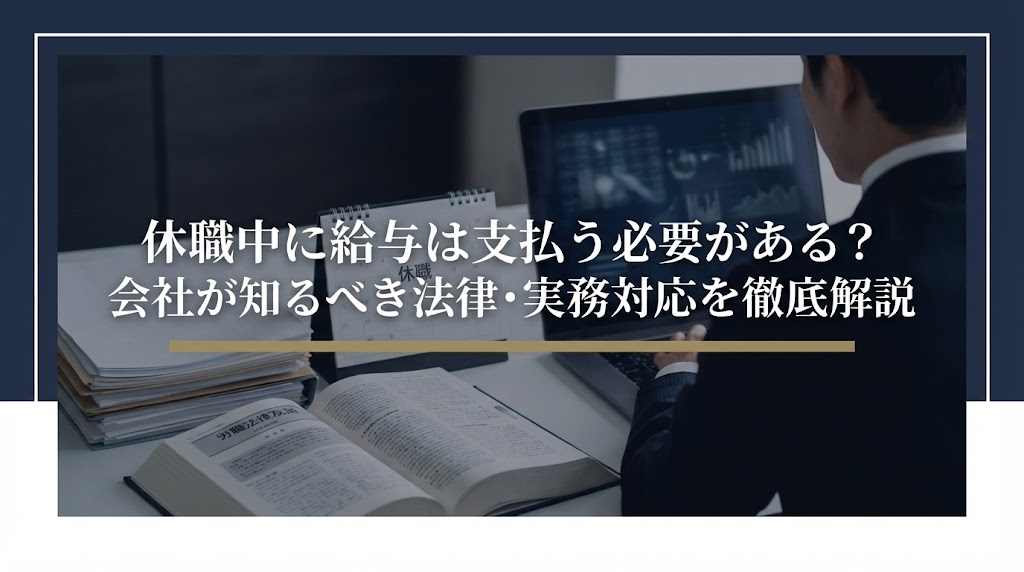 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説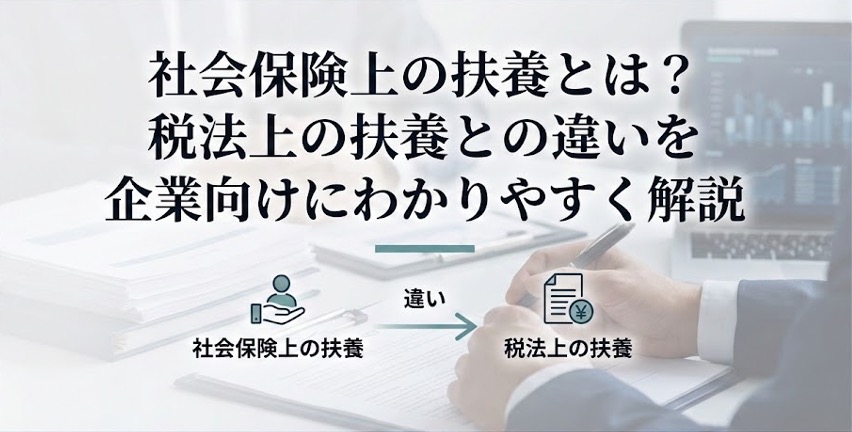 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説

