就業規則は、従業員10人以上の企業では作成が法的に義務付けられていますが、10人未満の小規模企業では任意とされています。
しかし、規模に関わらず就業規則を整備することには大きな意義があります。今回のコラム記事では、10人未満の会社が就業規則を作成するメリットや注意点を詳しく解説いたします。
労使間のトラブル防止や、円滑な事業運営のための重要なツールとしての就業規則の役割、さらに将来の成長を見据えた戦略的な意義まで、小規模企業の経営者や人事担当者が知っておくべき情報を網羅的にお伝えいたしますので、従業員が10人未満の企業で就業規則の作成をすべきか迷われている方のご参考になれば幸いです。
就業規則とは?10人未満の会社における位置づけ
従業員が10人未満の小規模企業にとって、就業規則は法的義務ではありませんが、その重要性は決して小さくありません。
まずは就業規則の基本的な定義と法的根拠を解説し、10人未満の会社における就業規則の必要性について詳しく見ていきましょう。
従業員規模に関わらず、適切な就業規則の整備が企業の健全な発展と従業員の権利を保護するための必要性についてお伝えいたします。
就業規則の定義と法的根拠
就業規則とは、簡単にご紹介すると従業員の労働条件や職場での規律を定めた社内文書です。
就業規則に記載が求められる内容としては、
- 労働時間や休日に関する取り決め
- 給与(賃金)の計算方法や支給日
- 入社や退職の手続き
- 服務規律や懲戒に関する規定
上記のようなルールを明文化することになります。会社では勤務する際の取り決めを記載しますので、就業規則は、単なる社内ルールではなく、法的な効力を持つ重要な規定集なのです。
法的根拠としては、労働基準法第89条が挙げられます。
この条文では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。ただし、この法的義務は10人以上の事業場にのみ適用されるため、10人未満の小規模企業には作成義務がありません。
第八十九条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
e-GOV「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」より引用
しかし、労働契約法第7条に注目する必要があります。
この条文は、使用者が合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に周知させていた場合、その就業規則の内容が労働契約の内容となると規定しています。つまり、10人未満の企業であっても、適切に作成・周知された就業規則は法的効力を持つのです。
第七条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
e-GOV「労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)」より引用
専門家の視点から見ると、就業規則は単なる法的要件の充足ではなく、企業経営の基盤を形成する重要なツールと言えます。適切に設計された就業規則は、従業員の権利保護と企業の円滑な運営の両立を可能にできるのです。
10人未満の会社における就業規則の必要性
10人未満の小規模企業では、就業規則の作成が法的に義務付けられていないため、その必要性を疑問視する経営者も少なくありません。
弊社でもよく経営者の方から「数人しか従業員がいないので、就業規則は作っていません」というお声はよくお聞きします。しかし、規模に関わらず就業規則を整備することには、以下のような重要な意義があります。
労使間トラブルの予防
明確な労働条件や規律を文書化することで、誤解や曖昧さに起因するトラブルを未然に防ぐことができます。小規模企業ほど、一つのトラブルが経営に与える影響は大きいため、予防的アプローチは極めて重要です。
公平性の担保
従業員の待遇や規律に関する基準を明確にすることで、恣意的な判断を避け、公平な職場環境を整備できます。これは従業員の信頼を獲得し、モチベーションを高める効果があります。
将来の成長への準備
現在は10人未満でも、将来的に規模が拡大する可能性を見据えて、早い段階から適切な就業規則を整備しておくことは戦略的に賢明です。成長に伴う制度の変更をスムーズに行うことができます。
コンプライアンスの強化
法令遵守の姿勢を明確にすることで、従業員の意識向上と、潜在的なリスクの軽減につながります。
中小企業の労務管理を支援している立場からお伝えすると、10人未満の企業こそ、トラブルを防止するためには柔軟かつ効果的な就業規則の策定を行う必要があると考えています。
大企業のような複雑な組織構造がない分、企業の実情に即した、より実効性の高い規則を作ることができるのです。
結論として、10人未満の会社であっても、適切な就業規則の整備は、健全な経営と従業員の権利保護の両立を実現する重要なステップと言えます。法的義務の有無にかかわらず、企業の持続的成長と良好な労使関係構築のために、就業規則の作成を積極的に検討することをお勧めします。
10人未満の会社が就業規則を作成するメリット
10人未満の小規模企業でも、就業規則を作成することには多くのメリットがあります。法的義務がなくても就業規則を整備することで、会社の安定した運営や成長、従業員との良好な関係構築に大きく貢献します。以下では、小規模企業が就業規則を作成することで得られる主要なメリットについて詳しく解説します。
労使間トラブルの予防と解決
就業規則を作成することで、労使間のトラブルを未然に防ぎ、発生した場合も円滑に解決できます。明確なルールを設けることで、従業員の権利と義務が明確になり、誤解や曖昧さに起因する問題を回避に繋がります。
例えば、残業や休日出勤の取り扱い、有給休暇の付与基準、懲戒処分の手続きなどを明確に定めることで、これらに関する紛争を防ぐことができます。また、トラブルが発生した際も、就業規則を基準として公平に対処できるため、従業員の納得性も高まります。
小規模企業こそ一つのトラブルが経営に与える影響が大きいため、予防的アプローチとしての就業規則整備は極めて重要と言えるでしょう。
会社の成長に伴う円滑な体制整備
小規模企業が成長していく過程で、就業規則はスムーズな体制整備の基盤となります。将来的な規模拡大を見据えて早い段階から適切な就業規則を整備しておくことは、戦略的に賢明な選択です。
例えば、採用活動の際に就業規則があることで、応募者に対して労働条件や会社の方針を明確に示すことができます。これにより、会社の価値観に合った人材を効率的に採用できる可能性が高まります。
また、組織が拡大する際も、既存の就業規則を基に円滑に新しい制度や規則を導入できます。これにより、成長に伴う混乱を最小限に抑えることができると考えられます。
従業員の帰属意識と生産性の向上
適切に設計された就業規則は、従業員の帰属意識を高め、結果として生産性の向上につながります。明確な労働条件や評価基準を示すことで、従業員は自分の立場や期待される役割を理解しやすくなります。
また、公平な待遇や福利厚生の規定を設けることで、従業員の満足度と会社への信頼感が高まります。これにより、従業員の定着率が向上し、長期的な視点で会社に貢献しようとする意識が醸成されます。
従業員の帰属意識の向上は、特に小規模企業において重要です。限られた人材で最大の効果を発揮するためには、一人一人の従業員が高いモチベーションを持って働くことが不可欠だからです。
助成金申請時の要件充足
就業規則の整備は、各種助成金の申請において重要な要件となることがあります。
例えば、キャリアアップ助成金や働き方改革推進支援助成金などの申請には、就業規則の提出が求められるため、従業員数に問わず助成金を活用する場合には就業規則を整備しなければなりません。
小規模企業にとって、これらの助成金は貴重な資金源となり得ます。事前に就業規則を整備しておくことで、助成金申請の機会を逃さず、スムーズに手続きを進めることができます。
専門家の視点から言えば、就業規則の整備は単なる法令遵守だけでなく、企業の成長戦略の一環として捉えるべきです。助成金の活用を通じて、従業員のスキルアップや労働環境の改善を図ることで、長期的な企業価値の向上につながるからです。
以上のように、10人未満の小規模企業であっても、就業規則を作成することで多くのメリットを得ることができます。法的義務の有無にかかわらず、会社の持続的成長と従業員との良好な関係構築のために、就業規則の整備を積極的に検討することをお勧めします。
10人未満の会社における就業規則作成の手順
10人未満の小規模企業でも、就業規則を作成することで労使間のトラブルを防ぎ、健全な職場環境を構築できます。法的義務はありませんが、将来の成長を見据えて早めに整備しておくことをお勧めしますので、小規模企業向けの効果的な就業規則作成手順を詳しく解説します。
現状の労働条件の棚卸し
就業規則作成をするためには、現在の労働条件を正確に把握することです。従業員数が少ない企業においては、労働条件や福利厚生について口頭での取り決めや慣習に頼っている部分が多いかもしれません。しかし、これらを明文化することで、従業員との認識の齟齬を防ぐことができます。
具体的には以下の項目を洗い出しましょう。
- 労働時間と休憩時間
- 給与体系と支払い方法
- 休日・休暇制度
- 福利厚生の内容
- 服務規律や懲戒規定
この段階で労働基準法などの関連法令との整合性をチェックすることが重要です。法令違反の労働条件が慣習化している可能性もあるため、注意が必要です。
従業員の意見聴取と反映
10人未満の会社では、全従業員の意見を直接聞きやすいという大きな利点があります。この機会を活用し、現在の労働条件に対する従業員の満足度や改善要望を聞き取りましょう。
意見聴取の方法としては、個別面談やアンケート調査、全体ミーティングが考えられます。
従業員の意見を反映させることで、より実効性の高い就業規則を作成できます。また、従業員の帰属意識や仕事へのモチベーション向上にもつながります。
法令遵守のチェックポイント
就業規則を作成する場合、その内容について労働関連法令の遵守は不可欠です。就業規則作成時には、特に以下の点に注意してチェックを心がけてください。
- 労働基準法に定められた労働時間や休憩時間の規定
- 最低賃金法に基づく給与水準
- 年次有給休暇の付与基準
- 育児・介護休業法に基づく休業制度
- ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ)の禁止
専門的な知識を持つ人材が不足しがちのため、小規模企業ほど法令違反のリスクが高くなる傾向にあります。法令遵守できる就業規則を作成される際には、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家によるレビューと修正
最後に、作成した就業規則案を専門家にレビューしてもらいましょう。社会保険労務士や弁護士など、労働法に精通した専門家のチェックを受けることで、法的な問題点や不備を洗い出すことができます。
専門家の視点を取り入れることで、現在の小規模企業の実情に合わせつつ、将来の成長にも対応できる就業規則を作成できます。また、専門家のアドバイスを受けることで、経営者自身の労務管理に関する知識も向上し、より良い職場環境づくりにつながります。
以上の手順を踏むことで、10人未満の小規模企業でも、効果的かつ法令に準拠した就業規則を作成することができます。将来の成長を見据えて、早めに整備しておくことをお勧めします。
10人未満の会社の就業規則作成時の注意点
10人未満の小規模企業が就業規則を作成する際には、大企業とは異なるアプローチが必要です。
柔軟性、将来性、従業員との良好なコミュニケーション、そして定期的な見直しが重要なポイントとなります。ここでは、小規模企業において就業規則を効果的に作成・運用するための具体的な注意点を解説します。
柔軟性を持たせた規定の作成
小規模企業の強みは、状況に応じて迅速に対応できる柔軟性にあります。就業規則もこの特性を活かし、硬直的な規定を避け、柔軟性を持たせることが重要と考えられます。
例えば、役職や職務内容についても、「会社の判断により変更することがある」といった文言を入れることで、従業員の成長や会社の状況に応じた柔軟な対応が可能になります。
将来の成長を見据えた内容設計
現在は10人未満でも、将来的に事業が拡大し、従業員が増える可能性を考慮に入れた就業規則の設計が重要です。
昇進・昇格の基準や評価制度について、現在は詳細な規定が不要でも、将来的に必要になる可能性を見越して、基本的な枠組みだけを定めておくことが賢明でしょう。
また、テレワークや副業など、将来的に導入する可能性のある制度についても、「別途定める」といった形で言及しておくと、後々の改定がスムーズになります。
従業員への周知と同意の取得方法
就業規則を作成しても、従業員に周知されなければ意味がありません。作成後、どのような手順で従業員に周知すべきか解説いたします。
書面での周知
10人未満の会社では、全従業員に書面で就業規則を配布することが最も確実な方法です。配布の際には、受領書にサインをもらうことで、確実に周知したことの証拠となります。また、会社の共有スペースに常時掲示しておくことも効果的です。
説明会の開催
書面での配布に加えて、説明会を開催することで、従業員の理解を深めることができます。10人未満の小規模企業では、全従業員が参加できる説明会を開催しやすいというメリットがあります。この機会に、就業規則の内容だけでなく、会社の方針や将来のビジョンについても共有することで、従業員の帰属意識を高めることができます。
定期的な見直しと更新の重要性
就業規則は「生きた文書」であり、定期的な見直しと更新が不可欠です。小規模企業では、年1回程度の頻度で見直しを行うことをお勧めします。法改正への対応はもちろん、会社の成長に伴う組織変更や、新たな働き方の導入など、様々な要因で就業規則の更新が必要になります。また、従業員からの要望や意見を積極的に取り入れ、より良い職場環境づくりに活用することも重要なのです。
専門家の立場から言えば、10人未満の小規模企業こそ、柔軟かつ効果的な就業規則の運用が可能です。大企業のような複雑な組織構造がない分、会社の実情に即した、より実効性の高い規則を作り、運用することができます。定期的な見直しと更新を通じて、従業員との信頼関係を築き、会社の成長を支える基盤として就業規則を活用していくことが、小規模企業の大きな強みとなるでしょう。
就業規則がない場合のリスクと対策
10人未満の小規模企業では就業規則の作成が法的義務ではありませんが、その不在は様々なリスクを伴います。就業規則がない場合に直面する可能性のある主要なリスクと、それらに対する実践的な対策を詳しく解説します。特に、労働条件の不明確さによるトラブル、懲戒処分の困難さ、会社の信用低下といった重要な問題に焦点を当て、小規模企業が取るべき具体的な対応策もご紹介いたします。
労働条件の不明確さによるトラブル
就業規則がない場合、労働条件が曖昧になり、従業員との間で誤解や紛争が生じやすくなります。具体的には、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 労働時間や休憩時間の解釈の相違
- 残業手当の計算方法に関する認識の相違
- 有給休暇の取得ルールの不明確さ
これらの問題は、従業員の不満や生産性の低下につながるだけでなく、最悪の場合、労働基準監督署への申告や訴訟リスクを高める可能性があります。
労働条件の明確化は単なる法令遵守の問題ではなく、従業員のエンゲージメントと組織の健全性を維持するための重要な要素です。明確な労働条件は、従業員の権利を保護すると同時に、会社の期待値を明確に伝えることができ、結果として労使双方にとって有益な職場環境を創出します。
懲戒処分の困難さ
就業規則がない場合、従業員の問題行動に対して適切な懲戒処分を行うことが極めて困難になります。具体的には、
- 懲戒の根拠が不明確になり、処分の正当性を主張しにくくなる
- 処分の種類や程度が不明確で、一貫性のある対応が取りづらくなる
- 従業員が処分に不服を申し立てた際、会社側の立場が弱くなる
例えば、重大な機密情報の漏洩や、深刻なハラスメント行為があった場合でも、明確な懲戒規定がないために適切な処分を下せず、問題の解決が遅れる可能性があります。
懲戒規定は単なる罰則ではなく、組織の秩序を維持し、健全な職場環境を守るための重要なツールだということです。適切に設計された懲戒規定は、問題行動の抑止力となるだけでなく、公平性と透明性のある職場文化の醸成にも貢献します。
対策:労働条件通知書の作り込み
就業規則の作成には時間がかかるため、暫定的な対策として労働条件通知書を作り込むことが考えられます。基本的な労働条件(労働時間、休日、給与など)だけでなく懲戒に関する基本方針を記載するなど、会社としてのルールを詳細に明文化するイメージとなります。
ただし、あくまで暫定的な措置であり、最終的には包括的な就業規則の整備を目指すべきだということです。労働条件通知書は個別の契約文書であるため、全社的な規則としての機能は限定的です。
長期的には、会社の成長に合わせて段階的に就業規則を整備していくことをお勧めします。例えば、まず基本的な労働条件と懲戒規定を含む簡易版を作成し、その後、福利厚生や評価制度などを順次追加していく方法が効果的です。この段階的アプローチにより、小規模企業でも無理なく就業規則を整備し、リスク軽減と組織強化を実現できるでしょう。
まとめ:10人未満の会社における就業規則の意義と活用
今回のコラム記事では、従業員が10人未満の企業における就業規則の重要性と活用方法について解説いたしました。
簡単に整理しますと、法的義務がなくとも、就業規則を整備することは企業の持続的成長と健全な労使関係構築につながる書類であり
- 労使間トラブルの予防と解決
就業規則は労働条件や職場のルールを明確化し、誤解や曖昧さに起因するトラブルを未然に防ぎます。問題が発生した際も、公平な基準に基づいて解決できます。 - 会社の成長基盤の構築
将来の規模拡大を見据えた就業規則を整備することで、円滑な組織拡大が可能になります。採用活動や新制度導入時にも、既存の規則を基に効率的に対応できます。 - 従業員の帰属意識と生産性の向上
明確な労働条件や評価基準を示すことで、従業員の帰属意識が高まり、結果として生産性向上につながります。 - 組織文化の形成
就業規則に会社の理念や価値観を反映させることで、独自の組織文化を形成し、従業員に浸透させることができます。 - 従業員の権利保護と公平性の担保
労働条件や評価基準を明文化することで、従業員の権利を保護し、公平な職場環境を整備できます。
上記のようなメリットがあります。
就業規則の作成を単なる法的要件の充足ではなく、戦略的な経営ツールとして捉えていただけると、その必要性がより身近なものになると思います。
一方で、就業規則は一度作成して終わりというものでもなく、自社の現状と将来のビジョンを反映させた柔軟な規則を作成し、定期的に見直すことで、会社の成長に合わせて進化させていくことが重要です。
少しでも就業規則の作成や見直しに不安がありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
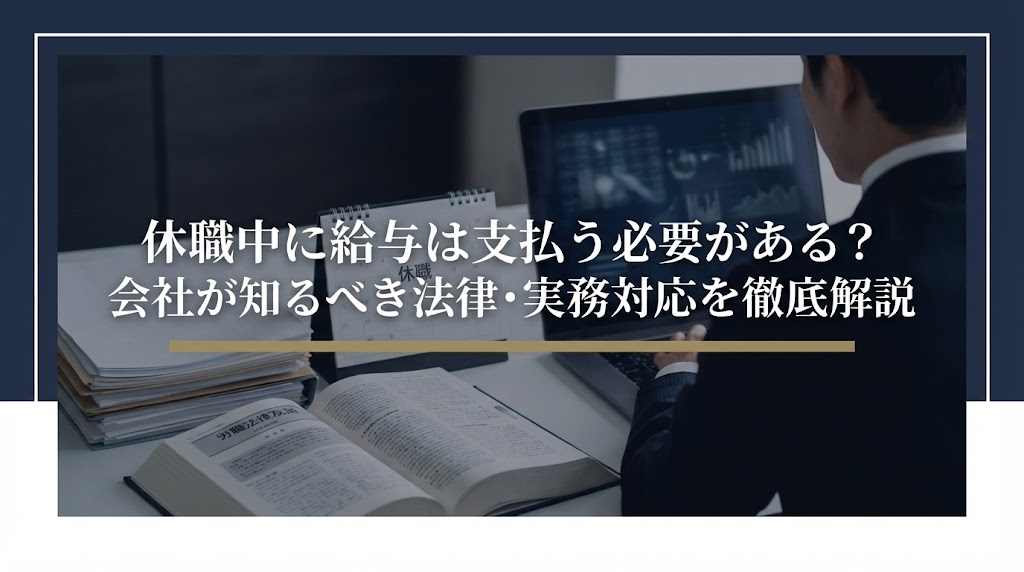 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説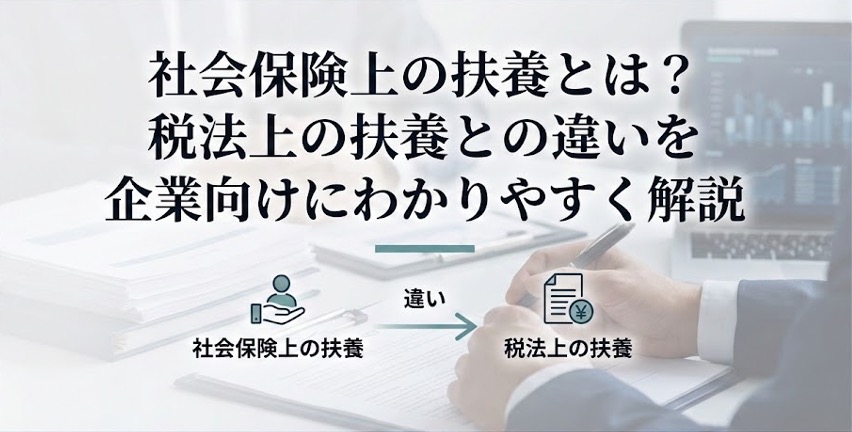 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説 ニュース一覧2026.01.08【重要】助成金に関する不正リスクについて
ニュース一覧2026.01.08【重要】助成金に関する不正リスクについて ニュース一覧2025.12.12顧問社労士に“ミスが多くて不満”と感じたときに会社が取るべき5つのステップ
ニュース一覧2025.12.12顧問社労士に“ミスが多くて不満”と感じたときに会社が取るべき5つのステップ