就業規則の届け出は、企業経営において「見過ごせない重要な義務」のひとつです。
特に、常時10人以上の労働者を雇用している事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が法律で義務付けられています。
しかし、いざ就業規則を整備しようとしても、
- 「そもそもどの書類を出せばいいのか?」
- 「提出期限はあるの?」
- 「電子申請もできるって本当?」
など、疑問が多く、手続きに戸惑う企業担当者の方も少なくありません。
本記事では、就業規則の届け出に必要な書類や手続きの流れ、提出時の注意点まで、実務に即した内容を専門家の視点でわかりやすく解説します。
さらに、労働基準監督署でよくある指摘や、電子申請のコツなど、実務経験に基づいた独自のアドバイスもお伝えいたします。
「初めての届け出で不安」「罰則を受けたくない」「安心して労務管理をしたい」そんな経営者・人事労務担当者の方はぜひご一読ください。
就業規則の届け出義務とは
企業が成長し、従業員の数が増えるにつれて、労務管理の重要性はますます高まります。
その中でも「就業規則の整備と届け出」は、法令順守の第一歩として欠かせない取り組みです。特に、常時10人以上の従業員を雇用する企業には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る法的義務があります。
この章では、そもそも「就業規則とは何か?」という基本から、「どのような場合に届け出が必要になるのか?」といった実務上のポイントまで、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
就業規則とは
就業規則とは、企業における労働時間・休日・賃金・退職・服務規律など、労働者の働き方に関わる基本的なルールを明文化した社内規程です。言い換えれば、会社と従業員の間における「職場のルールブック」と言えるでしょう。
特に注意すべき点は、就業規則が経営者だけでなく、従業員にとっても法的効力を持つ文書であるということです。
これは、企業が恣意的に就業条件を変更したり、従業員がルールを無視したりすることを防ぐ役割も担っています。
専門家の立場から言えば、就業規則は単なる「提出書類」ではなく、トラブルを未然に防ぐための“経営リスク回避ツール”でもあります。たとえば、懲戒処分のルールがあらかじめ明記されていないと、問題社員への対応が困難になるケースもあるため、内容の整備は極めて重要です。
届け出が必要な事業場
就業規則の届け出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用している事業場です。
この「常時10人以上」とは、正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、雇用契約を結んで働いている人すべてが対象ですので、注意が必要です。
労働基準法第89条では、このような事業場に対して就業規則の作成と届け出を義務づけており、違反した場合には30万円以下の罰金が科される可能性もあります。
届け出が必要かどうか迷ったときは、以下の点をチェックするとよいでしょう。
- 各支店・事業所単位で10人以上の従業員がいるか?
- 繁忙期などで一時的に10人を超えるケースも対象になるのか?
- 派遣社員や業務委託はカウントされるか?
特に、「本社は5人だが、支店に15人いる」といった場合、支店単位でも届け出が必要になる可能性があるため、慎重な確認が求められます。
また、10人未満の企業であっても、労務トラブルを防ぐために就業規則を任意で作成・運用することは非常に有効です。義務の有無にかかわらず、自社に合った労務管理の仕組みを整えることが、健全な組織運営への近道となるでしょう。
2. 就業規則の届け出に必要な書類
就業規則を作成しただけでは、届け出の手続きは完了しません。届け出の際には、所定の書類を揃えて労働基準監督署に提出する必要があります。この章では、実際に必要な書類の種類や、書類作成時の注意点について具体的に解説します。
現場で多いミスとして、「就業規則だけ提出すればOK」と思っているケースがありますが、それでは不備として差し戻されてしまうことも。正しく・スムーズに届け出を完了させるために、必要書類を一つずつ確認していきましょう。
就業規則本体
まず必要となるのが「就業規則そのもの(本文)」です。これは企業ごとにカスタマイズされたものであり、労働条件や勤務時間、賃金、服務規律、懲戒、退職などが明文化されていることが求められます。
特に注意が必要なのが、「モデル規程をそのまま使っているだけ」の場合。実態と合っていない内容で届け出をしてしまうと、後々トラブルになりやすいだけでなく、監督署からの指摘対象にもなりかねません。
- 社内の勤務実態に合った内容か確認する
- 法改正に対応した最新版になっているかチェック
- 不明点がある場合は社労士など専門家に相談を
就業規則を変更する場合には、最低限上記については押さえておきましょう。
就業規則(変更)届
次に必要なのが、「就業規則届」または「就業規則変更届」です。

- 新しく就業規則を作成した場合 → 「就業規則届」
- 既存の就業規則を変更した場合 → 「就業規則変更届」
この届出書は、所轄の労働基準監督署に提出する公式な文書であり、e-Gov(電子申請)でも提出可能です。
様式は厚生労働省や各労働局のホームページよりダウンロードが可能です。参考までに、東京労働局で公開されている「就業規則(変更)届」はこちらよりご覧ください。
労働者代表の意見書
最後に重要なのが「労働者代表の意見書」です。

就業規則の作成・変更には、労働者の過半数代表者の意見を聴取することが法律で義務付けられています(労働基準法第90条)。この意見書は、単なる「同意書」ではなく、意見を聴取した事実を証明するための書類です。
実務上の注意点としては
- 労働者代表は、使用者の意向で選任してはいけません(公正な手続きが必要)
- 意見の内容は「賛成・反対」いずれでも構いませんが、必ず署名が必要
- 意見書がないと、届け出書類は受理されません
これらは必ず確認しておきましょう。専門家から見ると、この意見書の取り扱いで法的トラブルに発展するケースが意外と多いため、代表者の選任方法や説明内容には十分注意を払いましょう。
就業規則の届け出手順
就業規則を作成し、必要な書類を準備したら、いよいよ労働基準監督署への「届け出手続き」に進みます。
このプロセスは単純に見えて、手順を誤ると書類の差し戻しや、労働者とのトラブルにつながることもあるため、慎重な対応が求められます。
この章では、就業規則の作成から届け出、そしてその後の社内周知まで、実務に即した流れを段階的に解説します。
「どの順番で進めればよいか分からない」「電子申請と紙の提出、どちらがよいのか迷っている」といった方にとっても役立つ情報になれば幸いです。
就業規則の作成・変更
就業規則を新たに作成する場合、まずは自社の実態や労務管理方針を踏まえて、必要なルールを文書化します。
すでにある場合でも、法改正や働き方の変化に応じて定期的な見直しが必要です。また、賃金規定や退職金規程などを「別規程」として扱う場合、それらも届け出対象となることがあるので注意しておきましょう。
弊社にご相談いただく企業様の中で「インターネットにあるテンプレートをそのまま使っている」ケースがよく見受けられます。自社の就業実態に即した内容にカスタマイズしなければ知らないうちにトラブルに繋がることがあります。また、法令違反となる表現や、あいまいな規定は労使間で認識が相違することになりますので、規定を作成・変更する場合は専門家にご相談されることを推奨いたします。
労働者代表への意見聴取
就業規則の作成・変更が完了したら、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)から意見を聴取します。
このプロセスは形式的なものではなく、法的義務に基づいた実質的なステップです。
意見書には、代表者の署名と日付を明記する必要がありますが、たとえ内容に反対意見が記載されていても、届け出自体は可能です。
ただし労働者代表の選出方法が不適切(例:会社が一方的に指名)だと、意見書が無効と判断されるリスクがあります。
必要書類の準備
以下3点の書類を揃えましょう。
- 就業規則本体
- 就業規則(変更)届
- 労働者代表の意見書
提出用と会社控え用で2部ずつ用意しておくと、返却された受理印付き控えを保存しておけるため安心です。
労働基準監督署への提出
書類が揃ったら、管轄の労働基準監督署へ届け出を行います。提出方法は3種類あり、自社の状況に応じて選択可能です。
- 窓口での提出
- 最も確実な方法です。担当者とその場でやり取りができるため、不備があってもすぐに対応できます。
- 郵送での提出
- 遠方の事業場など、訪問が難しい場合に適しています。
- 受理印付きの控えが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付・宛先明記)を必ず同封しましょう。
- 電子申請(e-Gov)
- オンラインで24時間手続きが可能な方法です。会社の代表電子証明書などが必要ですが、効率的かつ履歴管理もできるため、今後の主流になりつつあります。
就業規則の届け出期限
就業規則の作成や変更に取り組む際に、意外と見落とされがちなのが「いつまでに届け出をすればよいのか?」という点です。
実は、労働基準法上、届け出の「明確な期限」は定められていません。しかし、届け出のタイミングによっては、法令違反やトラブルのリスクが生じる可能性もあるため、実務的には注意が必要です。
この章では、就業規則の届け出の「実務上の適切なタイミング」や、「注意すべきケース」について、専門家としてのアドバイスも交えながら解説していきます。
就業規則の届け出に法的な期限はないが…
まず押さえておきたいのは、法律上は届け出の“期限”自体は存在しないという点です。
労働基準法第89条では、就業規則を作成・変更した場合、所轄労働基準監督署長に届け出る義務があると定めていますが、「いつまでに出さなければならない」とは明示されていません。
ただし、だからといっていつ出してもいいわけではありません。
実務上は「施行日までに届け出る」のが原則
実務では、就業規則を実際に社内で適用(施行)する前に届け出ることが求められます。
たとえば、ある規定を「来月1日から適用」とするのであれば、その施行日前に届け出を済ませておくのが基本です。
逆に、施行後に届け出た場合、労働者から「正式な手続きを経ていない規則」と見なされるリスクもあり、社内トラブルや無効主張につながる可能性もあります。
実務でよくある届け出タイミングの失敗例
就業規則の変更に関して、実務的にトラブルになりやすいケースとしては下記のようなものがあります。
- 規則改定後に「後出し」で届け出してしまい、トラブル時に有効性を疑問視される
- 賃金規程を変更し、すでに運用開始しているのに、届け出が未完了
- 施行日がすでに過ぎており、書類が差し戻された
こうした事態を避けるためにも、就業規則の完成と同時に届け出スケジュールも組み込むことが重要です。
労働基準監督署では、形式的な届出受理はしてくれますが、提出日と施行日の整合性や、意見書の日付が施行日より後になっていないかといった点を細かくチェックしている場合があります。
社労士など専門家のサポートを受けることで、届け出ミスやトラブルの芽を事前に摘むことができます。
「作って終わり」ではなく、「届け出て、活用し、トラブルを防ぐ」ことが、就業規則本来の目的といえるでしょう。
就業規則の周知義務
就業規則は、作成して届け出るだけでは不十分です。
労働者にその内容を「周知」させることも、法的に義務づけられている重要なステップです。
労働基準法第106条では、就業規則その他労働関係法令を「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること」などにより、労働者に周知させることが求められています。
この義務を怠ると、就業規則の内容が労働者に対して効力を持たない可能性もあるため注意が必要です。
この章では、「就業規則の周知とは具体的に何をすればいいのか?」を実務レベルでわかりやすく解説します。
周知義務とは何か?
周知義務とは、従業員が就業規則の内容をいつでも確認できる状態にしておくことを意味します。
この周知が不十分な場合、たとえ就業規則が適法に作成・届け出されていたとしても、労働者に対して効力を発揮しない可能性があるという点が、非常に重要です。
たとえば、懲戒処分や賃金控除のルールが規定されていても、それを周知していなければ、後から従業員から「知らなかった」と争われてしまうことがあります。
周知方法は複数ある
法律では周知の方法として明確に「これでなければならない」とは定められていませんが、代表的な方法は以下の通りです。
印刷して掲示する
- 社内の掲示板などに就業規則を印刷して掲示
- 一定期間、労働者が自由に閲覧できる場所に掲示することが大切
書面で配布する
- 各従業員に紙の就業規則を配布
- 配布記録を取っておくことで、後々の証明にも使える
パソコンや社内ネットワーク上で閲覧できる状態にする
- 社内のイントラネットや共有フォルダにPDFデータなどをアップロード
- 「誰でもアクセスできる」状態が前提
就業規則周知におけるポイント
近年ではペーパーレス化により、就業規則の電子配布・社内ネットでの公開が主流になっています。
ただし、ここで注意すべき点は、単にデータをアップしただけでは「周知した」とは言えないということです。
労働者に対して「どこにアクセスすれば見られるのか」を明確に案内することが不可欠です。また、アクセスログや周知メールを保存しておくことで、後日「見せた・見ていない」の水掛け論を回避できます。
また、繰り返しになりますが、就業規則は「周知されてはじめて法的効力を持つ」という点は非常に重要です。
つまり、懲戒処分や退職手続き、残業命令などを行う際、就業規則にその根拠があっても、周知されていなければ無効とされるおそれがあるのです。
「作ったけど伝えていない」では、就業規則は意味を持ちません。法的なリスクを避け、労務トラブルを未然に防ぐためにも、周知のプロセスは計画的・丁寧に行いましょう。
6. 就業規則の未届け出による罰則
就業規則の作成や変更を行ったにもかかわらず、労働基準監督署へ届け出をしていない――。このような状態は、労働基準法違反となり、行政指導や罰則の対象になる可能性があります。
特に、従業員が10人以上いるのに就業規則を届け出ていない場合、「知らなかった」「忙しくて後回しにしていた」では済まされません。
この章では、未届け出による具体的な罰則内容やリスク、そして専門家の視点から見た企業が受けるダメージについて解説します。
労働基準法に基づく罰則
労働基準法第89条に基づき、就業規則の届け出義務に違反した場合、同法第120条により「30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
これは単なる形式的な違反ではなく、「労働者の権利を守るための最低限の義務」に違反しているという重い評価になります。
特に、監督署の調査(定期調査・申告調査など)で違反が発覚すると、是正勧告書が交付され、対応期限内に是正しなければ追加指導や送検に発展することもありえます。
行政指導や企業イメージへの悪影響
実際に罰金を科されるケースはそれほど多くはありませんが、「是正勧告」や「報告命令」などの行政指導が行われる可能性は非常に高いです。
また、次のような二次的リスクも見逃せません。
- 社名が公表されるリスク(重大・継続的な違反がある場合)
- 労働者との信頼関係の毀損
- 労働トラブル(不当解雇・残業代未払等)での防御力低下
- M&Aや上場審査における評価ダウン
とくに、労働者とのトラブル時には「就業規則が有効に整備・周知されているかどうか」が重要な判断材料となります。
未届け出の状態では、企業側が不利になることがほとんどです。
就業規則変更における社労士からのワンポイントアドバイス
就業規則の作成・届け出・周知は、法律で定められたルールであると同時に、企業の労務管理の質を左右する重要な経営インフラでもあります。
「とりあえず作った」「届け出はしてあるけど、内容は見直していない」という企業も多く見られますが、就業規則は一度作って終わりではなく、定期的なメンテナンスが不可欠です。
この章では、社会保険労務士として、実務経験の中で得られたリアルな課題や対応策をもとに、企業の皆さまに向けて具体的なアドバイスをお伝えします。
ルールは「現場の実態」と一致させることが重要
多くの企業が陥る失敗が、「ひな形(テンプレート)をそのまま使ってしまう」ことです。
確かに、厚労省やネット上にはモデル規則がありますが、それが自社の働き方や価値観に合っているとは限りません。
- 現場での実際の勤務時間や休憩の取り方
- 柔軟な勤務制度(フレックス、テレワークなど)の有無
- トラブル時の対応方針(懲戒処分、ハラスメント対策など)
こうした要素を踏まえて、オーダーメイドで就業規則を設計することで、初めて“機能するルール”になります。
定期的な見直しと社内説明もセットで行う
就業規則は、法改正や社内制度の変更に合わせて更新していくべきものです。
特に近年では、
- 育児・介護休業法
- 時間外労働の上限規制
- 同一労働同一賃金
- テレワークガイドライン
など、働き方に関する法律が頻繁に変わっており、数年前の規則が「知らぬ間に時代遅れ」になっているケースも珍しくありません。
さらに、就業規則を改定した際は、単に社内掲示するだけでなく、従業員に向けた説明会やQ&A対応も大切です。「ちゃんと伝わっている」「理解されている」という状態が、就業規則の実効性を高めます。
社労士など専門家の活用でトラブルを未然に防ぐ
就業規則に関するご相談で多いのが、実際にトラブルが起きてから「見直したい」「整備したい」というパターンです。
しかし、本来就業規則は、トラブルを未然に防ぎ、企業と従業員双方の安心を守るための「予防ツール」です。
- 労働トラブルのリスクを減らしたい
- 自社の規則が法令に適合しているか確認したい
- 今後の法改正に備えてアップデートしておきたい
こうした課題に直面している企業は、ぜひ一度、社会保険労務士など専門家の意見を取り入れることをおすすめします。
相談や点検だけでも、思わぬ落とし穴に気づくことができ、結果として労務トラブルを大きく回避できます。
最後に:就業規則は「会社を守るルールブック」
就業規則は単なる書類ではありません。
従業員との信頼関係、トラブル回避、会社の成長を支える基盤であり、経営のリスク管理の一環として積極的に整備・活用していくべき武器です。
「うちは小さな会社だから…」と後回しにせず、今こそ一歩踏み出し、自社に合った働きやすい職場づくりを始めましょう。
就業規則の整備でお困りの方へ
「就業規則をどう整えればいいのかわからない…」「自社のルールが法律に合っているか不安…」そんなお悩みをお持ちの経営者・人事労務担当者の方もおられると思います。
社会保険労務士法人ステディでは、社会保険労務士が貴社の実情に合わせた就業規則の作成・変更・届け出を丁寧にサポートいたします。
- 初めての就業規則作成
- 法改正への対応
- 労働トラブルの予防
初回相談は無料ですので、どんな小さなご相談でもお気軽にいただければ幸いです。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
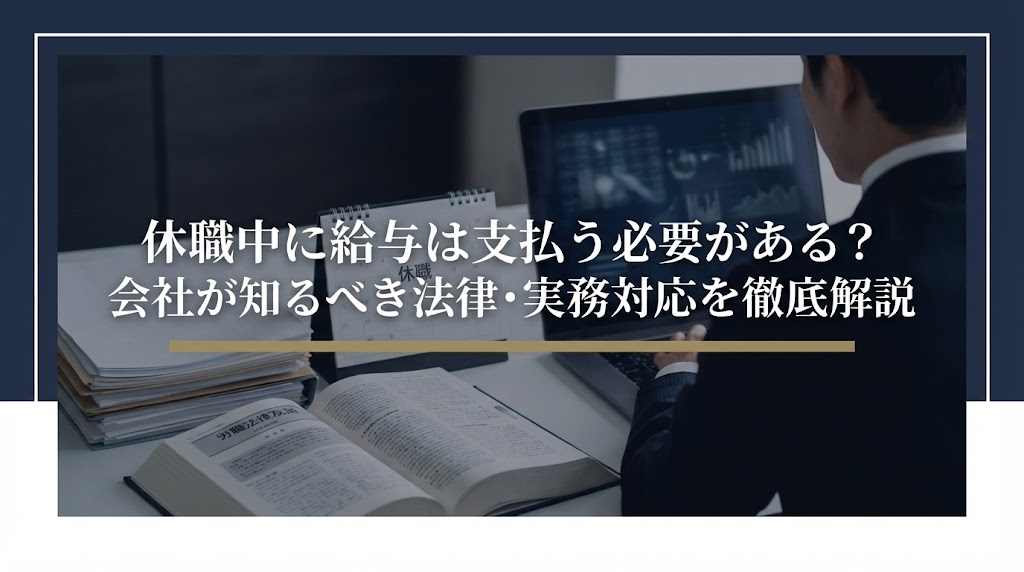 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説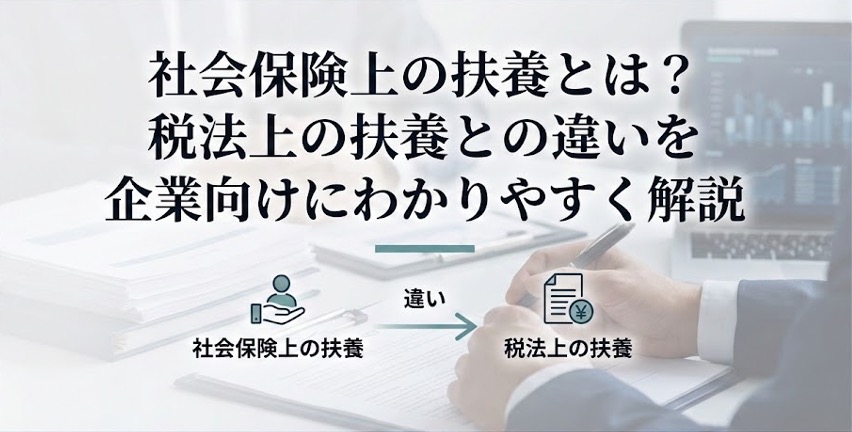 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説 ニュース一覧2026.01.08【重要】助成金に関する不正リスクについて
ニュース一覧2026.01.08【重要】助成金に関する不正リスクについて ニュース一覧2025.12.12顧問社労士に“ミスが多くて不満”と感じたときに会社が取るべき5つのステップ
ニュース一覧2025.12.12顧問社労士に“ミスが多くて不満”と感じたときに会社が取るべき5つのステップ

