経営者、人事労務担当者の方にとっては、従業員の方を解雇する際に非常に頭を悩ませる問題かと思います。
また、解雇といっても
- 普通解雇
- 懲戒解雇
と大きく2つに分けることができ、違いを正確に理解しておかなければトラブルに繋がりかねません。
今回のコラム記事では、普通解雇と懲戒解雇について、定義・目的・法的根拠・手続き・解雇後の影響まで広く解説をいたします。
また、企業が解雇の種類に悩んだときに選択する際の注意点や、懲戒解雇を行う際のリスクについても記載しますので、労務管理の一助になれば幸いです。
普通解雇と懲戒解雇の基本的な違いは何がある?
普通解雇も懲戒解雇も、雇用契約を終了させる点では同じ手段です。
一方で、解雇の性質や目的、法的な根拠は重要な違いがあるためしっかりと把握しておかなければ、人事管理上でリスクがありますので注意しておきしょう。
定義の違い
普通解雇は、従業員の能力不足・会社の経営状況など、様々な理由により雇用契約を終了させる一般的な解雇方法と言えます。
必ずしも従業員側に非があるわけではなく、会社の事情によっても行われることがあります。
一方で懲戒解雇は従業員の
- 重大な服務規律違反
- 会社の名誉や信用を著しく毀損する行為
このような行動に対する制裁として行われることになります。
従業員の行為が会社の秩序を著しく乱すものであり、雇用関係を継続することが困難な場合に懲戒解雇が判断されることがあります。
目的の違い
普通解雇の主な目的は、雇用関係を終了させることです。
会社と従業員の関係が、様々な理由により継続困難になった場合に、その関係を解消するために行われます。
懲戒解雇には二つの目的があります。
一つは雇用関係の終了ですが、もう一つは会社の規律維持です。
懲戒解雇は、他の従業員に対して規律違反の重大性を示し、同様の行為を抑止する効果も期待されています。
法的根拠の違い
普通解雇の法的根拠は、民法の雇用契約に関する規定や労働契約法に基づいています。
特に、労働契約法第16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利の濫用として無効であると定めています。
続いて懲戒解雇の法的根拠は、労働基準法第89条第9号に基づいています。
第八十九条常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
e-GOV「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
この条文は、就業規則に懲戒に関する事項を定めることを義務付けており、懲戒解雇を行うためには、あらかじめ就業規則にその旨を明記しておく必要があると言えます。
さらに、懲戒解雇は、最高裁判所の判例により「懲戒権の濫用」の法理が適用されます。
これは、懲戒処分が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利の濫用として無効になるというものです。
以上のように、普通解雇と懲戒解雇は、その定義、目的、法的根拠において明確な違いがあります。
企業は、これらの違いを十分に理解した上で、適切な解雇手続きを行うことが求められます。また、従業員も自身の権利を守るために、これらの違いを知っておくことが重要なのです。
普通解雇と懲戒解雇の解雇理由は?
普通解雇と懲戒解雇は、当然それぞれ異なる理由や状況で行われます。どのような解雇理由に違いがあるのか確認していきましょう。
普通解雇の主な理由
普通解雇は、従業員の能力や勤務態度に問題がある場合、または会社の経営状況などの理由で行われる解雇です。
主な理由には以下のようなものがあります。
- 能力不足や業務成績の著しい低下
- 長期にわたる病気や怪我による就労不能
- 協調性の欠如や職場環境への不適応
- 会社の経営悪化による人員整理
普通解雇の場合、会社は従業員に対して改善の機会を与えたり、配置転換などの措置を講じたりすることが求められます。
これらの努力を尽くしても状況が改善されない場合に、最終手段として解雇が検討されます。
懲戒解雇の主な理由
懲戒解雇は、従業員の重大な非行や規律違反に対して行われる、より厳しい形の解雇です。
主な理由には以下のようなものがあります。
- 業務上の横領や背任行為
- 機密情報の漏洩や不正利用
- セクハラやパワハラなどの重大なハラスメント行為
- 重大な業務命令違反や会社の信用を著しく損なう行為
- 犯罪行為や反社会的行為
懲戒解雇は、従業員の行為が会社の秩序や信用を著しく害する場合に選択される処分です。原則、就業規則に明記された懲戒事由に該当する必要があります。
解雇理由の重大性の違い
普通解雇と懲戒解雇の最も大きな違いは、解雇理由の重大性にあります。
普通解雇の場合、従業員の行為や状況が直ちに会社に重大な損害を与えるものではありませんが、雇用関係を継続することが困難な程度に至っている状態を指します。会社は段階的な措置を講じ、解雇回避の努力をする必要があります。
一方、懲戒解雇の場合は、従業員の行為が会社の秩序や信用を即座に著しく損なうほど重大なものであることが求められます。そのため、懲戒解雇は「企業秩序を乱した従業員に対する制裁」としての性質を持ちます。
重大性の違いは、解雇後の処遇にも影響します。
普通解雇の場合、退職金の支払いや失業保険の受給に関して比較的有利な扱いを受けることが多いのに対し、懲戒解雇では退職金の不支給や減額のペナルティが伴うことがあります。
解雇理由の重大性を判断する際は、以下の点を考慮する必要があります。
- 行為の悪質性や故意性の程度
- 会社や他の従業員に与えた影響の大きさ
- 過去の処分歴や指導の有無
- 行為後の態度や改善の見込み
企業は、解雇を検討する際に、これらの違いを十分に理解し、適切な判断を下すことが重要です。また、解雇理由の重大性に応じて、適切な手続きを踏むことで、不当解雇のリスクを軽減することができます。
手続きと要件の違い
普通解雇と懲戒解雇は、その性質の違いから手続きと要件にも重要な差異があります。ここでは、両者の主な違いについて確認しましょう。
就業規則での規定の必要性
普通解雇の場合、就業規則に具体的な解雇事由を定める必要は必ずしもありません。
しかし、10人以上の従業員を雇用する企業では、労働基準法に基づき就業規則の作成が義務付けられており、その中に退職に関する事項(解雇の事由を含む)を記載する必要があります。
一方、懲戒解雇は、企業の懲戒権の行使として行われるため、就業規則に懲戒解雇の事由を明確に定めておく必要があります。就業規則に規定がない場合、懲戒解雇を行うことはできません。
解雇予告の要否
普通解雇では、原則として30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。これは労働基準法で定められた従業員保護のための規定です。
懲戒解雇の場合も、基本的には同様の解雇予告が必要です。ただし、従業員の責に帰すべき重大な事由があり、労働基準監督署長の認定を受けた場合は、予告なしに即時解雇が可能となります。この場合、解雇予告手当の支払いも不要となります。
弁明の機会の付与
普通解雇の場合、法律上は弁明の機会を与えることは明確に義務付けられていません。
しかし、解雇の正当性を確保するためには、従業員に対して事情説明や弁明の機会を与えることが望ましいとされています。
懲戒解雇では、弁明の機会を与えることが非常に重要です。
懲戒解雇は従業員に対する制裁的な性質を持つため、対象となる従業員に十分な弁明の機会を与えないまま行われた懲戒解雇は、手続き的な瑕疵があるとして無効とされるリスクが高くなります。
具体的な弁明の機会の付与方法としては、以下のようなものが考えられますので、参考にしてください。
- 事前に懲戒解雇の可能性があることを本人に通知する
- 弁明の機会を設定し、日時と場所を本人に伝える
- 弁明の場では、懲戒解雇の理由となる事実を具体的に説明する
- 本人の言い分を十分に聴取し、記録する
- 必要に応じて、本人に弁明書の提出を求める
これらの手続きを踏むことで、懲戒解雇の正当性を高めることができます。
以上のように、普通解雇と懲戒解雇では、就業規則での規定の必要性、解雇予告の要否、弁明の機会の付与において重要な違いがあります。
企業は、これらの違いを十分に理解し、適切な手続きを踏まなければ、不当解雇のリスクに繋がりますので注意してください。
解雇後の影響の違い
普通解雇と懲戒解雇は、単に雇用関係を終了させるだけでなく、その後の従業員の生活や将来にも大きな影響を与えます。ここでは、退職金、失業保険、再就職という3つの重要な側面から、両者の違いを詳しく見ていきましょう。
退職金の取り扱い
退職金は、長年の勤務に対する報償や退職後の生活保障という性質を持つため、その取り扱いは従業員にとって非常に重要です。
普通解雇の場合、通常は就業規則や退職金規程に基づいて退職金が支給されます。ただし、解雇理由によっては減額されることもあります。例えば、能力不足や業績不振による解雇の場合は、全額支給されるケースが多いですが、軽微な規律違反による解雇の場合は、一部減額されることがあります。
一方、懲戒解雇の場合は、多くの企業で退職金の全額不支給や大幅な減額が規定されています。これは、懲戒解雇が重大な非違行為に対する制裁であるという性質上、退職金という功労報償を与える理由がないと考えられるためです。
ただし、退職金の全額不支給が常に認められるわけではありません。裁判上では、従業員の過去の功労や勤続年数、非違行為の内容などを総合的に考慮して、不支給や減額の妥当性を判断します。
失業保険(雇用保険)の受給への影響
失業保険は、失業中の生活を支える重要なセーフティネットです。普通解雇と懲戒解雇では、その受給資格や待機期間に大きな違いがあります。
普通解雇の場合、通常は「特定受給資格者」として扱われ、失業保険の受給において優遇されます。具体的には以下のような利点があります。
- 待機期間が7日間と短い
- 給付日数が自己都合退職よりも長い
懲戒解雇の場合、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」と判断されると、以下のようなデメリットが生じます。
- 待機期間が2ヶ月7日と長い
- 給付日数が自己都合退職と同じ
ただし、懲戒解雇であっても、その理由が「自己の責めに帰すべき重大な理由」に該当しないと判断された場合は、普通解雇と同様の扱いを受けることがあります。
再就職への影響
解雇の種類は、その後の再就職活動にも大きな影響を与えます。
普通解雇の場合、再就職への影響は比較的軽微です。能力不足や会社の経営状況による解雇であれば、次の就職先で不利に扱われる可能性は低いでしょう。ただし、軽微な規律違反による解雇の場合は、その内容によっては説明が必要になることもあります。
懲戒解雇の場合、再就職に大きな障害となる可能性が高くなります。以下のような影響が考えられます。
- 履歴書や職務経歴書での説明が必要になる
- 面接で詳しい経緯を聞かれる可能性が高い
- 採用に消極的になる企業が多い
- 信用を回復するまでに時間がかかる
ただし、懲戒解雇を受けたからといって、再就職が不可能になるわけではありません。真摯に反省し、その経験を糧にしていることを示せれば、チャンスは十分にあります。
以上のように、普通解雇と懲戒解雇では、解雇後の影響に大きな違いがあります。
企業側は、これらの違いを十分に理解した上で、慎重に解雇の種類を選択する必要があります。また、従業員側も、自身の権利を守るために、これらの違いを知っておくことが重要です。
法的リスクの違い
普通解雇と懲戒解雇は、その性質や目的が異なるため、法的リスクにも違いがあります。
解雇権濫用法理の適用と裁判所での判断基準の違いについて解説します。
解雇権濫用法理の適用
解雇権濫用法理は、労働契約法第16条に規定されており、普通解雇と懲戒解雇の両方に適用されます。しかし、その適用の仕方には違いがあります。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第16条
普通解雇の場合
普通解雇では、解雇権濫用法理がより厳格に適用される傾向にあります。
会社は、解雇の必要性や相当性を慎重に検討し、客観的に合理的な理由を示す必要があります。
例えば、能力不足を理由とする場合、単に成績が悪いだけでなく、改善の機会を与えたにもかかわらず改善が見られないことなどを示す必要があります。
懲戒解雇の場合
懲戒解雇においても解雇権濫用法理は適用されますが、従業員の非違行為の重大性が認められれば、比較的解雇が認められやすい傾向にあります。
ただし、懲戒権の濫用にあたらないかどうかの判断は厳格に行われます。
裁判所での判断基準の違い
裁判所は、普通解雇と懲戒解雇で異なる判断基準を用いる傾向にあります。
普通解雇の判断基準では
- 解雇理由の客観的合理性
- 解雇の社会通念上の相当性
- 解雇回避努力の有無
- 従業員への説明や協議の有無
裁判所は、これらの要素を総合的に考慮して判断を下します。特に、会社が解雇回避のための努力(配置転換や降格など)を行ったかどうかが重視されます。
懲戒解雇の判断基準では
- 非違行為の事実関係
- 非違行為の重大性
- 過去の処分歴
- 会社の規律や信用への影響
- 懲戒手続きの適正性
懲戒解雇の場合、非違行為の事実関係と重大性が特に重視されます。また、就業規則に定められた懲戒事由に該当するかどうかも重要な判断要素となります。
普通解雇の場合、裁判所は会社の解雇回避努力や従業員への配慮をより重視する傾向にあります。一方、懲戒解雇の場合は、非違行為の重大性と会社の規律維持の必要性をより重視します。
ただし、近年の傾向として、懲戒解雇においても、その処分が重すぎないかという観点から、より慎重な判断がなされるようになってきています。
結論として、普通解雇と懲戒解雇では、解雇権濫用法理の適用や裁判所の判断基準に違いがあります。会社は、これらの違いを十分に理解した上で、適切な解雇手続きを行う必要がありますので、慎重に判断してください。
また、解雇を検討する際は、事前に専門家に相談するなど、慎重な対応が求められます。
企業が選択する際の注意点
解雇は従業員の生活に大きな影響を与える重大な決定です。企業は、普通解雇と懲戒解雇のどちらを選択するかを慎重に検討する必要があります。
ここでは、両者の使い分けと、懲戒解雇を選択する際のリスクについて詳しく解説します。
普通解雇と懲戒解雇の使い分け
普通解雇と懲戒解雇は同じ「解雇」ではありますが、考え方や利用されるケースは大きく異なります。どのような対応が適切なのか以下の点を考慮してください。
- 解雇理由の性質
- 普通解雇は能力不足、業績不振、長期病欠など、従業員の責任が比較的軽い場合や、会社側の事情による場合に適しています。
- 懲戒解雇は、重大な非違行為や会社の信用を著しく損なう行為など、従業員の責任が重大な場合に選択されます。
- 会社の規律維持の必要性
- 普通解雇は、他の従業員への影響が比較的小さい場合に選択されます。
- 懲戒解雇は、他の従業員への見せしめ効果や、会社の規律維持が必要な場合に選択されます。
- 従業員への配慮
- 普通解雇は、退職金や失業保険の受給など、従業員の退職後の生活への影響が比較的小さいです。
- 懲戒解雇は、従業員への影響が大きいため、よほどの重大な事由がない限り避けるべきです。
- 法的リスク
- 普通解雇は解雇権濫用の判断基準が厳格であり、慎重な手続きが必要です。
- 懲戒解雇は非違行為の事実関係と重大性が明確であれば、比較的認められやすい傾向にあります。
企業は、これらの要素を総合的に考慮し、適切な解雇の種類を選択する必要があります。
特に、懲戒解雇は最後の手段として位置付け、他の選択肢(譴責、減給、出勤停止など)を検討してから判断することが望ましいでしょう。
懲戒解雇を選択する際のリスク
懲戒解雇は、従業員に対する最も重い処分であり、
- 法的リスク
- レピュテーションリスク
- 労使関係の悪化
- 時間とコストのリスク
のようなリスクを伴います
法的リスク
懲戒解雇が無効とされるリスク非違行為の事実関係や重大性が十分に立証できない場合、裁判所で無効とされる可能性があります。
損害賠償請求のリスク不当な懲戒解雇と判断された場合、従業員から損害賠償を請求される可能性があります。
レピュテーションリスク
不当な懲戒解雇と見なされた場合、会社の評判が低下し、人材確保に悪影響を及ぼす可能性があります。
SNSなどでの炎上リスク従業員が解雇の不当性をSNSで訴えた場合、会社が批判の的となる可能性があります。
労使関係の悪化
懲戒解雇が不当と感じられた場合、他の従業員の会社に対する信頼が低下する可能性があります。
時間とコストのリスク
懲戒解雇が裁判に発展した場合、多大な時間とコストがかかります。また、懲戒解雇自体が無効とされた場合、従業員の職場復帰に伴う調整や賃金の遡及支払いなどの負担が生じます。
会社が行えるリスクヘッジ
上記で記載しているリスクを考慮すると、懲戒解雇を選択する際は以下の点に注意が必要です。
- 非違行為の事実関係を客観的証拠で裏付ける
- 就業規則の懲戒事由に明確に該当することを確認する
- 過去の類似事例との処分の均衡を検討する
- 弁明の機会を十分に与え、その内容を記録する
- 懲戒委員会などの第三者機関で審議する
- 可能な限り、より軽い処分の可能性を検討する
企業は、これらの点を慎重に検討し、懲戒解雇のリスクと必要性を十分に吟味した上で判断を下す必要があります。また、判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。
まとめ懲戒解雇と普通解雇の主な違い
解雇は従業員の生活に大きな影響を与える重大な決定であり、法的リスクも伴います。
そのため、解雇を検討する際は、専門家のアドバイスを受けることが極めて重要です。
当社は、労働トラブルに関するご相談対応の実績もございます。会社の状況を詳しくお聞きした上で、最適な対処方法をご案内いたしますので、解雇に関する悩みや疑問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
その他の記事
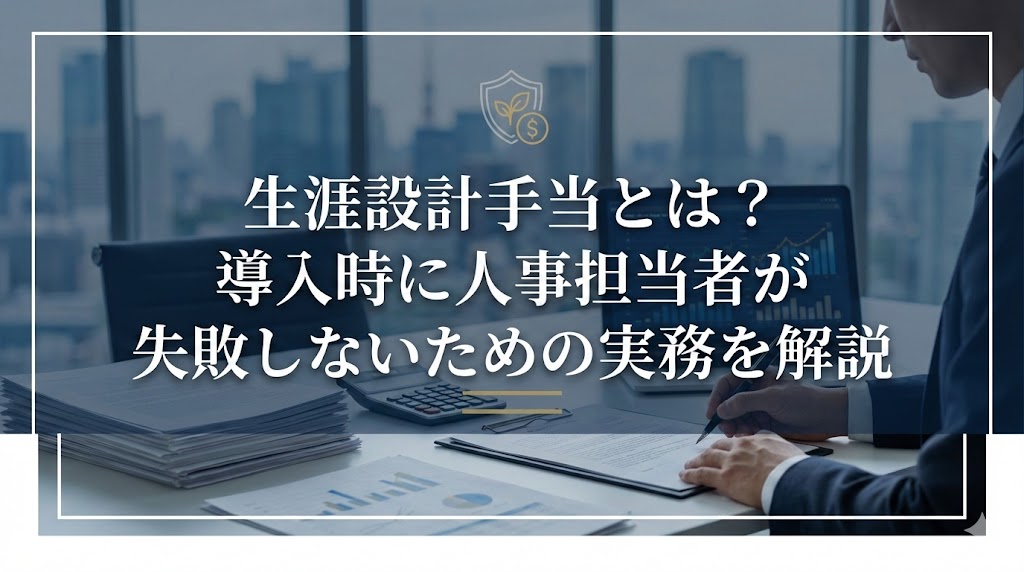 ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説
ニュース一覧2026.01.19生涯設計手当とは?導入時に人事担当者が失敗しないための実務を解説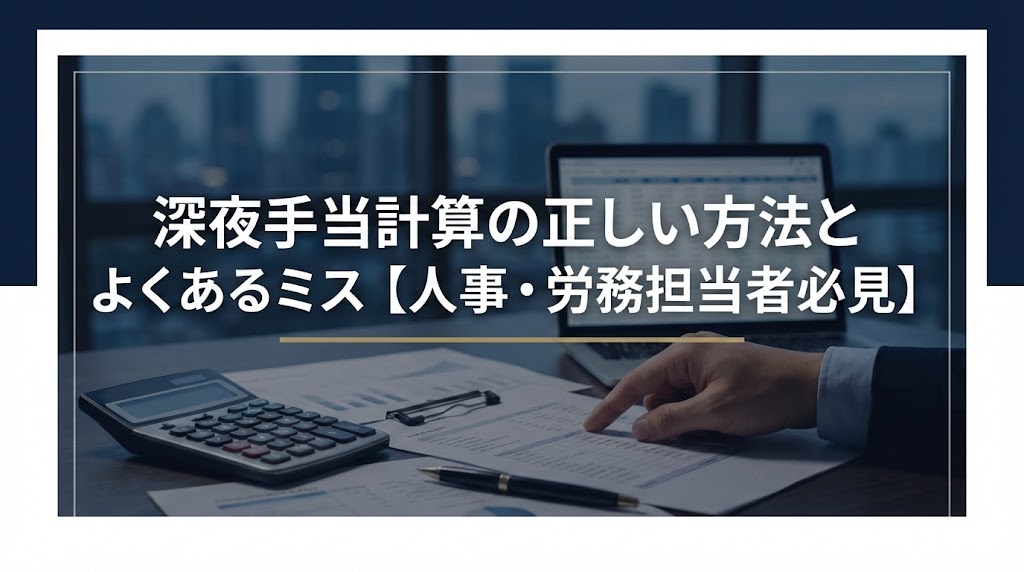 ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】
ニュース一覧2026.01.15深夜手当計算の正しい方法とよくあるミス【人事・労務担当者必見】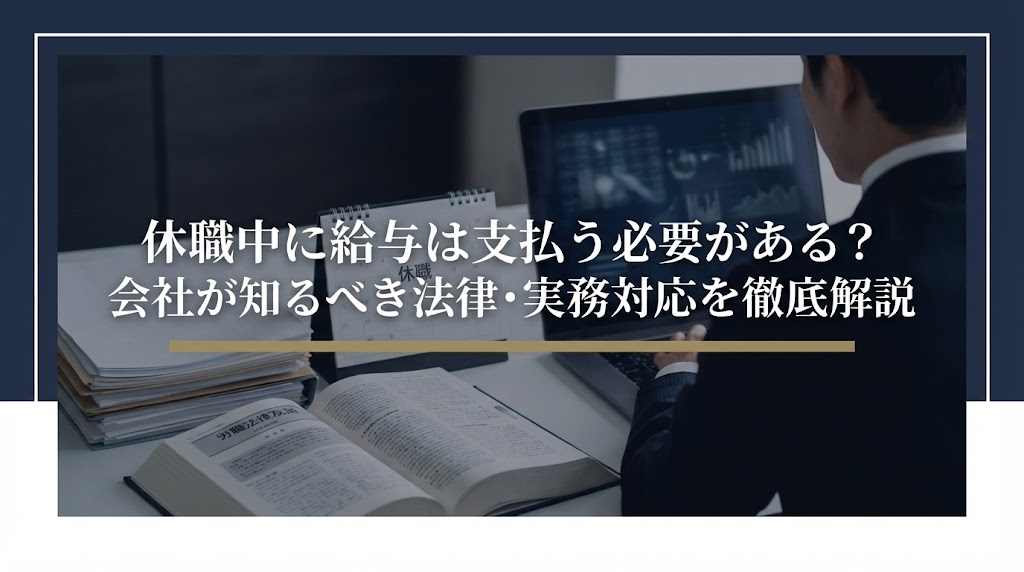 ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説
ニュース一覧2026.01.13休職中に給与は支払う必要がある?会社が知るべき法律・実務対応を徹底解説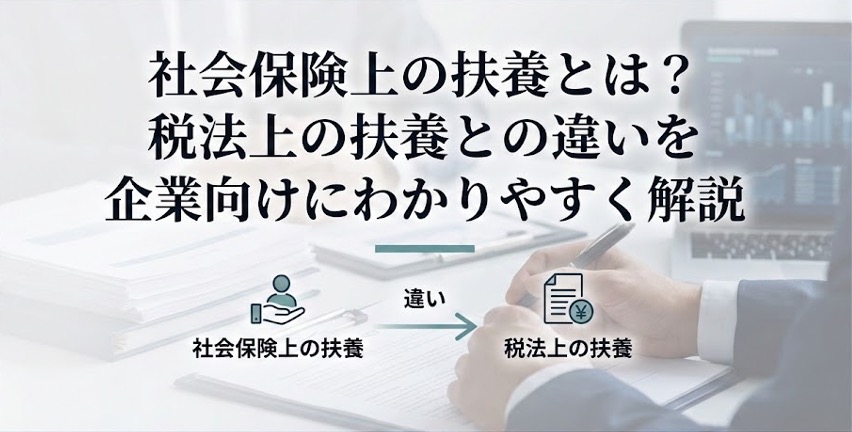 ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
ニュース一覧2026.01.12社会保険上の扶養とは?税法上の扶養との違いを企業向けにわかりやすく解説
